諸葛亮(しょかつりょう)は北伐の軍勢をひきいて大路を進む。蜀軍が堂々と直進してきたことに、各所に軍勢を分けていた魏軍は意表を突かれる。
魏の総大将の夏侯楙(かこうも)は鳳鳴山(ほうめいざん)で敗れた後、諸葛亮の計略の前に安定(あんてい)と南安(なんあん)の両郡も失う。
第279話の展開とポイント
(01)沔陽(べんよう)
蜀の大軍は沔陽まで進む。ここまで来たとき、「魏は関西(かんぜい。函谷関〈かんこくかん〉以西の地域)の精兵をもって長安(ちょうあん)に布陣し、そこに大本営を置いた」という情報が的確になった。
いわゆる天下の険。蜀の桟道を越えて出てくるだけでも、軍馬は一応疲れる。諸葛亮は沔陽に着くと言った。
「ここには亡き馬超(ばちょう)の墳(つか)がある。いまわが蜀軍の北伐に会うて、地下白骨の自己を嘆じ、懐かしくも思っているだろう。祭りを営んでやるがよい」
こうして馬岱(ばたい)に祭主を命じ、併せてその間に兵馬を休ませた。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第91回)では、馬超は諸葛亮が南方を平定し、都(成都〈せいと〉)へ帰還してから病気でこの世を去ったとある。だが吉川『三国志』では、馬超の動静が先の第260話(01)以降はうかがえない。
ある日、魏延(ぎえん)が説く。
「丞相(じょうしょう。諸葛亮)。それがしに5千騎をお貸しください。このようなことをしている間に、長安を壊滅させてみせます」
策によってはだが、と応ずる諸葛亮。さらに魏延は続けた。
「ここと長安の間は、長駆すれば10日で達する距離です。もしお許しあれば、秦嶺(しんれい)を越え、子午谷(しごこく)を渡り、虚を突いて敵を混乱に陥れ、その糧食を焼き払いましょう」
「丞相は斜谷(やこく)から進まれ、咸陽(かんよう)へ伸びて出られたなら、魏の夏侯楙などは、一鼓して破り得るものと信じますが――」
しかし諸葛亮は採り上げない。雑談のように軽く聞き流しただけだった。そして隴右(ろうゆう。甘粛省の隴山〈ろうざん〉・六盤山〈ろくばんざん〉以西、黄河以東の地域)の大路へ出て正攻法を採る。
(02)長安
これは魏の予想に反した。諸葛亮はよく知略を用いるという先入観から、さだめし奇道を取ってくると信じていたのである。ほかの間道へも兵力を分け、大いに備えていたところが、意外にも蜀軍は堂々と直進してきた。
夏侯楙は韓徳(かんとく)を呼んで命ずる。
「鳳鳴山まで出て蜀の先鋒を防げ。この一戦は魏蜀の第一会戦だから、以後の士気にも関わるぞ。十分に功名を立てるがいい」
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「鳳鳴山は山の名。雍州(ようしゅう)南安郡に属す。後漢・三国時代にはこの地名はなかった」という。
韓徳はこのたび魏軍が長安を本営としてから、西涼(せいりょう)の羌兵(きょうへい)8万騎をひきいて、何かひと手柄せんと参加した外郭軍の大将だった。
夏侯楙に励まされた韓徳は勇んで発つ。彼には韓瑛(かんえい)・韓瑤(かんよう)・韓瓊(かんけい)・韓琪(かんき)という4人の息子があり、みな弓馬に達し、力衆に超えていた。
(03)鳳鳴山
韓徳は望み通り蜀軍の先鋒と、鳳鳴山の下で出会ったが、その第一会戦に4人の息子たちを亡くしてしまう。相手は蜀の趙雲(ちょううん)だった。
★ここは韓瑤だけ趙雲に生け捕られたことになっていた(あとの3人は討ち死に)。だが原文に「4人の子を亡(うしな)って」とあるので、生け捕られた韓瑤も、その後に処刑されたという解釈らしい。なお井波『三国志演義(6)』(第92回)では、趙雲に捕らえられた韓瑤が、諸葛亮のもとへ護送されたことが見えた。
この様子を見た父の韓徳は心も萎え、大敗して長安へ逃げ崩れる。蜀の鄧芝(とうし)はつぶさに戦況を書き、まずは序戦の吉報を後陣の諸葛亮へ急送しておく。それに反して、魏の士気はそそけだった。
夏侯楙は長安の営府を離れ、自ら大軍を擁して鳳鳴山へ迫る。彼は美しき白馬にまたがり、燦爛(さんらん)たる黄金の兜を頂き、誠に曹叡(そうえい)の従兄弟たる貴公子的な風采をもって、日々旗の下から戦場を眺めていた。
そして、いつも趙雲が颯爽(さっそう)と往来するのを見ると、大言する。
「よし。明日は予が出て、あの老いぼれを討ち止めてみせる」
後ろにいた韓徳が、とんでもないことだと諫めると、夏侯楙はこう応えた。
「そちの子を4人も討たれたというか。ではなぜ親のお前は見ているのだ」
韓徳は差しうつむき、機会をうかがっているのですがと、ひどく恥じ入った様子。
翌日、韓徳は大きな斧を引っ提げて戦場を駆け巡った。趙雲と行き会うや否や、名乗りかけて一戦を挑んだが、10合とも戦わぬ間に槍先にかけられてしまう。副将の鄧芝も趙雲に負けない働きをした。
わずか4日間の合戦で、夏侯楙の軍容は半身不随になりかける。そこで退勢を改めるべく、総軍を20里ほど後退させた。
(04)鳳鳴山の近く 夏侯楙の本営
夏侯楙は軍議の席で、「いや、実に強いものだな」と、まるで他人事(ひとごと)のように趙雲の武勇を褒める。曹叡の金枝玉葉だけあり、大まかというのか何というのか……。諸将は彼の顔を眺め合っていた。
それでも、まずは趙雲を仕留めねばと熟議し、計策が整うと、魏軍は再び前進を始める。
★井波『三国志演義(6)』(第92回)では、ここで程昱(ていいく)の息子の程武(ていぶ)を登場させていたが、吉川『三国志』では使われていない。
(05)鳳鳴山
趙雲が一陣に駆け向かおうとするのを、鄧芝は少し変だと諫止した。だが、趙雲は猪突(ちょとつ)してしまう。向かうところ敵なきの快勝は得たものの、顧みると退路が断たれていた。
この日の魏軍は、神威将軍(しんいしょうぐん)の董禧(とうき)と征西将軍(せいせいしょうぐん)の薛則(せつそく)のふた手に2万騎ずつを付し、深く潜ませていたのだった。
★井波『三国志演義(6)』(第92回)では、夏侯楙が董禧と薛則にひきいさせたのは、それぞれ3万の軍勢。
★また井波『三国志演義(6)』(第92回)では、ここで潘遂(はんすい)という部将を登場させていたが、吉川『三国志』では使われていない。
趙雲は鄧芝とも別れ、部下とも散りぢりになり、日の暮れるまで敵に追われ、矢風に追われ、なお包囲から脱することができない。駒も疲れ、身も疲れ、倒れるように樹下の石へ腰を下ろす。そして差し昇る月を仰いでひとり泣いた。
すると、たちまち雨とばかりに石が降ってくる。雪崩かとばかりに大岩も降ってくる。趙雲は息つく間もなく、再び疲れた馬に鞭(むち)打って走った。
月明かりの野面を黒々と、一彪(いっぴょう)の軍馬が殺奔してくるのが見える。趙雲は我を忘れ、張苞(ちょうほう)に手を振った。近づいてきた張苞に子細を尋ねると、彼はこう答えた。
「丞相のご命令です。過日、鄧芝から勝ち戦の報告があるや否や、危うしとばかり、すぐ我々に救急の命を発せられましたので……」
見ると張苞は、左手に首級を持っていた。ここへ来る途中で討ち取った薛則の首だという。
そこへ反対の方角から、一軍が疾風のように駆けてくる。張苞に言われるまま待っていると、これも味方の関興(かんこう)で、父の関羽(かんう)の遺物(かたみ)である青龍刀を横ざまに抱えていた。
関興も、鞍(くら)にひとつの首級をくくりつけている。ここへ来る途中で道を阻めた董禧を討ち取ったのだという。
趙雲は涙をたたえ、ふたりを励ます。
「頼もし頼もし。この老骨の一命など、さしたることではない。董禧と薛則が討たれたと聞こえれば、まさに敵陣は壊滅状態であろう。その虚を逃すべきではない。我に構わず、ご辺(きみ)らは崩れる魏軍を追い、さらに夏侯楙の首をも挙げたまえ」
関興と張苞は別れを告げるや、手勢をひきいてまっしぐらに駆け去った。趙雲はふたりを見送ったが、やがて鞭打って後に続き、なお老軀(ろうく)を追撃戦の中に働かせる。
鄧芝もどこからか現れて加わり、一時は散りぢりになった蜀兵も、この好転にここかしこからこだまを上げて集まった。
夏侯楙はひと支えもできない。父の夏侯淵(かこうえん)とはあまりにも似ない、貴族らしさを多分に持った彼と部下たちは、逃げ崩れていく姿まで絢爛(けんらん)だった。そして南安城へ入り、諸方の大軍を吸って堅固を頼む。
★前の第278話(10)でも触れたが、史実の夏侯楙は夏侯淵の息子ではなく、夏侯惇(かこうとん。吉川『三国志』では「かこうじゅん」と読む)の次男である。
(06)南安
南安は著名な堅城である。日ならずして、続々とこれへ寄せてきた趙雲・鄧芝・関興・張苞などは、四方を囲み力攻したが、昼夜十数日の喚声も、そこの石垣の石ひとつ揺るがすことはできない。
その後ようやく諸葛亮も着陣したが、連れてきた軍勢は多くなかった。これへ臨む前に、沔陽や陽平(ようへい)、石城(せきじょう)方面にも兵を分け、自身はその中軍だけをひきいてきたからである。
南安は、東は天水郡(てんすいぐん)に連なり、北は安定郡に通じている険峻(けんしゅん)にあった。
翌日、諸葛亮は子細に地理を見て歩くと、関興と張苞を帷幕(いばく。作戦計画を立てる場所、軍営の中枢部)に招き、何事か計を授けていた。
また、物慣れた者を選んで偽使者に仕立て、これにも何やら言い含める。こうした準備を終えると、南安城への攻撃を再開した。
ここでもっぱら流言を放ち、「柴(シバ)を積み、硝薬を用いて、火攻めにして陥さん」と、敵にも聞こえるように言わせる。
(07)安定
南安の北に位置する安定城には、太守(たいしゅ)の崔諒(さいりょう)が籠もっていた。ここへある日、一使者が城門に立って呼ばわる。
「それがしは夏侯楙駙馬(ふば)の一将にて、裴緒(はいしょ)と申す者である。火急の事あってお使いに参った。早々に太守に告げたまえ」
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(駙馬都尉の)俸禄は比二千石(せき)。三国時代は皇女の夫のほか、外戚や宗室も就任した」という。
崔諒が会って来意を尋ねると、裴緒はこのように伝えた。
「南安はすでに危うく、事は急です。よってそれがしを使いとし、天水と安定の両郡に対して、かく救いを求められる次第です。急きょ郡内の兵を挙げ、諸葛亮の後ろを襲撃されたい」
「貴軍が後詰めくださる日を期し、城中からも合図の火の手を上げ、内外より蜀軍を撃ち挟まんとの手はずですから、何とぞお抜かりなく願いたい」
崔諒に促されると、裴緒は汗みずくな肌着の下から、しとどに濡れた檄文(げきぶん)を出してみせる。これから天水郡の太守へも、同様の催促に参らねばならないと言うと、供応も謝し、すぐに馬に鞭打って立ち去った。
偽使者とは夢にも気づかず、崔諒が兵を集めて赴援の準備をしていると、2日後にまた、一使者が来て城門へ告げる。
「天水太守の馬遵(ばじゅん)は瞬時に発し、はや蜀軍の後ろへ後詰めしておるのに、安定城は何を猶予しておらるるぞ。夏侯駙馬のご命令を軽んじておられるのか」
夏侯楙は魏の帝族である。崔諒は震え上がって発向にあわてた。
★井波『三国志演義(6)』(第92回)では、2日も経たないうちに、また早馬が来たとある。
(08)安定の郊外
だが城を出て70里、夜に迫ると、前方に火炎が天を焦がしている。斥候を放ったものの生死も知れず、ただ蜀の関興軍が猛進してきた。崔諒が驚いて退くと、後ろから張苞軍が鬨(とき)を上げてくる。
魏軍は支離滅裂となり、崔諒はわずかの部下とともに小路を迂回(うかい)し、安定城へ引き返した。
★井波『三国志演義(6)』(第92回)では、崔諒が関興と張苞の両軍に挟撃されそうになったのは、南安まで50里余りの地点だったとある。
(09)安定
ところが安定城を仰げば、蜀の旌旗(せいき)ばかりではないか。城頭には魏延が声をからし、乱箭(らんせん。箭〈矢〉が乱れ飛ぶ様子)を励ます姿も見える。今は敵の深い謀(はかりごと)と悟り、崔諒は身をもって逃げるほかなく、天水郡へ落ちていく。
(10)敗走中の崔諒
すると一彪の兵馬が鼓とともに道を開いた。一叢(いっそう)の森林から、鶴氅(かくしょう。鶴の羽で作った上衣に)綸巾(かんきん。隠者がかぶる青糸で作った頭巾。俗に「りんきん」と読む)の諸葛亮が、四輪車の上に端座して前へ進んでくる。
崔諒は目がくらむ。落馬したように跳び下り、そのまま地に平伏してしまう。諸葛亮は降を容れ、彼を伴って陣地へ帰った。
(11)南安の城外 諸葛亮の本営
数日後、諸葛亮は崔諒を呼び、慇懃(いんぎん。丁寧)に尋ねた。
「いま南安には、夏侯楙が入って総大将となっているが、前からの太守とご辺とは、どのような交わりをなしていたか?」
崔諒は、隣郡でもあるので甚だ親密だと答える。南安太守の楊陵(ようりょう)は楊阜(ようふ)の族弟で、自分とも兄弟のようにしていたとも。
これを聞いた諸葛亮は膝を寄せ、親しく説いた。
「城中に入り、楊陵によく利害を説き、夏侯楙を生け捕って降りたまえ。それは貴公のみならず親友のためでもあろう」
崔諒は首を垂れ、沈痛な面色でやや久しく考え込んでいたが、やがて決然と言う。
「参りましょう。高命を果たしてお目にかけます」
諸葛亮は彼の申し入れを認め、ただちに南安の囲みを解き、全軍を20里外へ退けた。
(12)南安
崔諒は秘命を帯びて城へ入り、太守の楊陵と会談。ふたりは親友なので、ありのままを告げる。
楊陵がこう応えた。
「馬鹿を言うな。いまさら魏の恩に背いて、蜀に降伏などできるものか。むしろきみがそういう秘命を受けてきたことを幸いに、謀の裏をかき、諸葛亮に逆手を食わせてやろうじゃないか」
もとより崔諒もその気なので、ふたりはそろって夏侯楙の前に行く。この話を聞いた夏侯楙も喜び、どういう逆計でひと泡吹かせるのかと乗り気になる。
楊陵が言った。
「ご苦労でも、崔諒にもう一度敵陣へ帰ってもらうことですな。こう言うのです。『楊陵に会って降参を勧めたところ、彼も蜀に降りたい気は大いにあるが、如何(いか)んせん城中では打ち明けてともに事をなす部下の勇士も少ない。これでは警護の厳しい夏侯楙駙馬を生け捕ることができない』と」
「そこで『もし一挙に成就を思し召すなら、丞相ご自身が兵をひきいて城中へ入りたまえ。同時に城中を攪乱(こうらん)し、騒擾(そうじょう)のうちに駙馬をうかがえば、手捕りになること物をつかむごとし』と勧めるのです」
「もちろん、おびき入れてしまいさえすれば、煮て食おうと、焼いて食おうと、諸葛亮の運命はもうわが手にありですから」
崔諒は示し合わせて城を出る。そして、諸葛亮をこの手に乗せようと大いに努めた。
(13)南安の城外 諸葛亮の本営
諸葛亮はいかにも信じきったように、崔諒の言葉にいちいちうなずいてみせる。そのうえでこう言った。
「では先に、ご辺とともに蜀軍へ来た100余人の降人がおるから、あれを連れていったらいいだろう。あれならもとからご辺の部下だから、ご辺のためには手足となり、命を惜しまず働くに違いない」
崔諒は承知しながらも、丞相も屈強な一隊をお連れになり、ともに城中へ紛れ入られてはいかがですかと勧める。
すると、諸葛亮はこう応えた。
「虎穴に入らずんば虎児を得ず。私にもそれくらいの勇気はないではないが、まずはわが軍の関興と張苞のふたりを、先にご辺の隊へ加えてやろう。その後、合図をなせば、ただちに私も城門へ駆け入るとするから」
★新潮文庫の註解によると「(『虎穴に入らずんば虎児を得ず』は)危険を冒さなくては大利は得られないというたとえ。後漢の班超(はんちょう)の言葉が典拠。貧しいころの呂蒙(りょもう)も、『まさに虎穴を探らざれば、安(いずく)んぞ虎子を得ん』と言ったという(『三国志』〈呂蒙伝〉)」とある。
崔諒は、関興と張苞を連れていくのは少し具合が悪いとためらう。だが、それを忌避すれば疑われるに違いない。
まずふたりを城中で殺してから、諸葛亮をおびき入れ、予定の目的を遂げることにしよう。そう肚(はら)を決めて、固く念を押した。
「承知いたしました。では、城門から合図があり次第に、丞相も必ず時を移さず、開いてある門から突入してください」
(14)南安
日暮れを計り、一隊が南安の城下に立つ。かねての約束通り楊陵は櫓(やぐら)に現れて、いずこの勢ぞ、と怒鳴る。
崔諒も声に応じ、安定から駆けつけた味方の勢だと言い、子細を伝えるとして矢文を射込む。
楊陵がそれを解いてみると、「諸葛亮は用心深く、関興と張苞の二将を目付として、この隊に付けてよこした。しかし、城中でふたりを殺してしまうのは何でもない。かねての密計はその後で行えるゆえ、懸念なく城門を開きたまえ」としたためてある。
楊陵がこれを見せると、夏侯楙は手を打ち、さっそくふたりを殺す用意を命じた。屈強の兵100人に剣槍(けんそう)を忍ばせ、油幕の陰に伏せておき、崔諒、そして関興と張苞のふたりを待つ。
楊陵が中門まで出迎える。すぐその先に本丸の堂閣があり、前の広庭に戦時の油幕が設けられていた。
関興が先に入る。続いて張苞を通そうと思い、崔諒は体をよける。すると張苞も如才なく身をかわし、崔諒の背を前へ押し出した。
そうして抜き打ちに、「崔諒っ。汝(なんじ)の役目は終わった!」と叫んでとっさに斬り伏せる。それとともに関興も先に立つ楊陵へ飛びかかり、不意に背から剣を突き通す。
崔諒が安心して連れてきた100余人の部下も、蜀陣に捕らわれているうち、深く諸葛亮の徳になずんでいた。
加うるに、これへ臨む前に恩賞を約されてもいたので、この騒動が勃発するや否や、言いつけられた通りに八方へ駆け分け、混乱に乗じて火を放つ。
この火の手を見ると、関興と張苞の殺害が終わった合図と早合点し、城門の兵が内から門を開く。すぐそこまで来て待機していた諸葛亮の蜀軍を、わざわざ招き入れてしまったのだ。全城の魏兵が殲滅(せんめつ)に遭ったことは言うまでもない。
夏侯楙も防ぐに手立てなく、扈従(こじゅう)の一隊を引き連れたのみで、辛くも南門から逃げ落ちた。
ところが、退き口ありと思われた南門の一道こそ、かえって先のふさがっている穴だったのである。行く間もあらせず、久しく待っていた蜀の王平(おうへい)が覆い包んだ。腹心や旗本、ことごとく討ち滅ぼされ、夏侯楙も手捕りになる。
諸葛亮は南安へ入城。法を出して民を安んじ、夏侯楙は檻車(かんしゃ)の内に虜囚としておく。また諸将を一閣に寄せ、その戦功をたたえた。
宴となって祝酒を分かつと、この席で鄧芝が質問する。
「丞相には、どうして最初に崔諒の偽りを見破られたのですか?」
これに諸葛亮が答えた。
「心をもって心を読む。さして難しい理由はない。直観して、この男、真に降伏したものではないと悟ったので、それ幸いにすぐ計に用いたまでにすぎない」
さらに、崔諒の噓を利用した経緯を詳しく打ち明け、また自己の戦を評して言った。
「ただ、今度の計でひとつ功を欠いたものがある。それは天水太守の馬遵だ。彼にも同じような計を施してあったが、何としてか、城を出てこなかった。ただちに向かって天水も併せ陥し、3郡の攻略を完璧にしなければならない」
こうして南安には呉懿(ごい)を留め、安定の守りには劉琰(りゅうえん)を遣って魏延と交代させ、全軍の装備を新たに天水郡へ進発した。
★井波『三国志演義(6)』(第92回)では、(諸葛亮は)呉懿を留めて南安を守らせ、劉琰に安定を守らせることとし、自分の代わりに魏延を派遣して、軍勢を動かして天水攻略に向かわせたとある。
また、呉懿は正史『三国志』では呉壱(ごいつ)。これは(西晋の宣帝である)司馬懿(しばい)の諱(いみな)を避けているため。
管理人「かぶらがわ」より
諸葛亮の言葉。「総じて、敵が我を謀らんとするときは、わが計略は行いやすい。十中八九は必ずかかるものだ」には含蓄がありました。
これまでの彼の相手にも、計ろうとして計られた例が多く見られます。現代では武器を使わない戦いもありますが、こういう傾向は変わっていませんね。

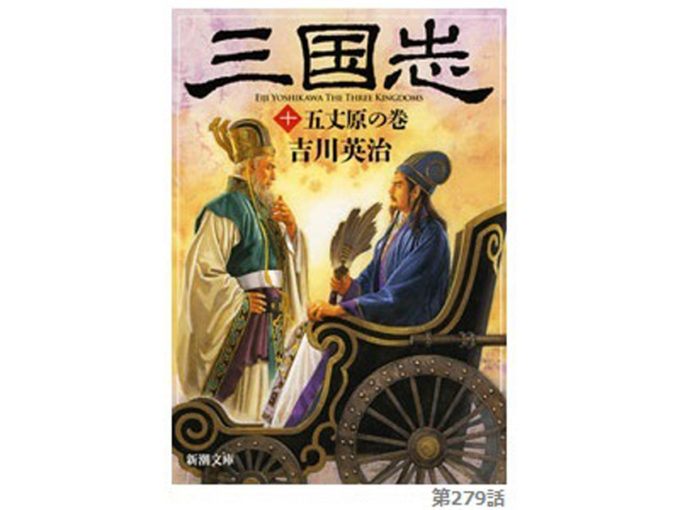















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます