安定太守(あんていたいしゅ)の崔諒(さいりょう)とは対照的に、天水太守(てんすいたいしゅ)の馬遵(ばじゅん)は、諸葛亮(しょかつりょう)の偽使者の計略にかからなかった。その陰には、姜維(きょうい)という名の若者の活躍があった。
諸葛亮は趙雲(ちょううん)に天水城を攻めさせるが、意外にも完敗。さらに諸葛亮自身も、姜維の巧みな戦略に敗北を喫してしまう。そこで別の策を用いて姜維を追い込み、ついに彼を帰順させることに成功する。
第280話の展開とポイント
(01)天水
それよりも前のこと、天水太守の馬遵は重臣を集め、隣郡の救援について議するところがあった。
主記(しゅき)の梁虔(りょうけん)が言う。
「夏侯駙馬(かこうふば。夏侯楙〈かこうも〉)は、魏の金枝玉葉。すぐ隣にありながら、南安(なんあん)の危機を救わなかったとあれば、後に必ず罪に問われましょう。即刻兵を整えて、しかるべき援護の策を取るべきでしょう」
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(駙馬都尉の)俸禄は比二千石(せき)。三国時代は皇女の夫のほか、外戚や宗室も就任した」という。
ここへ裴緒(はいしょ)という者が、夏侯楙の使いと称してやってきた。言うまでもなく、この男は、先に安定太守の崔諒のもとへも訪れていた例の偽使者である。
★諸葛亮が裴緒という偽使者を仕立てたことについては、前の第279話(06)を参照。
馬遵はそれと知る由もなく、折も折なのでさっそく対面した。裴緒は汗に濡れた書簡を出し、ここでも安定城で催促したときと同じ言葉で申し入れる。
「早々に後詰(うしろまき)して、諸葛亮の軍を突きたまえ」
書簡を開いてみると、これも同文である。だが、紛れもなく夏侯楙の親書と思われた。馬遵は拝承し、使者には客屋で休むようねぎらい、このことを重臣らに諮る。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第92回)では、(偽者の)裴緒は南安への救援を要請した後、そそくさと立ち去ったとある。
ところが裴緒は翌朝、再び城へ来て、半ば威嚇的(いかくてき)にこう告げて、立ち去ろうとした。
「事が急を要する非常の場合に、悠々ご評議で日を送っておられるようでは心もとない。ありのままを夏侯楙駙馬へご報告申しておくゆえ、後詰あるもなきも、随意になさるがよい。それがしは先を急ぎますから、今朝(こんちょう)お暇(いとま)申す」
★井波『三国志演義(6)』(第92回)では、このとき(安定から)やってきた早馬は(偽者の)裴緒とは別人だった。
後の祟(たた)りを恐れた馬遵はあわて、重臣たちも驚く。そこで、ただちに兵をひきいて救援に赴くことを約し、その場で誓書をしたためて託す。
裴緒は尊大に構え、念を押して帰った。
「よろしい。ではそのようにお伝えしておくが、安定の崔諒はすでに兵を出している時分。遅れることなく全軍の兵を発して、諸葛亮の後ろを脅かされよ」
その日のうちに廻文(かいぶん)が発せられ、天水郡の各地から続々と将兵が集まる。2日後には勢ぞろいし、馬遵自身もいよいよ城を出ようとした。
すると諸将の中から、胡蝶(こちょう)の可憐(かれん)な美しさに似たる一将が駆け出す。姜維(きょうい)という名の若武者で、「ご出陣無用、ご出陣無用」と、馬遵の駒を押さえて懸命に遮った。さらに声を励まし、身を挺(てい)して諫め続ける。
「この城を出たが最期、再び太守はお帰りになることができません。すでに太守は諸葛亮の計(はかりごと)に陥されておいでになる」
まだ年は20にも満たぬ紅顔の若者である。その素性を知らない人々は、傍らの者に聞いていた。
★史実の姜維は建安(けんあん)7(202)年生まれなので、この年(魏の太和〈たいわ〉元〈227〉年)には26歳となる。ここでは史実より若く設定されている。
同郷の者が語る。
「彼はこの天水郡冀城(きじょう)の人で、姜維、あざなを伯約(はくやく)という有為な若者です。父の姜冏(きょうけい)は、確か夷狄(いてき。未開の蛮族)との戦で討ち死にしたかと思います。ひとりの母に仕えて実に孝心の厚い子で、郷土の評判者でした」
「母も偉い婦人で、寒燈(かんとう)の夜遅く、物縫う傍らにも、常に孤(みなしご)の姜維をそばに置き、針を運ぶ間に子が群書を読むのを聞き、古今の史を教えていました。また昼は昼で耕しつつ武芸を励まし、兵学を学ばせていたということです」
「子の姜維も天才というのでしょうか、年15、6の時にはもう郷党の学者や古老でも彼の才識には舌を巻き、冀城の麒麟児(きりんじ)だと言っていたほどですよ」
そのようなうわさなども交わされながら、人々がざわめき見ているうちに、ついに馬遵も出陣を見合わせたものか、駒を下り、諸将や一族に姜維をも連れ、城閣へ戻ってしまう。
姜維は裴緒に会ってもいなかったが、それが偽使者であることは、天水城へ来るとすぐに看破していた。姜維は馬遵とその一族に向かい、掌(てのひら)を指すように敵の偽計を説いて教える。
馬遵は実(げ)にもと悟り、いまさらのごとく戦慄(せんりつ)し、彼の忠言に満腔(まんこう)の謝意を表す。年こそ若いが、姜維に対する馬遵の信頼は、このことによって、古参の宿将にも変わらない扱いを示すに至る。
馬遵はここまで問うようになった。
「今日の危難は逃れたが、明日からの難には、いかに処したらよいであろう?」
姜維は城の背後を指さして言う。
「目には見えませんが、あの搦(から)め手(城の裏門)の裏山には、もう蜀の伏兵がいっぱいに潜んでいるでしょう」
そのうえでこうも言った。
「ご心配には及びません。『彼ノ計ヲ用イテ計ルハ彼ノ力(ちから)ヲ以(もっ)テ彼ヲ亡(ほろ)ボス也』です。願わくは太守には、何もご存じない態で再びご出陣と触れられ、城外50里ほどに進まれ、すぐにまたお城へ取って返してください」
「私は別に5千騎を擁して要害に埋伏し、搦め手の山にある敵の伏兵が、虚に乗ってきたところを捕捉、殲滅(せんめつ)いたします。もしその中に諸葛亮でもいてくれれば、こちらの思うつぼです。必ず生け捕りにせずにはおきません」
★井波『三国志演義(6)』(第93回)では、このとき姜維が馬遵に求めていたのは3千の精鋭部隊。
その言は壮気凜々(りんりん)だった。一城一郡の興廃を、かかる弱冠の者のひと言に託すのは無謀であるとの意見も、一族や侍臣の内にないこともなかったが、馬遵は深く姜維に感じていたので、こう言った。
「もし姜維の観察が間違っていたところで、何も味方に損失はないことだ。ともあれ彼の献策を用いてみよう」
馬遵は再び触れを出し、その日の午(ひる)すぎから出陣を開始。南安城の後詰めに行くと唱えて、城外3、40里まで進んだ。
一方、諸葛亮の命を受け、天水城の後ろの山に旗を伏せていた趙雲(ちょううん)の兵5千。馬遵が出陣した直後、搦め手の門へ攻めかかる。
すると門内で、全城を揺るがすばかりにドッと笑う声がした。趙雲が励ましていると、続いてくる味方はない岩の山上から、鬨(とき)の声が起こる。
趙雲が振り返っている間に、土砂や乱岩、伐木などが雪崩のごとく落ちてきた。備えを改める暇もない。また、たちまち一方の沢からも鉦鼓(しょうこ)を鳴らし、一軍が奇襲してきた。
さしもの趙雲も狼狽(ろうばい)し、西の沢へ移れと号令したが、同時に城中から雨のような乱箭(らんせん。箭〈矢〉が乱れ飛ぶ様子)も加わり、倒れる部下は数知れない。
趙雲は、呼ばわりつつ追いかけてくる一騎の若武者を見て駒を止める。まさに花恥ずかしきばかりの美丈夫(びじょうふ)。
趙雲はほとんど一撃にと思って迎えたらしいが、この若武者の槍法(そうほう)たるや、世の常のものではない。
烈々と火華を交えること40余合。さすがに古豪の趙雲にはかなわじと思ったか、不意に若武者は後ろを見せて逃げる。
偽って城を出た馬遵は、城外30里ほども来ると後ろに狼烟(のろし)を見たので、すぐ全軍で引き返してきた。
すでに姜維の奇略に陥ち、散々に駆け散らされた趙雲の兵は、平路を求めて壊走してくると、ここでもまた馬遵に出会う。腹背に敵を受け、完膚なきまでに惨敗を喫した。
ただ、ここに蜀の遊軍の高翔(こうしょう)と張翼(ちょうよく)が救援に駆けつけたため、辛くも血路を開き得て、ようやく趙雲は敗軍を収めることができた。
(02)諸葛亮の本営
趙雲は諸葛亮の顔を見るや否や、衒気(げんき)でも負け惜しみでもなく、正直に言う。
「見事に失敗しました。負けるのもこれくらい見事に負けると、むしろ快然たるものがあります」
諸葛亮は大いに驚く。さらに、この計を看破した者が姜維という若年の一将だと聞くと、いったい何者かと尋ねる。
姜維と同郷の者がいて、即座に素性をつまびらかにした。
「姜維は、母に仕えて至孝。知勇人に優れ、学を好んで武を練り、しかも驕慢(きょうまん)ではありません。よく郷党に重んぜられ、また老人を敬い、誠に優しい少年です」
加えて、まだ20歳を出ていないはずだとも言う。趙雲もその言葉を裏書きした。
諸葛亮は舌を巻いて痛嘆する。自ら軍容を改めたうえ、他日、慎重に天水城へ迫った。
(03)天水
蜀軍は壕(ほり)を渡って城壁に取りつき、先手の突撃は盛んなるものだった。けれど城中は寂(じゃく)として抗戦に出ない。すでに一手の蜀軍が、城壁高きところの一塁を占領したかにすら見えた。
すると轟音(ごうおん)一声、たちまち四方の櫓(やぐら)から雨のごとき矢石が降る。壕の近くにいる兵の上にも、大木や大石が地響きして降ってきた。
昼の間だけでも、蜀軍はおびただしい死傷者を壁下に積む。さらに夜半に及ぶや、四方の森林や民家は炎と化し、鬨の声や鼓の音は、横にも後ろにも城中に湧き上がる。
ついに諸葛亮も総退却を令せざるを得なくなった。彼自身も急に車を後ろへ返したが、時すでに遅し。火蛇のごとき炎の陣は行く先々を遮る。それはことごとく敵の伏兵だった。今にして思えば、敵の大部分は城中になく、城外にいたのである。
退くとなるや、蜀勢は一度に乱れ、一律の連脈ある敵の包囲下に、随所に捕捉されて殲滅に遭った。討たれる者は数知れない。
諸葛亮の四輪車すら、煙に巻かれて炎に迷う。危うく敵中に包まれるところを、関興(かんこう)や張苞(ちょうほう)に救われて、ようやく死中に一路を得たほどである。さらに諸葛亮は姜維の軍勢とも出くわすが、戦わずにひたすら逃げて包囲から脱した。
(04)天水の郊外 諸葛亮の本営
遠く陣を退き、味方の損害をただしてみると、予想外の痛手を被っていたことがわかる。戦えば必ず勝つ諸葛亮も、ここに初めて敗戦を知った。
深思した諸葛亮は、にわかに安定郡の者を呼び、姜維の母が冀城にいること、そして天水郡の金銀兵糧が上邽(じょうけい)に蓄えられていることを聞き出す。
何か思うところがあるらしく、諸葛亮は魏延(ぎえん)の一軍を冀城へ走らせ、別に趙雲に上邽を攻めるよう命じた。
(05)天水
蜀軍の動きが伝わると、姜維は太守の馬遵に願い出て、3千騎をひきいて冀城へ行くことを許される。
姜維が道を急ぐと、途中で魏延の兵とぶつかった。しかし魏延は、あえて勝利を求めずに逃げ散った。
(06)冀城
冀城に至るや、すぐに姜維は家にいる母を守り、県城へ立て籠もる。
(07)上邽
趙雲が向かった上邽にも、天水から梁虔が一軍をひきいて救いに来た。
★井波『三国志演義(6)』(第93回)では、このとき梁虔がひきいてきた軍勢は3千。
ここでも趙雲はわざと負け、梁虔らを城へ通す。これらの予備作戦が、すべて諸葛亮の指図によるものであることは言うまでもない。
(08)諸葛亮の本営
諸葛亮は南安へ使いを遣り、捕らえておいた夏侯楙の身柄をこの地に移すよう命ずる。
★諸葛亮が夏侯楙を捕らえたことについては、前の第279話(14)を参照。
夏侯楙が命を惜しむ様子を見せると、諸葛亮が言った。
「実は、いま冀城におる姜維から、儂(み。我)へ書簡をよこして、夏侯楙を許したまわるなら、それがしも蜀に降らんと言ってまいった。そこで御身(あなた)を放つわけであるが、冀城へ行き、すぐ姜維を伴ってきてくれるか?」
夏侯楙が承諾すると、諸葛亮は衣食を与えたうえ、馬も供えて陣地から放した。
(09)冀城の郊外
夏侯楙が一騎で急ぐと、途中で大勢の避難民に出会う。聞くとみな冀城の民だと言い、県城を守っていた姜維が、蜀に降伏してしまったと話す。
もとより蜀に付く気など毛頭ない夏侯楙。放されたのを幸いに、魏へ逃げ帰る心だった。彼は急に道を変えて天水城へ向かう。その途中でも多くの避難民を見かけたが、みな異口同音に、姜維の寝返りと蜀兵の略奪を訴えていた。
(10)天水
馬遵は驚いて夏侯楙を迎え入れ、姜維が寝返ったという話を聞く。梁緒(りょうしょ)は、姜維が敵に降るなどということは信じられないと言い張った。
ところが、夜に入ると蜀軍が四門を取り巻き、柴(シバ)を積んで火を放つ。かつひとりの将が先頭に出て、声をからして叫んだ。
「城中の人々よ、よく聞け。この姜維は夏侯駙馬のお命を助けんものと、蜀に身を売って命乞いをいたしたのだ。おのおのもあたら命を無益に捨てず、我らとともに蜀へ降れ!」
馬遵と夏侯楙が櫓の上から望むと、鎧といい馬といい年ごろといい、姜維には違いないが、どうも言っていることは合点がいかない。
城下の姜維は、夏侯楙の姿を見て罵りながら城を攻めたが、やがて暁近くになると、兵をまとめて引き揚げた。
もちろんこれは本物の姜維ではない。年配や骨格のふさわしい者を選び、諸葛亮が仕立てた偽者である。けれども夜中の乱軍中に壕を隔てて見たことなので、馬遵や夏侯楙にも真偽の見分けはつかなかった。
(11)冀城
一方、本物の姜維は依然として冀城に立て籠もり、諸葛亮の軍勢に囲まれている。
姜維が籠城に際して、最も大きな苦痛だったのは、事が急だったために糧米を搬入する暇がなく、10日に足りない食糧しかなかったことだ。
ところが城中から見ていると、毎日のように多くの車が食糧を満載し、蜀の輜重(しちょう)部隊に守られて城外の北道を通っていく。
姜維は意を決して、兵糧を奪いに出た。これこそ彼が諸葛亮の手に落ちる一歩だったのである。
(12)冀城の城外
魏延・張翼・王平(おうへい)らの伏兵に待たれ、姜維は二度と冀城へ帰ることができなかった。従えて出た手勢はことごとく討ち取られ、残る数十騎も、張苞の一陣を突破するうちにほとんど死なせてしまう。
姜維はただ一騎となり、逃げるに道もなく、ついに天水城へ奔る。
(13)天水
しかし姜維が開門を求めると、意外にも櫓の上の馬遵から罵られた。
「黙れっ。汝(なんじ)の後ろには、遠く蜀の軍勢が見えるではないか。欺いて門を開かせ、蜀軍を引き入れん心であろう。匹夫め、裏切り者め、何の顔(かん)ばせあって、これへ来たか!」
姜維は仰天して、様々に事情を訴えたが、叫ぶほどに馬遵は腹を立て、辺りの弓手を励まして矢を射かけさせる。
あきれ惑いながら、姜維は目に涙をたたえ、是非なく乱箭を避け、長安(ちょうあん)のほうへ落ち延びた。そして上邽から馬首を巡らせ、長安を目指して逃走する。
★井波『三国志演義(6)』(第93回)では、姜維は天水から上邽へ行き、そこでも梁虔から罵られ、矢を射かけられていた。
(14)天水の郊外
こうして姜維が数十里も行くと、たちまち数千の軍馬をもって道を阻められる。蜀の関興の軍勢だった。
戦うすべもなく、姜維が馬を返して別の道を急ぐと、また一林の茂みが開かれる。見れば旗列を割り、一輛(いちりょう)の四輪車が進んできた。
綸巾(かんきん。隠者がかぶる青糸で作った頭巾。俗に「りんきん」と読む)鶴氅(かくしょう。鶴の羽で作った上衣)の諸葛亮は車上から羽扇を上げ、しきりに呼びかける。
「姜維、姜維。なぜ快く降参してしまわぬか。死は易し、生は難し。ここまで誠を尽くせば、汝の武門に恥はあるまい」
驚くべし。いつの間にか諸葛亮の後ろには、冀城に残してきた母が輿に乗せられ、大勢の大将に守られていた。姜維は胸がふさがり、馬を跳び下りるや否や大地にひれ伏し、すべてを天意に任せる。
諸葛亮は車を降りて姜維の手を取り、母のそばへ連れてきて言った。
「私が隆中(りゅうちゅう)の草廬(そうろ)を出てからというもの、久しい間、常に天下の賢才を心の内で捜していた。それは、いささか悟り得たわが兵法のすべてを、誰かに伝えておきたいと思う願いのうえからであった」
「しかるにいま御身に会い、日ごろの願いが足りたような気がする。以後はわがそばにいて、蜀にその忠勇を捧げないか? さすれば私もまた報ゆるに、自分の蘊蓄(うんちく)を傾けて、御身に授け与えるであろう」
母子は恩に感じて泣き濡れた。すなわち姜維はこの日以来、諸葛亮に師事して、蜀に身を置くことになったのである。
(15)諸葛亮の本営
本陣に帰ると、諸葛亮は改めて姜維を招き、礼を厚うして尋ねた。
「天水と上邽の二城を取るの法はいかに?」
姜維は答えて言う。
「一本の矢を射れば足りましょう」
諸葛亮がニコと笑い、すぐ傍らの矢を取って渡すと、姜維は筆墨を乞い、即座に二通の書簡をしたためた。彼の知る尹賞(いんしょう)と梁緒へ宛てたものである。姜維はそれを矢にくくり、天水城の内へ射込んだ。
(16)天水
矢文を拾った城兵が馬遵に見せる。馬遵は文意を見て驚き、これを夏侯楙に示して尋ねた。
「この通り、城内の尹賞と梁緒も姜維と通謀しています。どう処置いたしましょう?」
夏侯楙は、ふたりを刺殺するよう命ずる。すぐ使いを遣って招いたものの、尹賞と誼(よしみ)のある者から、このことはすでに伝えられていた。
仰天した尹賞は、友の梁緒を訪ねて誘った。
「犬死にをするよりは、いっそ城を開いて蜀軍を呼び入れ、諸葛亮に随身しようではないか」
馬遵の命を受けた軍士が屋敷を包囲し始めたので、ふたりは裏門から逃げ出して城門へ向かう。そして内から城門を開き、旗を振って蜀軍を招いた。
待ち構えていた諸葛亮は一令のもとに、精鋭を繰り込ませる。夏侯楙と馬遵は施す策もなく、わずか100余騎をひきいて北門から逃げ出し、ついに羌胡(えびす)の国境まで落ちていった。
★井波『三国志演義(6)』(第93回)では、夏侯楙と馬遵は数百の手勢をひきいて西門から脱出していた。
上邽の守将は梁緒の弟の梁虔だったので、やがて彼は兄に説伏され、蜀の軍門へ下る。
ここに3郡(南安・安定・天水)の戡定(かんてい。賊軍を平定すること)も成ったので、蜀は軍容を改めて、大挙、長安へ進撃することになった。
それに先立って諸葛亮は諸軍をねぎらい、梁緒を天水太守に推し、尹賞を冀城令(きじょうれい。冀県令)とし、梁虔を上邽令(上邽県令)に任ずる。
諸将が、なぜ夏侯楙を追わないのですかと問うと、諸葛亮は言った。
「駙馬のごときは、一羽の雁(ガン。カリ)にすぎない。姜維を得たのは、鳳凰(ほうおう)を得たようなものだ。千兵は得やすく、一将は得がたし。いま雁を追っている暇はない」
★井波『三国志演義(6)』(第93回)では、夏侯楙を一羽の鴨(カモ)に、姜維を一羽の鳳(おおとり)に、それぞれ例えていた。
管理人「かぶらがわ」より
諸葛亮の計を看破し、蜀軍に痛手を負わせた姜維。その姜維の偽者を仕立て、本物を味方に加えた諸葛亮。しかし、その母親まで使うというのは――。これでは曹操(そうそう)が徐庶(じょしょ)の時に使った手を批判できないでしょう。
★このことについては先の第127話(01)を参照。
姜維の年齢を若く設定して偉さを強調したり、彼の降伏を好意的に描いたり……。吉川『三国志』や『三国志演義』では、こういう描かれ方が目立ちますね。

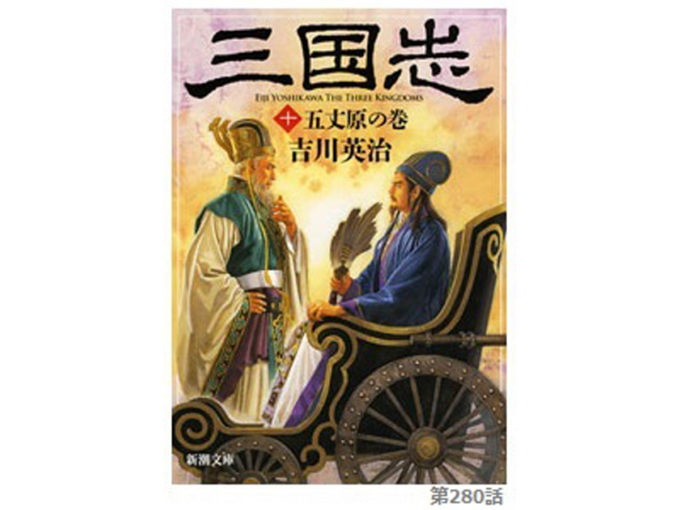















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます