諸葛亮(しょかつりょう)の計略により荊州(けいしゅう)に地盤を築いた劉備(りゅうび)は、休む間もなく荊州南部4郡の攻略に乗り出す。
最初の目的地である零陵(れいりょう)郊外において、諸葛亮は白羽扇を手に、劉度(りゅうど)配下の邢道栄(けいどうえい)と対峙(たいじ)する。
第169話の展開とポイント
(01)荊州(襄陽〈じょうよう〉?)
諸葛亮は劉備から、荊や襄の地になお遺賢がいるだろうかと尋ねられる。
そこで、襄陽宜城(ぎじょう)の人である馬良(ばりょう)や、その弟の馬謖(ばしょく)の名を挙げた。この兄弟5人はみな才名高く、世間から「馬氏の五常」と言われているとも。
★『三国志演義(4)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第52回)では、馬良や馬謖を招くよう勧めたのは伊籍(いせき)。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「馬氏の五兄弟はみな、あざなに常の字があるのでこう(馬氏の五常と)称された」という。
劉備は諸葛亮の進言を容れ、幕賓の伊籍を遣って迎える。
やがて馬良は城へ来たが、雪を置いたように眉の白い人だった。「馬氏の五常、白眉を良し」と世間に評があった。
★新潮文庫の註解によると「白眉の成語はこの故事に拠る」という。
劉備がこの先の計を尋ねると、馬良は、やはり劉琦(りゅうき)さまをお立てになることだと答える。ご病体なので、この荊州城に置かれて旧臣を呼び迎え、都(許都〈きょと〉)へ上表し、荊州刺史(けいしゅうしし)に任じてもらえるようにすべきだと。
こうすれば人心はみな、あなたのご仁徳と公明なご処置に随喜して懐く。それを強みや根本に持ち、南の4郡を切り取られたらよろしいかと思うとも。
続いて劉備が4郡の現状について尋ねると、馬良は、武陵(ぶりょう)には太守(たいしゅ)の金旋(きんせん)があり、長沙(ちょうさ)には韓玄(かんげん)、桂陽(けいよう)には趙範(ちょうはん)、零陵には劉度などが、おのおの地盤を占めていると説明。
この地方は総じて魚米の運送よろしく、地も中原(ちゅうげん。黄河中流域)に似て肥沃です。もって長久を計るに足りましょうとも。
さらに劉備が進攻順をも尋ねると、馬良は、湘江(しょうこう)の西にある零陵から手を付けるのが順序。次に桂陽、武陵と取り、最後に長沙へ進攻するのが自然かと思うと答える。要するに、兵の進路は流れる水なのだと。水の行くところが、自然の兵路と言えるのだと。
★馬良が提示した進攻路に違和感がある。武陵、零陵、桂陽、長沙の順のほうが自然ではないだろうか? なお井波『三国志演義(4)』(第52回)では、零陵、武陵、桂陽、長沙の順になっており、吉川『三国志』とは武陵と桂陽の順番が逆だった。
★井波『三国志演義(4)』の訳者注によると、「(馬良が挙げた4郡のうち)実際には武陵が最も近い」という。
賢者の言は皆ひとつで、劉備は自信を得る。味方の誰からも異論はなかった。
建安(けんあん)13(208)年の冬、劉備軍1万5千は南部4郡の征途に上る。趙雲(ちょううん)が後陣となり、劉備と諸葛亮はもちろん中軍。関羽(かんう)は留守を言いつかり、後に残って荊州を守ることになった。
★ここでは先陣に触れていなかったが張飛(ちょうひ)か? 井波『三国志演義(4)』(第52回)では張飛が先鋒、趙雲が後詰めを命ぜられ、劉備と諸葛亮は中軍となって、総勢1万5千の人馬をひきいることにしたとある。
(02)零陵
零陵太守の劉度は嫡子の劉延(りゅうえん)を呼び、劉備軍への対応を諮る。
★井波『三国志演義(4)』(第52回)では、劉度の息子は劉賢(りゅうけん)とあった。ただし井波『三国志演義(4)』の訳者注によると、「嘉靖本(かせいぼん)『三国志通俗演義』では劉延」という。
劉延は、家中の邢道栄の名を挙げて迎撃を促す。邢道栄は常に重さ60斤の大鉞(おおまさかり)を自由に遣う豪傑であるし、胸中の武芸も、いにしえの廉頗(れんぱ)や李牧(りぼく)に勝るとも劣らないのだと。
★新潮文庫の註解によると「(廉頗と李牧は)いずれも戦国時代末期、趙の名将」という。
(03)零陵の郊外
劉延は1万騎を乞い受けると、邢道栄を先陣に立てて城外30里に陣取った。
邢道栄が乱軍の中に馬を出し大音に呼ばわると、一輛(いちりょう)の四輪車が押し出されてくる。見れば、年まだ28、9としか思われぬ端麗な人物。
頭に綸巾(かんきん。隠者がかぶる青糸で作った頭巾。俗に「りんきん」と読む)を頂き、身には鶴氅(かくしょう。鶴の羽で作った上衣)を着て、手に白羽扇を持ち、悠然と乗っていた。
諸葛亮は呼びかけて、速やかに降参するよう促すが、邢道栄はわめき返すやいな、大鉞を頭上に振りかぶると悍馬(かんば)の脚を躍らせる。
★ここで諸葛亮が「南陽(なんよう)の諸葛亮孔明(しょかつりょうこうめい。孔明は諸葛亮のあざな)である」と名乗っていた。だが、史実の諸葛亮は南陽の人ではなく、琅邪郡(ろうやぐん。瑯琊郡)陽都県(ようとけん)の人である。
★またここでは、邢道栄が言い返した言葉が的を射ていたので載せておく。「わははは。聞き及ぶ孔明とかいう小利口者は貴様だったか。青二才の分際で、戦場に四輪車を用うるなどという容体ぶりからして嘔吐(ヘド)が出る。赤壁(せきへき)で曹操(そうそう)を破ったものは、呉の周瑜(しゅうゆ)の知とその兵力だ。小賢しい我こそ顔、片腹痛い」
諸葛亮の四輪車はたちまち一回転して逃げ出す。進むにも退くにも大勢の力者(りきしゃ)が押し、無数の刀槍(とうそう)で周りを守り固めていく。
邢道栄が柵門の中まで駆け込んで行方を捜していると、山の腰でジッとしていた張飛の部隊が動いた。
張飛と戦った邢道栄が見切りをつけて逃げ出すと、その先に趙雲が立ちふさがる。邢道栄は馬を下りて降参の意を示し、趙雲は縛り上げ本陣へ引っ立てた。
(04)零陵の郊外 劉備の本営
劉備は斬れと言ったが、諸葛亮がそれを止め、邢道栄にこう告げる。
「どうだ、汝(なんじ)の手で劉延を生け捕ってくれば、助命はもちろん、重く用いて遣わすが……」
邢道栄はこの話に乗り、夜を待って劉延の陣へ攻め入るよう言う。自分が内応し、劉延を擒(とりこ)にしてみせるとも。
劉備は口裏が軽々しいのを見て、重ねて首を刎(は)ねるよう促す。
しかし諸葛亮は顔を横に振りながら、邢道栄の言に噓はないようだと言い、彼の計に従って今夜のことを決行しましょうと勧めた。
(05)零陵の郊外 劉延の本営
命拾いした邢道栄は味方の陣へ逃げ帰り、劉延に子細を告げる。
劉延は、昼間の合戦で劉備軍の手並みを見ていたため奇防策を採った。すなわち、陣中の柵内には旗ばかりを立て、兵はみな別の場所に埋伏した。
その夜の二更(午後10時前後)のころ、一団の軍勢が手に手に炬火(たいまつ)を持ち、喚声を上げて近づくやいな、陣屋などへ火をかけ始める。
劉延と邢道栄はふた手に分かれて殺到し、押し包んで殲滅(せんめつ)にかかった。ふたりは逃げ退く敵兵を追いまくり、10里余りも駆ける。そして案外、逃げた兵数が少ないことに気づいた。
劉延は邢道栄を呼び止め、これだけ勝てば十分だとして引き揚げる。
ところがその帰り道、傍らから張飛の部隊が飛び出す。劉延と邢道栄はあわてふためき自陣へ逃げ込む。陣屋の火はあらかた消されていたが、余燼(よじん)の内より趙雲の部隊が現れた。
狼狽(ろうばい)し逃げ戻ろうとした邢道栄だったが、ここで趙雲の槍にかけられ無残な死を遂げる。劉延は生け捕られた。夜が白々と明けるころには諸葛亮の四輪車の前に、劉延の父の劉度もまた降伏を誓いに出ていた。
(06)零陵
劉備と諸葛亮は轡(くつわ)を並べて入城。前の太守である劉度をそのまま郡守(太守)として置き、息子の劉延を軍勢に加え、さらに桂陽へ進む。
★井波『三国志演義(4)』(第52回)では、劉延を荊州へ遣って軍務に就かせることにしたとあった。
(07)桂陽の郊外
桂陽を攻める日、まず劉備は先陣を務める将を募った。先に趙雲が手を挙げると、すぐに張飛も躍り出る。
諸葛亮は、返事が少し早かった趙雲に命ぜられてはと劉備に勧めたが、張飛は納得しない。結局、鬮(くじ)で決めることになり、趙雲が「先」の鬮を引いた。趙雲は3千の手勢を申し受け、一挙に桂陽城奪取に駆け向かう。
(08)桂陽
桂陽城には世に聞こえたふたりの勇将がいた。ひとりは鮑隆(ほうりゅう)といい、よく虎を手捕りにするといわれ、もうひとりは陳応(ちんおう)と称し、いわゆる力山を抜くの猛者だった。
太守の趙範は早く降参して旧領の安泰をすがろうと、すこぶる弱気だったが、鮑隆と陳応は強硬に抗戦を主張。やむなく趙範も陳応に4千騎を預け、城外に陣を布かせる。
★井波『三国志演義(4)』(第52回)では、このとき陳応がひきいた人馬は3千。
(09)桂陽の城外
両軍が接戦となると、趙雲は降伏を呼びかけたが、陳応に応ずる色はない。
陳応は飛叉(ひしゃ)と称する武器をよく遣う。ふた股の大鎌槍とでもいうような、すごい打ち物である。それでも趙雲に向かっては、その大道具も児戯に見えた。
十数合も戦うと、もう陳応は逃げ出していた。趙雲はこれを追い、捕らえて陣中に連れ帰る。そして陳応に訓戒を与え、今日のところは放してやるから、城中へ戻り、よく太守の趙範にも告げるがいいと諭す。陳応は野鼠(やそ)のように逃げ帰った。
趙範は「それ見たことか」と、初めに強がった陳応をかえって憎み、城外へ追い出す。そのうえで改めて降参を申し入れる。
趙雲は満足し上賓の礼を与え、酒などを出してもてなした。すっかり喜悦した趙範は兄弟の杯を乞い、4か月ほど早く生まれていた趙雲を兄と、独り決めしてしまう。
(10)桂陽
翌日、趙雲は趙範から書簡を受け取ると、50余騎をひきいて入城した。四門に高札を掲げて政令を示すと、趙範の招きで宴に臨む。
やがて趙範は席を替え、趙雲を後堂に請ずる。だいぶ酩酊(めいてい)して趙雲が帰ろうと言いだしたころ、趙範が美貌の嫂(あによめ)を引き合わせる。
この嫂が立ち去った後、趙雲はとがめた。なぜ嫂ともあろうお方を、侍婢(じひ)か何かのように軽々しく客席へ出されるのかと。
すると趙範は嫂の身の上について語りだす。まだ彼女は若いのだが、自分(趙範)の兄である夫と死別し、寡婦(やもめ)となってから3年になるのだと。もうしかるべき婿を取ったらどうだと勧めてはいるが、嫂には3つの希望があるのだと。
1つは世に高名を取り、2つには先夫と氏姓が同じ者、3つには文武の才ある人という贅沢(ぜいたく)な望みなのだと。
趙雲は失笑を漏らすが、趙範は熱心に、嫂を妻として室に入れてもらえないかと頼む。聞くと趙雲は目を怒らせ、いきなり趙範の横顔を殴りつけた。なおも散々に罵倒し、趙範を踏みつけにしたあと後堂から出ていく。
★新潮文庫の註解によると「『三国志演義』では、このとき趙雲と趙範は義兄弟になっているため、(趙範の嫂は)趙雲にとって(も)嫂にあたる」という。
趙範は起き上がってうろうろしていたが、やがて陳応と鮑隆を呼ぶと、趙雲の行き先を聞いた。
★呼び戻したのかもしれないが、この第169話(09)では、趙範が陳応を城外へ追い出したとあった。ただ井波『三国志演義(4)』(第52回)では、趙範が陳応を叱りつけ退出させたとだけある。吉川『三国志』の記述が踏み込みすぎのようだ。
ふたりは、趙雲が馬に飛び乗り城外へ駆けていったことを伝える。さらに、これから偽って趙雲の陣へ行き、彼をなだめると言い、太守は夜陰を待って急襲してくださいと持ちかける。そうすれば我々が陣中から呼応し、趙雲の首を搔(か)き取ってみせると。
こうしてふたりは趙範と示し合わせ、一隊の兵に美酒や財宝を持たせて趙雲の陣所を訪ねた。
(11)桂陽の城外 趙雲の本営
趙雲は詐術を看破していたが、わざと面を和らげ、土産の酒壺(しゅこ)を開かせ大杯を勧める。ふたりはすっかり油断し、泥のように酔ってしまう。趙雲は頃を計り、簡単にふたりの首を斬り落とした。
そして彼らの部下にも酒を振る舞い、引き出物などを与えておき、「私の手勢に付いて働けばよし。さもなくば陳応や鮑隆のようにするが、どうだ?」と、首を示して説く。500人の部下はたちまち降伏し、手勢に加わることを約した。
趙雲は、この夜のうちに降伏した500人を先頭に立たせ、後から1千余騎の本軍をひきいて桂陽城へ押し寄せる。
(12)桂陽
趙範が、陳応と鮑隆が帰ったものと思って門を開けさせると、趙雲以下の1千余騎の軍勢がなだれ込んできた。趙雲は苦もなく趙範を生け捕り、桂陽の占領が完了したことを早馬で報告。
日を経て劉備らが桂陽へ入城すると、諸葛亮はただちに趙範を引かせ、一応その口述を聞く。
子細を聞いた諸葛亮が、なぜ怒ったのかと尋ねると、趙雲は、自分も美人は嫌いではないが、趙範の兄とは遠い以前、故郷で一面識があったことを話す。
★井波『三国志演義(4)』(第52回)では、趙雲と趙範の兄に面識があったことには触れていない。
今その人の妻を私の妻としたら、世の人に唾されるだろう。また、再び嫁ぐとなれば、彼女は貞節の美徳を失う。しかも、このことを勧めた趙範の意中も真偽のほどが知れなかったのだとも。
加えて趙雲は、まだわが君が荊州を領されてから日が浅いとし、その翼臣たる自分がいち早く驕(おご)りを示しては、せっかくの大業もここに挫折するかもしれないと述べる。
劉備はこうした話を聞いたうえで、今ならばその美人を娶(めと)り、溺れない程度にそちの妻としても誰も非難する者はないだろうと、自ら仲人を買って出る。
しかし趙雲は断り、自分の武名が髪の毛ほどでも、天下に名分が立たないようなことがあってはならないと、それのみを恐れとすると言い切った。
劉備も諸葛亮も黙然と深くうなずいたまま、後は多くも言わない。このときは、あえて一片の恩賞をもって賞するにとどめた。
管理人「かぶらがわ」より
故事にまでなっている馬氏の五兄弟ですけど――。馬良と馬謖以外の3人はなぜ劉備に仕えなかったのでしょうね? 実は仕えていたものの、記録が残っていないだけとか?
なお『三国志』(蜀書・趙雲伝)の裴松之注(はいしょうしちゅう)に引く『趙雲別伝』によると、趙範の嫂は樊氏(はんし)という名(姓)で、やはり非常な美人だったということでした。
吉川『三国志』では姓が出てきませんでしたが、井波『三国志演義(4)』(第52回)でも樊氏と紹介されていました。

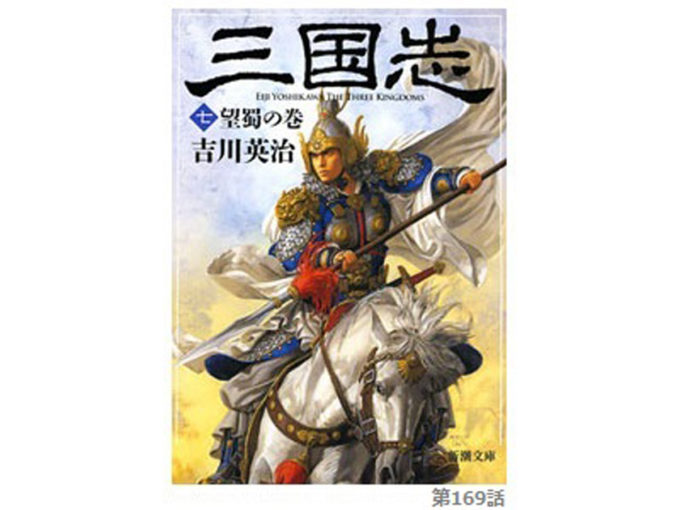













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます