赤壁(せきへき)の戦いで大勝利を収めた周瑜(しゅうゆ)は、当然のごとく荊州(けいしゅう)へ軍勢を進める。
一方の劉備(りゅうび)は油江口(ゆこうこう)まで本営を進めて留まっており、この動きを警戒した周瑜は直接会談に臨む。そして、その席で荊州併吞への強い自信を見せた。だが、事態は思わぬ方向に転がり始め――。
第168話の展開とポイント
(01)油江口 劉備の本営
劉備は戻った孫乾(そんけん)から、いずれ周瑜自ら答礼に来ると言っていたとの報告を受ける。
諸葛亮(しょかつりょう)は、まず今度は探りだけのことでしょうと言い、劉備に対談の際の受け答えを助言した。
先触れのあった日、劉備は油江口の岸に兵船を並べ、軍馬や兵旗を整々と立てて周瑜の到着を待つ。周瑜は随員と守護の兵3千騎を連れて上陸。趙雲(ちょううん)の一隊に迎えられ、陣の轅門(えんもん。陣中で車の轅〈ながえ〉を向かい合わせ、門のようにしたもの)を入る。
劉備や諸葛亮、そのほかの部将も出迎えて大賓の礼を執り、周瑜を会宴の上座へ勧めた。
酒が数巡すると劉備は杯を挙げ、しきりに赤壁の大勝を激賞しながら軽く言った。
「引き続き江北へご進撃と承り、いささか戦いのお手助けを申さんと、急きょ油江口まで陣を進めました。もし周都督(しゅうととく。周瑜)のほうで南郡(なんぐん。江陵〈こうりょう〉?)をお取りになるご意思がなければ、私の手をもって攻め取りますが――」
すると周瑜も気軽に笑って戯れた。
「どう致しまして。とんでもない。呉が荊州を併吞せんと望んでいたことは実に久しいものです。今すでに南郡は呉の掌(たなごころ)にあるものを、決してご心配くださるに及ばん」
劉備は、曹操(そうそう)が残していった曹仁(そうじん)を、北国の万夫不当と評価。おそらく周都督の手には、やすやすと落ちないのではないかと案ぜられると応ずる。
周瑜は眉の間に憤然と憤炎を表したが、すぐに皮肉な嘲笑に代え、こう言ってしまう。
「もしそれがしの手に取れなかったら、あなたの手で奪ったらよかろう」
劉備は、ここには魯粛(ろしゅく)や諸葛亮という生き証人もいると言い、念を押す。
諸葛亮も周瑜の言を褒め上げ、荊州の地は当然、まず呉軍からお攻めになるのが本当だとしたうえ、万が一にも呉の手に余ったときは、劉皇叔(りゅうこうしゅく。天子の叔父にあたる劉備)が試みに攻め取ってみられるとよいでしょうと述べた。
周瑜らが帰った後、劉備は嘆かわしい顔をして責める。だが、諸葛亮は別に一計があると言い、近いうちに必ず南郡城へ入れてみせると自信を示した。
(02)南郡(江陵?)の城外 周瑜の本営
周瑜は自陣へ帰ると、南郡城に向かって猛烈な行動を起こすべく指令を出した。先手の5千の兵は蔣欽(しょうきん)を大将とし、副将の丁奉(ていほう)と徐盛(じょせい)が続く。周瑜の中軍も前進し、堂々と城へ迫る。
(03)南郡(江陵?)の城内
このときまで城中の曹仁は、曹操が言い残した戒めを鉄則とし、ただ要害を厳しく守っていた。しかし、部下の牛金(ぎゅうきん)はしきりに出撃を願い出ていた。
曹仁は、彼の意見にも一理あるとして兵500を授けると、機を計っての奇襲を許す。
(04)南郡(江陵?)の城外
牛金は城門から突出し、敵の先鋒たる丁奉の軍勢を蹴散らした。丁奉は一騎討ちを挑むが、たちまち後ろを見せて逃げ出す。
牛金と500騎は逃げる丁奉を追いまくって深入り。にわかに返した丁奉軍は鼓を鳴らして味方を糾合し、追い疲れた牛金軍500を袋の中の鼠(ネズミ)とする。
(05)南郡(江陵?)の城内
城中の櫓(やぐら)から戦況を眺めていた曹仁は、牛金の危急を見て救いに出ようとする。だが長史(ちょうし)の陳矯(ちんきょう)は、口を極めて軽率な戦いを諫めた。
それでも曹仁は耳を貸さず、屈強な兵1千余をひきいて城外へ出たので、やむなく陳矯も櫓に駆け上り、太鼓を打って勢いを添える。
(06)南郡(江陵?)の城外
曹仁は呉軍の真っただ中に駆け入り、徐盛の一角を蹴破って牛金と合流し、首尾よく救い出した。けれど、まだ5、60騎の者が重囲の中に残されているのを知ると再び駆け入り、ひとりも余さず救って帰る。
呉の蔣欽は道を遮り、討ち止めようと試みたが、曹仁の勇は物ともせず、四角八面に奮戦。牛金もそれを助け、城中からも曹仁の弟の曹純(そうじゅん)が加勢に出て群がる敵へ当たったので、その日はうまく目的を達した。
(07)南郡(江陵?)の城外 周瑜の本営
周瑜は蔣欽や徐盛らを痛罵し、自ら南郡城をひともみに踏みつぶすと豪語。
これを甘寧(かんねい)が諫め、南郡と掎角(きかく)の形勢を作り、夷陵(いりょう。彝陵)には曹洪(そうこう)が立て籠もっていると注意を促す。
周瑜は甘寧の進言を容れ、3千騎を預けて夷陵城を攻めさせたうえ、その間に南郡城を片づけることにする。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(掎角の形勢とは)鹿を捕らえるのに後ろから足をひき(掎)、前からは角をとる(角)ように、前後が呼応して敵に当たること」だという。
(08)夷陵
南郡の曹仁は陳矯の進言を容れ、曹純と牛金に夷陵の救援を命じた。
曹純は外部から城内の曹洪と連絡を取り、力によらず、謀略を主として敵を欺こうではないかと一計を約束。
それと知らない甘寧は前進を続け、敗走する城兵を追い込み占領にかかる。曹洪も出て奮戦したが、実は策なので、たちまち支えがたしと見せかけ、城を捨てて逃げた。
日暮れに迫って甘寧の軍勢は残らず城内へなだれ入り、凱歌(がいか)を上げて誇った。
ところが曹純と牛金の後詰めに諸門を包囲され、曹洪も引き返して間道から糧道までを遮断。寄せ手の甘寧と曹純はまったく位置を替え、孤城の内に封じ込まれてしまう。
(09)南郡(江陵?)の城外 周瑜の本営
夷陵からの知らせを受けた周瑜は、程普(ていふ)らに策を諮る。程普は、甘寧を見殺しにはできないが、いま兵力を分けて夷陵へ掛かれば、敵は南郡城を出て挟撃してくるだろうと言う。
続いて呂蒙(りょもう)が、ここの抑えは凌統(りょうとう。淩統)に命じ、やはり甘寧を救うのが焦眉の急だと述べ、夷陵へ向かう先鋒を願い出る。
凌統が、10日間なら頑張ってみせると言うと、周瑜は兵1万を残し、そのほかの主力をことごとく夷陵方面へ動かした。
(10)夷陵
夷陵への道中で呂蒙が献策。夷陵の南に狭く険しい道があると言い、付近の谷へ500ほどの兵を伏せ、柴(シバ)や薪(たきぎ)を積んで道を遮っておけば、きっと後で物を言うと勧める。
周瑜はこれを容れ、その手はずを言いつけると、さらに前進して夷陵へ近づく。
夷陵城が桶(おけ)のごとく敵勢に囲まれているのを見ると、周瑜は城中の甘寧と連絡を取る勇士を募る。すると、この難役を周泰(しゅうたい)が買って出た。
周泰は陣中第一の駿足(しゅんそく)にまたがり、一鞭(いちべん)を加えて敵の包囲網へ駆け込む。
曹洪や曹純の部下たちは、ただ一騎で駆けてきた者を敵とは思わず、曹操の急使と称した周泰を止められなかった。こうして周泰は城内へ入り、甘寧に周瑜自身が救援に来ていることを伝え、一切の作戦を示し合わせる。
曹洪や曹純は、わざと甘寧を城へ誘い込んで袋叩(だた)きにするという策は、名案に似て、実は下の下策だったと悔やむ。それでも南郡の曹仁の加勢を待ち、とにかく一両日(1、2日)は頑張ってみることにする。
しかし翌日には周瑜の大軍が殺到。曹洪・曹純・牛金らはあわてふためき戦ったものの、もとより敵ではない。たちまち陣を崩して敗走の醜態を見せてしまう。
さらに、周瑜の急追を避けて山越えに出たはいいが、途中の険しい細道にかかると、道に積んである柴や薪に足を取られる。馬から谷へ落ちる者や、馬を捨てて逃げ出すところを討たれるやらで、散々な態になった。
(11)南郡(江陵?)の城内
呉軍は勝ちに乗り、途中で敵の馬を鹵獲(ろかく)すること300余頭。進撃を続けて南郡の城外10里にまで迫る。
★『三国志演義(3)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第51回)では、周瑜ら呉軍は500頭以上の馬を手に入れたとあった。
城に入った曹洪や曹純などは、兄の曹仁を囲み、暗澹(あんたん)たる顔つきをそろえていた。そして、やはり丞相(じょうしょう。曹操)のお言葉を守り、絶対に城を出ず、最初から城門を閉じて守備第一にしておればよかったと、及ばぬ愚痴をこぼしていた。
そのときふと曹仁が思い出す。曹操が都(許都〈きょと〉)へ帰る際、いよいよの危急となったら開いてみよ、と言って残した一巻があった。
(12)南郡(江陵?)の城外
南郡城を取り囲んだ周瑜は城外に組ませた井楼から敵情を眺め、敵兵がみな腰に兵糧を付け、逃げ支度をしていることに気づく。
城中の敵兵はおおよそ三手に分かれ、ことごとく外櫓(そとやぐら)や外門に出ている。本丸や主要な墻(かき)の陰には、すこぶる士気のない紙旗や幟(のぼり)ばかりがたくさん立てられているが、実は人もいない気配だった。
周瑜は自ら先手の兵をひきい、程普に後陣を命じて突撃する。群がる城兵の中から曹洪が躍り出、周瑜に名乗りかけた。
周瑜は一笑を与えたのみで、代わって韓当(かんとう)が応戦。30余合戦うと、曹洪はかなわじとばかりに引き退く。
すると今度は曹仁が駆け出し、周瑜に一戦を求める。これに周泰が応じて曹仁を退けた。
城兵は全面的に崩れ立ち、呉軍は勢いに乗り殺到。息もつかせぬ急追に、曹仁や曹洪をはじめ城門へ逃げ込み損ねた守兵は、みな城外の西北へ向かってなだれ打つ。
(13)南郡(江陵?)の城内
もう城は占領したものと思い込んでいた周瑜は、自身も城門の中へ駆け込む。
様子を門楼の上からうかがっていた陳矯は、狼煙筒(のろしづつ)に火を落とす。これを合図に、辺りの墻壁(しょうへき)の上から弩弓(どきゅう)や石鉄砲の雨が、一度に周瑜を目がけて降り注いだ。
★井波『三国志演義(3)』(第51回)では、陳矯が合図に使ったのは拍子木。
仰天した周瑜は駒を引き返そうとしたが、後から盲目的に突入してきた味方にもまれる。うろうろしているうちに足元の大地が一丈も陥没。これは落とし穴だった。穴から這(は)い上がろうとした将士は、殲滅的(せんめつてき)に討ち殺される。
周瑜は辛くも馬を拾い、門外へ逃げ出したが、一閃(いっせん)の矢が左肩に立つ。
★井波『三国志演義(3)』(第51回)では、周瑜の左肘に矢が当たり、もんどり打って落馬したとある。
周瑜が落馬すると、その首を搔(か)こうと牛金が駆け寄る。丁奉や徐盛らは馬の両膝を薙(な)ぎ払って牛金を防ぎ落とし、周瑜の体を担いで陣中へ逃げ帰った。
壕(ほり)に落ちて死ぬ者、矢に当たって倒れる者など、城の四門で同様な混乱に陥った呉軍の損害は実におびただしい。程普はあわてて総退却を命じ、南郡城から遠く後退する。
(14)南郡(江陵?)の郊外 周瑜の本営
軍医が診ると、周瑜の左肩には鏃(やじり)が残っていた。素人が下手な抜き方をしたため、矢の根元から折れてしまい、鏃が骨の中に残ったのだという。やむなく鑿(のみ)と木槌(きづち)を用い、骨を削る荒療治を施す。
苦熱は数日のうちに癒えたので、周瑜は病床から出たがった。
だが軍医は、軽々しく見てはいけないと言う。鏃には毒が塗ってあったので、何かに気を激すと、必ず骨傷と肉の間から病熱を発するだろうと。
程普は周瑜を中軍から出さないようにし、諸軍にも固く陣門を閉ざし、敵が挑んできても相手に出るなと厳戒した。
城兵は再び南郡城へ戻っていたが、牛金などはたびたび呉の陣営へ寄せてきて、散々に悪口を吐き散らす。
こうした悪口雑言を浴びせかけられても、程普はただ周瑜の病気が再発することばかり恐れていた。牛金の来訪はやまず、来ては辱めることが7回に及ぶ。
程普は、ひとまず兵を収めて国元へ帰り、周瑜の傷が完全に治ってから出直そうという意見を出したが、諸将の衆評は一致をみなかった。
こうしている間に城兵はいよいよ足元を見透かし、曹仁自身が大軍をひきいて寄せてくるようになった。当然、いくら秘しても周瑜の耳に聞こえる。
程普が味方の調練の声だと言い繕っていると、周瑜は病床から身を起こし、剣と鎧を出すよう罵る。
そして「大丈夫(だいじょうふ。意志が堅固で立派な人物)たる者が国を出てきたからには、屍(しかばね)を馬の革に包んで本国に帰ることこそ本望なのだ。これしきの負傷に無用な気遣いはしてくれるな」と言い放ち、ついに帳外へ躍り出してしまった。
★新潮文庫の註解によると「(『大丈夫たる者が……』は)馬超(ばちょう)の祖である馬援(ばえん)の故事。戦地から生きて還らない覚悟をいう」とある。
癒えきらない後ろ傷の身に鎧甲(がいこう)を着け、周瑜は剛毅にも馬に飛び乗り、自ら数百騎をひきいて陣外へ出ていく。
それを見た曹仁の兵は大いに恐れて動揺しだしたが、曹仁はまだ金瘡(きんそう。刀傷や矢傷)は治っていないと見て、皆で周瑜を嘲弄する。
周瑜の声に応じて潘璋(はんしょう)が駆け出そうとしたとたん、周瑜は矛を捨て、両手で口をふさぎながら落馬した。
曹仁が一斉に斬り入ると、呉軍は色を失い総崩れとなり、周瑜の身を拾って陣門へ逃げ込む。この日の敗色も惨たるものだった。
ところが周瑜は案外にも元気な様子で、今日の落馬はわざとしたもので、金瘡が破れたわけではないと話す。さっそく陣々に喪旗を立てて弔歌を奏で、「周瑜死せり」とうわさするよう言った。
(15)南郡(江陵?)の城内
翌日の夕方ごろ、曹仁の部下が、城外で呉の一将隊を捕虜にする。
曹仁が尋問してみると、昨夜ついに周瑜が、金瘡の再発から大熱を起こして陣没したのだという。呉軍は急に本国へ引き揚げることになったが、しょせん勝ち目はないと考え、一同談合して降参に来たのだとも。
曹仁・曹洪・曹純・陳嬉(ちんき)・牛金などは鳩首(きゅうしゅ)して密議にかかり、深更(深夜)に及んで呉陣への大襲を決行した。
★新潮文庫の註解によると「(陳嬉は)陳矯の誤りか」という。
(16)南郡(江陵?)の郊外 周瑜の本営
しかし、陣中には旗ばかり立っていて人影もない。寥々(りょうりょう)として、捨て篝(かがり)が所々に燃え残っていた。
曹仁らが疑っていると、東門から韓当と蔣欽、西門から周泰と潘璋、南門から徐盛と丁奉、北の柵門から陳武(ちんぶ)と呂蒙など、呉の名だたる手勢が猛撃してくる。
空陣の袋に入った曹仁以下の兵は度を失って騒ぎ立ち、蜂(ハチ)の巣のごとく叩かれた揚げ句、士卒の大半を討たれて八方へ壊乱した。
曹仁・曹純・曹洪などはみな南郡へ向かって逃げたが、途中で甘寧が道を遮っていたので城内に入れず、襄陽(じょうよう)方面へ遁走(とんそう)するほかなかった。
(17)南郡(江陵?)の城外
この夜、周瑜は十分に勝ち抜いて、意気すこぶる盛んに程普とともに乱軍の中を縦横し、このうえは南郡城に呉の征旗を高々と掲げんと、壕の近くまで進んでくる。
するとどういうことなのか、城壁の上には見慣れない旗や幟が、夜明けの空に翩翻(へんぽん)と立ち並んでいる。そして高櫓(たかやぐら)の上にはひとりの武将が突っ立ち、厳に城下を見下ろしていた。
周瑜が壕際から大音に尋ねると、趙雲も大音に名乗ったうえ、諸葛亮の下知を受けて城を占領したことを伝える。
周瑜はむなしく駒を返したが、すぐに甘寧を呼んで荊州城へ向かわせ、凌統には襄陽城を奪い取るよう命じた。
★これまでにも何度か触れたが、相変わらず荊州城と襄陽城との違いがわからない。このあたりで多用されている南郡(の)城というのも、実のところは江陵城だと思う。
★このうち荊州城と襄陽城については、井波『三国志演義(3)』の訳者注に指摘があった。「荊州の州庁所在地は襄陽。したがってここで荊州と襄陽を区別することはできない」という。
ところがたちまち早馬が着き、荊州城には張飛(ちょうひ)の手勢が入っていると告げる。周瑜が疑っているところへ襄陽からも早馬が着き、襄陽城にも関羽(かんう)の軍勢がいっぱいに入っていると告げた。
諸葛亮は南郡城を取るやいなや、曹仁の兵符を持たせて荊州へ人を遣り、「南郡危うし、すぐ救え」と言い送ったのだという。荊州城の守将は、この兵符を信じて救援に駆け出す。
留守を計っていた諸葛亮は、張飛を差し向け占領させる一方、同時に襄陽へも人を遣った。「われ(荊州城)いま危うし。呉の兵を外より破れ」という檄(げき)である。
襄陽を守っていた夏侯惇(かこうじゅん)も、曹仁の兵符を見ては疑っている暇(いとま)もなく、ただちに城を出て荊州城へ走った。かねて諸葛亮の命を受けていた関羽は、その後を乗っ取ってしまう。
こうして南郡・襄陽・荊州の三城は、血も見ずに諸葛亮の一握に帰したのだった。
子細を聞いた周瑜は失神せんばかりに顔色を変え、どうして曹仁の兵符が諸葛亮の手にあったのかと叫ぶ。
程普は、荊州城にいた陳矯が生け捕られたに違いないと言う。兵符は常に陳矯が帯びていたものだったと。
★井波『三国志演義(3)』(第51回)でも、諸葛亮が捕らえた陳矯から兵符を得たことが見えた。だが、これは南郡(江陵?)での出来事と思われる。吉川『三国志』で陳矯が荊州城にいたとするのは勘違いではないだろうか?
これを聞くやいな、周瑜は床に倒れる。今度は謀計ではなく、怒気を発したため金瘡が破れ、本当に再発したのだった。
人々の看護によって蘇生の色を取り戻すと、周瑜は諸葛亮を罵り、ひたすら南郡の奪回を策す。
ある日、魯粛が見舞いに来ると、周瑜は近々劉備や諸葛亮と一戦を決し、かの南郡を手に入れたうえで呉へ帰り、少し養生しようと思うと語る。
魯粛は、主君の孫権(そんけん)が先ごろから合淝(がっぴ。合肥)方面を攻めておられるようだと言い、ここで劉備との戦端を開くことに反対。
それでも周瑜は、赤壁で費やした莫大(ばくだい)な兵力と軍費に触れ、その戦果たる荊州地方を何もせぬ劉備に横取りされては黙止できないと言う。
すると魯粛は、劉備に会って道理を説いてみると言い、南郡城へ使いする。その後、南郡城の趙雲から劉備が荊州城(襄陽城?)にいると聞くと、その足で向かった。
(18)荊州(襄陽?)
魯粛は諸葛亮の出迎えを受けたが、賓主の座を分かつとすぐに責める。このたびの戦果として当然、荊州は呉に属してよいものと考えるが、ご辺(きみ)はどう思われるかと。
諸葛亮は、荊州の主権は荊州のもので、曹操のものでも呉のものでもないと答える。その理由として亡き劉表(りゅうひょう)の嫡男たる劉琦(りゅうき)の存在を挙げ、彼の叔父にあたる劉備が助け、この国を復興するに何の不道理がありましょうか、とも。
魯粛はここまでの深謀には気づいていなかったが、劉琦は江夏城(こうかじょう)にあると聞いていると反論。
すると諸葛亮は左右の従者に命じ、この場に劉琦を呼ぶ。左右の手を侍臣に取られた劉琦が姿を見せ、数歩前に歩いて立礼。諸葛亮に促されると、すぐに屛風(びょうぶ)をふさいで奥へ隠れた。
魯粛は、劉琦が亡くなるようなことがあった場合は荊州を呉に返すようにと言い、諸葛亮も同意してみせる。
(19)南郡(江陵?)の城外 周瑜の本営
戻った魯粛は周瑜に、劉琦の血色を見るに、近々危篤に陥るだろうと話してなだめる。そこへ孫権の早馬が着き、総軍みな荊州を捨てて、柴桑(さいそう)まで引き揚げるようにとの軍令を受けた。
管理人「かぶらがわ」より
かなりのボリュームがあった第168話。曹仁の兵符を用いた策はまだいいとしても、南郡の乗っ取りについては、だいぶ汚いなという印象。
周瑜の詰めが甘かったという描かれ方になっていましたが、ここでの「一摑三城」には引っかかるものも残りました。
南郡・襄陽・荊州の三城とあるうち、南郡の城というのは江陵城のことでしょうが、荊州城とは別に襄陽城が出てくるのもよくわかりませんでした。

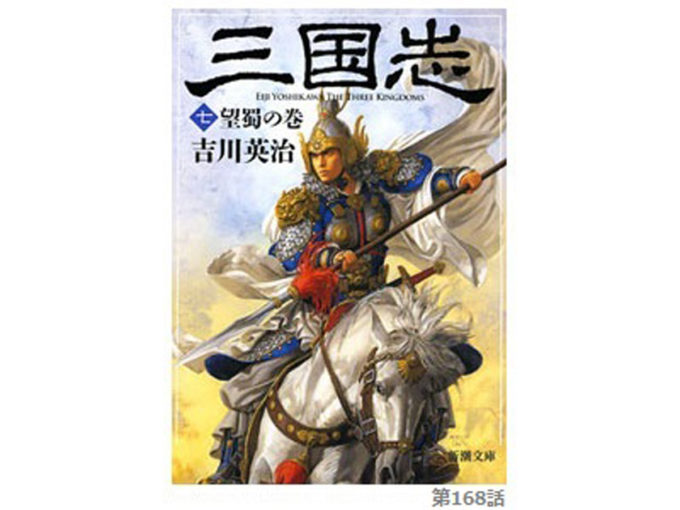













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます