周瑜(しゅうゆ)の頼みを引き受ける形で、10万本もの矢を3日のうちに調達することになった諸葛亮(しょかつりょう)。
借り受けた船20余艘(そう)に妙な細工を施すと、魯粛(ろしゅく)を伴い夜の長江へ漕(こ)ぎだす。その行き先は何と――。
第154話の展開とポイント
(01)長江
夜靄(よもや)が深く垂れ込める中、諸葛亮と魯粛らを乗せた20余艘の兵船は纜(ともづな)を長くつなぎ合い、北方へ向かい徐々に遡航していた。
魯粛は、藁(ワラ)と布でくまなく船体を覆い隠したことを「覆面の船」と表現。船団の目的をしきりに尋ねるが、諸葛亮は、夜靄が晴れたらわかると言うばかり。
(02)長江の北岸 曹操(そうそう)の本営
この夜靄に対し、曹操は宵のうちから特に江岸の警備に厳令を出していた。そして部下を督励したばかりでなく、自身も深更(深夜)まで寝ていなかった。
すると案の定、四更(午前2時前後)に近いころ、遠く水寨(すいさい)の辺りで鬨(とき)の声がする。
★『三国志演義(3)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第46回)では、諸葛亮の船団が曹操の水軍基地に近づいたのは五更(午前4時前後)とある。
不寝(ねず)の番をしていた徐晃(じょこう)と張遼(ちょうりょう)が様子を見に行くと、呉の船団が夜靄を破って現れ、水寨へ迫ってきたという。
知らせを受けた曹操は江岸の陣地へ臨み、徐晃と張遼に命じて3千の弩弓隊(どきゅうたい)を三団に作らせ、水上の防寨や望楼に拠らせて一斉に射させる。
★井波『三国志演義(3)』(第46回)では、このとき水軍を任されていた毛玠(もうかい)と于禁(うきん)も、弓や弩の射手を差し向け矢を放たせていたとあり、張遼と徐晃の指揮する3千の射手と合わせ、万余の兵士が長江に向かって矢を放ったとあった。
だが夜が明けると、江上にあった怪船団の影は見えなくなっていた。諸葛亮は江を下っていく船上から、水寨を振り向き言った。
「曹丞相(そうじょうしょう。曹操)よ、夜来のご好意を感謝する。贈り物の矢はもう十分である。おさらば!」
彼を乗せた一艘を先頭に、20余艘は満身に矢を負い、その矢のごとく下江する。厚い藁と布をもって包まれた船腹や船楼には、ほとんど船体が見えないほど敵の射た矢が立っていた。
計られたことに気づいたとみえ、曹操は無数の軽舸(けいか。速く進むことができる小舟)で追撃させたが、さっそく諸葛亮は昨夜(ゆうべ)から得た矢をもって射返す。
しかも水の流れは急で、順風は帆を助け、たちまち20余里も離され、魏船はむなしく見送ってしまった。
(03)長江
魯粛は昨夜から諸葛亮の知謀を悟り、今はまったく、その神算鬼謀にただただ舌を巻き、心服するのみだった。
さらに諸葛亮が、周瑜の真の目的は矢を得ることではなく、彼の命を得ることだったと知っていたことにも敬服させられる。
また諸葛亮は、昨夜、夜靄が出ることを予測していたとも明かし、周瑜に3日のうちと約束したのも、そうした気象の予感があったからだと話す。
(04)長江の南岸 周瑜の本営
やがて全船は無事に呉の北岸(長江の南岸)に帰り着く。兵を督して満船の矢を抜かせると、一船に約6、7千の矢が立っていた。総計で十数万という量である。
それらを一本ずつ改め、鏃(やじり)の鈍角となったものを除き、矢柄の折れたものも取り捨て、すぐに使用できるものばかりを束ね、10万の矢はきれいな山となって積み上げられた。
周瑜は、魯粛の語る始終を頭を垂れ黙然と聞いていたが、やがて面を上げ長大息する。そして自己を省みて深く恥じ、魯粛を遣り諸葛亮を迎えに行かせる。
諸葛亮が見えたと聞くと、周瑜は自ら轅門(えんもん。陣中で車の轅〈ながえ〉を向かい合わせ、門のようにしたもの)の傍らで出迎え、慇懃(いんぎん。丁寧)に師礼を執って上座に請じた。
諸葛亮が過分な優遇を怪しむと、周瑜は偽らずにこれまでの非礼を詫びる。そのうえで正客として一盞(いっさん)差し上げたいとし、なお忌憚(きたん)のない腹中を聞かせてほしいと頼む。
席を改め酒宴に移ると、周瑜は、曹操の水寨は実に法度にかなっていて容易に近づきがたいと認めたうえ、破陣の工夫を凝らしてはいるが、まだ確信を得ることができないと意見を求めた。
しばらく黙考していた諸葛亮が言った。
「ここにただひとつ、行えば成るかと思う計がある。が、都督(ととく。周瑜)の胸中もまったく無為無策ではありますまい」
そこで手のひらに一計を書き、互いに見せ合うことにする。こうして手のひらを見せると、どちらにも「火」の字が書かれていた。
ふたりは高笑いし、魯粛も杯を挙げて両雄の一致を祝す。決して人に漏らすなかれと互いに秘密を誓い合い、その夜は別れた。
管理人「かぶらがわ」より
曹操を計り、見事に10万の矢を狩ってきた諸葛亮。敵の水寨の堅固さにお手上げ状態の周瑜。手のひらに書いた最後の一計は「火」で、諸葛亮の考えとも一致。
この第154話に出てきた「草船借箭(そうせんしゃくせん)」は、井波『三国志演義(3)』(第46回)でも語られていて有名です。
また、これは『三国志』(呉書・呉主伝)の裴松之注(はいしょうしちゅう)に引く魚豢(ぎょかん)の『魏略』が基になっているようです。
建安(けんあん)18(213)年の正月、曹操が濡須(じゅしゅ)を攻めると孫権(そんけん)が防戦にあたり、両軍は1か月余り対峙(たいじ)します。このとき曹操は孫権の軍勢を眺め、少しの乱れもないことに感嘆して引き揚げました。
『魏略』には、孫権が大船に乗って軍情偵察に来たとき、曹操が弓や弩を乱射させたことが書かれており、孫権の船は突き刺さった矢で一方だけが重くなり、危うく転覆しそうになったのだといいます。
そこで孫権は船の向きを変え、もう一方の面で矢を受けました。こうして刺さった矢が均等になり、船が安定したところで自陣へ引き揚げたのだとか。
元ネタはこのほかにもあるそうですが、よくこういう話に仕上げたなという感じ。小説としてはとてもおもしろいと思います。暖を取ったり料理をしたり、火は暮らしに欠かせませんが、戦の切り札にもなるのですね。

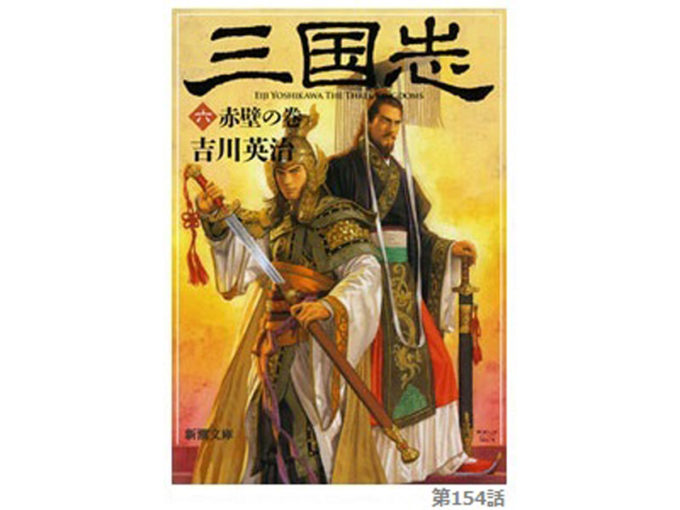













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます