会見の席で曹操(そうそう)の機嫌を損じた張松(ちょうしょう)は、声をかけてきた楊修(ようしゅう。楊脩)に誘われるまま奥書院で話をする。
なおも非難を続ける張松に、楊修が曹操の著書である『孟徳新書(もうとくしんしょ)』を紹介したところ、張松は思わぬことを言いだす。
第188話の展開とポイント
(01)許都(きょと) 丞相府(じょうしょうふ)
楊修(楊脩)は張松を奥書院に連れていき、座を勧めると、自ら茶を煮て遠来の労を慰める。そして、蜀の国情や地理などについて話を聴いた。
張松は、名門楊家の子たる者が、なぜ丞相府の一官吏となり、卑しき曹操の頤使(いし)に甘んじておられるかと言い、なぜ廟堂(びょうどう。朝廷)に立って天子(献帝)を助け、四海の政事(まつりごと)に身命を捧げようとはなさらぬかと尋ねる。
楊修は身を恥ずるがごとく、顔を赤らめたまま、しばしうつむいていたが、やがてこう言った。
「いや。丞相(曹操)の門下にあって軍中兵粮(ひょうろう)の実務を学び、また平時にはご書庫を預かり、庫中万巻の書を見る自由を許されているのは、自分にとって大きな勉強になりますからね」
すると張松は笑い、曹丞相は文武のどちらも中途半端で、ただ取り柄は覇道強権を徹底的にやりきる信念だけであると聞いている、と応ずる。
さらに張松から、曹操の大才を何か端的にお示しあるなら伺いたいと言われると、楊修は書庫の棚から一巻の書を取り出して手渡す。
題簽(だいせん)には「孟徳新書」とある。張松は、ざっと内容に目を通した。全巻13篇、すべて兵法の要諦を説いたものらしい。
★「孟徳」は曹操のあざな。
著者を尋ねると楊修は、「曹丞相がご自身、軍務の余暇に筆を執られ、後世の兵家のために著された書物です」と答える。
「古学を酌んで近代の戦術を説き、『孫子十三篇』になぞらえて『孟徳新書』と題せられる。この一書を見ても、丞相の蘊蓄(うんちく)のほどがうかがえましょう」とも。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「曹操の『孫子』注(魏武注孫子)は最も優れた解釈として、今も『孫子』理解の定番である」という。
張松は笑い、楊修の手に書物を返しながら言う。
「わが蜀の国では、これくらいな内容は三尺(さんせき)の童子も知り、寺子屋でも読んでおる。それを『孟徳新書』などとは――。あははは。新書とは人を馬鹿にしたものだ」
楊修が聞き捨てならないと言うと、張松は春秋(しゅんじゅう)戦国のころ、すでにこれとそっくりな著書が出ておると応ずる。
「著者が誰とも知れぬものゆえ、丞相はそのまま書き写し、自分の頭から出てきたもののように、無学の子弟に自慢しているものでござろう。いやはや、とんだ新書もあるものだ」とも言うと、哄笑(こうしょう)、また哄笑して笑いをやめなかった。
多少は彼に好意を持っていたらしい楊修も、その無遠慮な笑い方と大言には反感を覚えたらしく、目に蔑みを表して言った。
「いくら何でも、まさか三尺の童子がこのような難解な書を暗唱(そらん)じている、などということはありますまい。法螺(ほら)もおよそたいがいにお吹きにならんと、ただ人に片腹痛い気持ちを起こさせるだけですよ」
そのうえで、試みに御身(あなた)がまず暗唱してご覧なさいと言われると、張松は胸を正し、膝に手を置き、童子が書物を声読するように、『孟徳新書』を初めから終わりまで、一行一字も間違いなく読んでみせる。
楊修は驚いた。そして急に席を下り、恭しく張松を拝すと、曹丞相に申し上げ、改めてご辺(きみ)と対面なさるよう、お勧めしてくると言う。
楊修は褒めちぎったが、曹操はすぐに会うとは言わない。明日、衛府(えいふ)の西教場で大兵調練の閲兵をすることになっているから、彼を連れて見物に来い、と言っただけだった。
(02)許都 衛府
翌日、楊修は張松を連れて練兵場へ赴く。この日、曹操は5万の軍勢を統率し、龍爪(りゅうそう)の名馬にまたがり閲兵していた。
★龍爪の名馬というのがイマイチわからず。立派な馬だということは伝わるが……。
雄大壮絶な調練を終えると、曹操は桟敷の下へ馬を返してくる。そしてさも得意そうに、張松を見つけて呼びかけた。
「どうだな蜀客。蜀にはこういう軍隊があるか?」
さっきから張松は目を斜めにして見物していたが、ニコと笑って答える。
「ありません。が、蜀はよく文治と道義によって治まり、今日までのところ、兵革の必要がなかったのです。貴国のごとくには――」
またしても曹操の心を損じはしないかと、楊修はそばで気をもんでいた。
管理人「かぶらがわ」より
張松劇場の第二幕。このあたりのエピソードは、すべてが創作というわけではありません。張松が曹操のもとに遣わされたことや、その著書を暗唱してみせたことなどは、正史『三国志』やその裴松之注(はいしょうしちゅう)に見えます。
こうなると、楊修の年齢が若く設定されているのも効果的ですし、うまく話が組み立てられているように感じました。

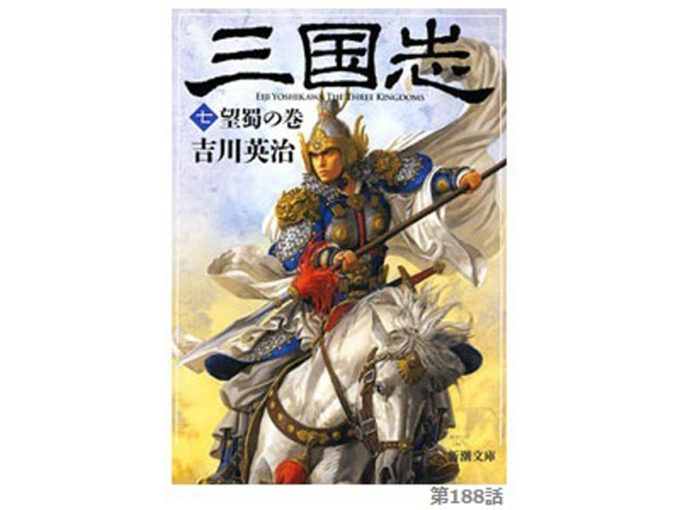













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます