蜀の地を治める劉璋(りゅうしょう)配下の張松(ちょうしょう)は、漢中(かんちゅう)の張魯軍(ちょうろぐん)の南下に対抗すべく、許都(きょと)の曹操(そうそう)の助力を得るため使者となる。
ところが曹操は張松の物言いに激怒し、会見の途中で席を立つ。この態度にあきれる張松に、あえて声をかけた若者がいた。
第187話の展開とポイント
(01)漢中
近年、漢中の土民の間を「五斗米教(ごとべいきょう)」と呼ばれる一種の道教が風靡(ふうび)していた。その宗教へ入るには、信徒になる証(しるし)として5斗の米を持っていくことが掟(おきて)になっていた。教主は師君(しくん)と称している。
素性を洗えば、蜀の鵠鳴山(こうめいざん。鶴鳴山〈かくめいざん〉)で道教を広めていた張衡(ちょうこう)という道士の子で張魯、あざなを公祺(こうき)という人物だった。
師君の張魯を巡り、治頭(じとう)や大祭酒(だいさいしゅ)などという道者が控え、その下に鬼卒(きそつ)と呼ぶ祭官が何百人とある。
★『三国志演義(4)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第59回)では、張魯に道術(仙人の術)を学びに来た者は、みな鬼卒と呼ばれる。その頭目は祭酒、大勢の鬼卒をひきいる主だった頭目は治頭大祭酒と呼ばれたとあり、吉川『三国志』の解釈とは異なっていた。
不具や病人などが祈とうを頼むと、「懺悔(ざんげ)せよ」と暗室に入れる。
7日後、名を書いたお札を、一通は山上に埋けて天神に奏するものだと言い、一通は平地に埋けて地神に詫びをすると言い、もう一通は水底に沈め、「お前の罪業は水神に願い流してもらった」と言い聞かせる。愚民は信ずるのだった。
その妄信からときどき奇跡が生ずる。すると大祭を執り行う。漢中の街は邪宗門のあくどい色で塗りつぶされ、廟門(びょうもん)には豚・鶏・織物・砂金・茶など、あらゆる奉納品が山と積まれ、5斗入りの米袋は10棟の倉庫にいっぱいになった。
こうして邪教の猖獗(しょうけつ)は年ごとに甚だしくなり、今年でもう30年にもなるが、その悪弊は聞こえても、中央に遠い巴蜀(はしょく)の地である。令をもって禁止することも、兵を向けて一掃することもできない。
そこでかえって中央政府は、教主の張魯に対して卑屈な懐柔策を取ってきた。彼を鎮南中郎将(ちんなんちゅうろうしょう)・漢寧太守(かんねいたいしゅ)に任じて、年々の貢納のみを誓わせてきたのである。
★『三国志』(魏書・張魯伝)によると、張魯は鎮民中郎将(ちんみんちゅうろうしょう)・漢寧太守に任ぜられていた。ただ、井波『三国志演義(4)』の訳者注によると「(漢寧とは)漢中郡のこと。張魯によって改められた。建安(けんあん)20(215)年、再び漢中郡となる」という。
したがって「五斗米教」は、中央政府の認める道教として、いよいよ毒を庶民に植え付け、今や巴蜀地方は一種の教門国と化していた。
するとつい最近のこと、漢中の一百姓が畑から黄金の玉璽(ぎょくじ)を掘り出し、驚いて庁に届けた。
★黄金の玉璽というのがよくわからず。金でできているなら玉璽ではなく、ただの金印なのでは? ちなみにこの件は『三国志』(魏書・張魯伝)にも見え、住民の中に地中から玉印を手に入れ(献上し)た者があったという。
張魯の群臣はみな口をそろえ、「これこそ、天が漢寧王の位に就くべしと、師君へ授けたもうたもの」と、彼に王位に就くことを勧めた。
すると閻圃(えんほ)がこのように述べる。
驕(おご)りが天井を突いた形の曹操を討つべきときに違いないが、まず我らは蜀41州を内に併合統一し、しかる後に彼に当たるのが正しいのではないか。
★ここで出てきた蜀41州は、おそらくいくつかの郡内の県を数えたものだと思うが、合算の対象はよくわからなかった。
張魯の弟の張衛(ちょうえい)も、閻圃の説こそ大計というものであると言いながら、兄に入蜀の兵馬を授けるよう乞うた。閻圃と張衛の言葉に意を動かされた張魯はこれを許し、漢中の兵馬は密かに蜀をうかがっていた。
(02)成都(せいと)
蜀の劉璋は漢の魯恭王(劉余〈りゅうよ〉)の後胤(こういん)と言われ、父の劉焉(りゅうえん)の跡を継いでいた。しかし、その家門と国の無事に慣れ、いわゆる遊惰脆弱(ぜいじゃく)な暗君だった
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(魯恭王は)景帝(劉啓〈りゅうけい〉)の皇子。劉備(りゅうび)の祖たる中山靖王(ちゅうざんせいおう。劉勝〈りゅうしょう〉)の兄弟にあたる」という。
劉璋や諸将は張魯の攻勢を聞くとおびえたが、ひとり張松が評議の席を立って言った。
「不肖ですが、それがし三寸の舌を動かして、よく張魯が軍勢を退けてご覧に入れる。乞う、ご案じあるな」
許都に上って曹操と会見し、将来の利害大計を述べ、この禍いを変じ、蜀の大幸としてみせるというのだった。
とにかく献策は用いられることになり、さっそく張松は遠く都へ使いしていくことになる。
(03)成都 張松邸
その旅行の準備にかかる傍ら、張松は屋敷に画工を雇い、西蜀41州の大鳥瞰図(だいちょうかんず)を一巻の絵巻にすべく、精密に写させていた。
画工は50日ほどかかって描き上げた。41州にわたる蜀の山川渓谷、都市村落、七道三道の通路、舟帆や駄馬の便、産物集散の模様まで、一巻数十尺(せき)の絵巻の内に写されている。
(04)成都
ただちに張松は劉璋に目通りし、出発の準備が整ったことを告げる。劉璋は、かねて用意しておいた金珠錦繡(きんしゅう)の贈り物を白馬7頭に積んで託した。もちろん曹操への礼物である。千山万峡の険阻を越え、使者の張松は都へ向かった。
(05)許都
このころ曹操は銅雀台(どうじゃくだい)へ遊びに行き、都へ帰ったばかりだった。
ひとまず張松は旅館に落ち着き、丞相府(じょうしょうふ)に入国の届けを出す。また、迎使部(げいしぶ)の吏を通じて姓氏や官職などを拝謁簿に記録し、沙汰があるのを待っていた。
ところが、幾日経っても召しがない。張松が怪しんでいると旅亭の館主が、「それは姓氏を簿に書き上すとき、吏員に賄賂を贈らなかったからでしょう」と注意してくれた。
そこで館主を通じて吏員に莫大(ばくだい)な賄賂を贈ると、ようやく5日目ごろに沙汰があり、曹操に目通りすることができた。
(06)許都 丞相府
曹操は一眄(いちべん)をくれ、「なぜ蜀は毎年の貢ぎ物を献じないのか?」と罪を責める。
張松は応え、「蜀道は険阻なうえ、途中に盗賊の害が多く、到底、貢ぎを送るすべもありません」と言った。
曹操は、甚だしく威厳を損ぜられたような顔をして言う。
「中国の威は四方にあまねく、諸州の害を払って、予は今や居ながらに天下を治めておる。何で交通の要路に野盗乱賊が出没しようか」
★ここは原文「中国の威は、四方に遍く、諸州の害を掃(はら)って、予は今やいながらに天下を治めておる……」とあった。「中国の威」「四方に遍く」「諸州の害を掃って」にはいずれも読点が打たれていたが、イマイチ文意が捉えづらい。
「四方に遍く」だけでは「隅々まで全体に」という意味にしか受け取れず、「及ぶ」などの一語が不足している印象。むしろ「中国の威は、四方に遍く諸州の害を掃って、予は今やいながらに天下を治めておる……」と取るほうがいいのかも?
これに張松が応ずる。
「いやいや、決してまだ天下は平定されていません。漢中に張魯あり、荊州(けいしゅう)に劉備あり、江南に孫権(そんけん)あり。加うるに緑林山野、なお無頼の巣窟に適する地方はどれほどあるかわからない」
曹操は急に座を立ち、ぷいと後閣へ入ってしまった。激怒した様子である。張松はポカンと見送っていた。階下に整列していた近臣も興を醒(さ)まし、張松の愚を笑った。
すると張松は、低い鼻の穴から嘲笑を漏らす。
「さてさて、魏の国の人は噓で固めているとみえる。わが蜀には、そのような媚言(びげん)やへつらいを言う佞人(ねいじん)はいない」
★佞人は口が上手で、相手に気に入られようとして、お世辞を言ったり機嫌を取ったりする人。
そこへ声が響いた。
「黙れ。しからば魏人は諂佞(てんねい)だというか」
張松が驚いて振り向くと、文化的な感じのする青年が、侍立の諸臣の内からつかつかと進んで彼の前に立つ。
年のころ、まだ24、5歳。一門から六相三公を出している名家の楊震(ようしん)の孫で楊修(ようしゅう。楊脩)、あざなは徳祖(とくそ)という。
★楊修は先の第92話(03)で(楊徳祖として)既出。
史実の楊脩は熹平(きへい)4(175)年生まれ。建安(けんあん)16(211)年の時点では37歳。さらに楊震は楊修の祖父ではなく、ずっと前代の人で、楊修の父である楊彪(ようひょう)の曾祖父にあたる。だが、ここは文字通りの「まご」ではなく、「同じ血筋の者」という意味合いで使われているため誤りとは言えない。
いま曹操に仕えて楊郎中(ようろうちゅう)と呼ばれ、内外の倉庫の主簿(しゅぼ)を務めていた。
「外国の使臣とはいえ、黙って聞いておれば怪しからんことを言う。少しきみに談じつける儀があるから、僕に従ってこちらへ来たまえ」
そう言うと、楊修は張松を閣の書院へ引っ張っていった。張松は彼の魅力に何か心を引かれたので、黙って後についていく。
管理人「かぶらがわ」より
舞台は漢中から成都、そして許都へ。『三国志』にはクセのある人物が数多く登場しますが、張松もそのひとり。曹操を相手に言いたい放題でした。

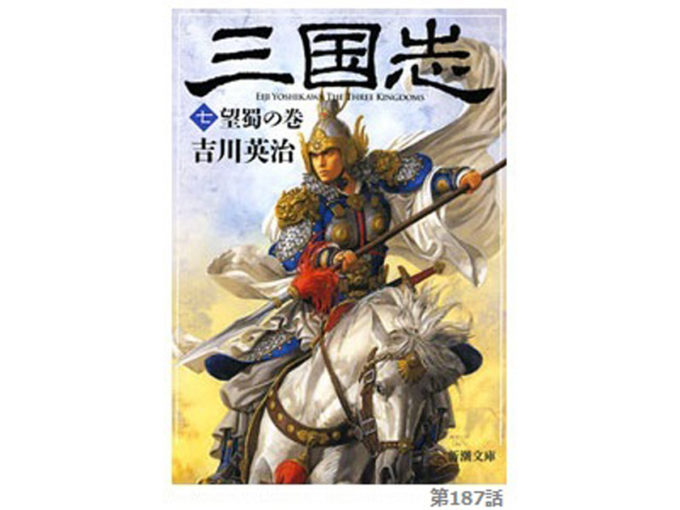














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます