鄱陽湖(はようこ)で水軍の調練にあたっていた周瑜(しゅうゆ)は、孫権(そんけん)から柴桑(さいそう)に来るよう呼び出しを受けた。
そして、ちょうど訪ねてきた魯粛(ろしゅく)から事情を聴くと、彼が呉へ連れてきたという諸葛亮(しょかつりょう)に会う。しかし、その席で諸葛亮は周瑜の心を揺さぶる話をする。
第148話の展開とポイント
(01)これまでの周瑜
周瑜は、呉の先主の孫策(そんさく)と同い年だった。また、妻(小喬〈しょうきょう。小橋〉)が孫策の妃(きさき。大喬〈たいきょう。大橋〉)の妹だったので、孫権とは義兄弟にあたっていた。
廬江(ろこう)の生まれで、あざなを公瑾(こうきん)という。孫策に知られて将となるや、わずか24歳で中郎将(ちゅうろうしょう)になったほどの英俊だった。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(中郎将は)将軍に次ぐ武官。俸禄は比二千石(せき)」という。
だから当時、呉の人々はこの年少紅顔の将軍を「軍中の美周郎」と呼んだり、「周郎、周郎」と持て囃(はや)したりしたものだった。
彼が江夏太守(こうかたいしゅ)だったとき、喬公(きょうこう。橋公)という名家の二女を手に入れた。ふたりとも絶世の美人で、「喬公の二名花」と言えば呉で知らない者はなかった。
孫策は姉を入れて妃とし、周瑜は妹を迎えて妻とした。孫策はまもなく世を去ったので姉のほうは未亡人となっていたが、妹のほうは今も周瑜のまたなき愛妻として、国元の家を守っていた。
周瑜は音楽に詳しく、多感多情な風流子でもあった。宴楽の時などに楽人(がくじん)の奏でる調節(ふし)や譜に間違いがあると、どんなに酔っていても奏手を振り返り、注意するような目をするのが常だった。
(02)鄱陽湖のほとり 周瑜の官邸
こういう周瑜も、今は孫策亡き後の呉の水軍提督(すいぐんていとく)たる重任を負っている。鄱陽湖へ来てからは家に残してある愛妻を見る日もなく、好きな音楽に耳を洗う暇(いとま)もなく、ひたすら大水軍建設にあたっていた。
今日も舟手の訓練を閲し、湖畔の官邸に引き揚げて来ると孫権から早馬が着く。柴桑城へ出向くようにとのことだった。
★『三国志演義(3)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第44回)では、孫権が周瑜を柴桑へ召す使者を出発させる前に、すでに鄱陽を発っていた周瑜が柴桑へ到着している。ということで井波『三国志演義(3)』(第44回)では、これ以降のくだりは柴桑にある周瑜邸での出来事として描かれていた。
ひと休みして出立の用意をしていたところ、日ごろ親密な魯粛が訪ねてくる。魯粛は諸葛亮が来ている事情から、群臣の意見がふたつに割れている実情などをつぶさに話す。周瑜が諸葛亮に会うと言うと、魯粛は馬を返して呼びに行く。
するとその日の午(ひる)すぎ、張昭(ちょうしょう)・顧雍(こよう)・張紘(ちょうこう)・歩隲(ほしつ。歩騭)などの非戦派が打ちそろい訪ねてくる。
彼らは魯粛の動きを批判し、開戦に反対する意見を論じ立てた。自分も同感だと答える周瑜だったが、ひとまず4人を帰らせる。
しばらくして、黄蓋(こうがい)・韓当(かんとう)・程普(ていふ)らの武将連が訪ねてきた。武将たちは文官らの弱音を批判し、即時開戦の急を激越な口調で論ずる。
自分ももとより曹操(そうそう)ごときに降る気はない、と応ずる周瑜。皆をなだめてひとまず帰す。
夕方に迫ったころ、また客が来る。闞沢(かんたく)・呂範(りょはん)・朱治(しゅち)・諸葛瑾(しょかつきん)らの中立派だった。
周瑜が諸葛亮の兄である諸葛瑾に考えを問うと、そういう立場ゆえ、わざと商議に関わらず、心ならずも局外に立ち、この紛論を眺めているとの答え。
周瑜は、兄であるとか弟であるとかいうことは私事だとし、呉臣としての考えを尋ねる。
すると諸葛瑾は、呉の安全を考えるなら戦わぬに限ると思うと答えた。
ともあれ大事一決の議は明日、それがしが君前に伺った後にすると言い、皆を帰らせる周瑜。
夜に入っても、呂蒙(りょもう)や甘寧(かんねい)といった将軍や文官たちが入れ替わり立ち替わり訪れては、たちまち出ていった。
こうして夜が更けたころ、取り次ぎの者が周瑜にそっと耳打ちする。魯粛が諸葛亮を連れてきたという。
ほかの客とは別に、奥の水亭の一室へ通すよう言いつける周瑜。それから大勢の雑客に向かい、すべては明日、君前で一決すると告げ、皆を追い返すように別れる。
一同が帰った後、周瑜は衣を更(か)え、魯粛と諸葛亮を待たせてある水閣へ向かう。
★新潮文庫の註解によると「更衣は着替えという意味から転じて、高貴な者が厠(かわや)へ行くこと」だという。
そこで初対面の挨拶を交わすと、続いて酒宴となる。周瑜と諸葛亮はさながら10年の知己のように、和やかな会話をやり取りした。
やがて座を巡る佳人も退き、主客3人となったのを見澄まして、魯粛が周瑜に最終決断を尋ねる。そして彼が曹操に降伏する考えだと知ると、激しく反論し始めた。
ふたりの激越な言い争いを見ていた諸葛亮は手を袖に入れ、何がおかしいのかしきりと笑いこけていた。
周瑜があえてなじると、諸葛亮は、魯粛どのがあまりに時務に疎いので、つい笑いを忍び得なかったと応ずる。
魯粛が色をなすと、諸葛亮は、国の滅亡もほとんど成り行きに任せているような呉の諸将の中にあって、ひとり粛兄(兄は主に先輩や同輩の名に添える尊敬語)だけが主義を主張し続け、今も提督(周瑜)に向かい無駄口を繰り返しておられるから、ついおかしくなったのだと言う。
周瑜はいよいよ苦りきるし、魯粛もまた甚だしく不快な顔をしてみせた。諸葛亮が言っていることはまるで反戦的だったからである。
ここで諸葛亮は、「呉の名誉も存立も事なく並び立つように、いささか一策を描き、その成功を念じている」と言う。
周瑜と魯粛が詳しい話を促すと、ただ一艘(いっそう)の小舟とふたりの人間を贈り物にすればいいとのこと。さらに、そのふたりは女性なのだとも。
諸葛亮は、隆中(りゅうちゅう)に閑居していたころに知人から聞いたとして、銅雀台(どうじゃくだい)を造営した曹操が、なおもうひとつ大きな痴夢を抱いていると話す。
★銅雀台については先の第122話(01)を参照。
それは、喬家の二女を銅雀台に置き、朝夕そばで眺めたいという野心なのだと。
諸葛亮は周瑜に、さっそく人を遣り喬家の門へ黄金を積み、二女を求めて曹操のもとへお送りになれば、たちどころに攻撃は緩和され、血塗らずして国土の難を救うことができると勧めた。
「これすなわち、范蠡(はんれい)が美姫の西施(せいし)を送って強猛な夫差(ふさ)を滅ぼしたのと、同じ計になるではありませんか」とも。
★新潮文庫の註解によると「范蠡は越王勾践(こうせん)に仕えた名臣。呉王夫差に美女の西施を贈って国を傾けさせた」という。
周瑜は顔色を変え、その話が巷(ちまた)の俗説ではない証拠を見せてほしいと言う。
そこで諸葛亮は、曹操が息子の曹子建(そうしけん。子建は曹植〈そうしょく〉のあざな)に作らせたという「銅雀台の賦(ふ)」を吟ずる。
★ここで曹子建(曹植)が曹操の第二子だとあった。先の第122話(01)でも触れたが、仮に戦死した曹昂(そうこう)を数に入れないとしても、曹丕(そうひ)と曹植の間には曹彰(そうしょう)がいるので、曹植を第二子とするのは適切でない。
不意に卓の下で、ガチャンと何か砕ける音がする。周瑜が手の酒盞(さかずき)を落としたのだった。そればかりか髪の毛はそそり立ち、面は石のごとくこわばっていた。
諸葛亮は酒盞を重ねる周瑜をいぶかってみせ、匈奴の勢いが盛んだったころ、天子が涙を吞んで胡族(えびす)の主に皇女を娶(めあわ)せ、一時の和親を保っている間に弓馬を磨いた例もあるとか――。
(前漢の)元帝(劉奭〈りゅうせき〉。在位、前48~前33)が王昭君(おうしょうくん)を胡地(こち)へ送った話も有名なものではないか、などと言い、なぜ民間の二女を送るぐらいなことを惜しむのかと問い返す。
ここで周瑜は、喬家の二女が養われて民間にあったことは事実だが、姉の大喬は早くに先君の孫策の室に迎えられ、妹の小喬は自分の妻になっているという事情を伝えた。
これを聞いた諸葛亮は打ち震えてみせながら、平謝りに詫び入る。
周瑜は一転して開戦の肚(はら)を固め、翌日の評議に臨むことになった。
管理人「かぶらがわ」より
舞台は柴桑から鄱陽湖へ。「銅雀台の賦」を用いて周瑜の感情を逆なでする諸葛亮。
ですが大局を見るなら、先君と自分の妻を侮辱されたという一事をもって、この重大な決断が変わるものかな? という感想も持ちました。
もしここで孫権が組んでくれなければ、ほどなく劉備(りゅうび)は終わりだった可能性が高いと思うのですけど……。この時点で孫権があっさり曹操に降るというのもあり得ない気がします。

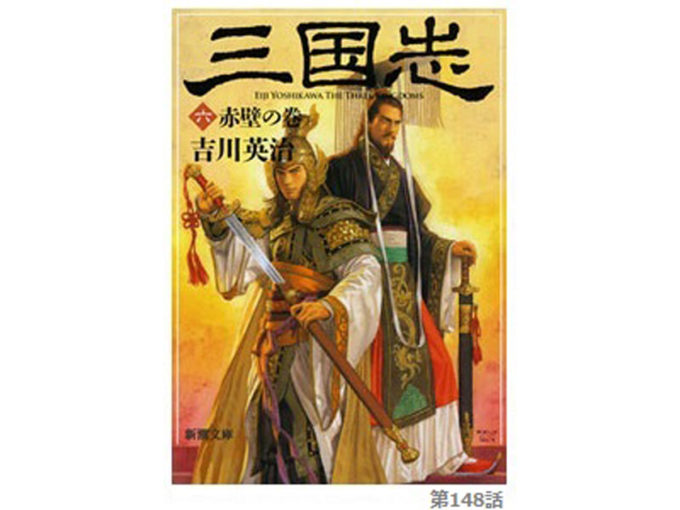














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます