西羌(せいきょう)の鉄車隊を鮮やかに撃破し、祁山(きざん)の本営に戻った諸葛亮(しょかつりょう)。魏の曹真(そうしん)は敗戦を重ね、渭水(いすい)から総退却せざるを得なくなる。
ここで曹叡(そうえい)は鍾繇(しょうよう)の進言を容れ、先に追放した司馬懿(しばい)を再び起用し、平西都督(へいせいととく)に任ずる詔(みことのり)を下す。
第283話の展開とポイント
(01)洛陽(らくよう)
渭水からの早馬は櫛(くし)の歯を引くように、洛陽へ急を告げる。そのことごとくが敗報だった。
魏の曹叡は色を失い、群臣を会して、誰かいま国を救う者はなきや、と憂いに満ちて言う。
華歆(かきん)は曹叡自身の出馬を勧めるが、太傅(たいふ)の鍾繇は反対して述べた。
「『彼ヲ知リ、己ヲ知ルトキハ百度戦ッテ百度勝ツ』と古語にあります」
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(『彼ヲ知リ……』は)『孫子』謀攻篇のことば。『知彼知己者、百戦不殆』」であるという。
「曹真は初めから諸葛亮の相手としては不足でした。いま天子(曹叡)御自らご進発あらせられても、その短を補うほどの効果は期しがたく、万一また敗れんか、魏一国の生命に関わりましょう」
「むしろこの際、野に隠れたる大人物を挙げ、彼に印綬(いんじゅ。官印と組み紐〈ひも〉)を下したもうて、諸葛亮をして窮せしめるにしく策はございません」
曹叡が忌憚(きたん)なくその人物を挙げよと促すと、鍾繇は続けて言った。
「その人とは、かの司馬懿であります。先年、敵の反間に乗せられたまい、市井の流言を信じて彼を追放なさったことは、返すがえすも惜しいことでございました」
「聞くところによりますと、いま司馬懿は郷里の宛城(えんじょう)に閑居しておるとか。あの大英才を国家が埋もれ木にする法はございません。よろしく今日こそお召しあるべきです」
★司馬懿は河内郡(かだいぐん)温県(おんけん)の出身。ここで(南陽郡〈なんようぐん〉の)宛県(宛城)を郷里としているのは不可解。
なお『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第94回)では、鍾繇が「近ごろ聞いたところでは、(いま司馬懿は)宛城に閑居している由です」とだけ言っており、宛城が郷里であるとまでは言っていなかった。
曹叡は、司馬懿を退けたことが過ちだったと認め、勅使に平西都督の印綬を持たせ、このような詔を伝えさせる。
「汝(なんじ)、国を憂い、南陽諸道の軍馬を糾合し、日を期して長安(ちょうあん)に出るならば、朕また鸞駕(らんが。天子の車)を備えて長安へ向かい、相会してともに諸葛亮を破らん」
(02)祁山 諸葛亮の本営
そのころ祁山の陣にある諸葛亮は、連戦連勝の機を外さずに、一挙、魏の中核を突かんものと準備していた。ところへ白帝城(はくていじょう)から、李厳(りげん)の息子の李豊(りほう)が唐突にやってくる。
諸葛亮は、呉が動きだしたのではと考えたが、父に代わってお喜び事を伝えに来たのだという。李豊は、荊州(けいしゅう)で関羽(かんう)が敗れた後、魏に降った孟達(もうたつ)の話を持ち出す。
孟達は、ひとたび曹丕(そうひ)の信寵を受けたものの、曹叡の代になってからは、ほとんど顧みられなくなったのだという。
ことに近ごろは、何かにつけ軽んぜられ、以前蜀臣だった関係から猜疑(さいぎ)の目で見られるので、怏々(おうおう)として楽しまない心境にあるのだと。
彼の部下も今では、故国の蜀を慕う者が多く、祁山や渭水の戦況を聞き、なぜ蜀を離れたかを、いたく後悔しているのだとも。
そこでついに孟達は、そうした心境を綿々と書中に託し、「どうかこの趣を丞相(じょうしょう。諸葛亮)にお取り次ぎいただきたい」と、帰参の斡旋方(あっせんかた)を、白帝城の李厳にすがってきたものだった。
さらに李豊は、父の李厳が孟達と会って話を聞いたことも伝える。
その際、孟達は帰参の執り成しを頼み、もしお聞き入れくださるなら、このたび丞相が長安へ攻め入られるとき、自分は新城(しんじょう)・上庸(じょうよう)・金城(きんじょう)の勢を集めて、ただちに洛陽を突き、不日に魏国を崩壊させてお見せすると言ったのだとも。
★このとき孟達は新城太守(しんじょうたいしゅ)を務めていたはずだが、上庸はいいとしても、ここで(涼州〈りょうしゅう〉に属する)金城の名も見えているのはよくわからなかった。
なお『続漢書』(郡国志)の劉昭注(りゅうしょうちゅう)によると、(孫盛〈そんせい〉の)『魏氏春秋』に「建安(けんあん)25(220)年、(魏の曹丕が)南郡(なんぐん)の巫県(ふけん)・秭帰(しき)・夷陵(いりょう)・臨沮(りんしょ)、ならびに房陵(ぼうりょう)・上庸・西城(せいじょう)の7県を分け、新城郡を設置した」とあるという。
これを聞いた諸葛亮は、手を打って限りなく喜ぶ。李豊を厚くねぎらい、幕将たちとともに酒宴を催した。そこへ早馬が着いて告げる。
「魏の曹叡が宛城へ勅使を遣わし、閑居の司馬懿を平西都督に任じ、強って彼の復帰を促しているようにうかがわれます」
諸葛亮は愕然(がくぜん)と首を垂れ、その酔色すら一度にあせてしまった。そばにいた馬謖(ばしょく)は、むしろ怪しむかのように尋ねる。
「丞相、いかがなさいました。何をそのように驚きあそばすのですか? たかが司馬懿ごときに」
諸葛亮は重く頭(かぶり)を振り、反対に馬謖を諭した。
「わが観るところでは、魏で人物らしい者は、司馬懿ひとりと言ってもよい。私の密かに恐るる者も、実にその司馬懿一個にあった」
「いま孟達の内応を喜び合っていたところだが、それすら悪くすると、司馬懿のために覆されるかもしれん。実に悪い折に悪い者が魏に立った」
諸葛亮は宴席を中座し、孟達に与える書簡をしたためる。その夜、急使はすぐに発ち、孟達のいる新城へ急いだ。
(03)新城
やがて孟達が喜色満面に書簡を開くと、帰参のことは許されていたが、終わりの章に少し気に食わない辞句がある。
それは、曹叡の命によって宛城の司馬懿が立ったことを告げたもので、司馬懿の知略を少なからずたたえ、それに対処する万全の策を、何くれとなくこまごまと注意してあることだった。
「なるほど。うわさのごとく、諸葛亮は疑い深い仁(ひと)だ……」
孟達はあざ笑い、ほとんど歯牙にもかけず、書簡を巻いてしまう。そして自分からも返書を書くと、使いの者に持たせて帰した。
(04)祁山 諸葛亮の本営
待ちかねた返書が届く。だが諸葛亮は一読するや否や、「咄(とつ。舌打ちする様子)、何たる浅慮者(あさはかもの)だろう」と、拳の中に握りつぶす。
馬謖が、何をお嘆きですかと尋ねると、諸葛亮は言った。
「馬謖か。この手紙を見てみよ。孟達の書簡によれば、たとえ司馬懿が新城へ寄せてくるにしても、洛陽へ上って任官の式を行い、それから出向いてくることゆえ、早くてもひと月余りはかかる。その間に守備は十分に整うから心配はご無用としたためてある」
「司馬懿のごとき何する者ぞと、ひとり暢気(のんき)に豪語を並べておるではないか。もう駄目だ。もういかん」
さらに馬謖が理由を問うと、諸葛亮はこう続ける。
「『ソノ備エザルヲ攻メ、ソノ不意ニ出(い)ヅ』。これしきの兵法を活用できぬ仲達(ちゅうたつ。司馬懿のあざな)ではない」
★新潮文庫の註解によると「(『ソノ備エザルヲ攻メ……』は)『孫子』始計篇のことば。『攻其無備、出其不意、此兵家之勝』」であるという。
「おそらく彼は洛陽に上ることを後とし、直線に宛城から孟達を突くだろう。その日数は、こちらから再び孟達へ戒告の使いを遣るよりずっと早い。事すでに遅しだ――」
それでも諸葛亮は、すぐにまた戒告の一書を封じ、「昼夜馬を飛ばしていけ」と、新城へ使いを走らせておく。
(05)宛城 司馬懿邸
郷里の田舎に引き籠もっていた司馬懿は、退官後まったく閑居の好々爺(こうこうや)に成り済まし、司馬師(しばし)と司馬昭(しばしょう)というふたりの息子を相手に、しごく麗らかに暮らしている。この息子たちも胆大知密。いずれも兵書を深く究め、父の目から見ても末頼もしい好青年だった。
★史実の生年から計算すると、この年(魏の太和〈たいわ〉元〈227〉年)には司馬懿が49歳、司馬師が20歳、司馬昭が17歳となる。
そこへ曹叡の勅使がやってくる。司馬懿は大命を拝受すると同時に、一族や郎党を集め、ただちに宛城の諸道へ檄文(げきぶん)を配布させた。日ごろ彼の名を慕い、彼の風を望む者は少なくない。たちまち郷関は軍馬で埋まる。
★この第283話(01)で触れたような事情から、ここで宛県(宛城)を郷関と表現することにも問題がある。
しかも司馬懿は、兵員が予定数に達することなど悠々と待ってはいない。その日から行軍を開始していたのである。募りに遅れた兵は、後から追いかけて軍に投じた。そのためこの行軍は、道を進んでいけばいくほど数を増す。
なぜこう急いだかと言えば、それには重大な理由がある。司馬懿は田舎にいても魏蜀の戦況はつぶさに聞いていたし、近ごろ新城の孟達に反意の兆しが見えることも、密かに耳にしていたのだ。
それを密告してきたのは、金城太守の申儀(しんぎ)の一家臣。すでに孟達は金城と上庸の両太守に秘事を打ち明け、洛陽攪乱(こうらん)の計をそろそろ画策し始めていたのである。
★『三国志』(蜀書・劉封伝〈りゅうほうでん〉)によると、申儀は(蜀から)魏に降伏した後、魏興太守(ぎこうたいしゅ)に任ぜられ、員郷侯(いんきょうこう)に封ぜられている。
★申儀の魏への降伏については、先の第245話(04)を参照。
(06)行軍中の司馬懿
司馬懿は洛陽へは向かわず、一路新城を指して急いだ。息子たちは少し案じたが、司馬懿は洛陽へ上っている暇(いとま)はないと言う。彼が急ぎに急いでいた理由は、諸葛亮が恐れつつも予察していたところと、まったく合致していたのである。
管理人「かぶらがわ」より
司馬懿の閑居が(河内郡の)温県ではなく(南陽郡の)宛県(宛城)にあったという設定は、初めはどうかと思いました。
しかし考えてみると、司馬懿が新城まで急行したという史実を使う以上、温県から駆けつけたとすると日数的に厳しくなりそう。温県から出て洛陽を素通りするというのも、宛県から出たとするよりも妙な感じになってしまいます。
そもそも史実では、このころ司馬懿は驃騎将軍(ひょうきしょうぐん。驃騎大将軍とも)のままで、官職を剝奪されていません。宛県は郷里ではなく駐屯地だったのですよね。
司馬懿の扱いをイジった結果、宛県に駐屯していた司馬懿を、郷里の宛県に引き籠もっていた司馬懿に変えざるを得なくなったのでしょうか?

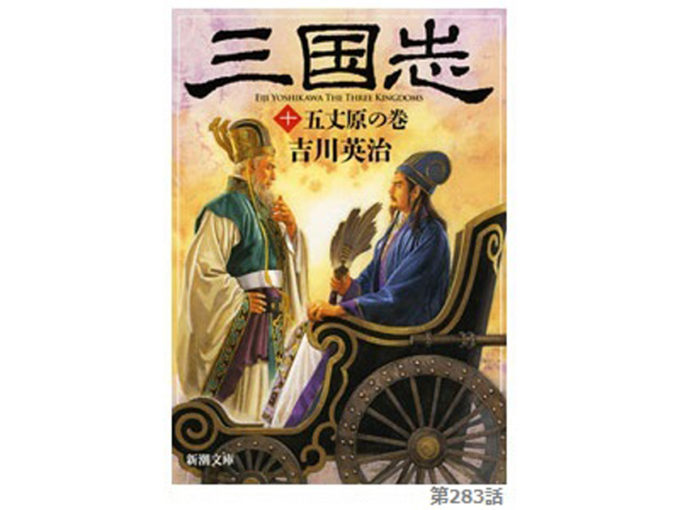














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます