魏の曹叡(そうえい)の指示を受けた西羌国王(せいきょうこくおう)の徹里吉(てつりきつ)は、武相(ぶしょう)の越吉(えつきつ)と宰相の雅丹(がたん)に25万の軍勢を預け、蜀境の西平関(せいへいかん)へ向かわせる。
諸葛亮(しょかつりょう)は祁山(きざん)と渭水(いすい)の間に本営を置いていたが、この急報を聞くや、関興(かんこう)と張苞(ちょうほう)に地理に詳しい馬岱(ばたい)を添え、5万の援軍を西平関へ差し向けた。
第282話の展開とポイント
(01)西羌王国と魏
この当時、中国の人士が西羌の夷族(異民族)と呼び習わしていたのは、現今の青海省地方――いわゆる欧州と東洋との大陸的境界の脊梁(せきりょう)をなす大高原地帯――の西蔵(チベット)人種と蒙古民族との混合体よりなる一王国を指して言っていたものかと考えられる。
その西羌王国と魏とは、曹操(そうそう)の時代から交易もしていたし、西羌より貢物の礼を執っていた。異民族が最も光栄と喜ぶ位階栄爵などを朝廷の名をもって贈与され、それを恩としているものだった。
曹叡は、祁山における曹真(そうしん)の大敗を聞き、遠く西羌王国へ使いを遣る。そして西羌国王の徹里吉に対し、以下のような教書によって行動を促した。
「高原の強軍を起こして蜀の諸葛亮の後ろを脅かし、西部の境に第二戦線を張られたし」
同時に曹真からも、同じ目的の使いが入国する。おびただしい重宝珍器の手土産が、武相の越吉と宰相の雅丹などに贈られた。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第94回)では、越吉は元帥と、雅丹は丞相(じょうしょう)と、それぞれある。
両相の建議により、国王の徹里吉は、ただちに羌軍の発向を許す。雅丹と越吉は25万の壮丁(成年に達した一人前の男)を集めると、やがて東方の低陸へ向かって進み出した。
★井波『三国志演義(6)』(第94回)では、このとき出動した羌軍は15万。
高原を下るや、黄河や揚子江(長江)の上流をなす清流が、山と山との間をうねり流れている。黄河の水も揚子江の水も、大陸へ流れ出ると真っ黄色に濁っているが、この辺りではそう濁りもない清澄な谷川だった。
平和に倦(う)んでいた高原の猛兵は、諸葛亮の名を聞いてもどれほどな者かを知らなかったし、その武器は夷(えびす)には似ず精鋭だったので、ほとんどすでに蜀軍を吞んでいるような気概で、それへ臨んでいくのだった。
欧州・土耳古(トルコ)・埃及(エジプト)などの西洋との交流が頻繁で、その文化的影響を中国大陸よりも早く受けていた。
そのため羌軍は、すでに鉄で外套(がいとう)した戦車や火砲を持ち、アラビア血種の良い馬を備え、弓弩槍刀(きゅうどそうとう)もすべて優れていたと言われている。
軍中の荷駄には駱駝(ラクダ)を用い、そのうえに長槍(ちょうそう)を引っ提げていく駱駝隊もあった。駱駝の首や鞍(くら)にはたくさんの鈴を下げ、無数の鈴の音と戦車の轍(わだち)の音は、高原兵の血をいやがうえにも高ぶらせる。
かくてこの大軍が、やがて蜀境の西平関へ近づいていたころ、寝耳に水、いま祁山と渭水の間にある諸葛亮のもとへ早馬が着いた。
「西部の動きただならず。急きょ援軍を仰ぐ」
★西平関について、井波『三国志演義(5)』の訳者注には「(西平関は)虚構の関名」との指摘があった。なお井波『三国志演義(6)』(第94回)では、ここで西平関の守将として韓禎(かんてい)を登場させていたが、吉川『三国志』では使われていない。
(02)諸葛亮の本営
事は急だし、道のりもある。しかも電撃戦をもって一挙に決し去らぬことには、総軍の不利は言うまでもない。それには関興と張苞の若手こそ屈強だが、ふたりとも西部地方の地理は不案内である。
そこで諸葛亮は、西涼州(せいりょうしゅう)出身の馬岱を添えて5万の兵を分かち、明日とも言わず出発させた。
(03)西平関の近く
蜀の援軍は西進し、たちまち羌軍の大部隊と相対する。まず高地から敵勢を一望してきた関興は、舌を巻いた様子で馬岱と張苞に話した。
「鉄車隊とでもいうか、鋼鉄をもって囲んだ戦車を連ねている。鉄車の周りには針鼠(ハリネズミ)のように釘(くぎ)のごとき棘(とげ)を一面に植え、その中に兵が乗っている。どうしてあれを撃滅できようか? 容易ならない強敵だ」
馬岱は、関興にも似げないではないかと、かえってその言を笑う。そして、ともあれ明日は一戦(ひといくさ)して、実力のほどを試してみようと励ました。
しかし翌日の合戦では、蜀軍が羌軍に散々に試されたり、翻弄されてしまう。
敗因は、何と言っても鉄車隊の威力だった。その機動力の前には、蜀軍の武勇もまったく歯が立たない。蜀軍の壊滅は全面に及び、随所で個々に殲滅(せんめつ)される。
わけて関興のごときは敵に目指されて、終日退路を走り惑い、危うく越吉の鉄槌(てっつい)に砕かれるような目に幾度も遭った。
(04)蜀軍の本営
先に本陣へ帰った馬岱と張苞は、夜に入っても関興が戻ってこないので、乱軍の中で討ち死にを遂げたかと、半ば絶望していたほど。
すると関興は夜更けに、ただ一騎で、満身血と襤褸(つづれ。破れた着物)になって引き揚げてくる。彼は肚(はら)の底から羌軍の猛威を述懐した。
馬岱は関興と張苞に言った。
「しょせんかなわぬことを知り、なおこれ以上ぶつかっていくのは、勇に似て勇ではない。それがしは敗軍を取りまとめ、要害の地に退き、ひとまず敵を支えている」
「貴公らふたりは大急ぎで祁山へ行き、丞相(諸葛亮)にまみえ、ご意見を求めてきてくれ。それまでは守るを主として、1か月や2か月は、石にしがみついても頑張っておるから」
関興と張苞にも、今はそれしか考えられない。ふたりは夜を日に継いで祁山へ急いだ。
(05)祁山 諸葛亮の本営
諸葛亮は西部方面の大敗を聞き、ただならぬ不安と焦燥(しょうそう)の陰を動かす。一夜を置いた翌日、このように告げた。
「いまこの祁山においては、曹真は守勢にあり、我が戦いの主導権を握っている。すなわち、われ戦わずんば彼も動かずという状態にあるところゆえ、諸将はよくわが留守を護れ。好んで策を用い、敵を刺激してはならぬ」
こうして諸葛亮は自ら西平関へ向かうことにする。新たに調えた3万余騎に姜維(きょうい)と張翼(ちょうよく)を加え、関興と張苞も伴って急援に駆けた。
★井波『三国志演義(6)』(第94回)では、諸葛亮が出発する前、趙雲(ちょううん)と魏延(ぎえん)に一手の軍勢をひきいさせ、潜伏に向かうよう命じている。
(06)西平関
かくて西平関に着くや、諸葛亮は、出迎えた馬岱を案内に高地に登り、羌軍の軍容を一眄(いちべん)する。そしてかねて聞く無敵鉄車隊の連陣を眺めると、呵々(かか)と一笑し、傍らの姜維に尋ねた。
「量るに、これはただ器械の力。これしきの物を持つ敵を破り得なくてどうしよう。姜維はどう思うか?」
姜維は言下に答える。
「敵には、勇があっても知略がありません。また器械力があっても、精神力はないものです。丞相の指揮とわが蜀兵の力で破れなかったら、むしろ不思議でしょう」
諸葛亮は、わが意を得たるものとしてうなずく。山を下りて陣営に入ると、諸将を会して語った。
「いま彤雲(とううん。赤い色の雲)野に起こって、朔風(さくふう。北風)天に雪を催す。まさにわが計を用うべきときである。姜維は一軍をひきいて敵の近くに進み、予が紅の旗を動かすのを見たら急に退け。そのほかの将には、後刻なお告げるところがあろう」
(07)西平関の近く
すなわち姜維は誘導戦法の先手となって羌軍へ近づいたのである。と見るや越吉の中軍は、例の鉄車隊を猛牛のごとく押し進め、敵勢を席巻せんとしてきた。
姜維は引き返しては踏みとどまり、また逃げ奔る。勝ち誇った羌軍は、この日を期して蜀軍を粉砕せよと戦線を拡大し、ついに諸葛亮の本陣まで突入した。
(08)諸葛亮の本営
鉄の猛牛は苦もなく柵門を突き破り、10輛(りょう)、20輛、30輛と、列をなして進み入る。これに続き、騎馬2千と歩兵3、4千も喚声を上げてなだれ入った。
ところが軍営のあちらこちらに、凍れる旗とおびただしい雪の吹き溜まりが眺められただけで、陣内には一兵も見えない。のみならず、その雪風か、枯れ葉の声か、あらず、どこからともなく不思議な美音が聞こえてくる。
越吉は味方を制し、馬上に耳を澄ませていたが、愕然(がくぜん)と身震いして、「琴の音だ。琴の音がする」とつぶやいた。
越吉は前後を警戒せよと言い、吹雪の中に立ちよどむ。
すると、続いてきた後陣の雅丹が大いに笑い、こう厳命した。
「諸葛亮は偽りを得意となすと聞く。ただそれ人の心を惑わしめんとする児戯に等しい計略。何をためらい、何を恐るる」
「すでに広野は雪積もること10尺(せき)。退くにはかえって難儀あらん。鉄車隊を先として、無二無三に陣内を駆け荒らし、しかる後、ここを占領して今宵の大雪をしのぐにしかず。もし諸葛亮を見かけたら、この機を外さず手捕りにせよ」
越吉もその言に励まされ、再び鉄車の猛進を命ずる。兵を分けて陣の四門をふさぎ取り、平攻めに敵の残兵の殲滅を計った。
と、奥深きひと叢(むら)の疎林の内に、なお一郭の兵舎がある。今しそこから、あわてて南門へ逃げ出していく一輛の四輪車があった。扈従(こじゅう)の者も、5、6騎の将と100人ばかりの小隊にすぎない。
あれよ、諸葛亮に紛れもなし。追いかけて我こそ捕らえんと、羌族の部将らは馬をそろえて駆け出そうとする。
越吉はいぶかしいと制したが、雅丹はこう言うと、自ら前に立って激しく下知した。
「たとえ彼に多少の詐謀があろうと、この軍勢をもって勝利の図に乗せて追えば、何ほどのことやあろう。敵の総帥を目に見ながら、これを見逃すという法はない。断じて逸すべからずである」
(09)諸葛亮の本営の近く
諸葛亮の車はその間に南の柵門を出て、陣後に続く林の中へ隠々として逃げていく。羌軍の騎馬・戦車・歩兵などは、雪を蹴り、雪にまみれ、真っ白な煙を立てて迫る。
このとき姜維の一手が、また南の柵外に現れ、羌族の大軍が諸葛亮を追撃するのを妨害するかのような態勢を取った。あれから先に片づけろと、羌軍は姜維に当たってくる。
姜維はよく抗戦したが、もとより比較にならない兵数。ほとんど、怒濤(どとう)の前の芥(あくた)のごとく蹴散らされた。
いよいよ勢いに乗った羌軍数万は、疎林の一道を中心として諸葛亮を追いかける。そして林を駆け抜けると、一眸(いちぼう)ただ白皚々(はくがいがい。雪が一面に降り積もるさま)たる原野へ出た。
ここは丘と彼方(かなた)の平野との間が、帯のような狭い沢になっている。騎馬隊や歩兵の一部はたちまち駆け下り、また向こうへ登っていく。
だが、鈍々たる鉄車隊はやや遅れたため、一団の車列になってそこを越えかけた。すでにして一団の鉄車が、窪地(くぼち)の底部に達するや否や突然、雪しぶきを上げ、すさまじい一瞬の音響とともに、その影が見えなくなる。
続々と後から下りかけていた鉄車の兵は、絶叫して車を止めようとしたが、傾斜の雪を滑っていく車輪は止まるべくもない。
あれよ、と騒ぎながらも、みすみす滑り落ち、またその上に滑り落ちて、ひとつの道だけでも何十輛という鉄車が忽然(こつぜん)と地上から消え失せた。しかもここ一道だけではなく、至るところに同じ惨害が起こっている。
そこを見直せば、緩やかな傾斜の窪と見えていたのは、太古の大地震の時にでも亀裂していたかのような長い断層。
数里にわたり板を敷き詰めて土をかぶせ、さらに柴(シバ)などで覆い包んであったところへ今朝からの大雪だったので、誰が見てもそれとは知れなかった。
しかも、騎馬や歩兵が駆け渡った程度では何のこともなかったため、羌族が力と頼む鉄車隊はまんまとその大半を、一挙にここへなげうってしまったわけである。
計略が図に当たったと見ると、蜀軍は鉦鼓(しょうこ)を鳴らし、鬨(とき)の声を合わせ、野の果てや林の陰、陣営の東西などから一度に奮い立ってきた。
馬岱軍は雅丹を生け捕りとし、関興は、恨み重なる越吉を馬上一刃の下に斬って、鬱懐(うっかい)を晴らす。姜維・張翼・張苞らの働きもまた言うまでもない。
何にせよ機動戦を主として、その力に驕(おご)りきっていた羌軍なので、こうなるとほとんど手ごたえなく蜀兵の撒血(さんけつ)に任せ、残る者は例外なく降伏する。
しかし諸葛亮は雅丹の縄を解き、懇ろに順逆を諭し、虜兵もすべて本国へ帰した。事成るや、ただちに自身も祁山へ軍勢を返す。途中で表をしたため、成都(せいと)の劉禅(りゅうぜん)に勝ち戦の模様を奏した。
(10)祁山
ここに大きな機を逸していたのは、渭水に陣している魏の曹真の大軍。曹真の不敏は魏にとって、取り返しがたい大不覚とも言えるもの。
なぜならば、その曹真が諸葛亮の不在を知り、祁山へ向けて行動しだしたのは、すでに諸葛亮が西部の憂いを払い、引き返してくるころだったからである。
しかも、祁山の留守にも諸葛亮の遺計が十分に守られていたため、魏軍はかえって幾たびも敗北を喫した。
やがて西部方面から帰った蜀軍のため、左右から包まれて多角的に打ち叩かれ、ついに渭水から総退却のほかなき態になってしまう。
★井波『三国志演義(6)』(第94回)では、このときの戦いで曹遵が魏延に討たれ、朱讃も趙雲に討たれている。たが吉川『三国志』では、このふたりの最期に触れていない。
曹真は、初めからあまり自信のなかった大任であるから、心ただ悲しみ、第二第三の良策とてない。洛陽(らくよう)へ早馬ばかり立て、ひたすら中央の援助と指令のみを仰いでいた。
管理人「かぶらがわ」より
馬岱・関興・張苞が手を焼いた西羌の鉄車隊も、諸葛亮にかかれば木っ端微塵(こっぱみじん)と――。
でも、この第282話って、すべて『三国志演義』の創作ですよね。
話はおもしろかったものの、やはりコメントしにくい。先の南蛮シリーズでの弾けっぷりを大いに残していた一話でした。

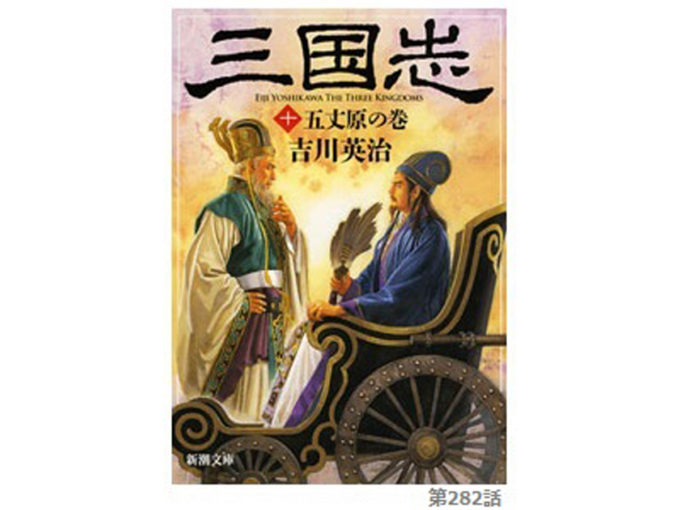













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます