諸葛亮(しょかつりょう)をはじめとする蜀の諸将が、敗軍とともに続々と漢中(かんちゅう)へたどり着く。
諸葛亮は、街亭(がいてい)の戦いに関わった王平(おうへい)・魏延(ぎえん)・高翔(こうしょう)から話を聞いたうえ、大敗の責任を取らせる形で馬謖(ばしょく)の処刑を断行した。
第286話の展開とポイント
(01)長安(ちょうあん)
長安に戻った司馬懿(しばい)は、ただちに曹叡(そうえい)にまみえて奏した。
「隴西(ろうせい)諸郡の敵はことごとく掃討いたしましたが、蜀の兵馬はなお漢中に留まっております。必ずしも魏の安泰が確保されたものとは言えません」
「ゆえにもし臣をして、さらにそれを期せよと勅したまわるならば、不肖、天下の兵馬をひきい、進んで蜀へ入って、寇(あだ)の根を絶ちましょう」
曹叡は献言を嘉納(喜んで受け入れること)しようとしたが、尚書(しょうしょ)の孫資(そんし)が大いに諫める。
いま魏が蜀へ入れば、その内政の困難をうかがい、呉が虚を突いてくることは必然だと。ここは諸境を堅守して、ひたすら国力を充実させ、蜀呉の破綻を待つべきではないかと。
曹叡は両説に迷うが、司馬懿はあえて孫資の意見に逆らわなかった。
そこで孫資の方針が採り上げられることになり、長安の守備に郭淮(かくわい)と張郃(ちょうこう)を留め、ほかの要路の固めに万全を尽くしたうえ、曹叡は洛陽(らくよう)へ還幸する。
(02)漢中
このとき諸葛亮は漢中にあり、彼としては覚えなき敗軍の苦杯をなめ、総崩れの後始末を整えていた。
すでに、あらかたの部隊は漢中まで引き揚げていたが、まだ趙雲(ちょううん)と鄧芝(とうし)が帰っていない。
やがて全軍が集まった最後になり、趙雲と鄧芝も険路を越えて到着する。困難と苦戦を極めた様子は、部隊の惨たる姿にも見て取れた。
諸葛亮は自ら出迎えて、斜めならず労をねぎらい、庫内の黄金50斤と絹1万疋(びき)を賞として贈る。
けれど趙雲は固く辞して受けない。さらにこうも言った。
「三軍いま尺寸(せきすん)の功もなく、帰するところそれがしらの罪も軽くはありません。さるをかえって恩賞に与(あず)かりなどしては、丞相(じょうしょう。諸葛亮)の賞罰明らかならずなどと謗(そし)りの元にもなりましょう」
「金品はしばらく庫内へお返しを願い、やがて冬ともなり、何かと物不自由になった時分、これを諸軍に少しずつでも分かちたまわれば、寒軍の中に一脈の暖気を催しましょう」
諸葛亮は深く感嘆する。かつて故主の劉備(りゅうび)がこの人を重用し、深く信任していたことを、さすがにといま新たに思い出された。
だが、このような麗しい感動に反して、彼の胸には別に、先ごろから解決をみていない苦しい宿題があった。馬謖の問題である。
ついに処断を決するため、一日、まず王平を呼ぶ。諸葛亮は街亭の敗因を王平の罪とは見ていなかったが、副将として馬謖に付けてやった者なので、彼の陳述を先に聞いたのだった。
王平の口書(くちがき)を取ると、続いて魏延や高翔も呼び出し、一応の調べを遂げる。こうして最後に吏に命じ、馬謖を連れてこさせた。
諸葛亮は抗弁を聴き終えると、こう言い渡す。
「馬謖よ。お前の遺族は死後も私がつつがなく養って取らせるであろう。汝(なんじ)は。汝は。死刑に処す」
諸葛亮は面を背け、武士たちの溜まりに向かって命じた。
「速やかに軍法を正せ。この者を引き出し、轅門(えんもん。陣中で車の轅〈ながえ〉を向かい合わせ、門のようにしたもの)の外において斬れ」
馬謖は声を放って泣きだす。
「丞相、丞相。私が悪うございました。もし私をお斬りになることが、大義を正すことになるならば、死すともお恨みはいたしません」
死を言い渡されてから、彼は善性を現した。それを聞くと諸葛亮も涙を垂れずにはいられなかった。
仮借なき武士たちは、ひとたび命を受けるや、馬謖を拉して轅門の外へ引っ立て、たちまち斬罪に処そうとした。
折ふし来合わせた成都(せいと)からの使い、蔣琬(しょうえん)が言う。
「待て。しばし猶予せい」
蔣琬は倉皇と営中へ入り、諸葛亮を諫めた。
「丞相。この天下多事の際、なぜ馬謖のような有能の士をお斬りになるのですか。国家の損失ではありませんか」
しかし諸葛亮は聞き入れず、惜しむべきほどな者なればこそ、なお断じて斬らねばならないと言う。侍臣を走らせて催促させると、まもなく変わり果てた馬謖が、首となって供えられた。
ひと目見ると諸葛亮は、「許せ。罪は予の不明にあるものを――」と、面を袖で覆い、床に泣き伏す。時は蜀の建興(けんこう)6(228)年の夏5月、馬謖はまだ39歳だったという。
馬謖の首は陣々に梟示(きょうし。さらすこと)され、ともに軍律の一文も掲げられた。
その後、糸をもって胴に縫い付け、柩(ひつぎ)に供えて厚く葬る。かつ、遺族は長く諸葛亮の保護によって、不自由なき生活を約されたが、諸葛亮の心は決して慰められなかった。
諸葛亮は成都へ帰る蔣琬に、劉禅(りゅうぜん)に奉る表を託した。それは全章、慙愧(ざんき)の文とも言うべきもの。このたびの大敗が、帰するところまったく自己の不明にあることを深く詫び、国家の兵を多大に損じた罪を謝したうえ、このように願い出る。
「臣亮は三軍の最高にありますために、誰も臣の罪を罰する者がおりません。ゆえに、臣自ら位を三等貶(おと)し、丞相の職称は宮中へお返し申し上げたいと存じます。願わくはしばし亮の寸命だけはお許しおきください」
この表を読んだ劉禅は、丞相の職に留まるよう伝えさせたが、諸葛亮はどうしても旧職に復さない。
やむなく朝廷も彼の願いを容れ、丞相の称を廃したうえ、「以後は右将軍(ゆうしょうぐん)として兵を総督せよ」と言い送る。諸葛亮は謹んで拝受した。
(03)街亭での大敗後の蜀
いかなる強国でも、大きな一敗を受けると、その後は当然、士気は衰え、民心も消沈するのが常である。
しかし蜀の民は気を落とさなかった。士気もまた、「見ろ、この次は!」と、かえって烈々たる敵愾心(てきがいしん)を燃え上がらせる。
諸葛亮が涙をふるって馬謖を斬ったことは、彼の一死を万世に活かした。
「時ニ二十万ノ兵、コレヲ聞イテミナ垂泣ス」と『襄陽記(じょうようき)』の内にも見える。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(『襄陽記』は)東晋の習鑿歯(しゅうさくし)の撰。自らの郷里の歴史を記す」という。
そのため、敗軍の常とされている軍令紀律の怠りは厳正に引き締められた。諸葛亮自身が官位を貶し、深く自己の責任を恐れている態度も、全軍の将士の敵愾心を高めた。
馬謖の死は犬死にではない、とともに、なお諸葛亮は善行を顕彰する。先には趙雲をねぎらったが、王平が街亭の戦で軍令に忠実だった点を賞し、新たに参軍(さんぐん)へ昇進させた。
諸葛亮は捲土重来(けんどちょうらい)を深く期し、漢中に留まる。そして汲々(きゅうきゅう)として明日の備えに心魂を傾けた。
「民ミナ敗ヲ忘レテ励ム」
当時、蜀の国情と士気とは、まさにこの語の通りだった。真の敗れは、その国の内より敗れたときである。たとい一敗を外に受けても、敗れを忘れて、より結束した蜀の国家には、なお赫々(かっかく)たる生命があった。
管理人「かぶらがわ」より
「泣いて馬謖を斬る」の真相については諸説ありますが、まぁ文字通りでいいのではないかと思います。
『三国志』(蜀書・馬良伝〈ばりょうでん〉)に付された「馬謖伝」によると、馬謖は緜竹県令(めんちくけんれい)、成都県令(せいとけんれい)、越嶲太守(えっすいたいしゅ)を歴任しています。
これは机上の学問だけでなく、実務能力も備えていたということ。そのような馬謖が40歳を前にして蜀の陣容から外れたのは、相当な痛手だったでしょう。

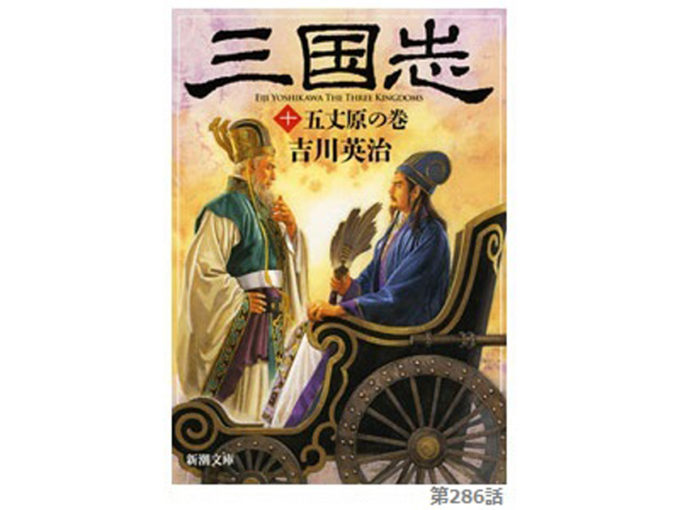













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます