司馬懿(しばい)は長安(ちょうあん)で20万の大軍を整えると、張郃(ちょうこう)を先鋒に進軍を開始。司馬懿の狙いは、いち早く街亭(がいてい)の地を押さえることにあった。
しかし諸葛亮(しょかつりょう)は、馬謖(ばしょく)と王平(おうへい)に2万余の軍勢を付け、すでに街亭を押さえていた。ところが、馬謖の失態から蜀軍は総崩れとなり、西城(せいじょう)に入った諸葛亮に、司馬懿ひきいる魏の大軍が迫る。
第285話の展開とポイント
(01)長安
魏の大陣容は整った。辛毘(しんび。辛毗)は、あざなを佐治(さじ)といい、潁川郡(えいせんぐん)陽翟県(ようてきけん)の生まれ。大才の聞こえつとに高く、今や曹叡(そうえい)の軍師となり、常に帝座間近く奉侍している。
孫礼(そんれい)は、あざなを徳達(とくたつ)という。護軍(ごぐん)の大将として、早くより戦場にある曹真(そうしん)の大軍へ、5万の精兵を加えて助けた。
そして司馬懿は、20万の大軍を長安の関から外に押し並べて扇形陣を展開。その壮観は、実に目もくらむばかりである。
司馬懿軍の先鋒に大将として推された者は、河間(かかん)の張郃で、あざなを儁乂(しゅんがい)という。司馬懿が曹叡に直奏して乞い受けた良将である。
★原文「河南の張郃」だが、彼は河間郡鄚県(ばくけん)の出身。ここは「河間の張郃」としておく。
その張郃を帷幕(いばく。作戦計画を立てる場所、軍営の中枢部)に招き、司馬懿はこう語った。
「いたずらに敵をたたえるわけではないが、仲達(ちゅうたつ。司馬懿のあざな)が観る限り、孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)は確かに蓋世の英雄、当今の第一人者。これを破るは容易でない」
「もし私が孔明の立場にあって、魏へ攻め入るとすれば、この地方は山谷険難。それを縫う10余条の道があるのみゆえ、まず子午谷(しごこく)から長安へ入る作戦を採るだろう」
「だが、おそらく孔明はそれをなすまい。なぜならば従来の戦いぶりを見ると、彼の用兵は実に慎み深い。いかなる場合も、絶対に負けない不敗の地を取って戦っておる」
司馬懿の言は、諸葛亮の心を掌(てのひら)に載せて解説するようだった。英雄は英雄を知るものかと、張郃は聴き惚(ほ)れていた。
さらに司馬懿は続ける。
「察するに、彼は斜谷(やこく)へ出て郿城(びじょう)を押さえ、そこから兵を分けて箕谷(きこく)へ向かうだろう」
「わが対策としては、檄(げき)を飛ばして、曹真の手勢に一刻も早く郿城の守りを固めさせ、一面、箕谷の道には奇兵を埋伏し、彼がこれへ伸びてくるのを破砕し去ることが肝要だ」
ここで張郃は、司馬懿自身の動きを尋ねる。司馬懿は、秘中の秘だがと声を潜めて教えた。
「秦嶺(しんれい)の西に街亭という一高地がある。傍らの一城を列柳城(れつりゅうじょう)という。この一山一城こそ、まさに漢中(かんちゅう)の喉にあたるもの」
「さはいえ孔明は、曹真がさして炯眼(けいがん)ならざるを察し、おそらくまだ兵を回しておるまい。のう張郃。ご辺(きみ)とわしとは、一方で急に進んで、そこを突くのじゃよ。何と愉快ではないか?」
張郃は神謀だとたたえる。司馬懿は、くれぐれも慎重に進軍するよう念を押し、張郃を先鋒へ返して支度を命じた。
続いて司馬懿は右筆に檄文をしたためさせ、これを曹真の本陣に送って作戦方針を示す。その際、次のように固く戒めた。
「孔明の誘いに釣られて、滅多に動きたもうな」
(02)祁山(きざん) 諸葛亮の本営
新城(しんじょう)陥落の一報は、諸葛亮の心に一抹の悲調を投げかける。その報を受けたとき、彼は左右の者に言った。
「孟達(もうたつ)の死は、はや惜しむに足らない。けれど、司馬懿がかく早く大軍をそろえてきたからには、街亭の一路が案じられる。彼は、ただちに街亭に目を付けるであろう」
「街亭はわが喉に等しい。一日の猶予もならん。誰かをして、さっそくこれを守らせねばならぬ……」
すると、参軍(さんぐん)の馬謖が傍らから身を進めて懇願した。
「丞相(じょうしょう。諸葛亮)。それがしをお差し向けください」
諸葛亮は顧みたが、初めはほとんど意中に置かないような様子だった。
しかし馬謖は、なお熱心に希望してやまない。馬謖は諸葛亮を父とも慕い、師とも敬っていた。諸葛亮もまた慈父のごとく、彼の成長を多年眺めてきたものである。
もともと馬謖は、夷族(異民族)の役に戦死した馬良(ばりょう)の幼弟だった。馬良と諸葛亮とは刎頸(ふんけい)の交わりがあったので、その遺族はみな引き取って懇ろに世話をしたが、とりわけ馬謖の才器をいたく鍾愛(しょうあい)していた。
★史実の馬良は、蜀の章武(しょうぶ)2(222)年に起きた夷陵(いりょう。彝陵)の戦いで亡くなった。
亡き劉備(りゅうび)は、かつてこう言ったことがある。
「この子、才器に過ぐ。重機に用うるなかれ」
だが諸葛亮の愛は、いつかその言葉すら忘れていたほどだった。
長ずるや馬謖の才能はいよいよ若々しき煥発(かんぱつ)を示し、軍計や兵略を解せざるはない。諸葛亮の門下で第一の俊才たることは、自他ともに許すほどになってきた。やがての大成を心密かに楽しみと見ているような、諸葛亮の気持ちだったのである。
そしていま、その馬謖からせがまれるような懇望を聞くと、丞相たる心の一面では、まだちと若いとも思い、まだ重任すぎるとも考えられた。
他方、苦しい戦と強敵に巡り会わせるのもまた、この将来ある人材の鍛錬であり、大成への段階であろうとも思い直す。
そうした機微な心理の間に、自己の小愛がふと動いていたことは、さしもの彼も深く反省してみる暇(いとま)もなく、つい「行くか」と言ってしまったのである。
馬謖は華やかな血色を顔に動かし、言下に「行きます!」と答え、そのうえこう誓った。
「もし過ちがあったら私は言うに及ばず、一門眷族(けんぞく)、軍罰に処さるるも、決してお恨み仕(つかまつ)りません」
諸葛亮は「陣中に戯言なしであるぞ」と重々しく念を押し、かつくれぐれも戒めた。
「司馬懿といい、副将の張郃といい、決して等閑の輩(やから)ではない。心して誤るなよ」
また、牙門将軍(がもんしょうぐん)の王平に命ずる。
「ご辺は平生よく事を慎み、いやしくも軽忽(けいこつ)の士でないことを私も知っておる。それゆえ、いま馬謖の副将として特に添える。必ず街亭の要地を善守せよ」
なお諸葛亮は入念だった。要道の咽喉たる街亭付近の地図を広げ、地形や陣取りの法を詳しく説く。決して進んで長安を攻め取ろうと考えるな、この緊要の地を押さえ、ひとりの敵の往来も漏らさぬことが、長安を取る第一義になると、かんで含めるごとく教えた。
こうして馬謖と王平は2万余の兵をひきい、街亭へ急ぐ。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第95回)では、馬謖と王平がひきいたのは2万5千の精鋭。
これを見送って1日おくと、諸葛亮は高翔(こうしょう)に1万騎を授けて命じた。
「街亭の東北、そのふもとに列柳城がある。ご辺もそこへ進み、もし街亭の危うきを見れば、すぐに兵(つわもの)を挙げて馬謖を助けよ」
街亭の要地を重視する彼の用意は、それでもなお足らぬものを覚えたか、さらに魏延(ぎえん)を後詰めとして出発させる。加えて趙雲(ちょううん)と鄧芝(とうし)の両軍をも、その援護として箕谷方面へ急派した。
そして諸葛亮の本軍は、姜維(きょうい)を先鋒に、斜谷から郿城へ向かう。まず郿城を取り、長安への進攻路を切り開かんとする態勢であるのは言うまでもない。
(03)街亭
街亭に着くと、すぐに馬謖は地勢を視察して回る。そして大いに笑って言った。
「どうも丞相は少し大事を取られすぎる。山と言っても大した山ではないし、やっと人の通れるほどな樵夫道(そまみち。樵〈きこり〉が使うような道)がいくつかあるにすぎない」
「このような街亭などへ、何で魏が大軍を傾けてくるものか。由来、丞相の作戦はいつでも念入りの度が過ぎ、かえって味方に疑いを起こさしめる」
そのあと馬謖が山上への陣構えを言いつけたので、副将の王平は厳しく戒めた。
「丞相の令したまえるご主旨は、山の細道の総口をふさぎ、そこを遮断するにありましょう。もし山上に陣取るときは、魏軍にふもとを囲まれて、その使命を果たしきれますまい」
これを聞き、馬謖が反論する。
「それは婦女子の見で、大丈夫(だいじょうふ。意志が堅固で立派な人物)の採るところではない。この山は低しといえども、三方は絶地の断崖。もし魏の勢きたらば、引き寄せて討つには持ってこいの天険だ」
★『三国志演義 改訂新版』(立間祥介〈たつま・しょうすけ〉訳 徳間文庫)の訳者注によると、「(絶地は)逃げ場のない地」だという。
王平が言う。
「丞相は、大いに勝てとは命ぜられませんでした」
すると、さらに馬謖は言った。
「みだりに舌の根を動かすのはよしてもらいたい。孫子も言っておる。『是ヲ死地ニ置イテ而(しか)シテ後(のち)生(い)ク』と」
「それがしは幼より兵法を学び、丞相すら事にあたっては、この馬謖に計を相談されておるのだ。黙ってわが命令のようにすればよい」
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(『是ヲ死地ニ置イテ而シテ後生ク』は)『孫子』九地篇のことば。『投之亡地、然後存。陷之死地、然後生』」であるという。
それでも王平は従わず、こう言った。
「では、あなたは山上に陣をお構えなさい。手前は5千騎を分かち、別にふもとに陣取って掎角(きかく)の勢に備えますから」
★新潮文庫の註解によると「(掎角の勢とは)鹿を捕らえるのに後ろから足をひき(掎)、前からは角をとる(角)ように、前後が呼応して敵に当たること」だという。
馬謖は露骨に不愉快な色を示す。大将の威厳を傷つけられた気がしたのだ。
着陣早々、主将と副将が議論に時を移している間に、早くも近郡の百姓が逃散(ちょうさん)しながら、「魏軍が来る。魏軍が来る」と告げていった。
もう猶予はできない。馬謖は自説を固持し、山上に陣取るよう命ずる。王平は手勢5千をもって、頑としてふもとに陣した。
王平はこの布陣を詳しく絵図に写し、諸葛亮のもとへ早馬を遣り、「直接ご命令を仰ぎたい」と訴える。
山上への布陣を終えた馬謖は、ふもとを見て切歯した。
「王平の奴、ついに俺の指図に従わんな……。凱旋(がいせん)の後は丞相の前へ出て、彼の僭上(せんじょう)と軍律に背いた罪をきっと問わねばならん」
翌日、また翌日と引き続き、味方の高翔や魏延などが、列柳城付近から街亭の後ろへも後詰めして、陰に陽にここを助け、魏軍を牽制(けんせい)しつつあると聞こえる。馬謖は大磐石(大きな岩)を据えている心地で、100万の軍も吞むような概をもって待ち受けた。
このとき魏の司馬懿の考えでは、まだ街亭には、蜀軍は一兵も来ていまいと観ていた。
ところが、先発した司馬昭(しばしょう)が先陣の張郃に会うと、すでに街亭は蜀旗翩翻(へんぽん)たるものがあると聞かされる。
★井波『三国志演義(6)』(第95回)では、司馬懿の命を受けた司馬昭が、前方の道を探りに行っていた。
司馬昭は急きょ引き返し、父にその趣を話す。司馬懿は非常に驚き、しばし呆然(ぼうぜん)となっていた。
だが、その本陣をやや動かして、街亭・箕谷・斜谷の三面に遺漏なき触覚を働かせる。そして一夜、わずか10騎ほどを連れて前線へ微行した。
月明かりを利して、密かに敵近き四山を巡り、やがて一高地から蜀の陣容を望む。司馬懿は一瞬啞然(あぜん)とした後、左右へ語った。
「ありがたし、ありがたし。天の助けか、蜀軍は絶地に陣を取り、自ら敗北を待っている」
(04)司馬懿の本営
司馬懿は本陣へ帰るやいな、帷幕の参軍たちを呼び集めて尋ねる。
「街亭を守る蜀の大将は、いったい誰か?」
そして、馬謖なりと聞くと笑って言い、斜めならず喜ぶ。
「千慮の一失というのはあるが、孔明にも、人の用い方に誤ることもあるか。山を守っている蜀の大将はまさしく愚物だ。一鼓して破れよう」
司馬懿は張郃に命ずる。
「山の西、10里のふもとに蜀の一陣がある。汝(なんじ)はそれへ攻めかかれ。我は申耽(しんたん)と申儀(しんぎ)のふた手を指揮し、山上の命脈を断ち切るであろう」
彼が山上の命脈と見たものは、実に、軍中にはなくてはならぬ「水」だった。その水を、山上の蜀軍は、山の下から兵にくませていたのである。
(05)街亭
翌日の早天、張郃は司馬懿の旨を受け、兵をひきいて蜀の王平軍の孤立を図った。すなわち山上の軍との連絡を遮断し、同時に、魏軍が山上の兵が水くみに使う通路を断つ動きを妨害できぬよう、その途中を切り取ったのだ。
しばらく後、司馬懿は自ら大軍をもって、街亭山麓を十重二十重に取り巻いてしまう。その間、鬨(とき)の声と金鼓の音は雲を動かし、地を震わせた。
山上の馬謖は、よじ登ってくる敵に掛かろうと必勝の概で待ち受ける。ところが魏軍は喚声や鼓雷を上げるだけで、攻め登っては来なかった。
馬謖は功に逸(はや)りきり、小道から逆落としに駆け下りて、魏将の首ふたつを得る。多数の味方は序戦に勝ったが、帰路は精を切らす。また山道を登るので、追撃の新手におびただしく討たれた。
(06)街亭 馬謖の本営
馬謖は目前の勝負にばかりとらわれていたが、たちまちその夜から水に窮する。愕然(がくぜん)、気づいたときにはすでに遅く、以来奪回を図るたび、ほとんど算なきまでの損害を繰り返した。
炊(かし)ぐに水もないありさまで、兵糧すら生か火食のほかなく、意地悪く、待てど待てど雨も降らない。
そのうちに、「水をくみに行く」と称しては、暗夜に山を下りていく兵はみな帰らない。討たれたのかと思うと、続々と魏に投降したものだとわかった。
(07)街亭
ついには、多数の兵が一団となって魏に降り、山上の困憊(こんぱい)は司馬懿の知るところとなる。
ここで魏は総攻撃を開始。馬謖も今は覚悟して、西南の一路からドッと下りた。
司馬懿はわざと道を開き、この窮鼠軍(きゅうそぐん)を通す。その大兵が山を離れるや、初めて袋包みとして殲滅(せんめつ)にかかった。
街亭の後詰めにあった魏延と高翔は、50里先から助けに来た。だが、その途中には司馬昭の伏兵があり、また一面には味方の王平も現れ、ここに両軍入り乱れての大混戦が展開される。
街亭の激戦は、帰するところ蜀の大敗に終わった。
ふもとに陣した王平、後詰めしていた魏延、列柳城まで出ていた高翔など、一斉に奮い出て馬謖軍を助ける。
しかし如何(いか)んせん、馬謖軍そのものが十数日の間、山上にあって水断ちの苦計に遭い、兵馬ともまったく疲れ果てていたので、これには戦力もなく、ただ壊乱混走して、魏軍の包囲下に手ごろな餌食となってしまう。
戦火は三日三晩の間、赤々と燃え広がっていた。魏延が馬謖の救出に動くことも察知していた司馬懿は、司馬昭に命じて横を突かせる。
魏の張郃もおびただしい奇兵を駆り、その大包囲鉄環の内に捉えんとしたが、王平や高翔が側面から助けたこともあり、ついに魏延を討ち取るには至らなかった。
とはいえ魏延軍は大損害を受けたし、王平軍もまた満身創痍(まんしんそうい)の敗れ方。4日目の朝、ようやく敗残兵をまとめ、高翔の意見に従って列柳城へ急いだ。
ところがまたまた、その途中で図らざる新手の敵に遭遇する。曹真の副都督(ふくととく)たる郭淮(かくわい)の軍勢だった。
魏延や高翔は、「この新手と戦うは自殺するも同じである」となし、急に道を変えて陽平関(ようへいかん)へ走り、ひとまずそこを守る。
郭淮は難なく列柳城へ入れるものと思い、城下まで来たところ、すでに司馬懿の軍勢が入った後だった。
(08)列柳城
郭淮は大いに驚き、心密かに、われ到底この人に及ばずと、城へ入って対面を遂げ、心服を表して敬拝した。
すると司馬懿が言った。
「街亭が破れたうえは、孔明も逃げ走るほかないだろう。速やかに貴下(あなた)の軍勢をもって追い崩したまえ」
郭淮は唯々諾々、再び城を出る。続いて司馬懿は張郃を招いて言った。
「敵の魏延や王平の徒は、敗軍を退いて陽平関を守るだろうが、それに釣られて軽々しく追い攻めをかけると、たちまち孔明が後を取り、大勢の挽回を図るに違いない」
「兵法にも『帰ル師(いくさ)ヲ掩(おお)ウコト勿(なか)レ、窮マル寇(あだ)ヲ追ウ勿レ』と戒めている。ゆえに、我はかえっていま、小路から蜀勢の後ろへ回ろう」
★新潮文庫の註解によると「(『帰ル師ヲ掩ウコト勿レ……』は)『孫子』軍争篇のことば。『帰師勿遏、囲師必闕、窮寇勿迫、此用兵之法也』」であるという。
「ご辺は山路を経て箕谷へ進め。そして蜀軍が滔々(とうとう)と崩れ立っても、これを全滅せんなどと急に追うな」
「武器・兵糧・馬・物の具などを収め、駸々(しんしん。事が早く過ぎるさま)と斜谷を取り広げ、やがて西城(西県〈せいけん〉)を占領した後、さらに次の作戦に入ろう」
「西城は山間の小県ながら、あそこには蜀の兵糧が蓄えてあるに相違ない。遠征流浪の蜀軍から糧食を取り上げてしまえば、彼らの敗退は必然的で、あえてわが軍が多くの犠牲を払う必要もない」
張郃は命を受け、おびただしい魏兵をひきいて箕谷へ向かう。申耽と申儀を列柳城に留めると、司馬懿も前進した。
(09)祁山 諸葛亮の本営
これより前のこと、王平の急使が着き、街亭の布陣を図面にしたものと書簡が届く。
諸葛亮は一見すると、「アッ。馬謖のばか者!」と、当惑の眉をひそめる。事に悔いぬ彼も、このときばかりは惨涙独語し、下唇を血のにじむほどかみ締めていた。
長史(ちょうし)の楊儀(ようぎ)が恐る恐る尋ねると、諸葛亮は王平の書簡と布陣図を投げやって言う。
「若輩の馬謖めは要道の守りを捨てて、わざわざ山上の危地に陣取ってしまった。何たる愚だ。魏軍がふもとを取り巻き、水の手を切り取ったらそれまでではないか。いくら若いにせよ、こうまで浅慮者(あさはかもの)とは思わなかった」
これを聞いた楊儀は、ただちに自分が行って、急いで布陣を変えさせると言う。しかし諸葛亮は、敵が司馬懿では、おそらく間に合わないと考えているようだった。
こうして楊儀が準備を整える間にも、次々と早馬が着き、街亭の敗れと列柳城の喪失を続けて告げる。
諸葛亮は天を仰いで痛哭(つうこく)した。
「大事去れり。あぁ、大事去る……」
そしてひと言、「わが過ちであった!」と叫んだ。
諸葛亮は関興(かんこう)と張苞(ちょうほう)を呼び、こう命ずる。
「おのおの3千騎をひきい、武功山(ぶこうざん)の小路に拠れ。魏軍を見ても討つな。ただ鼓を轟(とどろ)かせ、喚声を張れ。敵はおのずから走るだろうが、なお追うな、また討つな。いよいよ敵の影なきを見届けた後、陽平関へ入れ」
続いて張翼(ちょうよく)を呼び、汝は一軍をひきい、剣閣(けんかく)の道なき山に道を作れと命じた。
すでに彼は総退却のほかなきを悟ったのである。密々に触れを回して引き揚げの準備をさせ、一面、馬岱(ばたい)と姜維のふた手を殿軍(しんがり)に選び、悲痛な面で言い渡した。
「そちたちは山あいに潜み、敵きたらば防ぎ、逃げ続いてくる味方を容れ、その後に頃合いを計って引き揚げよ」
また、馬忠(ばちゅう)の一軍にもこう命ずる。
「曹真の陣を横ざまに攻め立てておれ。彼はその気勢を恐れ、よもや圧倒的な行動には出てこまい。その間に我は人を派す。天水(てんすい)・南安(なんあん)・安定(あんてい)の3郡の軍官民をすべてほかへ移し、それらを漢中へ入れるであろう」
退却の手はずはここに調う。かくて諸葛亮は5千余騎を連れ、真っ先に西城へ行った。
★井波『三国志演義(6)』(第95回)では、さらに諸葛亮は腹心の部下を冀県(きけん)に派遣し、姜維の老母を引き取って漢中に送り届けることにしたともある。
(10)西城
諸葛亮が、蓄えてあった兵糧をどしどし漢中へ移送していると、たちまち知らせが届く。
「大変です。司馬懿自ら、およそ15万の大軍をひきい、まっすぐにこれへ寄せてくる様子です」
諸葛亮は愕然と色を失う。左右を顧みるに、力と頼む大将の主なる者はほとんど諸方へ分け、これという者もいない。残っているのは文官ばかりである。
のみならず、先に従えてきた5千余の兵力も、その半分は、兵糧輸送の輜重(しちょう)に付けて漢中へ先発させた。西城の小城を見渡せば、寥々(りょうりょう)たる兵力しか数えられない。
ほどなく魏の大軍が、雲霞(うんか)のように見えてくる。城兵はうろたえるというよりは、むしろあきれて、人心地もなく、顔の血も去喪してただ震えていた。
諸葛亮は櫓(やぐら)に立ち、敵ながら見事と、寄せ手の潮を眺める。そして城兵に向かって凜(りん)と命じた。
「四門を開けよ。開け放て。門々には水を打ち、明々と篝(かがり)を焚き、貴人を迎えるごとく清掃せよ」
さらに、一段と声高く告げる。
「みだりに立ち騒ぐ者は斬らん。整々粛々と旗をそろえよ。部署ごとに旗下から動くなかれ。静かなること林のごとくあれ。門ごとの守兵は、わけてのどかに団欒(まどい)して、敵近づくも居眠るがごとくしてあれ」
命じ終わると、諸葛亮は日ごろ頂いている綸巾(かんきん。隠者がかぶる青糸で作った頭巾。俗に「りんきん」と読む)を華陽巾(かようきん。〈同じく〉隠者のかぶる頭巾)に改め、衣も新しき鶴氅(かくしょう。鶴の羽で作った上衣)に着替えた。
★井波『三国志演義(6)』(第95回)では、諸葛亮が綸巾を華陽巾に改めたという記述は見られない。
それから「琴を持て」と言い、ふたりの童子を従えて、櫓の一番上へ登っていく。高楼の四障も開け払うと、香を焚き、琴を据えて端然と座した。
魏の先陣は、この様子を遠く望見し、怪しみ疑いながら伝える。司馬懿は馬を飛ばして先陣へ臨み、城下まで近づいて眺めた。
仰ぐと高楼の一層、月の明るきところ、香を焚き、琴を調べ、従容として、ひとり笑めるかのような人影がある。まさに孔明その人に違いない。
清麗な琴の音は、風に遊んで欄を巡り、夜空の月に吹かれては、また満地の兵の耳へ、露のごとくごぼれてきた。
なぜともなく、司馬懿はブルブルと身を震わせる。いざ通られよと誰か迎え出ぬばかり、目の前の城門は八文字に開かれているではないか。
しかも、そこここと水を打って清掃してあるあたり、篝の火も清らかに、門を守る兵まで膝を組み合い、みな居眠っている様子である。
やにわに司馬懿は、「退けっ、退けっ」と先陣の上に鞭(むち)を振った。
驚いた司馬昭は、敵の詭計(きけい)だと言ったが、司馬懿は強く頭(かぶり)を振る。
「四門を開き、あのていたらくは、我を怒らせ、我を誘い入れんの計と思われる。うかつすな。相手は諸葛亮。測りがたし、測りがたし。退くにしくはない」
ついに魏の大軍は夜通し続々と退いてしまった。
諸葛亮は手を打って笑う。
「さしもの司馬懿も、まんまと自己の知に負けた。もし15万の敵兵が城に入ってきたら、一琴の力、何かせん。天佑(てんゆう)、天佑――」
かつ部下に言った。
「城兵わずか2千。もし恐れて逃げ走っていたら、もう生け捕られていたであろう。さるを司馬懿は今ごろ、ここを退いて北山(ほくざん)に道を取っているに違いない。かねて伏せておいた関興や張苞らの軍に襲われ、痛い目に遭うていることだろう」
すぐに諸葛亮は西城を出て、漢中へ移っていく。西城の官民もその徳を慕い、あらかた漢中へ去った。
(11)北山の峡谷
諸葛亮の先見にたがわず、司馬懿軍は北山の峡谷にかかるや蜀の伏勢に襲撃される。ここで一勝を博した関興と張苞は、あえて追わず、ただ敵が捨てていったおびただしい兵器や糧食を収め、漢中へ急ぐ。
(12)祁山
祁山の前面にあった曹真の本軍も、孔明ついに奔ると聞くや、にわかに揺るぎだして追撃にかかろうとした。しかしこれも馬岱と姜維の両軍に待たれ、したたか不意を討たれる。その折、魏は大将の陳造(ちんぞう)を失った。
★井波『三国志演義(6)』(第95回)では、馬岱が陳造を斬り殺したとある。
(13)漢中
漢中に入ると、諸葛亮は伝令を遣り、箕谷の山中にある趙雲と鄧芝へこう言い送った。
「予はつつがなく漢中へ退いた。殿軍の労を謝す。卿(けい)らまたつつがなくここに来たらんことを祈る」
(14)退却中の趙雲
ここは国境第一の険路である。加うるに友軍はみな漢中へ退き、いわば援護のために、山中の孤軍となった二将だった。
それでも趙雲はさすがに千軍万馬の老将。おもむろに退却の準備にかかる。まずは鄧芝の軍を先発させ、彼は留まって谷の内に潜んだ。
魏の郭淮は猛然と追撃にかかり、部下の蘇顒(そぎょう)に軽騎3千ばかりを付け、細道を飛ぶがごとく急がせる。
すると突如として趙雲が現れた。蘇顒は震い恐れつつも兵を励まして戦ったが、ついに趙雲に討たれてしまう。
趙雲が静々と後退を続けていると、また郭淮の一手の万政(ばんせい)が、前にも勝る兵力で追いついてきた。
趙雲は数人の旗本を身辺に残し、ほかはみな先へ行かせる。そして険しい細道の坂上に、作り付けの武者人形のように構えていた。
万政は近づくことができず、郭淮に訴えた。
「まだ趙雲は、以前の面影を失っていません。おそらく大なる損害を求めましょう」
だが、郭淮は聞かない。強って当たるよう命ずる。
道の左右は砥(と。砥石〈といし〉)のごとき絶壁。趙雲は坂の上に立ち、狭い口をふさいでいるので、大兵も用をなさない。駆け上がる者、当たる者、みな彼の槍に血を煙らせて倒れた。
やがて日が暮れる。趙雲は敵がひるむのを見て、馬を先へ進めていく。
万政が追いかけて一林の中まで来ると、不意に趙雲の影が跳びかかってきた。万政はうろたえるあまり、馬もろとも谷底へ落ちた。
趙雲は言う。
「そこまで、命を取りに行くのは面倒だ。陣へ戻ったら郭淮に言え。またいつかきっと会うぞと」
趙雲は味方の一兵も損せず、静かに漢中への引き揚げを果たした。
(15)西城
その後、司馬懿は蜀軍が漢中へ逃げ籠もったのを見届けてから、西城へ軍勢を移す。なおその地に残っていた百姓を呼び集めると、訓戒を与えた。
「敵を慕って漢中へ逃散した百姓どもは、魏の仁徳を知らないのだ。お前たちは先祖からの土地を動いてはならぬ」
さらに諸葛亮の施政ぶりや、この城にいたときの様子をいろいろ尋ねる。
これにひとりの老百姓が答えた。
「都督(司馬懿)さまが大軍をひきいてこの西城をお攻めになろうとされたとき、諸葛亮の下には、弱そうな蜀兵が、わずか2千ほどしかおりませんでした。どうしてあのとき急にお引き揚げになってしまわれたのでしょう。手前どもは不思議に存じておりました」
初めて諸葛亮の計だったことを知った司馬懿は、そのときには何の顔色も見せなかった。だが、後にひとり天を仰いで長嘆する。
「われ勝てり。しかしついに、われ孔明に及ばずであった」
そしていよいよ各所の要害を厳重に守り固めさせ、やがて長安へ凱旋の途に就いた。
管理人「かぶらがわ」より
街亭での馬謖の失態や、蜀の大敗が中心だった第285話。諸葛亮が一琴で、司馬懿の大軍を退かせたりもしていました。でも、これはちょっとアレでしたね……。
また、文庫で30ページを超える長い一話でもありました。ここは二話に分割したほうがよかったかも?

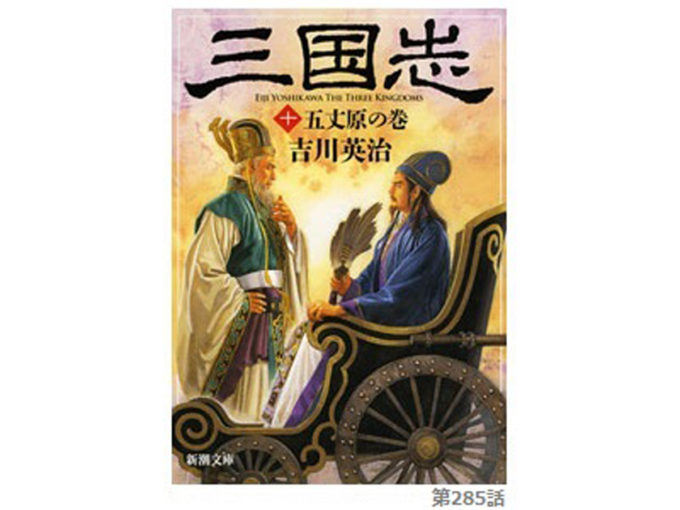













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます