本拠としていた銀坑山(ぎんこうざん)を失い、むたび捕らえられ、むたび諸葛亮(しょかつりょう)に放された孟獲(もうかく)。義弟の帯来(たいらい)の進言に従い、今度は烏戈国(うかこく)の兀突骨(ごつとつこつ)を頼る。
かの地の藤甲軍(とうこうぐん)は不敗の精鋭として知られ、実際に刃(やいば)を交えた魏延(ぎえん)から話を聞くと、諸葛亮は付近の地勢を見て回り、馬岱(ばたい)にある秘策を授けた。
第274話の展開とポイント
(01)銀坑山の郊外
すでに国なく、王宮もなく、行く当てもない孟獲は、悄然として周囲の者に諮る。
「どこに落ち着いて、再挙を図ろうか?」
彼の妻の弟である帯来が言った。
「ここから東南(たつみ)のほうへ700里行くと烏戈国があります。国王は兀突骨という者です」
「五穀を食(は)まず、火食せず、猛獣蛇魚を食い、身には鱗(うろこ)が生えているとか聞きます。また彼の手下には、藤甲軍と呼ぶ兵が約3万はおりましょう」
孟獲が藤甲軍について尋ねると、帯来が続けて言う。
「烏戈国の山野は至るところに山藤(ヤマフジ)がはびこっているのです。その蔓(ツル)を枯らした後、油に浸し、また日にさらしては油に浸し、これを何十遍も繰り返すのだとか……」
「そうした蔓を使って鎧を編むのです。この鎧を着込んだ兵を藤甲兵と呼び、まだこれに勝ったという四隣の国はありません」
孟獲が不敗の理由を尋ねると、さらに帯来はこう説明した。
「藤甲の特長ですが、第一には水に濡れても通しません。第二には非常に軽いので、体が軽敏です。第三には江を渡るにも船を用いず、みなよく水に身を浮かせて自由に浮遊します。第四には弓も刀も受け付けないほど強靭(きょうじん)なのです」
これを聞くと、孟獲は一族と敗兵を従えて烏戈国を頼る。
(02)烏戈国
孟獲から子細を聞いた兀突骨は、議にも及ばず、「よろしい」と大きくうなずく。即座に藤甲を着込んだ3万の部下が洞市に集まる。孟獲の残兵も追い追い寄って、両者の兵を合わせて10万余。烏戈国を発して桃葉江(とうようこう)に陣した。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第90回)では、ここで土安(どあん)と奚泥(けいでい)という兀突骨配下の部将が登場していたが、吉川『三国志』では使われていない。
★また井波『三国志演義(6)』(第90回)では、桃葉江は桃花水(とうかすい)とあった。
(03)桃葉江
江の水はあくまで青く、両岸には桃の木が多く茂っている。年経れば、葉が河水に落ちて一種の毒水を醸し、旅人が飲めば甚だしく下痢(げり)を病む。ところが烏戈国の土人には、かえって精力を加える薬水になると言い伝えられている。
(04)桃葉江の近く 諸葛亮の本営
一方の諸葛亮は銀坑山の蛮都に入ってからも、これを治めて掠(かす)めず、これを威服せしめて殺戮(さつりく)せず。ただよく徳を布き、さらに軍を整え、王征を拡大してきた途にあった。
諸葛亮は魏延に命ずる。
「魏延。一手をひきいて桃葉江の渡し口を見てこい。ただひと当てして、敵の勢いを測ってくればよいぞ」
(05)桃葉江の近く
すぐに魏延は桃葉江へ赴く。その途中、早くも烏戈国の兵と孟獲の連合軍にぶつかった。蛮軍は気負うこと満々、大胆にも江を渡り、攻勢を掛けてきたのである。
敵は新手の大軍、魏延の部隊は小勢でもあったが、蛮軍は喚声を上げ、猛威は完全に昨日の気勢を盛り返していた。
のみならず、序戦でまず驚いたのは、蜀軍の射る矢がまったく功を奏さないこと。当たっても当たっても、矢は敵兵の体から跳ね返ってしまう。
白兵戦となっても、敵の五体には刀が通らない。その自信もあるため藤甲軍の士気は猛烈で、かみつくように蛮刀を振るってくる。
たちまち蜀兵は斬り立てられ、総壊乱を起こす。ここで角笛を鳴らして、兀突骨は悠々と兵を引き揚げる。孟獲よりも兵法を知る者だった。
その帰るや、江を渡っていくのに、藤甲の兵はみな流れに身を浮かせ、あたかも水馬(ミズスマシ。アメンボ)の群れが泳ぐように易々と対岸へ上がっている。暑いので藤蔓の鎧を脱ぎ、鎧を水に浮かせ、その上に座ったまま渡っていく兵などもある。
★ここでは水馬のルビに「ミズスマシ」を採っていたが、「アメンボ」を優先したほうがいいかも? 本来、両者は別のものである。
(06)桃葉江の近く 諸葛亮の本営
魏延はありのままを伝え、不思議な異蛮だと語った。諸葛亮も首をかしげていたが、やがて呂凱(りょがい)を呼んで尋ねる。
呂凱は地図を案じた後、こう言って極力引き揚げを勧めた。
「さては烏戈国の藤甲軍でしょう。とても人倫をもって律せられない野蛮の兵です。加うるに桃葉江の毒水は、蛮外の人間にはくむべからざるものです」
「もはやこのへんでお引き揚げになってはどうです? あのような半獣半人の軍を敵にしていた日にはたまりません」
その諫めは了としたが、諸葛亮は面を振って、左右の者にも言う。
「事を成しかけて終始を全うしないほど大なる罪はない。その兵の無駄は幾ばくか? 幾万の霊に何と謝すべきか? ましてこの蛮界に王風を布くに、一隅の闇をも余して引き揚げてはすべてを無意味にする」
翌日、諸葛亮は四輪車を進ませて桃葉江岸を一巡し、付近の地勢を見て回った。さらには車を降りて、徒歩で北方の一山へ登り、険しきを探り案じ、黙々と陣地へ帰ってくる。
するとすぐに馬岱を招き、何事か小声で綿密なる秘策を授けた。
「先ごろ用いた木獣車のほかに、なお黒い櫃(ひつ)を載せた10余輛(りょう)の戦車があるだろう」
「汝(なんじ)はそれを引き、一軍の兵とともに、桃葉江の北にある盤蛇谷(ばんだこく)の内に潜め。そして戦車をこう用いるがよい」
よほど秘密裏に行う必要があるものとみえ、諸葛亮は、いつになく厳として戒める。
「もし事が漏れて内より敗れたときは、軍法に問うて罰するぞ。抜かりあるな」
馬岱の一軍は10余輛の戦車とともに、その日の夜中から忽然(こつぜん)と影を消していた。
翌朝、諸葛亮は趙雲(ちょううん)を呼び、一軍を授けて言い渡す。
「ご辺(きみ)は、盤蛇谷の裏から三江にわたる大路へ出て、かくかくの用意をなせ。必ず日限を誤るな」
★三江について、井波『三国志演義(6)』(第90回)によると、瀘水(ろすい)・甘南水(かんなんすい)・西城水(せいじょうすい)の3本の川が合流しているため、三江と称するという。
諸葛亮は、続いて魏延を呼び出して告げた。
「御身(あなた)は精鋭をひきい、敵の真正面に出て、桃葉江の岸に陣を構えろ。兵は望むままの数を連れていくがいい」
魏延は、我こそ先鋒の最前線を承る者なり、と大いに喜ぶ。
だが、諸葛亮は彼の勇躍を抑えるように語を継いだ。
「くれぐれも勝ってはならんぞ。もし敵が江を渡って強襲してきたら、ほどよく戦っては退け。陣屋も捨てて逃げろ。逃げる先には白旗を立てておく。またそこへ敵が寄せてきたら壊走して、次の白旗の立っている陣まで奔れ」
「いよいよ、敵は勝ちに乗るだろう。さらに汝は、第四の白旗の見ゆる地、第五の白旗の見ゆる地と、次々に陣屋を放棄して醜く逃げ続けよ」
魏延が面を膨らませて聞く。
「いったい、どこまで逃げろと仰せられるのですか?」
諸葛亮はこう説明した。
「およそ15日のうちに15回の戦いに負け、7か所の陣地を捨て、ただ身をもって白旗の見えるところへ逃れればよいのだ」
軍令なので否めないが、魏延は怏々(おうおう)と楽しまない顔をして退がる。このほか張翼(ちょうよく)・張嶷(ちょうぎ)・馬忠(ばちゅう)なども、それぞれ命を受けて部署に赴き、手ぐすね引いて戦機を測っていた。
(07)桃葉江の南岸
兀突骨と孟獲は、いったん江南に退き、大いに驕(おご)りながらも、お互いに軽挙を戒め合っていた。そこへ見張りの蛮兵から報告が届く。
「昨夜(ゆうべ)から北岸に、蜀兵が陣屋を作りだしております。だいぶたくさんな軍勢です」
兀突骨と孟獲は、岸へ出て手をかざす。あの要所に堅固な陣屋を作られては、ちとうるさいとし、今のうちにもみつぶそうとなった。
命が下ると、たちまち藤甲の蛮勢は、江を渡って北岸を襲撃。戦い戦い、魏延は逃げる。
ところが蛮軍は懲りており、深くは追ってこない。勝ちを収めると鮮やかに江を渡り、もとの南岸へ引き揚げてしまう。
魏延も北岸へ戻り、再び陣屋を構築しだす。諸葛亮から新手の兵も追加される。それを見ると、蛮軍もまた人数を増やして、攻撃を再開した。
管理人「かぶらがわ」より
蛮土の奥の奥、烏戈国の兀突骨を頼る孟獲。何せ藤甲が強烈でした。結局は弱点を突かれましたが、この鎧には捨てがたい魅力もありますね。

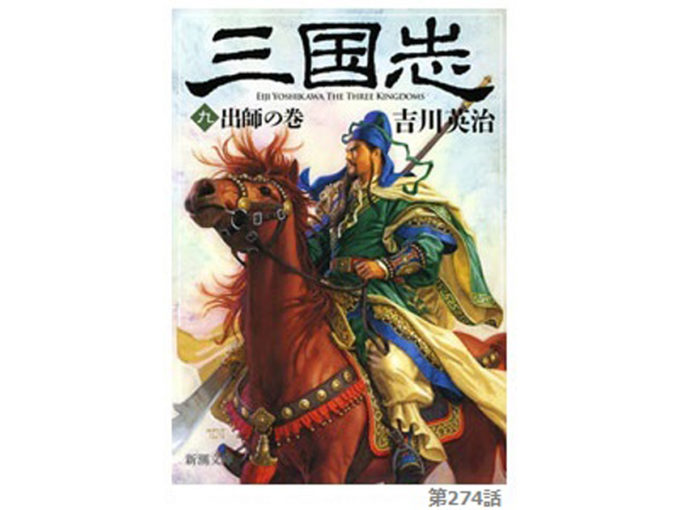













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます