左慈(さじ)は魏王宮落成を祝う大宴を台なしにしたうえ、痛烈な曹操(そうそう)批判を繰り返す。
そして宴席から姿を消すと、曹操の命を受けた許褚(きょちょ)の追跡もかわしたが、ほどなく人相書きそっくりの左慈が各地で捕らえられる。
第213話の展開とポイント
(01)鄴都(ぎょうと) 魏王宮
左慈が嬋娟(せんけん)たる牡丹(ボタン)の大輪を咲かせてみせると、王宮の千客は目をこすり合う。
そこへ各人の卓上に、庖人(ほうじん)が魚の鱠(なます)を供えた。左慈は一眄(いちべん)し、人もなげに言う。
「魏王が一代のごちそうと言ってもいい大宴に、名も知れぬ魚の料理とは貧弱ではないか。大王、なぜ松江(しょうこう)の鱸(スズキ)をお取り寄せにならなかったのか?」
曹操は赤面しながら、客の百官に言い訳をする。
「温州(うんしゅう)の果実はともかく、鱸と言っては生きていなければ値打ちがない。何で千里の松江から活けるまま持ってこられよう」
だが、左慈は造作もないと言い、釣り竿(ざお)を借りて玄武池に糸を垂れる。
★玄武池については前の第212話(02)を参照。
水は満々とそよぎ立ち、左慈の袖が翻るたび、たちまち大きな鱸が何尾も釣り上げられた。それでも曹操は、いま釣ったのは池に放しておいた鱸だと言う。
これに左慈が反論し、松江の鱸には必ず鰓(えら)が4枚あるが、ほかの鱸には2枚しかないと言う。試みに客が調べてみると、どれもこれも正しく4枚あった。
曹操も客も、愕然(がくぜん)たらざるはなかったが、なお何かで困らせてくれんものと、また左慈に言った。
「いにしえから、松江の鱸を鱠にして賞味するときには、必ず紫芽(しげ)の薑(はじかみ。生姜〈ショウガ〉)をツマに添えるという。薑はあるか?」
左慈が「お安いこと」と左の袂(たもと)へ手を入れると、幾つかみもの薑を黄金の盆に盛ってみせた。
怪しんだ曹操は、近侍の者に盆を持ってくるよう命ずる。するといつの間にか、盆の薑は一巻の書物に変わっていた。見ると『孟徳新書(もうとくしんしょ)』という題簽(だいせん)が付いている。
★『孟徳新書』については先の第188話(01)を参照。
曹操は皮肉を感じてむっとしたが、いずれは打ち殺さんという肚(はら)があるので、さりげなく聞いた。
「左慈。これは誰の書いた書物か?」
左慈は答えて言う。
「はははは。さて誰の著書でしょうな。どうせ大したものじゃありますまい」
試みに曹操が手に取って開いてみると、自分の書いたものと一字一句も違わない。いよいよ心中に、この怪士、生かしおくべからずと誓った。
左慈は曹操のそばへ進んで言う。
「大王に不老の千載酒(1千年の寿命が得られる酒)を差し上げよう」
そう言うと冠の上の玉を取り、杯の中ほどに一線を描き、その半分を自分が飲んでから献ずる。曹操が酒を含んでみると、まるで水っぽくて飲めたものではない。
★『三国志演義(4)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第68回)では、曹操はこの酒を飲んでいなかった。
思わず杯を下に置き、癇癪(かんしゃく)を破裂させようとした刹那、左慈はサッと手を伸ばして杯を奪い取り、堂の天井へ向かって放り上げた。
人々はアッと目を上げる。杯は一羽の白鳩(シロバト)に変じ、羽ばたきして飛び回っている。あるいは低く降りて酒をこぼし、花を倒し、客の肩や顔に戯れ回って果てしない。
満座みな怪しみうろたえているうち、いつの間にか左慈の姿は消えていた。曹操は宮門を閉じるよう命じたが、もう左慈と思われる老人が城外の街をうろついているという。
曹操は許褚に命じ、いかなる犠牲を払っても捕らえてくるよう命ずる。大げさにも許褚は万一を思い、親衛軍中の屈強な500騎をひきいて追いかけた。
★井波『三国志演義(4)』(第68回)では、許褚は300の鉄騎(精鋭の騎兵)をひきいて左慈を追っている。
(02)鄴都の郊外
許褚は左慈に追いついたと思ったが、いかに悍馬(かんば)に鞭(むち)を打っても、少しもその後ろ姿に近づくことができない。やがて山のふもとまで来ると、部下の500騎に命じて弓で射止めようとした。
ところが、彼方(かなた)の左慈の姿は矢の先に消え、悠々と地上に遊んでいる羊の群れだけがあった。許褚は駆けつけるやいな、数百匹の羊を一匹残らず打ち殺す。
そして引き返してくると、途中でおいおいと泣いている童子に出会う。「こら、童子。何を悲しむか?」と尋ねると、彼は恨めしそうに言った。
「おらの飼っている羊を自分の手下に殺させておきながら、何を悲しむかもないもんだ。馬鹿野郎!」
童子は罵って逃げ出す。部下のひとりは、あれも怪しいと矢をつがえ、後ろから放った。だがいくら射ても、矢はヘロヘロと地に落ちてしまう。その間に童子はわが家に飛び込み、もっと大きな声で泣き抜いていた。
(03)鄴都 魏王宮
翌日、童子の親が魏王宮へ謝りに来た。
昨日、家の腕白がお城の大将に向かって、羊を殺されたいまいましさのあまり、悪口を叩いて逃げたそうですが、今朝起きてみると、一夜のうちに死んだ羊がみな生き返り、いつものように牧場で群れ遊んでいる。
不思議でたまらないが、事実なので、何はともあれ、小倅(こせがれ)の罪をお詫びに参りました、と言うのである。
許褚の報告を聞いていたところへ、またこの奇怪な訴え。曹操は悪寒がしてきた。
「どうあっても捜し出せ。どうあっても打ち殺してしまわねばならん」
王宮の画工を呼び、左慈の肖像を描かせる。その人相書きを原本とし、各地に数千枚の同じ図を配布した。
「召し捕りました」「捕らえました」と、3日もするうちに、郡県から4、500人も同じ左慈を差し立ててくる。王宮の獄は左慈だらけになってしまった。
★井波『三国志演義(4)』(第68回)では、左慈そっくりの風体の者が3、400人も捕らえられたとあった。
そのどれを見ても、びっこで眇(すがめ)である。そして藤の花を挿し、青い衣を着ている。
「よいよい。いちいち調べるのも煩わしい」
曹操は命じて、城南の練兵場に破邪の祭壇をしつらえさせる。そこへ羊や猪(イノコ)の血を注ぐと、4、500人の左慈を数珠つなぎに引き、一斉に首を刎(は)ねてしまう。
すると屍(しかばね)の山から一道の青気が上り、空中に霧のごとく、ひとりの左慈が姿を見せた。彼は白い鶴に乗っていた。魏王宮の上を悠々と飛翔(ひしょう)しながら、やがて手を打ち叩き、宇宙から呼ばわる。
「玉鼠(ぎょくそ)金虎ニ随(したが)ッテ、奸雄(かんゆう)一旦ニ休(や)マン」
★井波『三国志演義(4)』(第68回)では、「土の鼠(ネズミ)が金の虎に従うとき、奸雄も一巻の終わりだ」とあった。
★井波『三国志演義(4)』の訳者注によると、「(『土の鼠が……』は)曹操が庚子(かのえね)の年(建安〈けんあん〉25〈220〉年)に死ぬことを暗示する」という。また「鼠は十二支の子。西の方位は五行では金、十干では庚辛(かのえかのと)、星宿では白虎にあたる。『土の鼠が金の虎に従う』とは子が庚に従う、すなわち庚子のこと」ともいう。
曹操は諸将に下知し、雲も裂けよと弓鉄砲を撃ちかけた。たちまち狂風が吹き起こり、沙(いさご。砂)を飛ばし、石を奔らせ、人々は地に面を覆い、天に目をふさいだ。
この日、太陽は妙に白っぽく、雲は酔人の目のように赤い無数の虹を帯びていた。市人も耕田の農夫も「これはいったい何の兆しだろう?」と恐れ怪しみながら、呆然(ぼうぜん)と天地を仰いでいた。
だがその間に、城南の練兵場から黄色い砂塵(さじん)が漠々と走り、王宮の門を入っていったのを見た者があるという。
後で聞けば。練兵場に積み上げられた4、500の屍が、瞬く間にムクムクと起きだし、ひとかたまりの濛気(もうき)となって王宮内へ流れ入った。
やがてそれは池畔の演武堂に走り上がり、4、500体の左慈そのままな姿の妖人が、怪しげな声を張り、奇なる手ぶりや足ぶりをして、約一刻の間も舞い狂っていたということだった。
さしも豪胆な魏の諸将も、これにはみな震え上がり、曹操もまた諸人に助けられ、後閣に狂風を避けた。
その夜から曹操は、「何となく悪寒がする」とか、「風邪ぎみのせいか、物の味が悪い」などと言い始めていた。
管理人「かぶらがわ」より
左慈劇場が最高潮となり、魏王宮は左慈だらけ。左慈が曹操を翻弄(ほんろう)するという設定は、かなり安易な曹操貶(おと)しだと思うのですけど……。吉川先生の巧みな描写は、そのあたりの不満を打ち消すほど素晴らしいものでした。

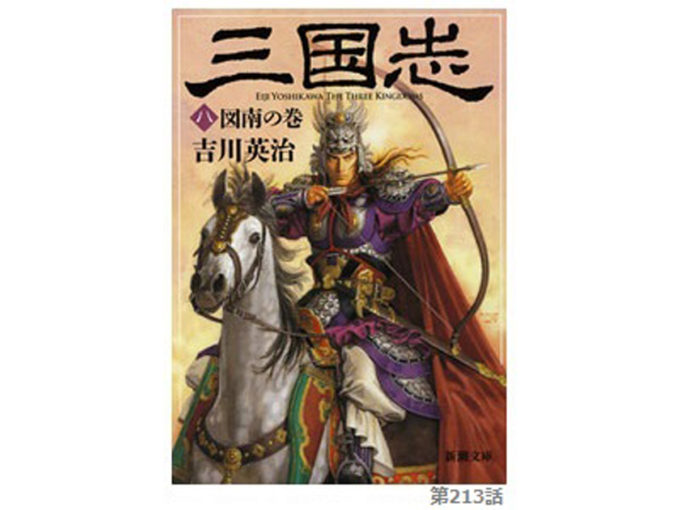















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます