魏の太和(たいわ)4(230)年8月、渭水(いすい)を挟み、司馬懿(しばい)ひきいる魏軍と諸葛亮(しょかつりょう)ひきいる蜀軍が射戦を交えた後、ふたりは陣頭で相まみえ、互いに陣法をもって優劣を競うことにする。
諸葛亮が、司馬懿の布いた陣形を混元一気(こんげんいっき)の陣と見極めると、司馬懿も、諸葛亮の敷いた陣形を八卦(はっけ)の陣と見極める。司馬懿は戴陵(たいりょう)・張虎(ちょうこ)・楽綝(がくりん)に打破の法を授けて攻めかからせる。
第296話の展開とポイント
(01)祁山(きざん) 諸葛亮の本営
魏は渭水を前に、蜀は祁山を後ろに、対陣のまま秋に入った。
ある日、諸葛亮は敵のほうを眺めてつぶやく。
「曹真(そうしん)の病は重体とみえる……」
斜谷(やこく)から敗退した後、魏の大都督(だいととく)の曹真が病に籠もるとの風説は、かねて伝わっていた。
どうしてその重体がわかりますか、と傍らの者が聞くと、諸葛亮はこう答えた。
「軽ければ長安(ちょうあん)まで帰るはずである。今なお渭水の陣中に留まっているのは、その病が甚だ重く、また士気に影響するところを恐れ、敵味方に秘しているからだろう」
諸葛亮はこうも言い、曹真あての戦書をしたため、軍使を遣って送りつける。その辞句はすこぶる激越なものだったという。
「予の考えが的中していれば、おそらく彼は10日のうちに死ぬだろう。試みにそれを問うてみよう」
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第100回)では、諸葛亮は魏の秦良(しんりょう)配下の降卒を釈放するにあたり、曹真あての手紙を届けるよう命じていた。
果たして、明答がない。梨の礫(つぶて)だった。
それからわずか7日後、黒布に包まれた柩車(きゅうしゃ)と、白い旗や幡(はん。幟〈のぼり〉)を立てた寂しい兵列が、哀愁に満ちた騎馬の一隊に護られて、密かに長安のほうへ流れていったという知らせが、物見の者から蜀の陣に聞こえる。
諸葛亮は、曹真の死を明言したうえで諸軍を戒めた。
「やがて今までにない猛烈な軍容をもって、魏が攻撃を取ってくるに違いない。ゆめゆめ油断あるな」
(02)洛陽(らくよう)
魏の中では、このような言が行われていた。諸葛亮が書をもって曹真を筆殺した、というのである。事実、重病だった曹真は、彼の戦書を一読した刹那から極度に興奮して危篤に陥り、まもなく果てたものだった。
★史実の曹真は(魏の)太和5(231)年3月に洛陽で死去している。吉川『三国志』や『三国志演義』(第100回)では、曹真が陣中で憤死したように描いているため、このあたりの時間的な経過がつかみにくくなっている。
これが宮中に聞こえるや、曹叡(そうえい)と門葉の激高はただならぬものがある。蜀に対する敵愾心(てきがいしん)は、延(ひ)いて司馬懿への激励鞭撻(べんたつ)となった。一日も早くこの恨みに報いよと、朝命は続々と陣へ下る。
(03)祁山 諸葛亮の本営
諸葛亮のもとに、司馬懿から先の戦書への返答が届く。
「曹真亡けれど、司馬懿あり。軍葬のこと昨日に終わる。明日は出でて、心ゆくまで会戦せん」
諸葛亮は一読後、莞爾(かんじ)として、「お待ちする。よろしく」とのみ口上で答える。返書は書かず、言づてだけで軍使を帰した。
(04)渭水
時は(魏の太和4〈230〉年の)秋8月、両軍はこの大天地に展陣した。
渭水を挟んで射戦を交え、やがて両々鼓角を鳴らして迫り合うや、門旗を開いて、司馬懿を中心に諸将一団となり、水のほとりまで進んでくる。
時を同じくして、諸葛亮も蜀軍を分け、四輪車を進めて羽扇を握り、その姿を近々と敵に見せていた。
陣頭で言葉を交わした諸葛亮と司馬懿。まずは陣法をもって戦うことにする。
先に司馬懿が一陣を布いてみせるが、諸葛亮は混元一気の陣と見極める。続いて諸葛亮も一陣を布くと、司馬懿は八卦の陣と見極める。
諸葛亮から、実際に陣を破ってみるよう言われると、司馬懿は戴陵・張虎・楽綝を差し招き、打破の法を授けた。
「いま孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)が布いた陣には八門がある。名付けて、休(きゅう)・生(せい)・傷(しょう)・杜(と)・景(けい)・死(し)・驚(きょう)・開(かい)の八部とし、うち開・休・生の三門は吉。傷・杜・景・死・驚の五門は凶としてある」
「すなわち東の生門、西南の休門、北の開門。こう三面より討って入れば、この陣は必ず敗れ、味方の大勝を顕すものとなる。構えて惑わず、法の通りに打ってかかれ」
★井波『三国志演義(6)』(第100回)では、まず真東の生の門から攻め入って、西南の休の門から飛び出し、もう一度真北の開の門から突入すれば、この陣は打ち破ることができるとあった。
魏の三軍は一斉に鼓を鳴らして鉦(かね)を励まし、八陣の吉門を選んで猛攻を開始した。
★井波『三国志演義(6)』(第100回)では、戴陵・張虎・楽綝が30騎ずつをひきいて、生の門から突入したとある。
けれど、諸葛亮の一扇一扇は不思議な変化を八門の陣に呼び、攻めても攻めても連城の壁を巡るがごとく、その内陣へ突き入る隙が見いだせない。
このうち魏軍は、重々畳々と諸所に分裂を来し、戴陵や楽綝ほか60騎は挺身(ていしん)して蜀の中軍へ突入していたものの、あたかも旋風の中へ飛び込んでしまったように、惨霧濛々(もうもう)と度を失う。
ここかしこに射立てられ、叫喚する味方の騒乱を感ずるだけで、少しも統一が取れない。のみならず気がついたときには、彼らは完全に捕虜となっていた。重囲を圧縮され、武装解除を受くるの地位に立っていたのである。
諸葛亮は、車から一眄(いちべん)して言う。
「これは当然の結果で、別に奇妙とするにも足らん。解き放して魏軍へ追い返してやれ。汝(なんじ)らは司馬懿によく申し伝えよ。『かかる拙なる戦法をもって、安(いずく)んぞわが八陣を破り得べき。もう少し兵書を読み、身に学問を加えよ』と」
戴陵や楽綝たちは恥じ入り、諸葛亮の姿を仰げなかった。
また、諸葛亮はこうも言う。
「すでにひとりでもわが陣内を踏みにじったことは無興である。生命を取るのも大人げないが、ただこのまま返すのも戒めとならぬ」
「擒(とりこ)ども60余名の太刀や物の具を剝ぎ取って赤裸となし、顔に墨を塗り、陣前より囃(はや)しては追い、囃しては返すべし――」
司馬懿はこれを眺めて烈火のごとく怒った。戴陵や楽綝らに加えられた辱めは、言うまでもなく自分への嘲弄である。
司馬懿は自ら剣を抜くと、左右の100余騎の大将を督し、麾下(きか)数万の兵力を一手に併せて、大山(たいざん)のおめき崩るるごとく、蜀軍へ向かって総攻撃の勢いに出た。
ところがこのとき、図らざる後方から、味方の軍とも思われぬ盛んな喚声と攻め鼓を聞いた。振り返ってみると、砂雲漠々として、こなたに迫る二大隊がある。
司馬懿は絶叫して、にわかに指揮を変えたが、すでに迅雷は魏軍の後方を撃っていた。いつの間にか迂回(うかい)した、蜀の姜維(きょうい)と関興(かんこう)の二将がおめき込んできたのである。
管理人「かぶらがわ」より
諸葛亮の八卦の陣を打破できず、思わぬ奇襲まで受けてしまった司馬懿。ここでは曹真の死が、魏軍を奮い立たせたような話になっていました。本文中でも触れましたが、史実の曹真は魏の太和5(231)年に洛陽で病死しています。
曹真の死と、諸葛亮が送ったという戦書を絡めることで、より劇的に見せているのでしょうね。ただ正史『三国志』における曹真は、こういうダメっぽい人物ではないですよ。

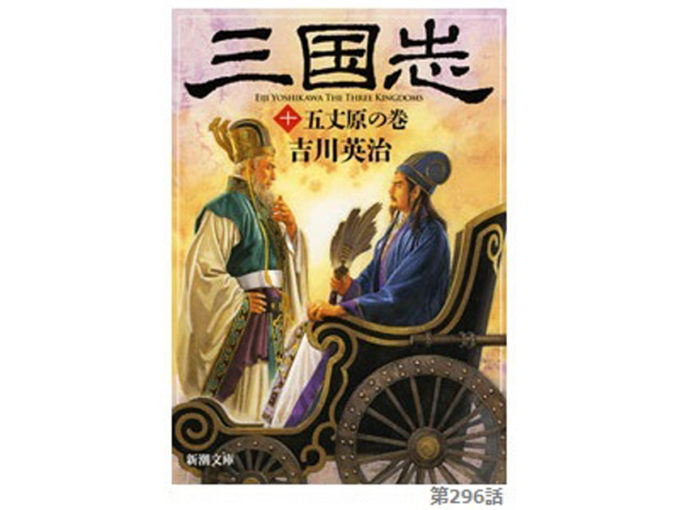














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます