街亭(がいてい)の敗戦以来、諸葛亮(しょかつりょう)は漢中(かんちゅう)に留まって蜀軍の再編制にあたり、ようやく目的を遂げつつあった。
趙雲(ちょううん)の訃報に接した後、諸葛亮は劉禅(りゅうぜん)に「後出師表(こうすいしのひょう)」を奉呈。出兵の許しを得ると、自ら30万の大軍をひきいて陳倉(ちんそう)へ進撃する。
第288話の展開とポイント
(01)洛陽(らくよう)
魏の大司馬(だいしば)の曹休(そうきゅう)は、石亭(せきてい)の大敗を深く恥じ恐れて洛陽へ逃げ戻ったが、まもなく癰疽(ようそ。悪性の腫れ物)を病んで亡くなってしまう。
彼は国の元老であり、帝族のひとりでもある。曹叡(そうえい)は勅して厚く葬らせた。するとその大葬を機に、呉の抑えとして南の境にいた司馬懿(しばい)が、取るものも取りあえず上洛する。
諸将が怪しんで尋ねると、司馬懿はこう答えた。
「お味方は街亭に一勝したが、その代わり呉に一敗を受けてしもうた。孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)は必ずお味方の敗色をうかがい、再び迅速な行動を起こしてくるに違いない」
「隴西(ろうせい)の地が急なるとき、誰がよく孔明を防ごうか? かく言う司馬懿のほか人はないと思う。それゆえに急ぎ上ってまいった」
これを聞いた者は笑う。
「彼は案外、卑怯(ひきょう)だぞ。呉は強いが蜀は弱い。そう見ておるのだ。先の一戦に味を占め、呉には勝てんが、蜀になら勝てるつもりでおるのだろう」
しかし、このような毀誉褒貶(きよほうへん)を気にかける司馬懿でもない。彼は彼として深く信ずるものあるがごとく、折々に悠々と朝(ちょう)に上り、また洛内に自適していた。
(02)漢中
時に諸葛亮もまた、以来漢中にあって軍の再編制を遂げ、その装備や軍糧などもまず計画通りに進み、おもむろに魏の間隙をうかがっていた。
呉の石亭での大勝が伝わると、成都(せいと)から三軍へ酒が下賜される。諸葛亮は一夜、盛宴を張って恩賜を披露し、併せて将士の忍苦精励を慰めた。
すると宴もたけなわのころ、一陣の風が吹き、庭上の老松の枝が折れる。諸葛亮はふと眉を曇らせたが、なお将士の歓を興ざめさせまいと、何げない態で杯を重ねていた。
そこへ侍中(じちゅう)の一士が取り次ぐ。
「ただいま趙雲の子の趙統(ちょうとう)と趙広(ちょうこう)が、ふたりして参りましたが、これへ召しましょうか?」
聞くと諸葛亮はハッとした顔をし、嗟嘆(さたん)しながら手の杯を床へ投げてしまう。
「あぁ、いけない。趙雲の子が訪ねてきたか。老松の梢(こずえ)はついに折れたそうな――」
彼の予感は当たっていた。やがてそこへ導かれてきたふたりの子は、「昨夜、父が亡くなりました」と、趙雲の病没を知らせに来たのである。
諸葛亮は耳をそばだてて惜しみ、潸然(さんぜん)と涙した。
「趙雲は先帝(劉備〈りゅうび〉)以来の功臣。蜀の棟梁(とうりょう)たる者であった。大きくは国家の損失であるし、小さくは、わが片臂(かたひじ)を落とされたような心地がする」
(03)成都
この悲しみは、ただちに成都へも報ぜられる。劉禅も声を放って泣いた。
「むかし当陽(とうよう)の乱軍中に、趙雲の腕(かいな)に救われなかったら、朕が今日(こんにち)の命はなかったものである。悲しいかな、いまその人は逝く」
勅して順平侯(じゅんぺいこう)と諡(おくりな)し、成都郊外の錦屛山(きんびょうざん)に国葬をもって厚く祭らしめた。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「錦屛山は山の名。益州(えきしゅう)蜀郡に属す。現在の四川省大邑県(だいゆうけん)東。後漢・三国時代にこの地名はなかった」という。ちなみに、先の第196話(01)で出てきた錦屛山とは別の山だった。
★このことについて、同じく『三国志演義大事典』によると「(錦屛山は)閬中山(ろうちゅうざん)ともいう。益州巴郡(はぐん)に属す。現在の四川省閬中県南。ふたつの峰が屛風のようにそそり立ち、四季の花が錦のように入り乱れて咲くことからこの名がある」という。
また、遺子の趙統を虎賁中郎将(こほんちゅうろうしょう)に任じ、弟の趙広を牙門将(がもんしょう)に任じて、父の墳(つか)を守らせた。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第97回)では、趙統を虎賁中郎に任じ、趙広を牙門将に任じて、父の墓守をするよう命じたとある。
ここへ漢中から、諸葛亮の使いとして楊儀(ようぎ)が到着。劉禅の闕下(けっか。ここでは御前の意)に伏し、恭しく一書を奉呈する。
これなん諸葛亮が再び悲壮なる第二次北伐の決意を披歴した、いわゆる「後出師表」であった。
表に言う。
「漢と賊とは両立しない。王業はまた偏安すべきものではない。これを討たざるは、坐(ざ)して亡(ほろ)ぶを待つに等しい。坐して亡びんよりは、むしろ出でて討つべきである。そのいずれがよいかなど、議論の余地はない」
諸葛亮は表の冒頭に、まずこのような大正案を下していた。彼の抱持する理想とその主戦論に対し、いまなお成都の文官中には、消極論がまま出るからであった。
しかし彼は筆を進めて、「この業たるや、けだし一朝一夕に成るものではなく、魏を撃滅することの困難と百忍を要することは言うまでもない」と、慎重かつ悲調なる語気をもって、魏の強大な戦力と蜀の不利な地勢弱点を正論する。
また今日、自己が漢中に留まり、戦衣を解かないでいる理由を6か条に分けて記し、不撓不屈(ふとうふくつ)、ただ先帝の遺託に応え奉るの一心と国あるのみの赤心を吐露した。
そして末尾の一章には、悲壮極まる言葉が読まれた。
「今、民窮シ、兵疲ルルモ、事熄(や)ムベカラズ、僅(わず)カニ一州ノ地ヲ以テ、吾(わ)レニ十倍ノ賊ト持久セントス。コレ臣ガマダ解カザルノ一也」
「臣、タダ鞠躬尽力(きっきゅうじんりょく。一所懸命に尽くすこと。鞠躬尽瘁〈きっきゅうじんすい〉)、死シテ後(のち)已(や)マンノミ。成敗(せいはい)利鈍ニイタリテハ、臣ガ明ノヨク及ブトコロニ非(あら)ザル也。謹ンデ表ヲタテマツッテ聖断ヲ仰グ」
★この表は(蜀の)建興(けんこう)6(228)年冬11月付になっていた。また井波『三国志演義(6)』(第97回)では、「後出師表」に書かれていた物故者にも触れており、趙雲をはじめ、陽羣(ようぐん)・馬玉(ばぎょく)・閻芝(えんし)・丁立(ていりゅう)・白寿(はくじゅ)・劉郃(りゅうこう)・鄧銅(とうどう)の名を挙げていた。だが、吉川『三国志』ではこのくだりを(おそらく意図的に)省いており、趙雲以外の7人は文中にも名が見えない。
先ごろ魏はおびただしい軍勢を呉の境に出したものの、戦い利あらず。のち曹休も没し、以後、魏の関中にはかつてのごとき勢いはなく、また戦気も見えない。
★『三国志演義大事典』によると「関中は現在の陝西省(せんせいしょう)関中盆地。東を函谷関(かんこくかん)、南を武関(ぶかん)、北を蕭関(しょうかん)、西を散関(さんかん)に囲まれていることからこの名がある」という。
西域の守りも自然、脆弱(ぜいじゃく)を免れまいと見た諸葛亮が、この再挙の機を捉えて、表を上せてきたものであることは、すでに言外にあふれている。
もとより劉禅は許した。これを受け、ただちに楊儀は漢中へ帰っていく。
(04)漢中
諸葛亮は詔(みことのり)を拝すと、半年余りの慎重な再備と軍紀に結集された蜀の士馬30万を起こし、陳倉道へ向かって進発した。
この年、諸葛亮48歳。時は冱寒(ごかん。厳しい寒気)の真冬。天下に聞こゆる陳倉道の険と四山の峨々(がが)は、万丈の雪に包まれ、眉も息も凍てつき、馬の手綱も氷の棒になるような寒さだった。
(05)洛陽
魏の境界にある常備隊は、漢中の動きを見るや大いに驚き、この由を洛陽へ伝令する。
「諸葛亮、再び侵攻す。蜀の大軍、無慮数十万。急ぎ防戦のお手配あれ」
曹叡は群臣を集めて問うた。
「果たして、諸葛亮はまた襲ってきた。長安(ちょうあん)の一線を堅守して、国防の全きを保つにはそも、誰を大将としたらよいか?」
この席にあった大将軍(だいしょうぐん)の曹真(そうしん)が、面目なげに言う。
「臣、先に隴西に派せられ、祁山(きざん)において諸葛亮と対陣し、功少なく罪は大でした。密かに慙愧(ざんき)して、いまだ忠を攄(の)ぶることができないのを恥ずかしく思っております」
「ですが、近ごろひとりの頼もしき大将を得ました。彼はよく60斤に余る大刀を遣い、千里の征馬に乗ってもなお鉄胎の強弓を引きます」
「また、その身には2個の流星鎚(りゅうせいつい)を秘し持って、一放すればいかなる豪敵も倒し、百(もも)たび発して百たび外すことがありません。願わくはこの者こそ、このたびは臣の先鋒にお命じ賜わらんことを」
★井波『三国志演義(6)』の訳者注によると、「流星鎚は飛鎚。紐(ひも)の両端に鎚(おもり)を付け、敵に当てるほうを正鎚、自分の手に残すほうを救命鎚と称する」という。
曹叡がすぐ呼ぶよう言うと、ほどなく殿上に一怪雄が現れた。身の丈7尺(せき)、目は黄色で面は黒い。腰は熊のごとく、背中は虎に似ている。しかもそれに盛装環帯して、傲岸(ごうがん)世になきがごとき大風貌をしていた。
★井波『三国志演義(6)』(第97回)では、王双(おうそう)の身長は9尺とある。
曹叡は喜び眺め、曹真に「彼の産はどこか?」と尋ねる。
曹真が直答するよう促すと、怪雄は伏して奉答した。
「隴西郡狄道県(てきどうけん)の生まれで王双、あざなを子全(しぜん)と申す者でございます」
曹叡は即座に、王双を前部大先鋒(ぜんぶだいせんぽう)に任じ、また虎威将軍(こいしょうぐん)の称号を授ける。
さらに「これは汝(なんじ)の偉軀(いく)に似合うだろう」と、鮮やかな錦の戦袍(ひたたれ)と黄金の鎧(よろい)を下賜した。
そして、なお曹真に言う。
「恥じて恥にひるむな。再び大都督(だいととく)として戦場に行き、先の戦訓を生かして諸葛亮を破れ」
こうして曹叡は、曹真に前の通り総司令官たる印綬(いんじゅ。官印と組み紐)を授けた。
曹真は恩を謝し、洛陽の兵15万を引き連れ、長安へ行って郭淮(かくわい)や張郃(ちょうこう)らの軍勢と合する。これらを前線諸所の要害に配し、防戦の備えを万端整え終わった。
(06)陳倉の城外
すでに漢中を発した蜀軍は、陳倉道を進むうち、ここの隘路(あいろ)と三方の険を負って、「通れるものなら通ってみよ」と言わんばかりに要害を構えている一城にぶつかっていた。
これなん先に魏が諸葛亮の再征を見越して、早くも築いておいた陳倉城で、そこを守る者も忠胆鉄心の良将、かの郝昭(かくしょう)である。
蜀の諸将は言った。
「この大雪に、この険路。加うるに魏の郝昭が要害に籠もっていては、とても往来はなりますまい。道を変えて太白嶺(たいはくれい。太白山〈たいはくざん〉)の鳥道を越え、祁山へ打って出てはいかがでしょう」
しかし、諸葛亮は容れずに応える。
「この一城をだに攻め落とせないようでは、祁山へ出たところで魏の大軍には勝てまい。陳倉道の北は街亭にあたる。この城を陥して味方の足だまりとなせ」
魏延(ぎえん)に攻撃の命を下して連日攻めさせたが、城は揺るぎもしない。
このとき、蜀の陣中に勤祥(きんしょう)という者があった。その勤祥が、敵の守将の郝昭とは同郷の友だと名乗り出て、諸葛亮に献言する。
★勤祥は、正史『三国志』や『三国志演義』では靳詳とある。
「ひとつ私を、城下まで出してください。郝昭とは、ずいぶん親しい間柄でしたが、私が西川(せいせん。蜀)に流落して以来、つい無沙汰のままに過ぎていました。懇々と利害を説いて、彼に降伏するよう勧めてみます」
諸葛亮は望むところと、その乞いを許す。勤祥は城門の下から呼びかけた。
「友人の勤祥である。久しぶりに郝昭に会いたくてやってきた」
(07)陳倉
郝昭は櫓(やぐら)から一見した後、門を開いて懐かしげに迎え入れる。勤祥は彼を説き、諸葛亮に引き合わせたいと言ったが、まったく相手にされない。
勤祥が帰ろうとしないため、郝昭は部将に命じて馬を引かせ、有無を言わせず、その背に押し上げる。そして城門を開かせると、自ら槍の柄で馬の尻を殴った。
(08)陳倉の城外 諸葛亮の本営
勤祥はありのままを復命する。ところが諸葛亮は、もう一度行って、さらに利害を説くよう命じた。郝昭の人物が惜しまれていたのである。
(09)陳倉の城外
勤祥は甲衣馬装を飾り、今度は堂々と城の壕際(ほりぎわ)に立つと、城中の郝昭に向かって呼びかけた。
「量るにこの一孤城、如何(いか)んぞ蜀の大軍を防ぎ得べき」
「わが丞相(じょうしょう。諸葛亮)は足下(きみ)の英才を惜しんでやまぬゆえに、再びそれがしをこれへ差し向けられたものだ。この機を逸せず、門を開いて蜀に降り、またこの勤祥とも、長く交友の楽しみを持て」
★ここで勤祥が諸葛亮のことを「わが丞相」と呼んでいたが、諸葛亮は街亭の敗戦の責任を取る形で、自ら願い出て右将軍(ゆうしょうぐん)に降格された。先の第286話(02)を参照。実際のところは形式的な降格で、後に丞相職に復帰していることもあり、勤祥ら蜀の将兵からすれば、ずっと「わが丞相」でいいのだとは思う。
郝昭は櫓の上から言い返す。
「言うをやめよ。汝とそれがしとは、なるほど、かつては相識(そうしき)の友であったが、弓矢の道では知り合いでもない。いったん魏の印綬を受け、たとえ100人の寡兵なりと、この身を信じて預け賜ったからには、その信に答うる義のなかるべきや」
「我は武門、汝は匹夫。いま一矢を汝に与えぬのも、武士の情けだ。戦の邪魔、疾(と)く疾く失せよ」
郝昭が櫓の上から姿を隠すと、たちまちおびただしい矢弾が空にうなった。勤祥は是非なく立ち戻り、ついに諸葛亮の前で匙(さじ)を投げる。
すると諸葛亮は、ひと言に決した。
「よし。このうえは、私自身が指揮して踏み破るまでのことだ」
管理人「かぶらがわ」より
趙雲の死をもって、かつての五虎大将軍(ごこだいしょうぐん)も、ついにみないなくなりました。時の流れを感じます。
★五虎大将軍について、井波『三国志演義(5)』(第73回)では五虎大将となっていた。
「後出師表」を奉呈し、陳倉道から進軍する諸葛亮でしたが――。ここは陳倉城の備えといい、郝昭の起用といい、司馬懿の読みが冴えてましたね。

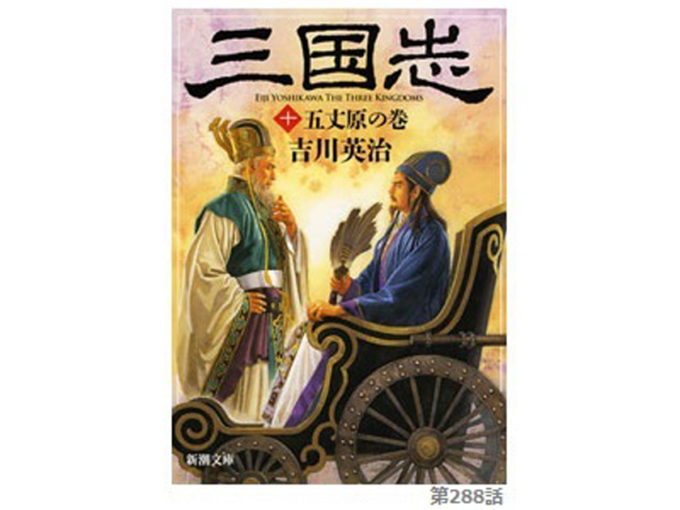















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます