4輛(りょう)の同じ四輪車を用いた諸葛亮(しょかつりょう)の巧妙な計に、司馬懿(しばい)ひきいる魏軍は大混乱を起こす。
やがて司馬懿は、捕らえた蜀兵から真相を聞きだすが、かえって諸葛亮の知謀に恐れを抱く。
第299話の展開とポイント
(01)隴上(ろうじょう)
「なるほど、妖気が吹いてくる……」
司馬懿は眸(ひとみ)を凝らして遠くを望み見ていた。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「隴上は地域名。隴山、現在の陝西省(せんせいしょう)隴県以西を指していう。現在の甘粛省に相当」という。
陰風を巻いて駆けきたる一輛の車には、それを囲む28人の黒衣の兵が見える。髪をさばいて剣を佩(は)き、みな裸足。北斗七星の旗はその先頭を駆け、炎の飛ぶがごとき赤装束の騎馬武者が全軍を叱咤(しった)してくる。
なおも司馬懿が見守っていると、諸葛亮の姿が見えた。四輪車は鳴り走ってくる。車上の白衣簪冠(しんかん。簪〈かんざし〉で髪を留めた冠)の人影こそ、紛れなき諸葛亮に違いない。夜目にも遠目にも鮮やかだった。
突然、司馬懿は大笑する。そして旗本以下、屈強な兵2千を後ろから差し招き、ただちに号令した。
「鬼面人を嚇(おど)すというやつだ。怪しむことはない。恐れることもない。破邪の剣を振るって駆け崩してみろ。化けた孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)も裸足になって逃げ出すだろう」
「汝(なんじ)らが迅速なれば、その襟髪をつかんで、彼奴(あやつ)を捕虜(とりこ)となすこともできる。それっ、近づいてきた。掛かれっ!」
2千の鉄騎(精鋭の騎兵)は励み合って、武者声を発しながら驀進(ばくしん)した。すると諸葛亮の車はピタリと止まり、28人の黒衣兵も七星の旗も、赤装束の騎馬武者もみなにわかに後ろを見せて、静々と引き退いていく様子。
魏の鉄騎隊は馬に鞭(むち)打ったものの、不思議なことに、追えども追えども追いつかない。
怪しき霧が吹き起こり、白濛々(はくもうもう)黒迷々。彼方(かなた)の車は目の前にありながら、馬は口に泡をかみ、身は汗に濡れるばかりで、少しも距離が縮まらないのである。
あきれ返った魏勢が馬を留め、呆然(ぼうぜん)と怪しみに打たれていると、諸葛亮の車と一陣はまたこちらへ向かって進んできた。
今度こそはと、魏勢がわめいて攻めかかる。だがこちらが走ると、彼方の影は再び後ろを見せ、悠々と騒がず乱れず逃げていく。
またも20余里追う。鉄騎2千はみな息を切らせたが、諸葛亮の車との隔たりは、依然として少しも変わっていない。
「これはいよいよ凡事(ただごと)ではない」と、魏勢は迷いにとらわれ、ひとつところに人馬の旋風(つむじ)を巻いていた。
そこへ後ろから馬を飛ばしてきた司馬懿が、口々に言う嘆を聞くと、さてはと悟り顔になる。にわかに下知を改めて、急に馬首を向け変えた。
「察するにこれは、孔明のよくなす八門遁甲(はちもんとんこう)の一法。『六甲天書(りくこうてんしょ)』の内にいう縮地の法を用いたものであろう」
「悪くすると冥闇必殺の危地へ誘い込まれ、全滅の憂き目に遭うやも計りがたい。もはや追うな。もとの陣地へ退け」
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(八門遁甲は)道教経典『秘蔵通玄変化六陰洞微遁甲真経(ひぞうつうげんへんげりくいんどうびとんこうしんけい)』のことか。招風の術や縮地の法を収め、諸葛亮が習得したと記す」という。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)の訳者注によると、「(縮地の法は)地脈を縮め、千里の彼方にある土地を目前に引き寄せる方術。東晋の葛洪(かつこう)の『神仙伝』では、費長房(ひちょうぼう)がこの術の使い手とされる」という。
すると不意に西方の山から鼓が鳴る。愕然(がくぜん)と闇を透かして望み見ると、星明かりの下を、一彪(いっぴょう)の軍馬が風のごとく駆けてきた。
たちまちその中から28人の黒衣の兵と、北斗七星の旗と、火炎のごとき騎馬の大将が現れて、真っ先に進んでくる。
近づいてきたのを見れば、黒衣の兵はみな髪を振り乱し、白刃を引っ提げて裸足の態。四輪車の上の白衣簪冠の人も、前に追いかけた者と少しも違わない。
「や、や。ここにも孔明がいる?」
司馬懿は味方がひるむのを恐れ、自ら先に立って追いかける。20里、30里と追いかけて馬に鞭打ったが、どうしても近づき得ないことも、前の時と同じだった。
「奇怪だ。これは実に不思議きわまる」
司馬懿すらへとへとになって引き返してくると、また一方の山の尾根から、七星の旗と黒衣の怪兵28人が、同じ人を乗せた四輪車を押し進めてきた。
人か鬼(死者)か? 実か幻か? 魏勢は駭然(がいぜん。驚く様子)と震え上がり、あえて討とうとする者もない。
「退けや、退けや」と、司馬懿も今は、肝も魂も身に添わず、逃げ奔る一方だった。
するとまたまた、行く手の闇の広野に、颯々(さつさつ)たる旗風の声と車輪の音がしてくる。司馬懿は驚倒して目を見張った。車上の人は確かに孔明であり、左右の20余人の黒衣白刃の影も、北斗七星の旗も、初めに見たものと寸分の相違もない。
「いったい孔明は何人いるのか? この分では蜀軍の数も計り知ることができない」
司馬懿と数千の鉄騎は、ほとんど悪夢の中を夜通し駆け歩いたように疲れ果て、翌朝ごろ、ようやく上邽(じょうけい)へ逃げ帰ってきた。
(02)上邽
その日、ひとりの蜀兵が捕虜となる。調べによれば、青麦を刈って鹵城(ろじょう)へ運送していたのだという。
事態を悟った司馬懿が自ら吟味してみると、昨夜の怪しい妖陣のうち、確かに一陣は諸葛亮の車に違いないことがわかった。
だが、あとの三陣の隊伍と車は、姜維(きょうい)・魏延(ぎえん)・馬岱(ばたい)などが偽装していたもので、諸葛亮の影武者にすぎなかったことがわかる。
司馬懿は縮地の法の手段(てだて)が読めたものの、正直に諸葛亮を恐れた。そしていよいよ守るを主としていた。
郭淮(かくわい)がしきりに主張する。
「鹵城にある蜀兵を深く探ってみましたところ、案外に少数です。大軍と見せていたのは諸葛亮の軍(いくさ)立てによる用兵の妙であり、味方の兵力をもって包囲すれば、おそらく袋の鼠(ネズミ)でしょう」
以後、良策のなきまま消極的に堕しすぎていたことを、自身も反省していた司馬懿。郭淮に説かれると言った。
「では、動かずと見せて急に前進し、一挙に鹵城を包囲してしまおう。それが成功すれば、後の作戦はいくらでも立つ」
夕日が西へ沈むころ、上邽の大軍は一度に発足した。鹵城はさして遠くない。夜半までには難しいが、明日の未明には着けるはずである。
(03)鹵城
途中の湿地帯と河原や山を除いたほかは、すべて熟れたる麦の畑。蜀の斥候は、その中に点々と一町おきに隠れていた。
一条の縄から縄が、鹵城のすぐ下までつながっている。一兵が鳴子を引くと、次の兵から次の兵へ鳴子を伝え、電瞬の間に、「魏の襲撃あり」は蜀軍の内へ予報されていた。
そのため諸葛亮は、来たるべき敵に対して策を立て、配備をなし、なお十分に手ぐすね引いているほどの暇を持っていた。
もとより地方の一城なので、塀は低く、濠(ほり)は浅い。城に取りつかれては最期である。姜維・馬岱・馬忠(ばちゅう)・魏延などの諸隊は、おおむねいち早く城外へ出ていた。
★井波『三国志演義(6)』(第101回)では、姜維と魏延がぞれぞれ2千の兵をひきいて、(鹵城の)東南と西北の2か所に潜伏。馬岱と馬忠もそれぞれ2千の兵をひきいて、(鹵城の)西南と東北の2か所に潜伏したとある。
城外は一望の麦野で、潜むには絶好である。深夜の風は麦の穂を波立てていた。音なき怒濤(どとう)のごとく、魏の大軍は迫ってくる。「敵はまだ悟らず」と思ったか、全軍を分散して、城の東西南北に分かち始めた。
と思う間に鹵城の上から、数千の弩(ど)が一度に弦を切って乱箭(らんせん。箭〈矢〉が乱れ飛ぶ様子)を浴びせる。魏軍が濠を越えて城壁にかかると、大石や巨木がなだれ落ちた。浅い濠はたちまち屍(しかばね)で埋まる。
「少々苦戦」と司馬懿はなお励ましていたが、一瞬の後、その少々は大々的に変わった。背後の麦畑がみな蜀兵と化したのである。いかに精鋭な魏軍でも乱れざるを得ない。
暁のころ、司馬懿はひとつの丘に馬を立てて唇をかんでいた。見事に夜来の一戦も敗れたのである。損害を数えると、1千余の死傷者が出ているという。
★井波『三国志演義(6)』(第101回)では、このとき魏軍の出した死傷者は3千以上だった。
(04)上邽
以来また司馬懿は、上邽城の殻に閉じ籠もる臆病なヤドカリになった。郭淮は無念に堪えず、日夜知恵を絞って次の一策を勧める。その計は奇想天外で、ようやく司馬懿の眉を晴れしめるに足りた。
(05)鹵城
鹵城は決して守るにいいところではなかったが、魏軍の動向は容易に計りがたい。諸葛亮もジッと堅守していた。
しかし彼は、この自重も策を得たものとはしていない。なぜなら近ごろ、司馬懿が雍涼(ようりょう。雍州と涼州)に檄文(げきぶん)を飛ばし、孫礼(そんれい)の軍勢を剣閣(けんかく)へ招いているふうが見える。
ひとたび魏がその膨大な兵力を分けて、蜀境の剣閣でも襲うことになろうものなら、帰路を断たれ、運輸の連絡はつかなくなり、ここの陣地にある数万の蜀軍は孤立してしまう。
★剣閣を蜀境(にある)としていることについては、先の第294話(04)を参照。
諸葛亮は、魏延と姜維にこう命じた。
「あまりに動かざるは、かえって、大なる動きあるによるともいう。どうも近ごろ魏軍の静かなのは不審だ。ふたりとも1万騎ずつを連れて、剣閣へ加勢に行け。何となく心もとないのはあの要害である」
魏延と姜維は即日軍勢を整え、剣閣へ向かう。
★井波『三国志演義(6)』(第101回)では、この任務を与えられていたのは姜維と馬岱。
その後、長史(ちょうし)の楊儀(ようぎ)が言った。
「先に漢中(かんちゅう)を発たれる際、丞相(じょうしょう。諸葛亮)は軍をふたつに分けられ、100日交代で休ませると宣言なされたでしょう。どうも弱ったことです」
諸葛亮がさらに聞くと、楊儀は続ける。
「もはやその100日の日限が来たのです。前線の兵と交代する漢中の兵は、もうかの地を出発したと伝えてまいりました」
諸葛亮は、すでに法令化した以上、一日もたがえてはならないとし、ここにいる8万の軍勢を、4万ずつ二度に分けて還すよう命ずる。諸軍は大いに喜び、それぞれ帰還の支度をしていた。
ところが、ここへ剣閣から早馬が着く。魏の孫礼が、雍涼の勢を新たに20万騎も募り、郭淮とともに猛攻してきたという。
それに加え、司馬懿が時を同じくして、全軍に総攻撃の命を発し、今しもここへ押し寄せてくるとも伝えてきた。蜀軍が驚き恐れたことは言うまでもない。
楊儀は倉皇と諸葛亮に告げる。
「こうなっては交代どころではございません。帰還のことはしばらく延期し、目前の敵の強襲を防がせねばなりますまい」
だが、諸葛亮は強く面を横に振って言った。
「わが師(いくさ)を出して、多くの大将を用い、数万の兵を動かすも、みな信義を本(もと)としていることである。この信義を失っては蜀軍に光彩もなく、大きな力は出せなくなる」
「また彼らの父母や妻子も、すでに百日交代の規約を知っておるゆえ、家郷にあって指折り数え、わが子やわが夫の帰りを門(かど)に待っているだろう。たとい今いかなる難儀に及ぶとも、予はこの信義を捨てることはできない」
さっそく楊儀は、この言葉を蜀軍の兵に告げた。それまでいろいろと臆測して、多少の動揺を見せていた兵たちも、諸葛亮の心を聞くと涙を流す。
彼らはこぞって願い出た。
「願わくは命を捨て、丞相のご高恩に報ぜん」
諸葛亮はなお還れと勧めたが、彼らは結束して踏みとどまる。そして目に余るほどの魏の大軍に反撃を加え、ついには先を争って城外へ突出。雍涼勢の新手をも粉砕し、数日の間に、さしもの敵を遠く退けてしまった。
けれど、一難去ればまた一難。全城が凱歌(がいか)に沸き満ちている暇(いとま)もなく、永安城(えいあんじょう)にある李厳(りげん)から、図らずも意外な急報を告げてきた。
管理人「かぶらがわ」より
縮地の法って――。この手の不思議戦術の登場には、どうも抵抗感が抜けません。
『三国志』(蜀書・諸葛亮伝)の中で、郭沖(かくちゅう)の諸葛亮弁護を裴松之(はいしょうし)が次のように批判していました。
「諸葛亮の大軍が関(関中?)や隴(隴西?)にいるのに、どうして魏の兵がそれらを通り過ぎ、剣閣へ直行することができるのだろうか?」
★『三国志演義大事典』によると、「関中は現在の陝西省関中盆地。東を函谷関(かんこくかん)、南を武関(ぶかん)、北を蕭関(しょうかん)、西を散関(さんかん)に囲まれていることからこの名がある」という。
これは確かにおっしゃる通り。少数の部隊が密かに急行したというならまだしも、魏の大軍が祁山(きざん)の蜀軍を避ける形で、さらに漢中にも気づかれずに、いきなり剣閣へ猛攻してくるというのは……。
また祁山にいた諸葛亮が、守備兵の10分の2ずつを、休養のために代わるがわる下山させていたとする郭沖を、ここでも裴松之が批判。
諸葛亮は戦場に出た後、その地に長期にわたって滞在する計画など、もともと立ててはいなかった。ところが、そのときに兵を休ませ、蜀に帰らせるなどとは、まったくつじつまの合わぬ話であると。百日交代の制を完全否定しています。
この第299話ほど創作が過ぎると、かえって興味も削がれるものだという気がしました。
創作が、というよりも、このあたりの魏蜀の戦いでは、たびたび『三国志演義』の訳者である井波先生も指摘されているように、地理的な誤解が多いのですよね。
特に目立つのは剣閣がらみの記述で、『三国志演義』の作者らは剣閣が実際よりずっと北にあったと誤解されています。

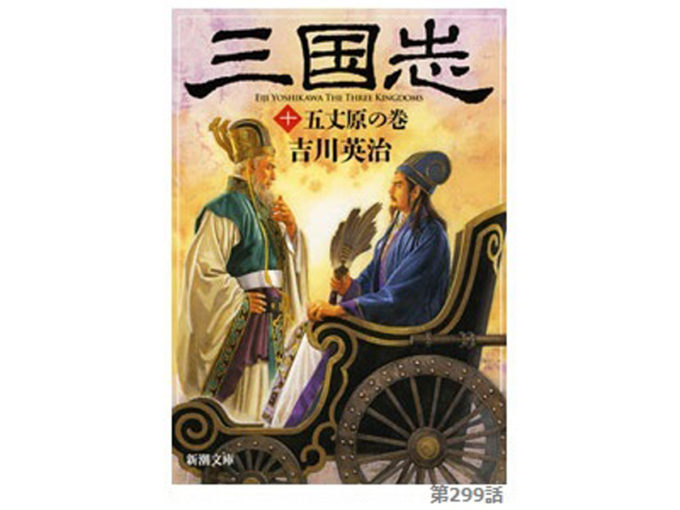














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます