魏は渭水(いすい)に、蜀は五丈原(ごじょうげん)に、それぞれ陣して、なおもにらみ合いを続けていた。
ここしばらく、諸葛亮(しょかつりょう)は体調を崩す日が増えていたが、ある夜、天を仰ぎ見て、己の命数を悟る。それでも姜維(きょうい)の勧めに従い、祭壇を設けて禳(はらい。神を祭って災いを除くこと)の法を執り行う。
第308話の展開とポイント
(01)五丈原 諸葛亮の本営
諸葛亮の病は明らかに過労だった。それだけに、ドッと打ち伏すほどのこともない。むしろ病めば病むほど、傍人の案ずるのも押して、軍務に精励してやまない。
近ごろ聞くに敵の軍中には、気負うこと盛んなる将士が、大いに司馬懿(しばい)の怯惰(きょうだ)を罵り、激語憤動、ただならぬ情勢がうかがわれるとしきりに言ってくる。
原因は例の、諸葛亮から贈られた女衣(にょい)巾幗(きんかく)の辱めが、魏の士卒にまですっかり知れ渡ったこと。そこから再燃した決戦論者の動揺であることが看取される。
★諸葛亮が司馬懿に縞衣(こうい。女衣)と巾幗を贈ったことについては、前の第307話(06)を参照。
諸葛亮は病中ながら、その機微を知るや、心密かに秘策を描く。なお敏捷(びんしょう)な諜者(ちょうじゃ)を放ち、魏勢が出軍するか否か、しっかりと見届けてくるよう命じた。
やがて、帰ってきた諜者が告げる。
「敵の営中に騒然たる戦気は確かに感じられました。けれど営門に一老夫が立っているのです」
「白眉朱面、金鎧(きんがい)まばゆきばかり装って、毅然(きぜん)と突っ立ち、手に黄鉞(こうえつ。黄金の鉞〈まさかり〉)を杖ついて、八方をにらまえ、かりそめにも軍門をみだりに出入りなすを許しません。ために、営中の軍も出ることができないでおりまする」
諸葛亮は、思わず手の羽扇を取り落として言う。
「あぁ、それこそ、先に魏の朝廷から軍監(ぐんかん)として下った辛毘佐治(しんびさじ。左治は辛毘〈辛毗〉のあざな)に違いない。それほどまで厳に戦うを戒めておるか」
一身を蜀に捧げ、すでに自覚される病もおいて、日々これ足らずと努めている諸葛亮にとって、このことはまた大きな失意を加えた。
(02)渭水の北岸 司馬懿の本営
時に渭水の流れは満ち、また河底は涸(か)れ、風雨の日や炎熱の日、天象は日々同じではなかったが、戦局は一向に改まる様子もない。すでに秋は満地の草や花に見え、朝夕の風はようやく冷涼を帯びてきた。
「蜀の陣上には一抹、何やら寂しきものが見える」
ある夕、司馬懿は密かに人を放ち、諸葛亮の陣をうかがわせる。その結果によっては、突如、奇襲して出でんとしたか、銀甲鉄冑(てっちゅう)に身を固め、燭光(しょっこう)密やかに待っていた。
ようやく四更(午前2時前後)のころ、姿を変えて探りに行った将が戻り、額の汗を押し拭いながら復命する。
「蜀陣の旌旗(せいき)は依然、粛として寸毫(すんごう)の惰気も見えませぬ」
「深夜だというのに、諸葛亮は素輿(そよ。白木の輿)に乗って陣中を見回り、常のごとく綸巾(かんきん。隠者がかぶる青糸で作った頭巾。俗に「りんきん」と読む)を頂き白羽扇を持ち、その出入りを見るや衆軍みな敬して、進止軍礼、一糸の乱れも見ることができません」
「実に、驚きました。森厳そのもののごとき軍中の規律です。近ごろ、諸葛亮が病気であるというようなうわさが行われておりますが、おそらくあれも、敵がわざと言わせている噓言(きょげん)でしょう」
司馬懿は嘆じて、息子の司馬師(しばし)や司馬昭(しばしょう)に言った。
「諸葛は真に古今の名士だ。名士とは、彼のごときをいうものだろう」
★『三国志演義(7)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第103回)では、このような形で司馬懿が諸葛亮の陣をうかがわせたことは見えない。
(03)五丈原 諸葛亮の本営
これより先に、諸葛亮から呉へ要請していた蜀呉同盟の条約による第二戦線の展開については、まだここには何の詳報も入っていない。
それはすでに、この年(蜀の建興〈けんこう〉12〈234〉年)の5月、呉の水陸軍が三道から魏へ攻撃を起こしたことによって、条約の表面的な履行は果たされた形になっていたものである。
★ここにある呉の出兵については、先の第304話(01)を参照。
秋の初めごろ、突然、成都(せいと)から尚書(しょうしょ)の費禕(ひい)がやってくる。呉のことを伝えに来たのだという。
諸葛亮はさてこそと思い、その日も容体は何となく優れなかったが、平然と常のごとく応接した。
費禕は唇に悲調をたたえて語る。
「夏5月ごろから、呉の孫権(そんけん)は約30万を動員して三方より北上し、魏を脅かすことしきりでした」
「魏の曹叡(そうえい)も合淝(がっぴ。合肥)まで出陣し、満寵(まんちょう)・田予(でんよ。田豫)・劉劭(りゅうしょう)らの諸将をよく督して、呉軍の先鋒を巣湖(そうこ)に撃砕。呉の兵船や兵糧の損害は甚大でした」
「ために、後軍の陸遜(りくそん)は孫権に表を捧げ、敵の後ろへ大迂回(だいうかい)を計ったもののようでしたが、この計も事前に魏へ漏れたので、機謀はことごとく裏をかかれ、ついに呉の全軍は何らの功もなく、大挙して退いてしまったのです」
「どうも誠に頼みがいなき盟国と言うしかありませんが――」
これを聞いた諸葛亮は急に血色が悪くなる。驚いた費禕は侍臣を呼び立てたものの、人々が駆け寄ったときには袂(たもと)をもって面を覆い、榻(とう。長椅子。ソファーに似た寝台)の上にうっぷしていた。
諸将も来て、ともに搔(か)い抱き、静室へ移す。典医(てんい)に諮り、あらゆる手当てを尽くすと、半刻(はんとき)ほどして面上にポッと血色がよみがえってきた。
諸葛亮は胸を大きく波動させている。そして、ひとつひとつの顔に眸(ひとみ)を注いで言ったが、語尾は独り言のようにしか聞こえなかった。
「思わず病に負けて、日ごろのたしなみも昏乱(こんらん)したとみえる。これは旧病の起こってきた兆(しるし)と言えよう。わが今生の寿命も、これでは久しいことはない」
しかし夕方になると、諸葛亮はこう言った。
「心地はさわやかだ。予を助けて露台に伴え」
侍者や典医などが、そっと抱えて外へ出ると、諸葛亮は深く夜の大気を吸い、「あぁ、美しい」と、秋夜の天を仰ぎ見る。だが突然、何事かに驚き打たれたように、悪寒(さむけ)を催してきたと言って内に隠れた。
諸葛亮は侍者をして、急に姜維を迎えに行かせ、駆けつけた彼に告げる。
「今宵、何げなく天文を仰ぎ、すでにわが命が旦夕にあることを知った。死は本然の相(すがた)に帰するだけのことで、別に何の奇異でもないが、そちには伝えおきたいこともあるので早々に招いた。必ず悲しみに取り乱されるな」
それでも姜維が涙を見せると、諸葛亮は子にするように叱った。
馬謖(ばしょく)の亡き後、その愛は姜維に傾けられている。日常、彼の才を磨いてやることは、珠を愛(め)でる者が珠の光を慈しむようであった。
姜維が、もう泣きませぬと言うと、諸葛亮はこう説く。
「姜維よ。わしの病は天文に現れている。今宵、天を仰ぐに、三台の星はみな秋気燦(さん)たるべきに、客星は明らかに、主星は鈍く、しかも凶色を呈し、異変歴々である。ゆえに、自分の命の終わりを知ったわけだ。いたずらに病に負けて言うのではない」
★『三国志演義 改訂新版』(立間祥介〈たつま・しょうすけ〉訳 徳間文庫)の訳者注によると、「(三台〈の〉星は)三能(さんだい)・天柱とも呼ばれる。地上の三公に擬せられる星。2つずつ、6つの星が並び、それぞれ上台・中台・下台と呼ばれる」という。
また「客星は不意に現れる大きな星で、これが三台のところに現れたので、主星つまり三台の光が映えなくなったことを言うのであろう」ともいう。
すると姜維が言った。
「丞相(じょうしょう。諸葛亮)。それならばなぜ、禳をなさらないのですか? 古くからそういうときには、星を祭り、天を禱(いの)る、禳の法があるではございませんか」
こう促されると、諸葛亮はその準備を言いつける。
「まず鎧(よろ)うたる武者(つわもの)、七々四十九人を選び、みな皁(くろ)き(黒き)旗を持ち、皁き衣を着て、禱りの帳外を守護せしめよ。帳中の清浄や壇の供えは人手を借りることはできない。予が自ら務めるだろう」
「そして秋天の北斗を祭るが、もし7日の間、主灯が消えなければ、わが寿命は今からまた12年を加えるだろう。しかし、もし禱りの途中で主灯が消えたときは、今生ただいま、わが命は終わろう。それゆえの帳外の守護である。ゆめ、余人に帳中をうかがわせるな」
姜維は謹んで命を受け、ふたりの童子に、よろずの供え物や祭具を運ばせる。
諸葛亮は沐浴(もくよく)した後、帳内に入って清掃を取り、壇をしつらえた。一切のことに祭司(さいし)を用いず、やがて北斗を祭る秘室の内に、帳を垂れて閉じ籠もる。
諸葛亮は食を断ち、夜が明けるまで一歩も出ない。これが一日、二日、三日と続く……。
姜維は49人の武者とともに帳外に立ち、諸葛亮の禱りが終わるまではと、以来、彼も食や水を断ち、石のごとく屹立(きつりつ)していた。帳中の諸葛亮はと見れば、祭壇に大きな七盞(しちさん)の灯明が輝いている。
その周りには49の小灯を掛け連ね、中央に本命の主灯一盞を置き、千々種々(ちぢくさぐさ)の物を供え、香を焚き、咒(じゅ。呪)を念ずる。また折々に盤の清水を換え、換えること七度、拝伏して天を禱った。
禱りの必死懸命となるときは、願文を誦(じゅ)する(読む)声が、帳外の武士の耳にも聞こえてくるほどだった。
こうして晨(あした。朝)になると、諸葛亮は綿のごとく疲れ果てたであろう身に、また水をかぶって、病をなげうち、終日、軍務を見ていたという。
管理人「かぶらがわ」より
辛毘の戒めにより、出陣の気配を見せない魏軍。天文を観て自らの寿命を悟った諸葛亮は、最後の望みとも言える禳の法を執り行います。もう大詰め、という感じが強く伝わってきた第308話でした。

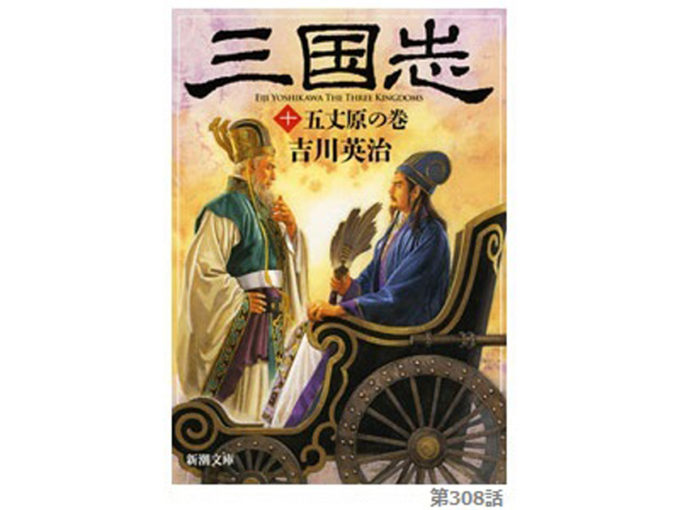















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます