建安(けんあん)23(218)年の正月15日の夜、東華門の門外にある王必(おうひつ)の営中の各所から火の手が上がる。
反乱軍の射た矢を受け落馬した王必は、助けを求めて金褘(きんい)の屋敷を訪ねるが、夫が帰ったものと思い込んだ金褘の妻の口から思わぬ言葉を聞く。
第216話の展開とポイント
(01)許都(きょと) 東華門の門外
街は戸ごとに灯を連ね、諸門の陣々も篝(かがり)に染まる。人の寄るところ、家のあるところ、五彩の灯(ひ)に彩られているため、こよい(建安23〈218〉年の)正月15日の夜、天上一輪の月はなおさら美しく見えた。
東華門の門外にある王必の営中では、宵の口から酒宴が開かれ、将士はもとより馬飼いの小者に至るまで、怪しげな鳴り物を叩いたり、放歌したり、踊ったり、無礼講というので大変なにぎわいだった。
ここへ招かれていた金褘(きんい)は大酔を装い、酒席を退がりかける。
これを目早く見つけた王必が引き留めた。そうしていると、営中の2か所から火が出たと告げる者があり、酒席は一瞬のうちに暗黒となる。金褘の姿はいつの間にか見えなくなった。
王必はあわてて馬に乗り、南門の火の手を望んで走りだしたが、肩に矢を受け、馬上から勢いよく転げ落ちる。
★『三国志演義(5)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第69回)では、王必は耿紀(こうき)が放った一本の矢に腕を射抜かれ、危うく落馬しそうになったとある。
そのとき、西門と南門から営中へ斬り込んできた一隊の反乱軍があった。王必を射たのは先頭に立つ耿紀。
ところが耿紀は、自分の射た敵が、まさか王必だとは思わなかった。もっと営中の奥深くにいると信じていたため、落馬した王必を馬蹄(ばてい)の下にし、先へ奔迅してしまう。
(02)許都の近郊 金褘邸
命拾いした王必は混乱の中に馬を拾い、燃えている南門から市街へ逃げ出す。郊外にある夏侯惇(かこうじゅん)の陣地まで急を告げに行こうとしたものの、道を間違えてあちこち駆け回るうち、肩の傷からあふれ出る血潮に眩暈(めまい)を覚え、また馬を捨てた。
ここで王必は、近くに金褘の屋敷があることを思い出す。その屋敷を尋ね当てると、あわただしく門を叩いた。
門番も奴僕もいないようだが、ほどなく答えがあり、奥のほうから燭(しょく)の光が動いてくる。金褘の妻が門を開けに来たらしい。彼女は扉の閂(かんぬき)を内側から外しながら言った。
「オオ。お帰りあそばせ。今すぐ開けまする。王必は首尾よくお討ち取りになりましたか?」
王必は仰天し、今宵の反乱の張本人が金褘だったことを初めて悟る。「いや、門違いした。ご免」と言い捨てるやいな、今度は曹休(そうきゅう)の屋敷へ行った。
(03)許都 曹休邸
曹休は子細を聞き取ると、すぐに一族と郎党をひきい、火の粉の降りしきる下を禁門(宮門)へ向かって駆け出した。
(04)許都
市中といわず禁門の中といわず、火の狂うところには「逆、曹賊を殺して、順、漢室(かんしつ)の復古を助けよ」という声が上がる。また、もろ声合わせて「死ねや死ねや。漢朝のために」と、悲壮な叫びが聞こえた。
けれど曹休をはじめ、曹氏の一族は市街に戦い、禁門に争い、これもまた命を惜しまず反乱兵と斬り結び、よく宮中を守っていた。
かかるうちに、火は東華門から五鳳楼(ごほうろう)へ燃えてきたので、天子(献帝)は御座所を深宮へ遷(うつ)し、ひたすら成り行きを見守っていた。
そのうち、城外5里に屯(たむろ)していた夏侯惇の3万騎も、続々と市街へ入ってくる。こうなってはもう金褘・耿紀・韋晃(いこう)らの計画も、その成功を期することはおぼつかない。
韋晃は天子の御動座を促すべく禁中(宮中)へ入ろうとしたが、すでに曹休が軍馬を並べていた。王必を討ち取って合流するはずの金褘や耿紀も、いつまでも来ない。
当然、韋晃は苦戦に陥ったのみならず、こういう手違いと情勢の不振を見たため、御林軍(ぎょりんぐん。近衛軍)の多くは二の足を踏んでしまい、反魏王、反曹一族の声明をすることすら避けてしまった。
亡き吉平(きっぺい)の子、吉邈(きつぼう)と吉穆(きつぼく)のふたりは、民衆に檄(げき)を伝えて街頭から義兵を糾合するつもりで、大いに活躍していた。
しかし、殺到した夏侯惇の大軍に出会うや、ひとたまりもなく掃滅され、兄弟枕を並べて討ち死にした。
(05)鄴都(ぎょうと)
曹操は夏侯惇から、許都での反乱の首謀者以下をあらまし召し捕り終えた、との早馬を受ける。そこでこのように厳達した。
「こういうときは根を刈らねばならん。およそ漢朝の旧臣と名のつく輩(やから)は、その位官の高下を問わず、ひと束にして鄴都へ送りよこせ」
熱血児の耿紀は後ろ手に縛され、大路を引かれていきながら天をにらみ、罵ってやまなかった。
「曹操、曹操。今日、生きて汝(なんじ)を殺すあたわずとも、死して鬼となり、必ず数年のうちに、汝を鬼籍に招いてやるぞ。待っておれっ!」
韋晃は刑場に座り、その頭(こうべ)へ刃の下らんとする刹那、「待てっ!」と刑吏をにらみつける。
さらにカラカラと自嘲を漏らしたかと思うと、「恨むべし、恨むべし。天にあらず、微忠のなお至らざるを!」と叫ぶ。
そして頭上の一閃(いっせん)も待たず、自ら頭を大地へ叩きつけ、歯牙も頭蓋骨も粉々に砕いて死んでしまった。
★井波『三国志演義(5)』(第69回)では、金禕および吉邈と吉穆は乱戦の中で殺され、韋晃と耿紀も含めた5人の一族は全員、許都の市場で斬刑に処されたとある。そのうえで、鄴郡(鄴都)へ送られたのは朝廷の官僚たちだったともある。
金褘の三族もすべて死を被った。わずかに市人の胸を慰めたものは、御林軍の大将の王必が、矢傷がもとで、これもまもなく死んだということだけだった。
★井波『三国志演義(2)』の訳者注によると、「(三族については)諸説あるが、漢代において三族皆殺しの対象となるのは、父母・妻子・兄弟姉妹である」という。
(06)鄴都 魏王宮
代々漢朝の臣であり、累代の朝廷に仕えてきた公卿(こうけい)という理由だけで、たくさんな官人たちは車に盛られ、馬の背に乗せられ、まるで流民のように鄴都へ差し立てられた。
ここへ来て、彼らは初めて曹操の魏王宮を見、その華麗壮大さにあっけに取られた。そして心密かに、「あぁ、もう都は許都にはなく、鄴都にあるようなものだ……」とつぶやき合う。
曹操は、この汚い百官の群れを、壮麗な魏王宮の庭園に立たせて言い渡す。
「先ごろの乱の時、汝らのうちには、門を閉じてただ震え上がっていた者もあろうし、敢然と出て火を鎮めんと、働いた者もあるだろう」
「いちいち調べるのは面倒くさい。あれに紅白二旒(にりゅう)の旗が立ててあるから、火を防ぎに出た者は紅の旗の下に立て。門を閉じて出なかった者は白い旗の下に固まれ」
官人たちはお互いに右を見、左を見、どちらへ行こうかと迷っているふうだったが、期せずしてその8割までが、ぞろぞろと紅の旗の下へ駆け集まった。
★井波『三国志演義(5)』(第69回)では、白旗の下に立ったのが3分の1で、紅旗の下に立ったのは3分の2だった。
これはおのおのが、「もし門を閉じて出なかったと言えば、きっと過怠なりとし、とがめを受けるに違いない。都下の騒擾(そうじょう)とともに火を防ぎに出たと言えば、何の罪科にも触れはしまい」という心理であった。
ところが、曹操は高台の上から見届けるや、叱呼して武将に命ずる。
「よしっ。紅の旗の下に集まった輩は、残らず異心ある者とみてよろしい。ひとり残らず引っくくり、漳河(しょうが)の岸へ引っ立てろ。もちろんみな打ち首だ!」
残るわずかな官人。白旗の下に立った者だけは、これを許して許都へ返させた。同時に宮廷の侍側、閣員、内外の諸官人などに大更迭が行われた。
鍾繇(しょうよう)を相国(しょうこく)に、華歆(かきん)を御史大夫(ぎょしたいふ)に、曹休を王必亡き後の御林軍総督に、それぞれ任ずる。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(相国は)漢における最高位の宰相。ただし、ここでは漢帝国ではなく、魏王国における宰相職」だという。同じく「(御史大夫は)魏王国の副宰相」という。
さらに侯位勲爵の制を六等十八級に定め、金印・銀印・亀紐(きちゅう。亀の形に刻んだつまみ)・鐶紐(かんちゅう。リング形のつまみ)・紫綬(しじゅ。紫色の組み紐〈ひも〉)など、これらの大法を勝手に改めたり、それを授与したり、ほとんど朝廷を無視して魏王の意のままとなした。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「『侯爵六等十八級』は後漢時代に置かれた列侯と関内侯(かんだいこう)の下に、曹操が新たに名号侯(めいごうこう)・関中侯(かんちゅうこう)・関外侯(かんがいこう)・五大夫(ごたいふ)を加えて6等としたもの。軍功ある者を賞するために創設された」という。
また「『十八級』とは新設された名号侯以下18の爵位のこと。名号侯は臨時に置かれた称号で食邑(しょくゆう。領地)はなく、関内侯に次ぐ第18級に位置する」という。
その曹操も管輅(かんろ)の卜(うらない)にはひどく傾倒し、感謝もしていたらしく、何なりと褒美を望めと言った。
しかし管輅はどうしても受けず、こう言った。
「私には、火を防ぐ力も、水を支える力もありません。大王が鄴都に留まったのも天の定数です。許都の乱も約束事です。また、私が大王に見いだされて予言申し上げたのも、おそらく天意でしたろう」
「こう考えると、私が大王から恩爵を頂く理由はちっともない。拝謝いたします。褒美の儀はご勘弁ください」
管理人「かぶらがわ」より
金褘・耿紀・韋晃らの魏王転覆計画はあえない幕切れ。そしてこの件にかこつけ、紅旗に集った数多くの朝廷の旧臣を始末する曹操――。
あれもこれも管輅が言う天意だったとすれば、確かに天意は計り知れないものですね。

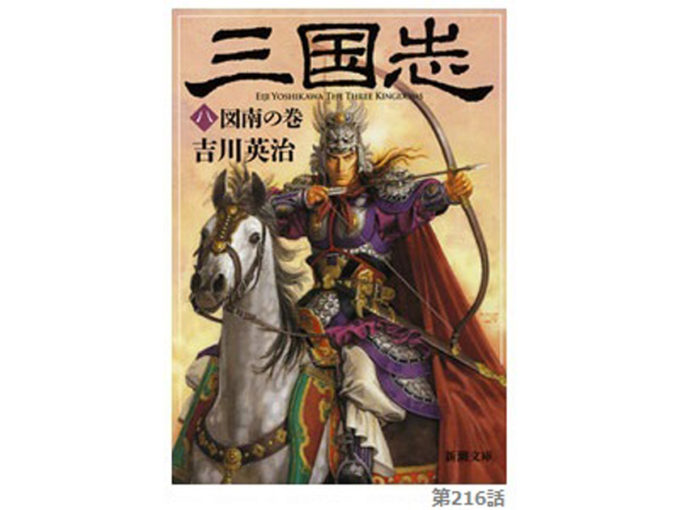













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます