諸葛亮(しょかつりょう)亡き後、蜀が急速にしぼんでいくさまを描いた篇外余録の2話目。
蜀にとって諸葛亮がどのような存在だったのか、痛いほど伝わってくる……。
篇外余録(2)の全文とポイント
(01)孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)の没後、破滅したふたりと蜀を支えたふたり
孔明なき後の、蜀30年の略史を記しておく。
いったい、ここまでの蜀は、ほとんど孔明一人がその国運を担っていたといっても過言でない状態にあったので、彼の死は、即ち蜀の終りといえないこともない。
しかし、それは孔明自身が、以(もっ)て大いに、自己の不忠なりとし、またひそかなる憂いとしていた所でもある。従って、自身の死後の備えには、心の届くかぎりのことを、その遺言にも遺風にも尽してある。
以後、なお蜀帝国が、30年の長きを保っていたというも、偏(ひとえ)に、「死してもなお死せざる孔明の護り」が内治外防の上にあったからにほかならない。
★炎興(えんこう)元(263)年11月、蜀は劉禅(りゅうぜん)が魏の征西将軍(せいせいしょうぐん)の鄧艾(とうがい)に降伏し、滅亡した。
そこで孔明の歿(ぼっ)した翌年すなわち蜀の建興(けんこう)13年にはどんなことがあったかというに、蜀軍の総引揚げに際し、桟道の嶮(けん)で野心家の魏延(ぎえん)を誅伐した楊儀(ようぎ)も、官を剝がれて、漢嘉(かんか)に流され、そこで自殺してしまった。
★蜀の建興13(235)年1月、楊儀は漢嘉郡へ配流され、この年のうちに自殺した。
延は儀を敵視し、儀は延を邪視し、この二人は、すでに孔明の生前から、互いによからぬ仲であったが、孔明の大度がよくそれを表面に現わすなく巧みに使ってきたものに過ぎなかった。
それというのが二人ともひそかに、孔明の死後は、われこそ蜀の丞相(じょうしょう)たらんと、おのおの、その後継をめぐって相争っていたからである。
かつて、呉の孫権(そんけん)は、蜀の使いに、孔明の左右にある重臣はたれかと訊(たず)ね、「さてさて、儀や延を両腕にして戦っているのでは、さだめし孔明も骨が折れるだろう」と、同情的な口吻(こうふん)のうちに、延や儀の人物を嘲評していたという話もあるが、たしかに、この二人物は、蜀陣営の中の、いわゆる厄介者にちがいなかった。
「――延は矜高(きょうこう。驕〈おご〉り高ぶる様子)。儀は狷介(けんかい。頑固で心が狭く、他人と調和しない様子)」とは、孔明が生前にも、呟(つぶや)いていた語であった。――で彼は、そのいずれにも後事を託さず、かえって、平凡だが穏健な蔣琬(しょうえん)と費禕(ひい)とに嘱すところ多かったのである。
楊儀の失脚も、結局、その不平から起ったもので、彼は、成都(せいと)に帰って後、さだめし大命われに降るものと、自負していたところ、なんぞはからん、重命は琬に降り、自分は中将軍師(ちゅうじょうぐんし)を任ぜられたに過ぎないので、以後、しきりに余憤をもらし、あまっさえ不穏な行動に出んとする空気すらうかがわれたので、蜀朝は、これに先んじて、彼の官を剝ぎ、漢嘉の地に流刑するの決断に出たものであった。
これが、孔明死後の成都に起った第一の事件であった。支柱を失うと、必ず内争始まるという例は、一国一家も変りがない。蜀もその例外でなかった。
けれど、蔣琬はさすがに、善処して、過らなかった。彼はまず尚書令(しょうしょれい)となって、国事一切の処理にあたったが、衆評は、彼に対して、「あの人は平凡だが、平凡を平凡として、威張らず衒(てら)わず、挙止、ありのままだから至極よい」と、みな云った。
孔明が、彼を挙げたのも、その特徴なきところを特徴として、認めていたからであったろう。
(建興)13(235)年4月。琬は、大将軍(だいしょうぐん)に累進したので、そのあとには費禕が代って就任した。また、呉懿(ごい)が新たに車騎将軍(しゃきしょうぐん)となって、漢中(かんちゅう)を総督することになった。
遠征軍の大部分は引揚げても、漢中は依然、蜀にとって、重要な前衛基地であった。なお多くの国防軍はそこに駐屯していた。呉懿の赴任は、その為にほかならない。
ここに、たちまち豹変(ひょうへん)を兆しはじめたのは、同盟国の呉であった。その態度は、孔明の死と同時に、露骨なものがあった。
「いま、蜀を救急しなければ、蜀は魏に喰(く)われてしまうであろう」
これを名目として、呉は、数万の兵を以て、蜀国境の巴丘(はきゅう)へ出て来た。
この物騒きわまる救援軍に対して、蜀も直ちに、兵を派して、「ご親切は有難いが、まず大した危機もこの方面にはないからお引揚げ願いたい」と、対峙(たいじ)の陣を布いた上、こう外交折衝に努めたので、呉もついに、火事泥的な手を出し得ずに、やがて一応、国境から兵を退いた。
(02)蜀の将星、次々と落つ……
建興15(237)年、蜀は、延熙(えんき)と改元した。
★『三国志』(蜀書・後主伝)によると、「延熙」への改元は建興15(237)年中のことではなく、翌年1月のこと。
この年、蔣琬は、討魏の軍を起して、漢中に出で、ひそかに、魏の情勢をうかがっていた。
孔明なき後も、劉玄徳(りゅうげんとく。劉備〈りゅうび〉)以来の、中原(ちゅうげん。黄河中流域)進出の大志は、まだ多くの遺臣のうちには、烈々と誓われていたことが分る。
琬は、孔明がいつも糧道の円滑に悩んでいた例を幾多知っていたので、こんどは水路を利用して魏へ入ろうとして建議したが、蜀の朝廷では、「北流する水を利して進むは、入るに易い道には違いないが、ひとたび退こうとするときは、流れを遡上(さかのぼ)るの困難に逢着(ほうちゃく)するであろう」といって、ついに彼の建議をゆるさなかった。
これは、その作戦を否定したばかりでなく、すでに遠征を好まない空気が、ようやく、廟議(びょうぎ)の上にも顕著となった一証だと見てよい。
「守らんか、攻めんか」
蜀の輿論(よろん)は、ここ数年を、ほとんどそのいずれともつかずに過ごした。
そのうちに、延熙7(244)年の3月、魏は蜀の足もとを見て、「いまは一撃に潰(つい)えん」となし、すなわち曹爽(そうそう)が総指揮となって、十数万の兵を率い、長安(ちょうあん)を出て、駱谷(らくこく)を経、積年うかがうところの漢中へ、一挙突入せんとした。
ところが、蜀軍いまだ衰えずである。蜀は、その途中に邀撃(ようげき)して、魏を苦戦に陥らしめた。
費禕の援軍が早く来たのと、涪(ふ)方面に蜀兵の配置が充分であったため、たちまち、魏軍を諸所に捕捉して、痛打を加え、特有な嶮路を利用して、さんざんに敵を苦しめたのである。
「いけない、なお未だ孔明の遺風は生きている」
曹爽はそういって退却した。
その翌年、蜀の蔣琬は死んだ。
★『三国志』(蜀書・後主伝)および『三国志』(蜀書・董允伝〈とういんでん〉)によると、蔣琬は蜀の延熙9(246)年11月に死去した。
蜀の良将はこうして一星一星、暁の星のように姿を消して行った。何かしらん力を以ては及び難いものが蜀の年々に黒框(くろわく)の歴史事項を加えていた。
蔣琬はついに丞相にはならなかったが、孔明の遺嘱を裏切らなかった忠誠の士であったことに間違いない。
同年、12月にはまた、尚書令の董允が死んだ。允は琬に次ぐ重臣であり、剛直をもって鳴っていたので、琬の死以上、これを惜しむ人もあった。
この二者が亡ぶと、「わが世の春が来た」といわぬばかりに擡頭(たいとう)してきた一勢力がある。宦人(かんじん)の黄皓(こうこう)を中心とする者どもである。
皓は日頃から帝の寵愛を鼻にかけていたが、政治に容喙(ようかい。口出し)し始めたのは、このときからである。
骨のある忠臣は相次いで世を去るにひきかえ、こういう類(たぐい)の者が内政から外務にまで新たに面(かお)を出すにいたっては、もはやその国の運命は量り知るべきである。
だが、ここになお、いささか蜀のために意を強うするに足るものはあった。それは、費禕、姜維(きょうい)の両人が健在なことだ。
以後、彼らが鋭意国政に当って、この衰亡期にある国家を支え、故孔明の遺志にこたえんとする努力には、涙ぐましいほどなものがある。
ただ――これは結果論となるが――姜維のただ一つの欠点であったことは、孔明ほどな大才や機略にはとうてい及ばない自己であるを知りながらも、その誓うところ余りに大きく、その任あまりに多く、しかも功を急ぐの結果、彼の英身が、かえって蜀の瓦解へ拍車をかけるの形をなしてしまったことである。
さもあらばあれ、武人として、また唯一の遺法を、孔明手ずから授けられた彼としては、(玉砕か、貫徹か)まさにこの二途を賭して、あくまで積極的に出るしか生きがいはなかったであろう。
で彼は、かねて、涼州(りょうしゅう)地方の羌族(きょうぞく)を懐柔していたので、この一勢力を用いて、魏へ進攻する策を企てた。
それの実現を見たのは、延熙10(247)年の秋である。維は、雍州(ようしゅう)へ攻め入った。
魏の郭淮(かくわい)、陳泰(ちんたい)などが、この防戦に当り、各地で激烈な戦闘を展開したが、結局、魏の諸郡を踏み荒らした程度で、蜀は退却のやむなきに至った。魏に退路を断たれ、また部下から多くの脱走者を出したりしたためだった。
(03)蜀、傾く
ここにまた、蜀にとって一不幸が起った。費禕の死である。
孔明の衣鉢をつぐ大器としては、まず費禕であろうとは、衆目の視ていたところであったが、突然、この訃が知れわたったので、蜀中は非常な哀愁につつまれた。
死因も、その折は、秘密にされていたが、後に自然一般にも知れてしまった。一夕、蜀の将軍連と歓談している宴席において、突然、魏の降将、郭循(かくじゅん)という者に刺し殺されたのであった。
★蜀の延熙16(253)年1月、費禕は漢寿(かんじゅ)で魏の降人の郭循(郭脩〈かくしゅう〉)に殺害された。
費禕なき後、蜀の運命は、いよいよ姜維一人の双肩にかかった。
維は、(延熙)18(255)年8月、魏の王経(おうけい)と洮西(とうせい)に戦って、久しぶりの大戦果をあげた。この時の殲滅(せんめつ)には、魏兵万余人を斬り尽して、洮西の山河をほとんど紅にしたといわれている。
ために、彼は大将軍に叙せられた。
しかしすぐ次の戦いには、魏の名将鄧艾と段谷(だんこく)にまみえて、こんどは逆に惨敗を喫した。
若きから孔明に私淑(密かに師として慕い、学ぶこと)して来たものの、孔明に似て孔明にとどかず、その人格に力量に、如何(いかん)ともなし得ぬ先天的な器量の差は、こういう風に、軍をうごかすたび、歴然と結果に出てくる。
延熙20(257)年。維は秦川を衝いた。魏軍が関中方面へ移動したのでその虚をついたものである。
魏の鄧艾・司馬望(しばぼう)の軍は、彼の鋭鋒を避けて、敢えて当らなかった。維はさまざまに挑んだが、消耗するに止(とど)まって、大した戦果も獲(え)られずに終った。
彼が、孔明の遺志をついで、しきりに積極的となっていた背後には、内廷における黄皓らの反戦的空気が、ようやく濃厚になりかけていた。
かくては維も思うように戦えなかった。国家として、まことに危険な状態にあったといわねばならない。
延熙の年号は、20年を以てあらためられ、景耀(けいよう)元(258)年となった。
帝劉禅は、この頃からようやく国政に倦(う)み、日夜の歓宴に浸りはじめた。
時艱(じかん。その時代の難局)に耐うる天質のいとど薄い蜀帝をして、この安逸へ歓楽へと誘導するに努めていたものが、黄皓などの宦臣の一群であったことはいうまでもない。
「ああ、国は危うい」
「かくては、蜀の落日も、一燦(いっさん)のうちであろう」
心ある者はみな歎いた。
しかし、帝の寵威を誇る黄皓にたいして、歯の立つ者はいなかった。
ひとり姜維は、面を冒して、諫奏幾度か、「佞臣(ねいしん)を排されたい」と、劉禅の賢慮を仰いだ。
饐(す)えたる(腐った)果物籠の中にあって、一箇の果物のみ饐えないでいるわけもない。
帝の心はすでに甘言のみを歓ぶものになっている。朝(あした)に美姫の肩の柳絮(りゅうじょ)を払い、夕べに佳酒を瑠璃杯に盛って管絃に酔う耳や眼をもっては、忠臣の諫言は余りにもただ苦い気がした。
「蜀は風前の燈火(ともしび)だ」
維は、慨嘆した。
果たせるかな、魏は、「時到る」とこれを見ていた。
そして景耀6(263)年の秋、一挙に蜀中に攻め入って、その覆滅を遂ぐべしと、鄧艾、鍾会(しょうかい)を大将として、無慮数十万の大兵は、期して、魏を発し、漢中へ進撃した。
蜀の前衛は、たちまち潰えた。
姜維は、剣閣(けんかく)の嶮に拠り、この国難に、身を挺(てい)して防いだ。さすがに、ここは容易に、抜けなかった。
けれど一方、陰平(いんぺい)の険隘(けんあい)を突破した鄧艾の軍は、ときすでに蜀中を席巻し、直ちに成都へ突入していた。
成都。ああ、成都。
彼ら蜀人は、ここに魏兵を見ようなどとは、まったく夢想もしていなかったのである。殺到する魏の大軍を見て初めて、「これは、この世のことか」と、狼狽(ろうばい)した程だったという。
ためにこのとき、城郭の防備などは、少しもしていなかったといわれている。知るべし、跳梁(ちょうりょう)する敵人の残虐ぶりを。魏兵の蹂躙(じゅうりん)に悲鳴して逃げまどう婦女老幼のみじめさを。
――かかるとき、なお毅然(きぜん)としてある都門第宅(ていたく)の輪奐(りんかん)の美も、あらゆる高貴を尊ぶ文化も、日頃の理論や机上の文章も、ついに何の役をもなさなかった。むなしく災いの暴威と敵兵の闊歩(かっぽ)におののくだけであった。
(04)劉禅ッ!
蜀宮は混乱した。ここもまた、かつての、洛陽(らくよう)の府や長安の都そのままの日を現出した。
帝劉禅には、何らの策も決断もない。妃(きさき)とともに哭(な)き、内官たちと共にうろたえているのみである。
魏軍はすでに城下へ迫って歌っている。蜀亡びぬ、蜀すでに亡し。有るはただ城門を開いて魏旗の下にひざまずく一事のみと。
「どうしたらよいか。汝(なんじ)らの意見に従おう。ただ朕の為に善処せよ」
劉禅は、これを告ぐるのがやっとであった。夜来の重臣会議もまだ一決を見ずにある。沈湎蒼白(ちんめんそうはく)、誰の顔にも生気はない。
「呉を恃(たの)みましょう。陛下の御輦(みくるま)を守って、呉へ奔り、他日の再起を図らんには、またいつか蜀都に還幸の日が来るにちがいありませぬ」
「いや呉は恃み難い。むしろ呉は、蜀の滅亡をよろこぶ者であっても、蜀のために魏と戦うような信義のないことは、丞相孔明の死去のときから分りきっている」
「いっそ、南方へ蒙塵(もうじん。天子が難を避けて都から逃げること)あそばすのが、いちばん安全でしょう。南方はまだ醇朴(じゅんぼく)な風があるし、丞相孔明が布いた徳はまだ民の中に残っています」
衆論は区々(まちまち)である。帝はただ迷うばかりだった。
ときに重臣の譙周(しょうしゅう)が、やっと不器用な口つきで、最後に私見を述べた。
「もの事にはすべて、始めがあり終りがあり、また中道があります。始めや途中のことなら一時の変ですから、挽回の工夫もあり、立て直しもききますが、今日の変は、要するに、丞相孔明が逝かれた後の万事の帰着です。天数の帰結です」
「もういけません。呉へ奔るも愚策、南方に蒙塵あるも、何もかも、唯(ただ)、末路の醜態を加えることでしかありません。……願うらくはただ、努めて先帝の御徳を汚さぬよう、蜀帝国の最期として、世の嗤(わら)い草にならぬよう、それのみを祈りまする」
「では、汝は、蜀城を開いて、魏に降伏するのがよいというのか」
「臣として、口になし得ないことですが、天命にお従い遊ばすならば、それしかほかに途(みち)はありません」
案外にも、劉禅はすぐ、「そうしよう。譙周のいうことが、いちばん良いようだ」といって、むしろ一時の眉をひらくような容子にさえ見えた。
重臣はみな痛涙に咽(むせ)んだ。けれど誰も皆、譙周の意見が悪いものとは思わなかった。諦めの底に沈黙した。
この譙周については、有名な一挿話がある。
彼が初めて蜀宮に召されたのは建興(223~237年)の初年頃で、まだ孔明の在世中であった。
孔明は彼の学識と達見を夙(つと)に聞いていたので、帝にすすめて田舎出の一学者を、勧学従事(かんがくじゅうじ)の職に登用したのである。
ところが、最初の謁見の日、蜀朝の諸官は、彼のすこぶる振わない風采と、また余りに朴訥(ぼくとつ)すぎて、何を問うても吃(ども)っていっこう学識らしい話も場所柄に応じた答えもできないでいる容子をながめ、皆クツクツと失笑を洩(も)らした。
「あのような不嗜(ふたしな)みなことは、朝廷の儀礼と尊容を甚だしく紊(みだ)すものです。笑った者を処罰しようではありませんか」
廟堂(びょうどう)監察の吏は、問題として、これを取り上げ、一応、孔明のところへ相談に来た。
すると、孔明はこういった。
「われなお忍ぶ能(あた)わず。いわんや左右の衆人をや」
彼は、取り上げなかった。
孔明は笑いはしなかったが、やはり心のうちで、おかしさを覚えていたのである。――自分の身にとってすら忍び得なかったことを、衆にたいして罪として問おうというのは法の精神に悖(もと)るとなしたものであろう。
孔明が戦場で死んだと聞いたとき、この譙周はその夜のうち成都を去って、はるばる途中まで弔問に駈(か)けつけて行った。その以後、離京した者は、官吏服務規程に問われて、反則の咎(とが)をうけたが、真っ先に行った譙周だけは、何の問責もうけなかった。
――衆論に因(とら)われず、劉禅に開城をすすめた彼は、まずそういう風な人物だったのである。
(05)成都開城
開城を宣すると、蜀臣はその旨を魏軍へ通告した。
城外には、魏軍の奏する楽の音や万歳の声が絶えまなく沸き立っている。蜀宮の上には降旗が掲げられ、帝は多くの妃や臣下を連れて城外へ出た。そして魏将鄧艾の軍門に、降をちかう、の屈辱に服したのであった。
かくて、蜀は、成都創府以来、2世43年の終りを、この日に告げたのであった。
昭烈廟(しょうれつびょう。玄徳を祀〈まつ〉る所)の松柏(しょうはく)森々(しんしん)と深き処(ところ)、この日、風はいかなる悲愁を調べていたろうか。
定軍山の雲高き処、孔明の眦(まなじり)はいかにふさがれていたろうか。
なおなお、関羽(かんう)、張飛(ちょうひ)、そのほか幾多の父、幾多の子、また、無数の英骨、忠臣、義胆の輩(ともがら)はいかに泉下の無念をなぐさめていたろうか。
かつて皆、この土のために、生命をささげ、骨を埋め、土中に蜀の万代を禱(いの)っていたろうに、今や地表は魏軍の土足にとどろき、空は魏旗に染められている。
そもそも誰の罪か。心なき蜀中の土民こそ嘆かぬはなかったであろう。
ただここに、なお劉家の血液を誇った一皇子がある。帝劉禅の五男北地王(ほくちおう)諶(じん。劉諶〈りゅうしん〉)であった。
皇子は初めから帝の蒙塵にも開城にも大反対で、「蜀宮を墳(つか)としても、魏と最後の最後まで戦うべきです」と主張していたが、ついに言は聴かれず、自分と共に討死しようという烈士もいないので、憤然ひとり祖父の昭烈廟へ行って、妻子をさきに殺して自分もいさぎよく自殺した。
蜀漢の末路、ただこの一皇子あるによって、歴史は依然、人心の真美と人業の荘厳を失っていない。
剣閣の嶮に依って、鍾会と対峙していた姜維も、成都の開城を伝え聞き、また勅命に接して、魏軍に屈伏するのやむなきにいたった。
「武器を抛棄(ほうき)せよ」と姜維に命ぜられて、魏の前に降兵として出ることになった彼の部下は、このとき皆、「無念」と、剣を抜いて、石を斫(き)ったということである。
これを見ても、蜀人の意気戦志は、まだ必ずしも地に墜(お)ちていたとはいえない。
いやむしろ、孔明なき後の30年も、年々、進攻的な気概を外敵にしめし、「攻むるは守るなり」の積極策を持ちつづけて来た気力にはむしろ愕(おどろ)かれるものがある。
とはいえ、姜維らのこの意気は愛すべしだが、ために、費禕の言なども多くは耳をかさず、求めて欠陥を生じ、急いで国家を危殆へ早めて来たこともまた、否み得ない作用であったというしかない。
費禕は、存生中にも、姜維にむかって、しみじみ、こういっていた事実がある。
「自分などは、どう贔屓目(ひいきめ)に見ても、とうてい、故丞相に及ばないこと甚だ遠い者だ。――その丞相ですらなお中夏(ちゅうか。中国)を定め得なかったことを思うと、況(いわ)んや、われら如きにおいてをやと、痛感しないわけにはいかない」
「だからしばらくはよく内を治め、社稷(しゃしょく。土地と五穀の神。国家)を守り、令を正し、国を富ましめるのが、われらのなし得る限度ではあるまいか。外の功業の如きは、やがて孔明のような能者を待って初めて望み得ることだ」
「僥倖(ぎょうこう)を思うて、成敗を一挙に決せんとするようなことは、くれぐれもおたがいに慎まなければなるまいと思う」
これは一面の善言であった。
しかし姜維はべつに姜維の抱負を持しつづけた。いずれが是であったか非であったか、これはかえって譙周の最後のことばに傾聴するものが多いようだ。
だが、過去を天地の偉大な詩として観るとき、姜維の多感熱情はやはり蜀史の華といえよう。
彼はついに長く屈辱的武人たるに忍びきれず、後また、魏の鍾会に反抗して、たちまちその手に捕えられ、妻子一族とともに、首を刎(は)ねられた。彼の血液はやはり魏刀に衂(ちぬ)られるものに初めから約束されていたようである。
(06)蜀の滅亡後
魏の成都占領とともに、蜀朝から魏軍の鄧艾に引き渡された国財の記録によると、領戸28万、男女人口94万、帯甲将士10万2千人、吏4万人、米44万斛(ごく)、金銀2千斤、錦綺綵絹(きんきさいけん)20万匹、――余物これにかなう。とあるからそのほかの財宝も思うべしである。
しかし国力はかなり疲弊していたものだろう。蜀将の意気もすでに昔日の比ではない。帝以下百官、城を出て魏門にひざまずき、城下の誓いを呈したのである。いかなる国家も亡ぶとなると実にあっけないものだ。
この亡滅を招いた原因は、数えれば種々ある。帝劉禅の闇弱、楊儀の失敗、董允、蔣琬の死去、費禕の奇禍、等々、国家の不幸はかさなっていた。
最後となっては、劉禅の親政と、宦人黄皓の専横などが、いよいよ衰兆に拍車をかけていた。
亡ぶものの末期的症状にかならず見られるのは、宦官的内訌(かんがんてきないこう)とこれに伴う暴政、相剋(そうこく)、私的享楽などである。蜀の終り頃もこの例外を出ていない。
――特に、もっとも蜀を弱めたものは、蜀中の学者の思想分裂であった。彼らのうちには、三国鼎立策にも大陸統合にも、ほとんど何の興味も感じていない者が多かった。要するに思潮は戦に倦み戦を否定し始めていたのである。
門を閉じて、高く取り澄ましていた杜瓊(とけい)なども、春秋讖中(しゅんじゅうしんちゅう)の辞句をひき出して、「漢に代るのは当塗高(とうとこう)だろう」などと平気で放言していた。
当塗高とは魏をさしていっているのである。魏という文字は「高閣」を意味する。――道に当りて高いもの――という伏字(ふせじ)だ。蜀の粟(ぞく)を喰いながら、こんなことを平気で説いていたのである。
また学府の学者でも、もっと甚だしい説を撒(ま)いていたのがある。
「――先帝の名は備(び)なり。備は、備(そな)うるなり、また具(そな)うるを意味す。後主の諱(いみな)は禅にして禅(ゆず)るの意をもつ。すなわち禅り授くるなり。劉氏は久しからずして当(まさ)に他へ具え禅るべし」
こういう学者を内に養っていた国家が内に病を起していないわけはない。いわゆる最後の「あっけなさ」は、すでに蜀の肉体のこういう危険な病症が平時に見のがされていたにほかならない。
ところで降人に出た劉禅の余生はどうなって行ったろう。魏へ移った旧蜀臣は、おおむね魏から新しい官職を与えられて、その隷属に甘んじた。
劉禅もまた、魏の洛陽に遷(うつ)され、後、魏から安楽公(あんらくこう)に封ぜられて、すこぶる平凡な日を過していた。
――ある時、彼の心懐を思いやって、魏人の一人が、彼の邸(やしき)を訪(と)うて面接したとき、試みに、「魏へ来ても、日常のご不自由はないでしょうか、何かにつけ、蜀のむかしを思い出されて、折には、ご悲嘆にくるることもおありでしょうな」と、たずねてみた。
すると、凡庸な彼は、「いやいや、魏のほうが、はるかに美味もあるし、気候もよいから、べつに蜀を思い出すようなこともありません」と、いっこう無感情に答えたということである。
この無感情が、大悟(たいご。大いに悟った様子)の無表現ででもあったなら偉いものであるが、彼の場合は、現れたとおりの、懸値なしであるからまことに愍(あわ)れというほかはない。
管理人「かぶらがわ」より
古今の数多くの国家で見られますが、確かに一国の巨星を失うと、とたんに内輪もめが始まりますよね。
その巨星のほうは、落ちる前に後継者の育成までやらなくてはならないとは……。これは大変そう。そこまで巨星に求めていいのかも甚だ疑問です。
ただ、巨星がうまくつながった国家は、長く保っているのもまた事実。『三国志』は現代に生きる人々にも、多くの示唆を与えてくれます。

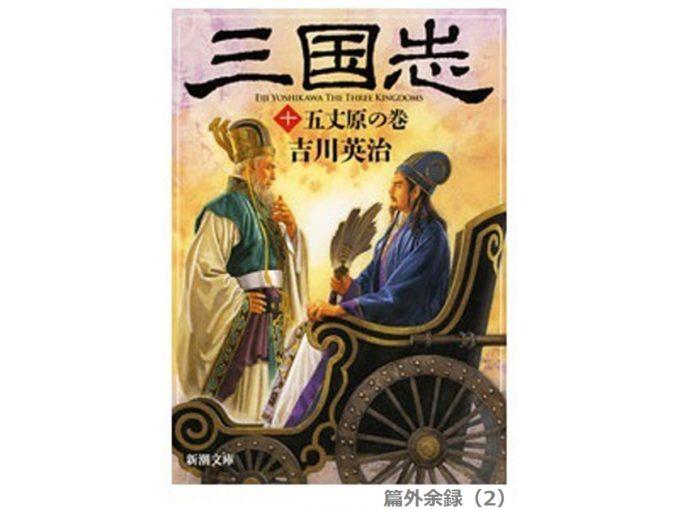































コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます