涪城(ふじょう)の劉備(りゅうび)のもとに、荊州(けいしゅう)から諸葛亮(しょかつりょう)の書簡を携えた馬良(ばりょう)が着く。
諸葛亮への劉備の揺るがぬ信頼ぶりを目の当たりにした龐統(ほうとう)は複雑な感情を抱き、あえて速やかな進軍を促す。涪城を発った劉備は龐統と別々の道を行くことにし、雒城(らくじょう)で合流する手はずを整えるが――。
第198話の展開とポイント
(01)涪城
劉備は、荊州から馬良が携えてきた諸葛亮の書簡に読み入る。このとき龐統がそばにいたものの、彼は繰り返し繰り返し書簡に心を取られていた。
龐統は胸の内でため息を覚える。不思議なため息であり、嫉妬にも似た感情だった。
やがて劉備は書簡の内容を話す。荊州はしごく無事ながら、天文を案ずると今年は征軍に利がなく、大将の身には凶事の兆しすらあるという。
龐統は気のない返事をしたが、さらに劉備は、ひとまず使いの馬良を返し、自分も一度荊州へ立ち帰り、諸葛亮と会ってよく協議したいと言いだす。
龐統は胸の中で闘っていた。抑えようもなく心の底に起こってくる、不思議な妬み心を自ら恥じ、これを打ち払おうと努めていたが、結果は我にもなく、その理性と反対のことを口に出していた。
「これは意外な御意。命は天にあり、どうして人にありましょうや。いま征馬をここまで進めながら、孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)の一片の書簡にお心を惑わせたまうなどとは何たることですか」
龐統は、むしろ速やかに兵を進めるべきだと言う。いつまでも黄忠(こうちゅう)と魏延(ぎえん)を涪水(ふすい)の線に立たせておくのは下策だと。
こう励まされると翌日、劉備は涪城を発して前線へ赴いた。
(02)雒城の郊外 劉備の本営
劉備が、以前に張松(ちょうしょう)から贈られた西蜀四十一州図を広げて策を練っていると、法正(ほうせい)が別の一本の絵図を携えてくる。
ここで法正は言う。
「雒山の北にひと筋の秘密路(かくしみち)があります。それを踏み越えれば雒城の東門に達するということです」
「また、あの山脈の南にも一道の間道があり、それを進めば雒城の西門に出るという。この絵図と張松の絵図とを照らし合わせてご覧ください」
子細に見比べると、まさにその通りだった。劉備は信念を得て軍をふたつに分け、龐統に北の道を進むよう言う。自分は南から山を越えていくので、目指す雒城で落ち合おうと。
龐統は不足な顔をする。なぜなら、北山の道は広くて越えやすいが、南山の道は狭く、甚だ険阻であるからだ。彼の顔色を見て、劉備はこう言い足した。
「昨夜(ゆうべ)、夢に怪神(けしん)が現れ、予の右の臂(ひじ)を鉄の如意で打った。今朝までも痛む気がする。ゆえに軍師の身が気遣われるのだ。いっそのこと御身(あなた)は後を守っておらぬか?」
★如意はイマイチつかめず。道教の僧が持つ道具のひとつ、または説教の時などに用いた仏具のひとつ、ということだが……。「右の臂を鉄の如意で打った」とあるので、ここでは後者をイメージしたものか?
もとより龐統は一笑に付し、出発にかかろうとする。ところが陣払いして発つ朝、彼の馬が妙に狂い、右の前脚を折った。そのため不吉にも落馬の憂き目をみた。
劉備は馬から下りて助け起こし、自分が乗っていた素直な白馬を贈る。龐統は拝謝して乗り換え、ここで別れて北の大路へ向かった。
★『三国志演義(4)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第63回)では、龐統は魏延を先鋒に、南の細い道を進むことになっていた。吉川『三国志』では龐統が北の大路を進んでいるが、特別な意図があったのかはわからない。
(03)雒城
蜀の呉懿(ごい)・張任(ちょうじん)・劉璝(りゅうかい)らは、先に味方の冷苞(れいほう)を討たれて遺恨やるかたなく、雒城の内に額を集めて一意報復を議していた。
そこへ前衛の斥候部隊から、劉備の大軍が南北二道に分かれて前進してくるとの知らせが届く。張任は将軍たちと手はずを定め、自分は屈強な射手3千人を選りすぐり、山道の険阻に伏せ、斥候の第二報を待っていた。
(04)雒山の山中 落鳳坡(らくほうは)
そのうち斥候頭(ものみがしら)がやってきて告げる。ここへ向かってくる大将は、まさしく鮮やかな月毛の白馬に乗っていると。
張任は膝を打って喜び、白馬に乗りたる者こそ劉備だと言い、ここへかかったら白馬を目印に狙いを集め、矢数石弾のある限り浴びせかけろと、3千の射手に命じた。
時は(建安〈けんあん〉18〈213〉年の)夏の末、草も木も猛暑に萎え、虻(アブ)や蜂(ハチ)のうなりに肌を刺されながら、龐統の軍勢は燃ゆるがごとき顔を並べ、10歩よじてはひと息つき、20歩しては汗を拭い、あえぎあえぎ踏み登ってきた。
★「どちらかと言うと北路のほうが越えやすい」という意味だったのか、このあたりの記述からは、龐統が進んだ北路も越えやすいように見えない。もしかしたら、この第198話(02)における龐統の進路設定に勘違いがあるのかも……。
ふと前方を仰ぐと、両側の絶壁は迫り合い、樹木の枝は相交差し、天も隠れるばかりの鬱蒼(うっそう)たる険隘(けんあい)な道へ差しかかる。
日陰に入り、龐統はホッと肌に汗の冷えを覚えながら、途中で捕虜にした敵兵に地名を尋ねた。降参の兵は言下に答える。
「落鳳坡と呼び申し候(そうろう)」
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「落鳳坡は益州(えきしゅう)広漢郡(こうかんぐん)に属した。なお、この地名は後漢・三国時代にはなかった」という。
龐統は道号(道士の法名)を鳳雛(ほうすう)という。馬を向け直すと、にわかに全軍に戻るよう命じ、道を変えてほかから越えろと、鞭(むち)を差し上げて振った。その鞭こそ彼自身、死を呼ぶ合図となってしまう。
突然、峰谷も崩れるばかりの石砲や火箭(ひや)の轟(とどろ)きがこだまする。身を隠す隙もなく、彼の白馬はたちまち紅に染まった。
雨よりしげき乱箭(らんせん。箭〈矢〉が乱れ飛ぶ様子)の下に、龐統は希世の雄才をむなしく抱き、白馬とともに倒れ死んだ。まだ36歳という若さだった。
張任は白馬の主が劉備だと思い込んでいたので、絶壁の上から遠くその死を見届けると、荊州の残兵を残さず蹴散らし谷を埋めよと、歓喜して号令した。
このとき魏延は龐統の中軍に先んじ、すでに遥か前方へ進んでいたが、後続部隊で戦闘が起こったと聞き、引き返してくる。
ところが途中、そびえ立つ岩山の横をくりぬいた洞門の手前まで来ると、張任の一手が岩石や矢を一度に注ぎ落とした。
魏延も進退窮まってしまい、やむなく単独で雒城まで押し通り、南路から越えていった劉備の本軍と連絡を取ることにする。
(05)雒城の城外
ようやく魏延が雒山の背を越え、西方のふもとを望んで下りていくと、真下に雒城の西曲輪(にしくるわ)が見えた。
峨眉門(がびもん)・斜月門(しゃげつもん)・鉄鬼門(てっきもん)・蕀冠門(らかんもん)などが、さらに次の山を後ろにし、鋭い反り屋根の線を宙天に並べていた。
当然それらの門々は、敵を見るや警鼓戦鉦(せんしょう)を打ち鳴らし、煙のごとく軍兵を吐き出して囲む。指揮する者は呉蘭(ごらん)と雷同(らいどう。雷銅)だった。
中軍を後に残し、頭部だけで敵地に入った魏延は、もとより討ち死にを覚悟した。ただ死出の土産と、当たるに任せて血闘奮力の限りを尽くす。
ここへ突然、背面の山から金鼓を鳴らし、喚声を上げてきた一軍がある。だが、劉備の軍勢ではなく張任の軍勢だった。魏延も今は観念した。
しかし、ここで南路の山道から黄忠の軍勢が駆けつける。続いて劉備の中軍も到着。これにより双方の戦力は伯仲し、いよいよ激戦の様相となった。
劉備は龐統が見えないことを怪しむと、涪城へ退けと命じ、街道の関門を突破して引き揚げた。
(06)涪城
関平(かんぺい)や劉封(りゅうほう)の留守部隊は、城を出て劉備を迎え入れる。このころ早くも、「軍師の龐統は、山中の落鳳坡と呼ぶところにて無残な討ち死にを遂げた」という事実が、逃げ帰った残兵の口から伝えられた。
劉備は祭壇を築いて亡き龐統の魂魄(こんぱく)を招き、遠征の将士はみなぬかずいて袖を濡らした。
魏延や劉封らの若武者は雪辱に逸(はや)り立ったものの、劉備は愁いとともに城門を閉じ、ただ堅きを守る。そして関平を荊州へ急がせ、「一刻も早く蜀に来たれ」と、諸葛亮に宛てた書簡を届けさせた。
管理人「かぶらがわ」より
『三国志』(蜀書・龐統伝)によると、龐統は軍勢をひきいて雒城を包囲したとき、流れ矢に当たり亡くなったということです。
つまり落鳳坡は彼の死と無関係なのですが、史実を大きく変えずにこういう話に仕上げてあるのは、なかなかうまいなと感じました。

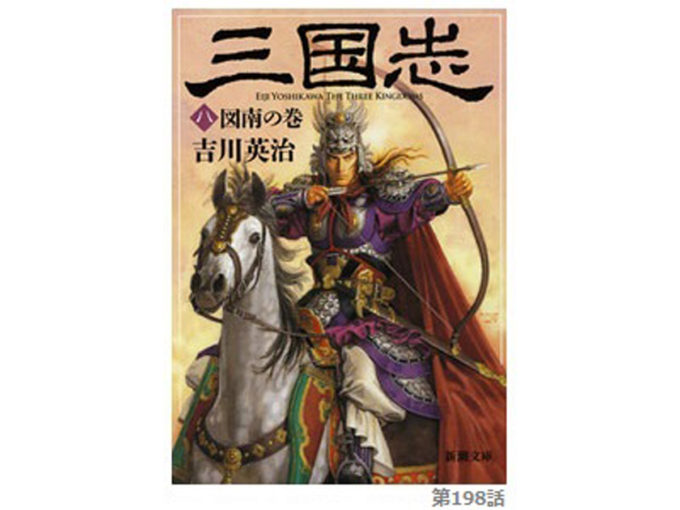













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます