涪城(ふじょう)を出てから劉備(りゅうび)とふた手に分かれ、雒城(らくじょう)を目指す龐統(ほうとう)。彼が落鳳坡(らくほうは)で無念の戦死を遂げたころ、ちょうど荊州(けいしゅう)では七夕の祭りが行われていた。
劉備が遠征中のため、城中で催す酒宴もささやかなものだったが、このとき諸葛亮(しょかつりょう)は西の夜空に破軍星を見る。
第199話の展開とポイント
(01)荊州(襄陽〈じょうよう〉?)
(建安〈けんあん〉18〈213〉年の)七夕の宵だった。城内の街々は紅燈(こうとう)や青燈に彩られている。
★いつもながら荊州(城)がどこの城を指しているのかわかりにくく、ここでもはっきりしない。
毎年の例なので荊州の城中でも、諸葛亮は主君の留守ながら祭を営み、酒宴を設けて諸将を慰めた。
すると夜も更けたころ、ひとつの大きな星が怪しい光芒(こうぼう)を引き、西の空へ飛んだと思うと白い光煙を残し、パッと砕けるごとく大地へ吸い込まれた。
「あぁ、破軍星……」
諸葛亮は杯を落とし、悲しいかな、と不意に叫んだ。
みな酔いを醒(さ)まして杯を置くと、諸葛亮は、今日からは遠出しないよう言う。必ず数日のうちに凶報が届くだろうと。
それから7日後のこと、劉備の使いとして関平(かんぺい)が征地から帰ってくる。
★『三国志演義(4)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第63回)では、七夕節の夜宴から数日後のこととあった。
「軍師龐統は戦死し、わが君以下は涪城に籠もり、四面みな敵、今は進退窮まっておられます」
関平はこう告げると、さらに劉備の書簡を差し出す。諸葛亮は書簡を読んで泣き、すぐに主君の救援に赴くべく準備を命じたが、案ぜられるのは後の荊州の守りだった。
諸葛亮は関羽(かんう)に任せることにし、劉備から預かった荊州総大将の印綬(いんじゅ。官印と組み紐〈ひも〉)を手渡す。関平も荊州に残すことにした。
関羽は感激して言う。
「大丈夫(だいじょうふ。意志が堅固で立派な人物)、信を受けて、しばしなりと一国の大事をつかさどるうえは、たとい死んでも惜しみはない」
しかし、諸葛亮は喜ばない顔をする。関羽に死を軽んずるような口ぶりがあったからである。
そこで、こう試問してみた。
「貴公のことだ。万に一も過ちはあるまいが、もし呉の孫権(そんけん)と北の曹操(そうそう)とが、同時に荊州を攻めてきたときはどう防ぐか?」
関羽が答えた。
「もちろん兵を二分してふた手に分かれ、一を撃破し、また一を討ちます」
諸葛亮は、それでは危ないと言い、八字の教えを伝える。
「北ハ曹操ヲ拒(ふせ)ギ、東ハ孫権ト和ス。お忘れあるな」と。
関羽を補佐する者としては、文官に伊籍(いせき)・糜竺(びじく。麋竺)・向朗(こうろう)・馬良(ばりょう)などを留め、武将には関平・周倉(しゅうそう)・廖化(りょうか)・糜芳(びほう。麋芳)などを残す。
そして諸葛亮がひきいていった荊州の精兵といえば、わずか1万に足らなかった。張飛(ちょうひ)を大将とし、峡水の水路と険山の陸路とのふた手になって進む。
★井波『三国志演義(4)』(第63回)では、諸葛亮がひきいた軍勢は1万5千で、別に張飛が1万の精鋭をひきいていた。
(02)行軍中の諸葛亮
諸葛亮が告げた。
「まず張飛は巴郡(はぐん)を通り、雒城の西に出でよ。自分は趙雲(ちょううん)を先手として船路を取り、やがて雒城の前に至らん」
ふた手に軍勢を分けて発つ日、野宴を張り、「どちらが先に雒城へ着くか、先陣を競おう。いずれも健勝に」と杯を挙げ、お互いの前途を祝し合った。
別れに臨み、諸葛亮が張飛に忠言する。
「蜀には英武の質が多い。貴下(あなた)のごとき豪傑は幾人もいる。加うるに地は剣山刀谷である。軽々しく進退してはならない」
「よく部下を戒め、かりそめにも掠(かす)め盗らず虐げず、行くごとに民を哀れみ、老幼を馴(な)ずけ、ただ徳をもって衆に臨むがいい」
★原文「老幼を馴ずけ」だが、手なずけるという意味合いなら「懐け」としたほうがいいかも?
「また、軍律は厳かにするとも、みだりに私憤をなして士卒を鞭(むち)打つようなことは、くれぐれも慎まねばならぬ。こうして迅速に雒城へ出て、めでたく第一の功を勝ち取られよ」
張飛は拝謝して、勇躍、先へ進んだ。
(03)巴郡
張飛がひきいた1万騎は漢川(かんせん)を風靡(ふうび)した。
★ここで張飛が1万騎をひきいたとあったが、この第199話(01)で言っていた兵数と違いすぎる。途中で降兵を容れて増えたなら、そのあたりにも触れてほしかった。
しかしよく軍令を守り、少しも略奪や殺戮(さつりく)の非道をしなかったので、行く先々の軍民は、彼の旗を望んでみな降参してきた。
やがて巴郡へ迫る。ここを守る蜀の名将の厳顔(げんがん)は、老いたりといえどよく強弓を引き太刀を遣い、その士操も凜々(りんりん)たるものがあった。
張飛が城外の10里まで寄せ、使いを立てて降伏を促すと、厳顔は使いの耳と鼻を切って城外へつまみ出した。
怒った張飛は真っ先に馬を飛ばし、空壕(からぼり)の下へ迫る。だが、敵は城門を閉じて防塁を堅固にし、ひとりも出て戦わない。のみならず櫓(やぐら)から首を出し、散々に悪罵した。張飛は日没まで猛攻を続けたが、頑として城は陥ちない。
そこに野営して、翌日も早天から攻めかかる。すると櫓の上に厳顔が初めて姿を現し、からかった。
「先ごろ使いの口上で、満城を血にせんと言ったのは、さては寄せ手の血漿(けっしょう)をもって彩ることでありしか。いや見事、見事。ご苦労、ご苦労――」
張飛が大きく口を開け、「よしっ。汝(なんじ)を生け捕り、汝の肉を食らわずにはおかんぞ!」と言ったとたん、厳顔の引き絞った強弓から一矢が放たれる。
張飛がアッと馬のたてがみへ身を伏せたので、矢は兜の脳天に跳ね返った。さすがの張飛もふらふらと眩暈(めまい)を覚え、早々に後陣へ隠れてしまう。
張飛は厳顔の手並みに感心するが、力ずくな攻城が、いかに労して効の少ないものかを教えられもした。
城の一方に高い丘陵があり、張飛はここに登って城内をうかがう。城兵の部署や隊伍(たいご)は整然としていて甚だ立派だった。
そこで声の大きな部下を選び、様々な悪口を城中へ放送させてみる。けれど城の者はひとりも出てこないし、相手にもならない。
誘いの兵を少しばかり近づけ、偽って逃げる態をなし、城兵が追ってきたら捕捉して、そのまま一気に突入しよう、などという策も行ってみたが……。
「彼の戦法は、まるで児童の戦遊び。抱腹絶倒に値する――」
厳顔は一笑の下に、そのあがきを見ているだけで、張飛の策にはてんで乗ってこないのだった。
管理人「かぶらがわ」より
劉備の要請を受け、蜀へ向かう荊州の援軍。吉川『三国志』には相手を悪罵しておびき寄せる、みたいな手がよく出てきますけど、これはあまり効果がないのでは?
ここ巴郡でも多くの戦死者が出ているのでしょうが、その描写に笑いの要素が入っていたのはどうも……。当時の士卒や民衆は大変だっただろうと、容易に想像できますからね。

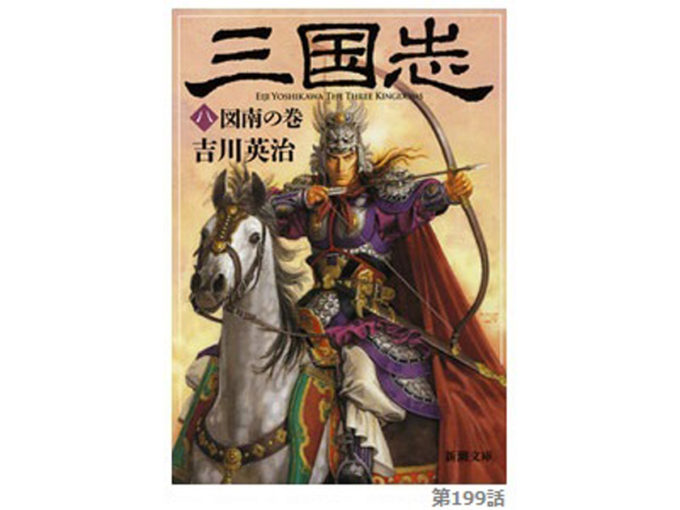













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます