先に龐統(ほうとう)から勧められた連環の配列を完成させると、いよいよ曹操(そうそう)は大船団をひきいて烏林(うりん)まで進む。
吹きすさぶ烈風にも鎖でつながれた船の動揺は少なかったが、程昱(ていいく)はある不安を覚え、曹操に注意を促す。
第161話の展開とポイント
(01)長江の北岸 曹操の本営
数日後、水軍の総大将の毛玠(もうかい)と于禁(うきん)が、命令通りに連環の配列を成し終えたと報告。曹操は旗艦に上がって水軍を閲兵し、手分けを定める。
中央の船団は黄旗を翻し、毛玠や于禁のいる中軍の目印とする。前列の船団は檣頭(しょうとう。帆柱の先)に紅旗を掲げ、この一手の大将には徐晃(じょこう)。
★『三国志演義(3)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第48回)では、(水軍の)前軍の紅旗は張郃(ちょうこう)となっており、徐晃は(陸軍として歩騎をひきいる)前軍の紅旗とある。
黒旗の船列は呂虔(りょけん)の陣。左備えには青旗が並び、これは楽進(がくしん)のひきいる一船隊。
★井波『三国志演義(3)』(第48回)では、(水軍の)左軍の青旗は文聘(ぶんぺい)となっており、楽進は(陸軍として歩騎をひきいる)左軍の青旗とある。
反対の右備えには白旗を並べ、その手の大将は夏侯淵(かこうえん)。
★井波『三国志演義(3)』(第48回)では、(水軍の)右軍の白旗は呂通(りょとう)となっており、夏侯淵は(陸軍として歩騎をひきいる)右軍の白旗とある。なお、吉川『三国志』では呂通を使っていない。これに加え、(陸軍として歩騎をひきいる)後軍の黒旗として李典(りてん)の名も見える。
このときの曹操軍は南へ向かって進攻するため、前軍(紅旗)が南側、後軍(黒旗)が北側、左軍(青旗)が東側、右軍(白旗)が西側となる点に注意が必要。
また、水陸の救応軍には夏侯惇(かこうじゅん)と曹洪(そうこう)の二陣が控え、交通守護軍や監戦使(かんせんし)として許褚(きょちょ)や張遼(ちょうりょう)が固めていた。
即日、この大艦隊は呉へ向かって迫ることになった。三通の鼓を合図に水寨(すいさい)の門は三面に開かれ、一糸乱れず大江の中流へ出る。
★『完訳 三国志』(小川環樹〈おがわ・たまき〉、金田純一郎〈かねだ・じゅんいちろう〉訳 岩波文庫)の訳注によると、「太鼓をひとしきり(しばらく続く様子に)打ち立てるのを一通という。その数は唐代の兵法書によると、333回を一通とする由である(『通典〈つてん〉』巻149に引く趙国公王琚〈おうきょ〉の『教射経』)。三通は合計1千回に近い打ち方となる」という。
(02)長江
この日、風浪は天にしぶき、三江の船路は暴れぎみだったが、連環の船と船とは鎖のために動揺の度が少なかったので、士気は甚だ振るった。
たが風浪がやまないので、全艦艇は江を下ることわずか数十里の烏林の湾口に停泊。この辺までも、陸地は要塞たることもちろんである。
そしてここまで来ると、呉の本営である南の岸は、すでに晴天の日なら指さし得るほどな彼方(あなた)にあった。
(03)烏林
ここで程昱が、烈風を見て心にかかりだしたことがあると言う。
鎖をもって船の首尾をつなげば揺れは少なく、士卒の間に船酔いも出ず、しごく名案のようだが、万一敵に火攻めの計を謀られたら、一大事を惹起(じゃっき)するのではないかと。
しかし曹操は笑って、今は11月で、西北(いぬい)の風は吹く季節だが、東南(たつみ)の風が吹くことはないと言い、南にある呉が火攻めを行うことはないと断ずる。諸将は皆その知慮に感服した。
何と言っても、彼に従う麾下(きか)の将士は大部分が青州(せいしゅう)・冀州(きしゅう)・徐州(じょしゅう)・燕州(えんしゅう)などの生まれで、水軍に不慣れな者ばかり。この連環の計に不賛成を唱える者は少なかった。
★燕地方のことを、当時の設定として燕州と呼んでもいいのか、いくらか気になった。
こうして風浪が鎮まるのを待つうちに、もと袁紹(えんしょう)の大将で、今は曹操に仕えている燕の人、焦触(しょうしょく)と張南(ちょうなん)が20隻の船を貸してほしいと名乗り出る。
曹操は叱っただけで許さなかったが、ふたりは、蒙衝(もうしょう。突撃艦。艨艟)5、6隻と走舸(そうか。速く走る小舟)十数艘(そう)で敵の岸辺へ突入すると言って聞かない。
★ここで燕の人だというふたりが、「我らは長江のほとりに育ち、舟を操ること、水をくぐること、平地も異なりません」と言っていた。だが燕は幽州(ゆうしゅう)に相当するので、長江は関係ないだろう。持ち出すなら黄河(こうが)のほうか。
なお井波『三国志演義(3)』(第48回)では、曹操がふたりに、「お前たちは北方育ちだから、おそらく船に乗るのは下手だろう……」と言っている。
ついに曹操は乞いを容れたが、大事を取り、別に文聘に30隻の兵船と兵500を授けた。
★ここで当時の艦船の種別や装備の大略が説明されていた。
闘艦(とうかん)は最も大きく、また堅固にできている。艦の首尾には石砲を備えつけ、舷側には鉄柵が結い回してある。楼には弩弓(どきゅう)を掛け連ね、螺手(らしゅ)や鼓手が立ち、全員に指揮や合図を下す。ちょうど今日の戦闘艦にあたるものである。
大船と呼ぶ普通兵船型のものは、現今の巡洋艦のような役割を持つ。兵力や軍需の江上運輸から、戦闘の場合には闘艦の補助的な戦力も発揮する。
蒙衝は、船腹を総体に強靱(きょうじん)な牛の皮で外装した快速の中型船。もっぱら敵の大船隊の中を駆逐し、奇襲戦にも用いる。兵6、70人は乗る。
走舸は小型の闘艦のようなもの。20人余りを乗せることができ、江上一面に雲霞(うんか)のごとく散らかって闘船や大船に肉薄。投火や挺身(ていしん)などのあらゆる方法で敵を苦しませる。
このほかにも、なお雑多な船型や大小の種類もあるが、総じて船首の飾りや船楼は濃厚な色彩で塗り立て、それに旌旗(せいき)や刀槍(とうそう)のきらめきが満載されているので、その壮大華麗は水天に映じ、言語を絶するばかりであると。
(04)長江の南岸 周瑜(しゅうゆ)の本営
呉のほうでも決戦の用意は怠りなかった。駆け違いに軽舸のもたらしてくる情報は引きも切らない。付近の山上には昼夜、物見の兵が江上に目を光らせ、芥(あくた)の流れるのも見逃すまいとしていた。
ほどなく周瑜のもとに、二列に分かれた敵の蒙衝と走舸が寄せてくるとの知らせが届く。周瑜の許しを得た韓当(かんとう)と周泰(しゅうたい)は、すぐに江岸より十数隻の牛革船を解き放ち、左右から鼓を鳴らして敵船へ迫った。
(05)長江
魏の焦触と張南のふたりは、しゃにむに岸への突進を試みる。韓当はこれを防ぎつつ、自身も長槍(ちょうそう)を手に一船の舳(みよし。船首)に立ち現れ、横ざまに船をぶつけていく。
焦触も矛を振るって譲らず、十数合ほど戦ったが、風浪が激しく船と船はもみ合い、勝負はいつ果てるとも見えなかった。
そこへ周泰が船を漕(こ)ぎ寄せ、韓当を励ましながら手にした一槍を投げる。焦触は串(くし)刺しになって水中へ落ちた。
★井波『三国志演義(3)』(第48回)では、焦触を槍で刺し殺したのは韓当。
★井波『三国志演義(3)』の訳者注によると、「焦触の伝記は不明だが、曹丕(そうひ)に対して皇帝に即位するよう勧めた上尊号碑(尊号を上〈たてまつ〉る碑)(220年)に列挙された46人の臣下の中に、征虜将軍(せいりょしょうぐん)都亭侯(とていこう)臣焦という人物がおり、王昶(おうちょう。1724~1806年)はこれを焦触ではないかと考えている(『金石萃編〈きんせきすいへん〉』巻23)」という。
これを見た張南は、周泰の船に近づきながら弩を浴びせかける。周泰は舷(ふなべり)の陰に身を伏せ、矢面をくぐって敵船へ寄せた。
船腹と船腹の間に勢いよく水煙が上がった刹那、周泰は相手の船に躍り込み、張南をただ一刀に斬り捨てたのみか、その船を分捕る。
こうして水上の序戦は魏の完敗に終わり、首将のふたりまで討たれたので、魏船は乱れに乱れ、風波の中を逃げ散らかった。
望戦台の丘に立つ周瑜は大変な喜色を表す。しかし、すぐに曹操がおびただしい闘艦や大船の艨艟(もうどう)を押し開き、呉岸へ向かって動きだす気配を見せる。
★艨艟のルビは「もうしょう」と「もうどう」で揺れが見られる。
すると突然、江上の波が怒り、狂風が吹き捲(ま)いて、ここかしこに数丈の水煙が立った。そして、曹操の乗る旗艦の帥の字の旗竿(はたざお)が折れてしまう。立ち騒ぐ江上の狼狽(ろうばい)ぶりが目に見えるようだった。
臨戦第一日のこと、これは誰しも忌む大不吉に違いない。まもなく連環の艨艟はことごとく帆を巡らせて舵(かじ)を曲げ、烏林の湾口深くに引き返した。
(06)長江の南岸 周瑜の本営
周瑜は手を叩いて狂喜。ところが江水を吹き捲いた竜巻は、南岸一帯からこの山へも、大粒の雨を先駆としてすさまじく暴れ回る。
アッと周瑜が絶叫したので、周りにいた諸将が仰天して駆け寄ってみると、傍らに立ててあった大きな司令旗の旗竿が、狂風のためふたつに折れていた。彼の体はその下に押しつぶされていたのだった。
諸将は血を吐いた周瑜を抱え上げ、山の下へ運んでいったが、気を失っているらしく、その途中も声すら出さなかった。
管理人「かぶらがわ」より
動きだす曹操の大艦隊。序戦に勝利した周瑜でしたが、旗竿の下敷きになって血を吐くに至りました。
いくら曹操軍が大軍だったとはいえ、水戦に不慣れな兵士が多かったのなら、急には戦力にならないでしょうね。

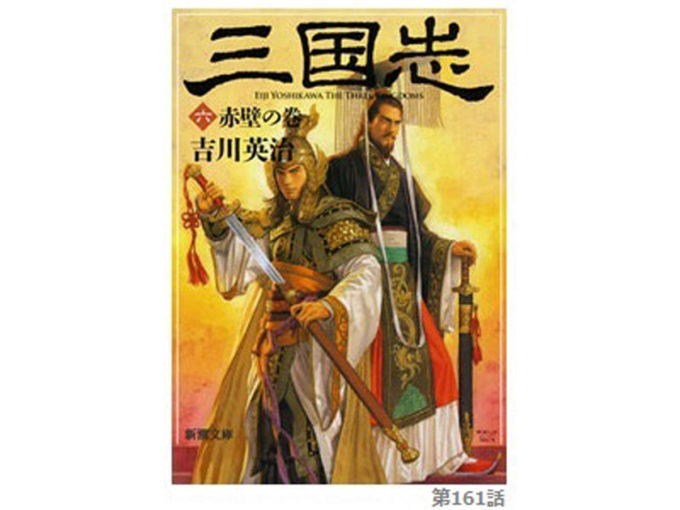












コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます