司令旗の旗竿(はたざお)に押しつぶされて血を吐き、陣中で寝込む周瑜(しゅうゆ)。だが、魯粛(ろしゅく)とともに見舞いに来た諸葛亮(しょかつりょう)は、彼の苦悩の原因を見抜く。
その場で周瑜に乞われた諸葛亮は、若いころ身に付けたという『八門遁甲の天書(はちもんとんこうのてんしょ)』の知識を用い、東南の風が吹くよう祈ってみると言いだす。
第162話の展開とポイント
(01)長江の南岸 周瑜の本営
よほど打ちどころが悪かったとみえ、周瑜は営中の一房に安臥(あんが)して昏々(こんこん)とうめき苦しんでいる。軍医や典薬(てんやく)が駆けつけて極力看護にあたる一方、孫権(そんけん)のもとへは急使が飛んだ。
(02)長江の南岸 諸葛亮の船住居
周瑜の容体を心配した魯粛は、諸葛亮を訪ねて善後策を相談。諸葛亮はさして苦にする様子もなく、ふたりでお見舞いしてみようと言う。
(03)長江の南岸 周瑜の本営
諸葛亮は周瑜を見て、心病だから起きられるはずだと声をかける。そして人払いを促すと、一服の涼剤を処方すると称して16字を書き示す。
欲破曹公宜用火攻(そうこうをやぶらんとほっすれば、よろしくひぜめをもちうべし)
万事俱備只欠東風(ばんじともにそなう、ただとうふうのかくを)
周瑜は愕然(がくぜん)と諸葛亮の顔を見ていたが、先生には何事も隠し立てはできないと笑う。そのうえかえって彼の垂教を仰いだ。
すると諸葛亮は、若年のころ異人に会い、『八門遁甲の天書』を伝授されたと話す。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(『八門遁甲の天書』は)道教経典の一種。明代には諸葛亮が習得したとする『秘蔵通玄変化六陰洞微遁甲真経(ひぞうつうげんへんげりくいんどうびとんこうしんけい)』などの道教経典が成立していた」という。
もし都督(ととく。周瑜)が東南の風をお望みなら、私が畢生(ひっせい)の心血を注ぎ、天書に依り風を祈ってみるとも。
だがこれは、諸葛亮の心中に別な自信のあることだった。
毎年の冬11月ともなれば、潮流と南国の気温の関係から季節外れな南風が吹き、1日か2日の間、冬を忘れることがある。その変調を後世の天文学語で貿易風という。ところが今年に限り、まだ貿易風がやってこない。
諸葛亮は長らく隆中(りゅうちゅう)に住んでいたので、年々つぶさに気象には細心の注意を払っていた。1年といえども、まだそれのなかった年はない。なので、どうしても今年も、やがて間近にその現象があるものと確信していたのである。
さらに諸葛亮は、11月20日は甲子(きのえね)にあたり、この日にかけて祭りをすれば、三日三夜のうちに東南風(たつみかぜ)が吹き起こると言う。
★『三国志演義(3)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)の訳者注によると、「(11月20日は)甲子ではなく、正しくは壬申(みずのえさる)」だという。
そうしたうえで、南屛山(なんぴょうざん)の上に七星壇(しちせいだん)を築かせてほしいと願い出る。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「南屛山は山の名。荊州(けいしゅう)江夏郡(こうかぐん)に属す。現在の湖北省蒲圻市(ほきし)西北。後漢・三国時代にはこの地名はなかった」という。また「現在では蒲圻市赤壁山(せきへきざん)のうち、長江に突き出た先端部分を南屛山と呼んでいるようである」ともいう。
(04)長江の南岸 南屛山
周瑜は病を忘れ、たちまち陣中を出て指図。魯粛や諸葛亮も馬を速めて南屛山へ行き、地形を見定め工事の督励にかかる。500人の士卒は壇を築き、120人の祭官は古式に則り準備を進めた。
東南の方(かた)には赤土を盛って方円(周囲)24丈とし、(一層の)高さ3尺(せき)。三重(合わせて高さ9尺)の壇を巡らせ、下の一重目には二十八宿の青旗を立て、二重目には64面の黄色の旗に64卦(け)の印を書く。
そして三重目には、束髪の冠を頂き身に羅衣(薄絹の着物)をまとい、鳳衣(ほうえ。鳳凰〈ほうおう〉を描いた着物)博帯(幅の広い帯)、朱履(赤い履〈くつ〉)方裙(ほうくん。四角の裙〈すそ〉)した者4人を立てる。
左のひとりは長い竿に鶏の羽を挟んだものを持って風を招き、右のひとりは七星の竿を掲げ、あとのふたりは宝剣と香炉を捧げて立つ。
こうした祭壇の下には、旌旗(せいき)・宝蓋・大戟(たいげき)・長槍(ちょうそう)・白旄(はくぼう。犛牛〈からうし〉の尾を竿の先に飾った旗)・黄鉞(こうえつ。黄金の鉞〈まさかり〉)・朱旛(しゅはん。朱色をした長く垂れた印の旗)を手に、兵士24人が魔を寄せつけじと護衛に立つなど、何にせよ途方もない大仰な行事だった。
11月20日、諸葛亮は前日から斎戒沐浴(もくよく)して身を清め、白の道服(道士の服)を着て素足のまま壇に登り、いよいよ三日三夜の祈りにかかるべく立った。
その一瞬の前に魯粛を呼び、3日のうちに風を吹き起こすことがあれば、時を移さず、かねての計をもって敵へ攻め寄せるよう周瑜に伝えてほしいと念を押す。
魯粛が去ると諸葛亮は壇下の将士らを戒め、自分が風を祈る間に持ち場を離れたり、私語することを一切禁ずる。また、いかなる怪しいことが起きても驚き騒がないようにとし、行(ぎょう)を乱し法に背く者は、たちどころに斬って捨てるとも言った。
こうして南面すると香を焚いて水を注ぎ、二刻ほど天を祭る。祝文(神を祭る文)を唱えて詛(じゅ)を切ることみたび、なお久しく黙とうすると辺りに神気が立ち込め、壇上にも壇下にも人の声なく、天地万象また寂(せき)たるもの。
★「詛を切る」は祈りの中の動作だと思うが、ルビも含めてイマイチつかめなかった。
夜が更けかけたころいったん壇を降り、油幕の内で休息。この間に祭官や護衛の士卒などにも交代で食事と休息を取ることを許した。
初更(午後8時前後)から再び壇に登り、夜を徹しての行にかかる。それでも深夜の空は冷々と死せるがごとく、何の兆しも表れてこなかった。
(05)長江の南岸 周瑜の本営
一方の魯粛は周瑜に万端の手はずを促し、孫権にも早馬で事の次第を伝えておく。もし諸葛亮の祈りの験(しるし)が表れ、望むところの東南の風が吹いてきたら、ただちに総攻撃へ移ろうと待機していた。
また黄蓋(こうがい)は、かねての計画通りに20余艘(そう)の兵船や快速舟を用意して、内に干し草や枯れ柴(シバ)を満載し、その下に硫黄や焰硝(えんしょう。火薬)を隠した。
これを青布の幕ですっかり覆い、水上の進退に慣れた精兵300余を各船に分乗させ、周瑜の命令を密かに待っていた。
もちろん、この一船隊は初めから密計を抱いているので、黄蓋と同心の甘寧(かんねい)や闞沢(かんたく)などが、敵の諜者(ちょうじゃ)である蔡和(さいか)と蔡仲(さいちゅう。蔡中)を巧みに捉え、わざと酒を酌んだりして遊惰のふうを見せていた。
はや翌日も暮れたころ孫権の伝令が着き、すでに本軍が遡江の途中にあり、この前線から80里ほどまで来ていることが伝わる。
周瑜が諸葛亮の祈りの験を怪しみだしてから二刻も経たないうちに、一天の星色が次第に改まり、ようやく風が立ち始めた。しかも、それは東南に特有の生暖かい風だった。
周瑜は身震いし、急に丁奉(ていほう)と徐盛(じょせい)を呼んで水陸の兵500を授け、南屛山へ急がせる。
★井波『三国志演義(3)』(第49回)では、このとき丁奉と徐盛が連れていったのはそれぞれ100人。
(06)長江の南岸 南屛山
陸路と水路のふた手に分かれて南屛山へ迫った500の討手のうち、丁奉の兵300が真っ先に山へ登っていく。丁奉が諸葛亮の所在を尋ねると、油幕の内で休んでいるという。
ここで徐盛の船手勢も来たのでともに油幕を払ってみたが、どこにも姿はない。ふたりは鞭(むち)打って馬を速め、山のふもとで情報を得ると、さらに長江の岸まで駆けた。
(07)長江
丁奉と徐盛は数艘の舟を出して追いかけ、諸葛亮の小舟を見つける。しかし白衣姿の諸葛亮は舟を止めず、笑いながら答えた。
「周都督のお旨は承らずともわかっておる。それよりもすぐに立ち帰って、東南の風もかく吹けり、はや敵へ攻めかからずやとお伝えあれ。それがしはしばらく夏口(かこう)に帰る。他日、好縁もあらばまたお目にかからん」
この声が終わるやいな彼の影は船底に隠れ、しぶきは舟も帆も包み、見る見るうちに遠くなってしまった。
管理人「かぶらがわ」より
「あぁ、東南の風が吹いちゃったよ――」だった第162話。
この吉川『三国志』では、諸葛亮が貿易風のことを知っていたというフォローがありましたが、『三国志演義』では思いっきり彼の祈りが風を呼んだという展開に……。
『三国志』(呉書・周瑜伝)の裴松之注(はいしょうしちゅう)に引く虞溥(ぐふ)の『江表伝』には、この戦いの日、ちょうど東南の風が激しく吹いていたことだけが書かれていました。
「諸葛亮まったく関係ないじゃん!」と言いたくもなる膨らませ方なのですよね。

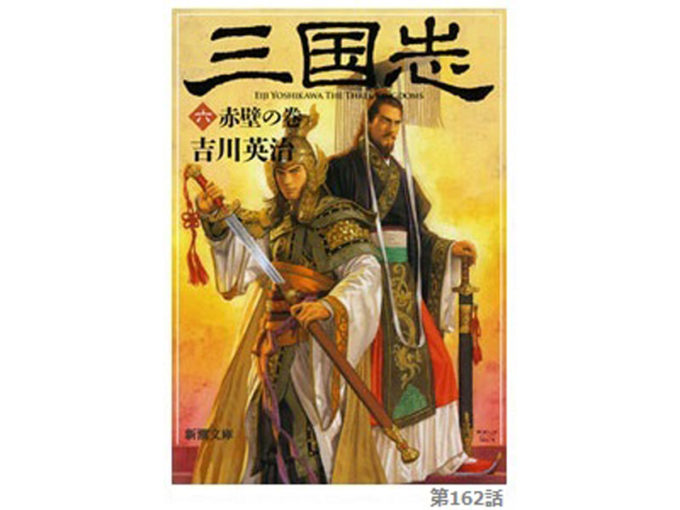














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます