孫権(そんけん)の命を受け、魯粛(ろしゅく)は劉備(りゅうび)を訪ねたものの、やはり荊州(けいしゅう)の返還問題については話が進まない。
魯粛は帰途で柴桑(さいそう)に立ち寄ると、周瑜(しゅうゆ)の秘策を携え、南徐(なんじょ)まで戻らず荊州へ引き返す。ところがこの秘策も不発に終わり、ついに周瑜は――。
第178話の展開とポイント
(01)南徐(京城〈けいじょう〉?)
周瑜は柴桑で傷養生をしていたが、勅使に接し南郡太守(なんぐんたいしゅ)に任ずるとの沙汰を拝すると、孫権に書簡を送って知らせた。
このころ孫権は南徐に都しており、書簡が届くと魯粛を呼んで相談。魯粛は孫権の許しを得て、荊州へ使いすることになった。
(02)荊州(江陵〈こうりょう〉?)
劉備は魯粛の到着を聞くと、対応を諸葛亮(しょかつりょう)に諮る。諸葛亮は、魯粛が荊州の問題を持ち出したら、声を放ってお嘆きになるとよいと言う。後は私がよいように計らうとも。
やがて堂上に迎えられ、かつ上席に請ぜられると、もの堅い魯粛はあくまで辞退し、横に席を取った。だが、答礼も終わり用件の段階に入ると、さすがにその謙虚も払って荊州譲渡の件を切り出す。
すると劉備は、魯粛の言葉の半ばから面を覆い、声を漏らして泣きだした。魯粛が驚いているところへ、衝立ての後ろから諸葛亮が歩いてきて言う。
「蜀の劉璋(りゅうしょう)は漢朝の骨肉。いわば皇叔(こうしゅく。天子の叔父。ここでは劉備のこと)とは血において兄弟も同じです」
「ゆえなく兵を起こして蜀へ攻め入れば、世人は唾して不徳を罵るであろう。さりとて荊州を呉侯(孫権)に返せば、身を置く国もありますまい」
魯粛が情に動いた様子を見ると、諸葛亮はここぞと言う。
「粛公(魯粛)には呉侯に対し、皇叔がこのように苦衷しておられる子細を、何とぞよろしきようにお伝えたまわれ。よも呉侯とてお怒りはなさるまい」
急に我に返り、大げさに手を振る魯粛。それでも諸葛亮の言葉を聞くと、とかくの議論にも及ばなかった。
魯粛はただ劉備の立場に同情し、引いては主君の意思の裏にも一片の情けはあるはずだと思い込んでしまう。ついに今度も空手で帰国の途に就くしかなかったが、途中で柴桑へ船を寄せたついでに周瑜を訪ねる。
(03)柴桑
周瑜は次第を聞くと、またしても卿(けい)は孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)に一杯食わされたのだと言い、あまりにも善意的な見解をなじった。すべて孔明の遷延策にほかならないと。何とかかんとか言って、荊州を呉へ返さない算段を巡らせるに決まっているとも。
魯粛は、孫権に取り次ぐ言葉がないことに気づき、青くなる。そこで周瑜は一大秘策を授け、再び彼を荊州へ送り出す。
(04)荊州(江陵?)
魯粛は再び劉備に会うと、主君にあなたのご苦衷とお嘆きの態をありのままお伝えいたしたところ、大いに同情の色を表されたと話した。
そのうえで群臣とご評議の結果、こういう一案をお立てになりましたと言い、周瑜の知謀から出たのっぴきさせない一要求を持ち出す。
それは、劉備の名で蜀へ攻め入るのがまずいならば、呉の大軍をもって呉が直接、蜀を取るというものだった。その節には荊州を通過することと、多少の軍需兵糧を補給する確約を結んでもらいたいとの条件も出してきた。
劉備は異議なく協力を誓う。その前に諸葛亮から言われていたので、むしろ喜びを表し、恩を謝してみせる。
魯粛が心密かに喜悦し、さっそく柴桑へ帰っていくと、劉備は諸葛亮に、呉の提案の真意を尋ねた。
諸葛亮は、魯粛が南徐まで帰っていないことを見抜いており、これは荊州を取るための周瑜の策だと看破する。時節到来だと言い、趙雲(ちょううん)を呼んで策を授ける一方、彼自身も、やがて来るべきものに対して万端の備えをしていた。
(05)柴桑
周瑜は劉備の返事を聞くと、手を打って喜ぶ。魯粛は船を急がせ南徐へ下り、孫権に子細を報告。孫権もただちに早打ちを遣って周瑜を励まし、程普(ていふ)を大将として彼を助けさせた。
このとき周瑜は傷もあらかた平癒し、膿水(のうすい)も止まり、歩行に不自由ない程度にはなっていたので、勇躍して武装を整え、自ら戦陣へ赴く決心をする。
こうして甘寧(かんねい)を先手に、徐盛(じょせい)と丁奉(ていほう)を中軍に、凌統(りょうとう。淩統)と呂蒙(りょもう)を後陣として、総勢5万の水陸軍を編制。周瑜自身は2万5千をひきいて、船で柴桑を出た。
(06)夏口(かこう)
周瑜が土地の役人に尋ねると、荊州から糜竺(びじく。麋竺)が迎えに来ているという。まもなく糜竺は周瑜のところへ着き、すでに主君が軍需の用に供える金銀兵糧を調え終えていると伝えた。
(07)公安
糜竺が帰ると周瑜はすぐに上陸。江上一帯に兵船の備えを残し、陸路で荊州へ赴く。ところが公安まで来ても、劉備の出迎えはおろか小役人にも会わない。荊州までの道のりを尋ねると、もうわずか10里しかないという。
★荊州(城)というのがどの城を指しているのかわからないが、ここでは「公安から10里しかない」と言っていた。これは手がかりになりそう……。だが周瑜が荊州城に向かう過程で、夏口で下船して陸路で公安へ行ったとするなど、地理的にわかりにくい記述になってもいる。病み上がりなら、柴桑からずっと船に乗ってさかのぼり、夏口を経て公安まで水路を行くのが自然なのでは?
★これについて『三国志演義(4)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)の訳者注に指摘があった。「この荊州(城)は南郡の役所が置かれた江陵県城を指す。したがって、後文で関羽(かんう)が江陵から攻め寄せてきたとするのは合わない。劉琦(りゅうき)の死後、関羽は襄陽(じょうよう)の守備に就いているので、襄陽とするほうがよいか」という。
また「要するに、東から進んできた呉軍に対し、趙雲が要の荊州城を守り、関羽は北から、張飛(ちょうひ)は西から、黄忠(こうちゅう)と魏延(ぎえん)は南から攻める形を取ったことになる」ともいう。この訳者注から、趙雲が守っていたのは江陵城だということがわかった。
皆がいぶかしみながら休息していたところへ、先手の斥候が馬を飛ばしてきて告げた。
「何か様子が変です。見渡す限り人の影も見えず、荊州城を望めばまるで葬式のように、二旒(ふたながれ)の白旗がしょんぼりなびいているだけなのです」
聞くやいな、周瑜は甘寧と丁奉についてくるよう言い、精兵1千余騎だけを連れ、まっしぐらに荊州城まで駆け通した。
★井波『三国志演義(4)』(第56回)では、周瑜は甘寧・徐盛・丁奉ら部将を引き連れ、3千の精鋭部隊をひきいて荊州城へと向かったとある。
(08)荊州(江陵?)
周瑜が城門を開けよと呼ばわると、趙雲が姿を現して言い返す。
「わが軍師孔明には、すでに足下(きみ)が道ヲ借リテ草ヲ枯ラスの計を推量し、それがしをここの番に付け置かれた。よそを探したまえ。それとも城中の趙雲に御用があるか?」
驚いた周瑜が馬を引き返すと、城下の街角から「令」の一字を書いた旗を背にした一騎が駆け寄ってきて告げた。
「いよいよ怪しいことばかりです。いま諸方の巡警から知らせてきたところによると、関羽は江陵より攻めきたり、張飛は秭帰(しき)より攻めきたり、黄忠は公安の山陰から現れ、魏延は孱陵(せんりょう)の横道から殺到しつつあるということです」
「兵数そのほか事態はまだよくわかりませんが、何しろ鬨(とき)の声は遠近に響き、さながら四方50余里が敵に埋まったかのような空気で――」
周瑜は馬のたてがみにうっぷす。治りかけていた金瘡(きんそう。刀傷や矢傷)がことごとく破れ、血を吐いたかと思うと、そのまま馬の背から落ちてしまう。諸将は仰天して周瑜の身を抱え、辛くも救命薬を与えて蘇生させる。
そこへまた物見が来て、劉備と諸葛亮がついこの先の山上に、蓆(むしろ)を延べて幕(とばり)を巡らし、酒を飲んで楽しみ興じている態だと告げた。
周瑜は歯がみをして無念の拳を握り締める。侍医や近侍たちはこもごもになだめ、安臥(あんが)を勧めた。
そこへ孫権の弟の孫瑜(そんゆ)が援軍をひきいて駆けつける。孫瑜は周瑜の様子を見ると、ただちに彼を病輿に乗せ、ひとまず夏口の船場まで退くことにした。
(09)巴丘(はきゅう)
その途中で巴丘まで来ると、彼方(かなた)に荊州の一軍がいて江頭の道を切りふさいだという。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「(ここで出てきた巴丘は巴丘山のことで、)巴丘山は周瑜が死んだ場所である」という。
また「巴丘という地名は『三国志演義』(第29回)にも周瑜の駐屯していた県として登場するが、裴松之(はいしょうし)は『呉書・周瑜伝』の注において、巴丘山は当時(南朝宋)の巴陵県(はりょうけん)であり、江西省の巴丘県とは別の場所であると述べている」という。
★周瑜が巴丘に駐屯していたことについては、先の第113話(05)を参照。
物見を放ってうかがわせると、関羽の養子の関平(かんぺい)と(劉備の養子の)劉封(りゅうほう)が待ち構え、厳しく陣を巡らせているとのこと。
周瑜は輿から降ろせと叫んだが、病輿はどんどん道を変え、ほかの方向へ走る。そして孫瑜の命により、夏口にある一隻を別の江岸へ呼び、かろうじて周瑜の身を船へ移した。
(10)長江(ちょうこう)
するとそこへ、荊州の軍使と称する者がやってきて、周瑜に一書を渡す。見れば諸葛亮の手跡だった。
この中で諸葛亮は、呉軍が蜀を攻め取るのは無理だとし、曹操(そうそう)が赤壁(せきへき)で犯した愚轍(ぐてつ)を追うなと注意を促す。
読み下していくうちに、周瑜は恨気胸にふさがり、手はわななき、顔色も壁土のようになってしまう。
ここで長嘆一声すると、急に筆硯(ひっけん)と紙を引ったくり、必死の形相をしながら何か懸命に書きだす。文字は乱れて墨は散り、文は綿々と長かったが、ついに書き終えるや筆を投げた。
「あぁ、無念っ……。無情や人生。皮肉なることよ宿命……。天すでにこの周瑜を地上に生ませたまいながら、なぜまた孔明を地に生じたまえるや!」
言い終わると昏絶(こんぜつ)して、いったん目を閉じたが、再び目を見開いて言う。
「諸君。不忠、周瑜はここに終わったが、呉侯を頼む。忠節を尽くして……」
忽然(こつぜん)と薄黒い瞼(まぶた)を落とし、まだ36歳の若い寿(とし)に終わりを告げた。建安(けんあん)15(210)年の冬12月3日であったという。
管理人「かぶらがわ」より
呉の巨星たる周瑜の死。彼の風采が立派だったことは正史『三国志』に言及されているほどで、誠に華のある人物でした。
この吉川『三国志』や『三国志演義』では、諸葛亮を持ち上げるために貶(おと)されている印象が強いですが……。赤壁の戦いにおける活躍など、特に武功には輝かしいものがあります。

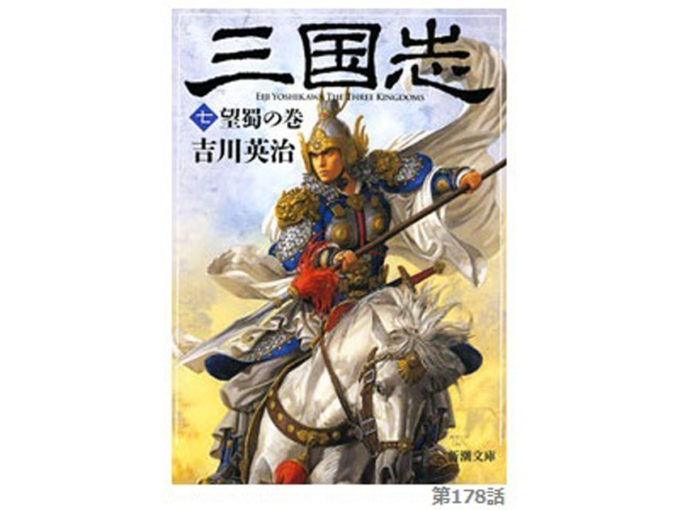















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます