先発した水軍に続き、周瑜(しゅうゆ)自身も旗艦に乗り込み江上を進む。やがて対岸の曹操(そうそう)のもとに、約束通り黄蓋(こうがい)の船団が現れたとの報告が届く。
ところが程昱(ていいく)は、兵糧や武具を満載しているはずの黄蓋の船が深く沈んでいないと警告。曹操はすべてを悟り、黄蓋の船団を近づけないよう文聘(ぶんぺい)に命ずるが――。
第165話の展開とポイント
(01)長江の南岸 周瑜の本営
すでに初更(午後8時前後)に近いころ、蔡和(さいか)の首を供えて水神と火神に祈り、血を注いで軍旗を祭った周瑜は、最後の水軍に出航を下知する。
このとき先発の第1船隊、第2船隊、第3船隊などは、舳艫(じくろ。船首と船尾)をそろえて江上へ進んでいた。
(02)長江の北岸 曹操の本営
北岸の魏の陣中で、誰か吟詠している者がある。曹操は、程昱から艦尾に番している哨兵だと聞くと、一杯の酒を褒美にやろうと言う。
それとほぼ同時に、南のほうからたくさんの船隊が上ってくるとの声が聞こえる。すべての船の帆檣(はんしょう。帆柱)に青龍の牙旗(がき)が見えるとのこと。
★『三国志演義 改訂新版』(立間祥介〈たつま・しょうすけ〉訳 徳間文庫)の訳者注によると、「(牙旗は)大将の旗。陣頭に立てる大きな旗で、竿(さお)の先を象牙で飾るからこう言うともいわれる」とある。
さらに曹操は、遠く後方から来る一船団のうちの大船には、「黄(こう)」の字を印した大旗が立ててあるように見える、とも聞く。
東南風(たつみかぜ)を受けてくるので、彼方(かなた)の機船隊の速度は驚くほど速い。すでに団々たる艨艟(もうどう。突撃艦)は目の前にあった。
★艨艟のルビは「もうどう」と「もうしょう」で揺れが見られる。
すると程昱がいぶかしいと言いだし、味方の人々を戒める。曹操が聞きとがめると、彼はこう言った。
兵糧や武具を満載した船ならば、必ず船脚が深く沈んでいなければならない。それなのに、いま目の前に来る船は水深が浅く、さして重量を積んでいるようには見えないと。
曹操は万事を悟り、誰か行って、あの船隊を水寨(すいさい)の内へ入れぬように防げと命ずる。
文聘が旗艦から小艇に乗り移り、近くの兵船7、8隻と快速の小艇10余艘(そう)をひきい、たちまち彼方なる大船団の針路へ漕(こ)ぎ寄せた。
(03)長江
文聘は舳(みよし。船首)に立ち、近づいてくる大船団に停船を呼びかける。ところが相手は答えないばかりか、先頭の一船から一矢が放たれ、彼の左臂(ひだりひじ)に当たった。
文聘が船底に転がると同じくして、船列と船列との間にはまるで驟雨(しゅうう)のような矢と矢が交わされる。このとき呉の奇襲艦隊の真ん中にあった黄蓋の船は、はや水寨の内へ突入していた。
黄蓋が腰の刀を抜き、味方の一船列を差し招くと、かねて巧みに偽装し先頭に立ててきた一団の爆火船隊は、一度に巨大な火炎を盛り、魏の大艦巨船へぶつかっていく。
炎の音とも、波の音とも、風の声ともつかないものが、瞬間、三江の水陸を包んだ。火の鳥のごとく水を翔(か)け、敵船の巨体に食らいついた小艇はどうしても離れない。
後でわかったことだが、それらの小艇の舳先(へさき)には、槍のような釘(くぎ)が植え並べてあった。敵船の横腹へ深く突き込んだと見ると、すぐに呉兵は木の葉のような小舟を降ろし、逃げ散ってしまうのだった。
いかに大きくとも木造船や皮革船である。見る間に山のような紅蓮(ぐれん)と化し、大波の底に沈没した。
加えて困難を極めたのは、例の連環の計により、大船と大船、大艦と大艦はほとんどみな連鎖交縛していたことである。
そのため一艦が炎上すればまた一艦、一船が燃え沈めばまた一船。交戦態勢を整える暇(いとま)もなく、焼けては没し、焼けては沈み、烏林湾(うりんわん)の水面はさながら発狂したように、炎々と真っ赤に逆巻く渦を描いた。
しかも、この猛炎の津波と火の粉の暴風は江上一面にとどまらず、陸の陣地にも燃え移っていた。烏林(北岸)、赤壁(せきへき。南岸)の両岸とも、岩も焼け林も焼け、陣所陣所の建物から糧倉、柵門、馬小屋に至るまで、目に映る限りは炎々たる火の輪をつないでいる。
この夜、周瑜は放火艇の突入する後から、堂々と大船列を作って進んできたが、味方の有利と見るやさらに陸地へ迫り、水陸の両軍を励ましていた。
曹操は幕将らに促されて旗艦から小舟へ移るが、それを見つけた呉の走舸(そうか。速く走る小舟)や兵船は、逃すなと四方から迫る。
無二無三に逃げ回る曹操の一艇に、快速船に乗り換えた黄蓋が近づく。ここで曹操のそばにいた張遼(ちょうりょう)が突っ立ち、鉄弓から一矢を放つと、矢は黄蓋の肩に立つ。アッという声とともに、黄蓋は波間へ落ちた。
あわてた呉兵が、その姿を水中に求めている間に、辛くも曹操は烏林の岸に逃げ上がった。しかしそことて一面の火炎。どこを見ても面も向けられない熱風だった。曹操は一嘆して大きく空へ叫ぶと、落ちゆく馬の背に飛び乗る。
★このあたりで「対岸の赤壁、北岸の烏林、西方の夏水(かすい)ことごとく火の魔か敵の影ばかりである」という記述があった。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「漢水のうち、襄陽(じょうよう)より下流の部分(襄江〈じょうこう〉)を夏水とも称した」という。
これだと夏水は烏林や赤壁の西というより、北や北西になるはず。いずれにせよ、このときの曹操が夏水(襄江)の状況を見られるはずがないので、ここは作者目線の語りということか?
管理人「かぶらがわ」より
黄蓋の爆火船隊の突撃により、炎上する曹操の水軍。連環の計は創作でも、曹操の大艦隊が烏林で火計を受けたことは史実です。
また、このときの曹操軍が80万超だったというのも創作ながら、それでも数万の呉軍に比べ、7、8倍の軍勢を投入していたことも史実。
どうも赤壁の戦いにおける曹操の配陣には納得がいきません。にわか仕込みの水軍に、ここまでこだわる必要があったのかなと。

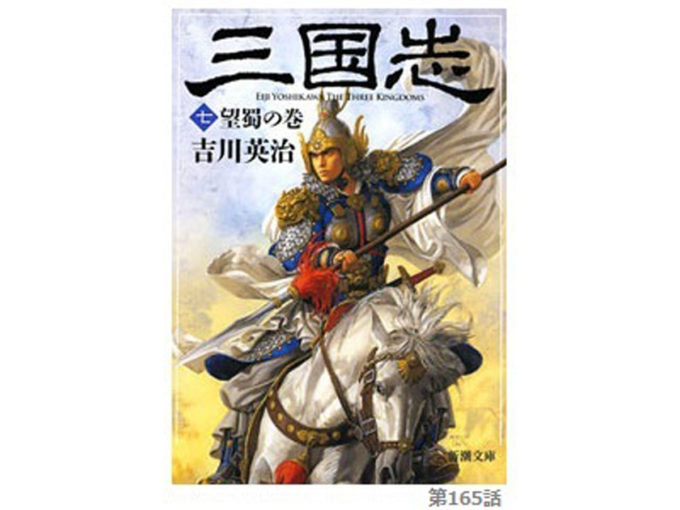












コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます