赤壁(せきへき)の戦いで惨敗を喫し、一夜にして全軍の3分の2以上を失ってしまった曹操(そうそう)。
彼自身は何とか戦場を離脱できたものの、逃げる先々に待っていた劉備(りゅうび)配下の諸将から追撃を受ける。
第166話の展開とポイント
(01)長江の北岸 曹操の本営
80余万と唱えていた曹操軍は、この一敗戦で一夜に3分の1以下になったという。溺死(できし)した者、焼け死んだ者、矢に当たって倒れた者――。また陸上でも、馬に踏まれ、槍に追われ、山をなすばかりな死傷者を出し、三江の要塞から壊乱した。
だが当然ながら、犠牲者は呉のほうにも多かった。
(02)長江
乱戦中に波間から声を聞いた韓当(かんとう)が熊手で引き上げてみると、今宵の大殊勲者の黄蓋(こうがい)で、肩に矢を受けている。韓当は鏃(やじり)を掘り出すと旗を裂いて傷口を包み、さっそく後方へ送った。
(03)長江の北岸 曹操の本営
甘寧(かんねい)・呂蒙(りょもう)・太史慈(たいしじ)などは早くに敵の要塞の中心部へ突入し、十数か所に火を放った。
このほか凌統(りょうとう。淩統)・董襲(とうしゅう)・潘璋(はんしょう)なども、縦横無尽に威力を振るい回った。誰かそのうちのひとりは蔡仲(さいちゅう。蔡中)を斬り殺し、首を槍の先に刺して駆けていた。
★『三国志演義(3)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第50回)では、蔡中(蔡仲)を斬ったのは甘寧。
(04)烏林(うりん)
曹操は張遼(ちょうりょう)らと逃げ続けたが、ここへ毛玠(もうかい)が10騎ばかりの将士と追いつく。その中には、先に深手を負った文聘(ぶんぺい)も助けられていた。
曹操は、この辺もまだ烏林だと聞かされ、わずか20数騎でさらに馬に鞭(むち)打って逃げる。林道の一方から呂蒙の兵が飛び出すと、張遼は殿軍(しんがり)を引き受け、曹操を先へ逃がす。
しかし、また1里も行くと凌統の軍勢が現れる。曹操が肝を冷やして林の中に駆け込むと、そこにも一手の兵馬が潜んでいた。
だがこれは敵ではなく、麾下(きか)の徐晃(じょこう)だった。曹操が張遼の苦戦を助けるよう命ずると、徐晃は一隊をひきいて駆け戻り、敵の呂蒙と凌統の兵を蹴散らし、重囲の中から張遼を救い出してくる。
曹操主従は再び一団となり、東北へ東北へと指して落ち延びた。
★烏林から華容(かよう)へ向かったのなら、ここは東北ではなく西北とすべき。なお井波『三国志演義(3)』(第50回)では、ここで曹操は血路を開いて北へ逃げたとある。
すると一彪(いっぴょう)の軍馬が山に拠り控えている。張遼や徐晃が物見をさせると、それはもと袁尚(えんしょう)の部下で、曹操に降ったあと久しく北国の一地方に屈踞(くっきょ)していた馬延(ばえん)と張顗(ちょうぎ)だった。
このふたりは北国の兵1千余を集めて烏林の陣へ加勢に来たのだが、昨夜来の猛風と満天の火光に行軍を止め、万一に備え、ここで差し控えていたものだった。
★井波『三国志演義(3)』(第50回)では、馬延と張顗がひきいていたのは3千の軍勢。
曹操は大いに力を得、馬延と張顗に道を開かせて500騎を後陣に回し、ここからは少し安らかな思いで逃げ落ちた。
★井波『三国志演義(3)』(第50回)では、曹操は馬延と張顗に1千の軍馬をひきいて先駆けさせ、残りの軍馬を留めて身辺警護にあたらせたとある。
そして10里ほど行くと、味方の倍もある一軍が真っ黒に立ちふさがり、ひとりの大将が駒を乗り出し何か言っている。
馬延が味方かと近づいてみると敵の甘寧で、馬を躍らせ近寄りざま一刀の下に斬り落とした。後ろにいた張顗も槍をひねって突きかかるが、これも敵ではなかった。
曹操は甘寧の勇に震え上がり、差しかかった南夷陵(なんいりょう。南彝陵)の道を避け、急に西へ曲がって逃げ走る。幸いにも味方の残軍に出会ったので、後から来る敵を防ぐよう命じながら、鞭も折れよと駆け続けた。
(05)烏林の西 宜都(ぎと)の北
夜もすでに五更(午前4時前後)のころ、振り返ると赤壁の火光もようやく遠くに薄れている。
曹操は、ややホッとした面持ちで駆け遅れてくる部下を待ちながら、「ここはどこか?」と左右に尋ねた。
もと荊州(けいしゅう)の士(さむらい)だった一将が、「烏林の西。宜都の北のほうです」と答える。
★井波『三国志演義(3)』の訳者注によると、「曹操は荊州を平定後、南郡(なんぐん)の枝江(しこう)以西を臨江郡(りんこうぐん)とし、後に劉備(りゅうび)が宜都郡と改めた。現在の湖北省枝城市(しじょうし)。したがって(宜都の北では)方位が合わず、距離的にも遠い」という。
曹操は、馬上からしきりに付近の山容や地形を見回していたが、突然、声を放って笑いだす。
諸将が奇異な顔を見合わせて尋ねると、周瑜(しゅうゆ)の浅才や諸葛亮(しょかつりょう)の未熟がわかったから、ついおかしくなったのだという。
もし自分が周瑜か諸葛亮だったら、まずこの地形に伏兵を置き、落ちていく敵に殲滅(せんめつ)を加えるところだ、と兵法講義を弁ずる。
ところがその講義が終わるか終わらないうちに、左右の森林から一隊の軍馬が突出した。趙雲(ちょううん)の声を聞いた曹操は、危うく馬から転げ落ちそうになる。
敗走、また敗走。曹操の残軍は散々に痛めつけられ、張遼や徐晃らの善戦により辛くも虎口を免れた。
★井波『三国志演義(3)』(第50回)では、ここでふたり掛かりで趙雲と戦ったのは徐晃と張郃(ちょうこう)。
降りだした大雨の中、曹操をはじめ幕下の者の疲労困憊(こんぱい)は、その極に達する。
(06)貧しげな山村
ようやく夜が白みかけたころ、一同は貧しげな山村にたどり着く。曹操の部下たちはそこらの農家に争って入り込み、漬物の甕(かめ)や飯櫃(めしびつ)、鶏や干菜、漿塩壺(しょうえんつぼ)などを思い思いに抱えてきた。
それでも、火を焚いて食べ物を胃袋に入れる間もない。山村の後ろの山から火の手が上がり、またまた逃げるに急となったからである。
しかしその一団が追いついてみると、味方の大将の李典(りてん)や許褚(きょちょ)ら100人ばかりの将士が、山越えで逃げてきたものだった。
(07)夷陵の分かれ道
みな馬をそろえて道を急ぐ。日は高くなり夜来の大雨もやみ、皮肉にも東南風(たつみかぜ)すらだんだんと凪(な)いでいた。
曹操は、南夷陵の大道と北夷陵の山路との分かれ道に差しかかる。ここで許都(きょと)へはどちらが近いのか尋ねると、幕将のひとりが南夷陵だと答えた。途中で葫蘆谷(ころこく)を越えていくと、非常に距離が短くなるとも。
これを聞いた曹操は、すぐに南夷陵の道を取って急いだ。
★井波『三国志演義(3)』(第50回)では、曹操が「どちらの道が南郡や江陵(こうりょう)に近いのか?」と尋ねていた。
★ここで葫蘆谷が出てくるのはよくわからなかった。そう呼ばれていた場所がいくつかあるのかも?
このことについて『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「葫蘆口(ころこう)は後漢では荊州南郡に属す。現在の湖北省江陵県西北」という。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「ここで曹操が向かうのは北夷陵が正しいが、『三国志演義』は南夷陵とする版もある」という。
(08)葫蘆谷
午(ひる)すぎに葫蘆谷へかかるが、馬も兵も飢え疲れ動けなくなってきた。曹操は休息を命じ、先に山村から略奪してきた食糧を1か所に集める。
柴(シバ)を積んで焚き火とすると、士卒たちは兜の鉢や銅鑼(どら)を鍋として、穀類を炊(かし)いだり鶏を焼いたりし始めた。
曹操も暖を取ったあと林の下に座っていたが、何を感じたかひとり笑いだす。諸将がギョッとして尋ねると、周瑜と諸葛亮ともに大将の才はあるが、まだ知謀が足りないことを笑っているのだという。
もし自分が敵ならば、ここに一手の勢を伏せ、逸ヲ以テ労ヲ待ツの計(鋭気を養ったうえで疲れた敵に当たるという計略)を施すだろうというのだった。
その言葉が終わらないうちに、金鼓や喚声が四山(周りの山々)にこだまし、四方八面に敵の姿が見えてくる。
こうして張飛(ちょうひ)が流星のごとく飛んでくると、曹操軍の士卒はみな狼狽(ろうばい)。鎧や下着を火で乾かしていたところなので、赤裸のまま散乱する者もいた。
許褚はあわてて鞍(くら)もない馬に飛び乗り、駆け寄ってきた張飛と戦い、しばらく食い止める。この間に張遼や徐晃らは鎧を着け、曹操を先へ逃がしてから馬を並べ、張飛に掛かっていった。
とはいえ、張飛の振り回す蛇矛(じゃぼう)には当たるべくもなく、その猛烈な突進をいくらか防ぎ支えるのがやっとだった。
★『三国志演義 改訂新版』(立間祥介〈たつま・しょうすけ〉訳 徳間文庫)の訳者注によると、「(蛇矛は)穂先が蛇のように曲がっている矛」だという。
曹操は耳をふさぎ、目をつぶって、数里の間は生ける心地もなく、ただ逃げ走る。やがて散りぢりに味方の将士も追いついてきたが、傷を負っていない者はないありさまだった。
(09)再度の分かれ道
またふた筋の分かれ道に出ると、曹操はどちらへ向かうべきかと尋ねる。
地理に詳しい者が、いずれも南郡へ通じているが、道幅の広い大道のほうは50里以上も遠道になると答えた。
これを聞いた曹操は山上へ部下を走らせる。
その部下が戻り、山路のほうは峠や谷間の諸所からほのかに人煙が立ち上っていると報告。敵の伏兵がいるに違いないとも。
ところが曹操は、あえて山路を越えていくと言い、「虚ナル則(とき)ハ実トシ、実ナル則ハ虚トス」だとして、いぶかる諸将らを諭す。
(10)華容道
みな曹操の深慮に感服。こうしている間にも後から後から残兵が追いつき、今は敗軍の主従一団となった。荊州にたどり着けば何とかなろうと、華容山麓から峰越えの道へ入る。
けれど、気はいくら焦っても馬は疲れ抜いており、負傷者も捨ててはいけない。1里登っては休み、2里登っては憩い、10里の山道をあえぐうち、もう先陣の歩みは遅々として止まってしまう。折から山中の雲気は白い雪さえ交えてきた。
管理人「かぶらがわ」より
苦難の逃走劇を続ける曹操。彼が笑っては趙雲や張飛が飛び出してくるというのは、いかにも講談っぽい。
とはいえ、曹操ほどの人が退路のことを考えずにこのような危機に陥るというのは、実際には考えにくいと思います。

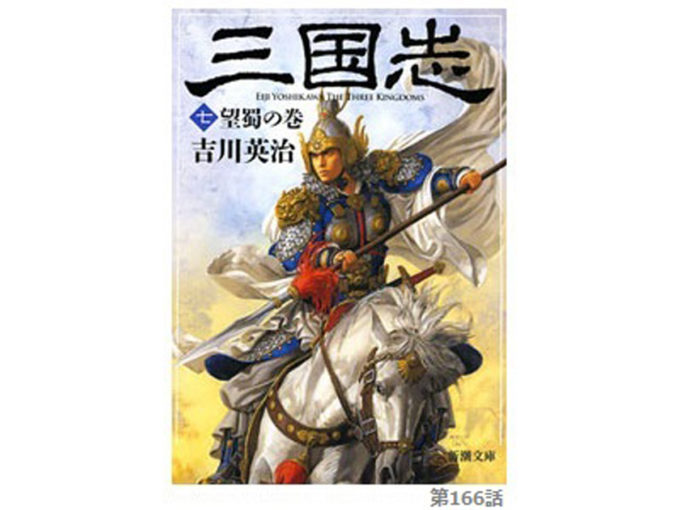













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます