雒城(らくじょう)の守りは堅く、劉備(りゅうび)らが攻めても陥ちる気配はない。やがて城内の劉璋軍(りゅうしょうぐん)が反撃に転ずると、不意を突かれた劉備軍は敗走。だが荊州(けいしゅう)から張飛(ちょうひ)が合流し、劉備は命拾いする。
その後、出撃した呉蘭(ごらん)と雷同(らいどう)が捕らえられ、劉備に降ったことが伝わると、雒城の士気は著しく低下。そこで張任(ちょうじん)は一計を案じ、呉懿(ごい)や劉璝(りゅうかい)の意向を聞く。
第201話の展開とポイント
(01)涪城(ふじょう)
諸葛亮(しょかつりょう)が荊州を発つときに出した(建安〈けんあん〉18〈213〉年の)7月20日付の返簡は、やがて劉備の手に届いた。水陸ふた手に分かれて蜀へ急ぐとのことに、涪城に籠もる劉備は到着を待ち遠しく思う。
ある日、黄忠(こうちゅう)が、寄せ手の蜀兵は長陣に倦(う)み飽き、惰気満々のていたらくだと伝える。そして、むなしく援軍を待つのみでなく、敵の虚と乱れを突いて一勝を制しておくことは、大いに成都(せいと)への入城を早めることにもなると促す。
思慮深い劉備も意を動かされ、涪城の軍勢は100日の籠居を破って出た。もちろん夜陰に奇襲したのである。案の定、野陣の寄せ手は散々に混乱して逃げ崩れた。
おもしろいほどの大快勝で、途中、莫大(ばくだい)な兵糧や兵器を鹵獲(ろかく)しつつ、ついに雒城の下まで追い詰めた。
(02)雒城
壊走した蜀兵は城中に隠れ、ヒタと四門を閉じてしまう。城の南は二条の山道。北は涪水(ふすい)の大江に接している。
劉備は自ら西門を攻め、黄忠と魏延(ぎえん)は東門を攻めた。けれど陥ちない。びくともしない。4日間も東西両門へ力攻したが、さしたる損害も与え得なかった。
蜀の張任は「もうよかろう」と、呉蘭と雷同(雷銅)の二将軍に言った。ふたりもよかろうと言う。
すなわち、ここまでは本心の戦をなしていたのではない。要するに誘引の計をもって引き出し、さらに劉備軍の疲労困憊(こんぱい)を待っていたのである。
蜀兵は南山の間道から続々と山地へ入り、遠く野に下り迂回(うかい)していた。また北門から江に舟を出し、夜中に対岸へ上がり、劉備の退路を断つべく枚(ばい。夜に敵を攻める際、声を出さないよう兵士の口にくわえさせた細長い木)を含んで待機する。
「城内の守りは百姓だけでよい。一部の将士のほかはみな城を出て、この際、劉備軍を徹底的に殲滅(せんめつ)せよ」
張任は勇断を下し、やがて一発の烽火(のろし)を合図に城門を開いた。
時刻は夕暮れ。ここ数日の疲れに劉備軍は鳴りを潜め、今しも夕方の炊煙を上げていたところである。当然、間に合わない。まったくひと支えもせず八方へ逃げなだれた。
だがその先に、山と江から迂回した蜀兵が手に唾し、陣を展開済みだった。呉蘭と雷同やその旗本は、ほとんど血に飽くばかりな勇を振るう。
(03)敗走中の劉備
劉備は悲痛な顔を馬のたてがみに沈めながら、魂も身に添わず、無我夢中で逃げていた。見回せば一騎とて自分のそばにいない。幸いにも夜だった。彼は疲れた馬に鞭(むち)打ち、辛くも山路へ追い上げた。
だが、後ろからいつまでも蜀兵の声が追ってくる。「天も我を見放したか……」。劉備は泣いた。
しかし、たちまち山上から駆け下ってくる一軍があるのを知ると、きっと涙を払い、静かに最期の心支度を整えた。
ところが、はや殺到した軍馬の中から聞き覚えのある声がする。見れば張飛だった。張飛は馬を飛び下りると劉備の手を取り、この奇遇に涙した。
蜀兵は山のふもとまで迫っている。事態は急なり、子細の物語は後にせんと、張飛は全軍を配備し、蜀兵に反撃して散々に追い討ちした。
張任は不思議な新手が忽然(こつぜん)と現れ、勢いをもって城下まで追ったので、濠橋(ほりばし)を引かせて城門を閉じると全軍を収容し、見事に鳴りを静めてしまった。
(04)涪城
劉備は無事に涪城へ戻り、張飛から厳顔(げんがん)の功労を聞くと、金鎖の鎧を脱いで言った。
「老将軍。これは当座の寸賞です。あなたのお力がなければ到底、この義弟もかく早く、途中30余か城の要害を踏破してくることはできなかったでしょう」
事実、厳顔が説き、途中の30余か城を無血招降してきたために、張飛の兵力は新しい味方を加えて数倍になっていた。
涪城はにわかに優勢となる。それと計らずに数日後、雒城を出て強襲してきた呉蘭と雷同は、その日の一戦に張飛・黄忠・魏延らの策した巧妙な捕捉作戦に陥る。
こうして捕虜となったふたりが、ついに劉備の前で降伏を誓うというような情勢に逆転した。
(05)雒城
呉懿や劉璝は歯ぎしりし、このうえは伸るか反るかの一戦を試み、一方で成都に急を告げ、さらに大軍の増派を仰ごうといきり抜く。
張任は沈痛に言い、筆を執って作戦図を書きながら、何事かささやく。
「それもよいが、まずこうしてみては?」
(06)雒城の城外
翌日、張任は一軍の先に馬を飛ばして城門から繰り出す。張飛が見かけて十数合戦うも、張任は叫びながら逃げ走る。
城北は山すそから谷へ、また涪水の岸へも続き、ひどく地形は複雑だった。張飛はいつか張任を見失い、味方の小勢とともにおちこち駆け歩いていた。
そのうちに四山、旗と化し、四谷、鼓を鳴らし、蜀兵の重囲は彼の部下を皆殺しにする。ひとり辛くも張飛は血の中を走り、涪水のほうへ逃げ延びた。
罵りながら追った呉懿は、そのとき一方の堤を越えて躍り駆けた大将に、横合いから槍をつけられ、数合のうちに得物を奪われて生け捕られた。
張飛が呼ぶ声を聞いて戻ると、それは荊州をともに発ち、途中、諸葛亮とひとつになって別れた趙雲(ちょううん)だった。
敵の雑兵を蹴散らした後、趙雲が諸葛亮も到着していることを語ると、張飛は急に連れ立って涪城へ帰る。
(07)涪城
劉備が優しく降伏を勧めると、呉懿は彼のただならぬ人品を仰ぎ、心から降参した。劉備は諸葛亮とともに上賓の礼を与え、雒城の兵力や守将について尋ねる。
呉懿は言う。
「劉璝はともかく、張任は知謀機略、衆を超えています。まず蜀中の名将でしょう。容易に雒城は抜けますまい」
すると諸葛亮が座談的に、まるで卓上の椀(わん)でも取るように言った。
「ではまず、その張任を生け捕ってから、雒城を攻めるのが順序ですな」
呉懿は、怪しむような目でその面を見守る。
翌日、諸葛亮は呉懿を案内に、付近の地勢を視察に歩く。帰ってくると、黄忠と魏延を呼び、さながら盤の駒でも動かすように言った。
「金雁橋(きんがんきょう)のほとりの5、6里の間は、蘆(アシ)や葭(ヨシ)が茂っているから兵を伏せるによい。戦の日、魏延は鉄槍(てっそう)部隊1千人をあの左に隠し、敵がかかったら一斉に突き落とせ」
「また黄忠は右に潜み、総勢すべてに薙刀(なぎなた)を持たせ、ただ馬の脚と人の足を薙ぎつけるがいい。張任は不利と見るとき、必ず東方の山地へ向かって逃げるであろう」
さらに諸葛亮は、張飛と趙雲へも別に策を授けた。
(08)雒城の城外
雒城の前に金鼓が鳴った。城兵への挑戦である。望楼から兵機を眺めていた張任は、寄せ手の後方に連絡がないのを見て「孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)兵法に暗し」と思った。できるだけ手近に引き寄せておき、大殲滅を計ったのである。
寄せ手は濠に近づき、城壁へたかりだした。張任は八門を開かせ、城外へ打って出るよう命ずる。同時に、南北の山すそに埋伏しておいた城兵も鵬翼(ほうよく)を作り、寄せ手を大きく抱えた。壊乱、惨滅。劉備軍は討たれに討たれて後へ退く。
ここで張任も陣前に現れる。自ら指揮して自ら戦い、金雁橋を越えること2里まで奮迅してきた。張任が振り向くと、後ろに敵の一団が見える。しかも金雁橋はめちゃめちゃに破壊されていた。
あわてて張任が回ろうとすると、左右の蘆荻(ろてき)の茂みから槍の穂が雨と突いてくる。なだれ打って避け合おうとすれば、また一方から薙刀の群れが馬の脛(すね)を払い、人の足を斬る。
張任は南へ退けと言うが、すでにそこも荊州兵(劉備軍)が占めていた。是非なく涪水の支流に沿い、東方の山地へ逃げた。
浅瀬を越え、ようやく対岸の広野へ渡る。ところが、そこにも怪しげな一陣の兵が満々と旗を立て、一輛(いちりょう)の四輪車を護っていた。
張任は車上に座っているのが諸葛亮だと聞くと、肩を揺すって笑った。なぜなら四輪車を囲む兵は弱そうな老兵で、そのほかの兵もみなぶよぶよに肥え、見るからに脆弱(ぜいじゃく)な士卒ばかりだったからである。
張任の一令に、なお背後に残っていた数千の兵は、ドッとおめきかかっていく。すると、四輪車は右往左往の態で逃げ出す。
手づかみにして生け捕ることも易しと、張任は馬を打って跳び込み、雑兵には目もくれず、あわや車蓋の上から巨腕を伸ばしかけた。
「捕ったっ!」。それは足元の声だった。いきなり下から馬の脚を担ぎ、ひっくり返した猛卒がいる。張任は見事に落馬した。たちまち別のひとりが跳びかかる。これも雑兵にしては驚くべき怪力の持ち主だった。
それもそのはず、このふたりは雑兵の中に隠れていた魏延と張飛だったのである。破壊したと見せた金雁橋も、実は完全に破壊してはいなかった。
張任が諦めて上流の支川へ避け、浅瀬を渡って城のほうへ迂回したと見るや、蘆茅(あしかや)の中にいた全軍は四輪車を包んで対岸へ越え、ここに先回りして待っていたものだ。
山地や谷間に逃げ込んだ蜀兵も、あらまし討たれるか降伏した。その中には、つい前日に成都から援軍に来たばかりの卓膺(たくよう)という大将なども交じっていた。
張飛・黄忠・魏延などの諸隊もおのおの功を上げ、圧縮してくる。総勢一軍となった後の陣容や行軍は、いかにも鮮やかだった。
「あぁ、蜀の改まる日は来た……」
捕虜として檻送(かんそう)されていく途中、張任は天を仰いで長嘆した。
(09)涪城
劉備は降伏を勧めるが、張任は昂然(こうぜん)と拒む。その人物を惜しんでいろいろ説いたが、どうしても聞かない。
諸葛亮が見るに見かねて言った。
「あまりにくどく強いるは、真の忠臣を遇する礼ではありません。大慈悲の心をもって疾(と)く首を刎(は)ね、忠節を全うさせておやりなさい」
こうして張任の首を斬り、その屍(しかばね)を納め、金雁橋の傍らに忠魂碑を建てた。
(10)雒城
雒城は本格的な包囲の中に置かれる。降参の大将、呉懿や厳顔らが陣前に出て城中の者に説いた。
すると、櫓(やぐら)の上に残る一将の劉璝が現れ、「蜀の恩顧を忘れた人間どもが何を言うか!」と罵った。
とたんに彼は、櫓の窓から蹴落とされていた。何者かが後ろから弱腰を突いたものとみえる。同時に城門は内より開いた。たちまち城頭に劉備の旗が翻る。城中の者はその7割まで降伏した。
劉璋の嫡子の劉循(りゅうじゅん)は急変に驚き、北門の一方からわずかな兵とともに、成都を指して逃げ出す。
★『三国志演義(4)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第64回)では、劉循は西門から脱出し、成都へ向かって逃亡したとある。
占領後、劉備は劉璝を櫓から蹴落とした張翼(ちょうよく)に謁を与え、これを重く賞す。雒城の市街は平静に返り、避難していた民も続々と帰ってきて、お触れの高札を囲んで新しい政道を謳歌(おうか)した。
ここで劉備は諸葛亮の進言を容れ、部隊を分けて各地へ宣撫(せんぶ)に赴かせる。厳顔と卓膺には張飛を付け、巴西(はせい)から徳陽(とくよう)地方へ。張翼と呉懿には趙雲を添え、定江(ていこう)から犍為(けんい)地方へ。
それらの諸隊が地方宣撫の効を上げている間に、諸葛亮は降参の一将を招き、成都への攻進を工夫していた。雒城から成都までの間にある要害は綿竹関(めんちくかん)が第一で、そのほかは往来を改める関所程度だという。
そこへ法正(ほうせい)がやってきて意見を述べる。
「いずれ後には、成都の人民はご政下に付くものです。その民を驚かし、苛烈な戦禍におびえさせることは好ましくありません。まず四方に仁政を示し、徐々に恩徳をもって民心を得ることを先とすべきでしょう」
「一方、それがしから書簡をもって、よく成都の劉璋を説きます。彼も民の離れるのを悟れば、自然に来て降るに違いありません」
諸葛亮は法正の考えを非常に称揚し、その方針に依ることに決めた。
(11)成都
成都では今にも劉備が攻めてくるかと、人心は動揺してやまない。府城の内でも恟々(きょうきょう)と対策に沸騰していた。劉璋を中心に、いかに防ぐかの問題が今日も議論されている。
ここで従事(じゅうじ)の鄭度(ていど)は、巴西地方からすべての農民を追い、ことごとく涪水以西の地方へ移してしまうよう勧めた。それらの部落には鶏一羽も残さず、米穀は焼き捨て、田畑は刈り、水には毒を投ずるのだと。
そして成都と綿竹関を固め、奇策や奇襲をもって敵を苦しめ抜けば、おそらくこの冬の到来とともに、劉備以下の大軍は絶滅を遂げるに違いないと。
みな黙っていたが、劉璋はいつにも似げない名言を吐き、この策を否決した。
「昔から、国王は国を防いで安んずるということは聞いておるが、まだ民を流離させて敵を防ぐというのは聞いたことがない。それはすでに敗戦の策だ。おもしろくない」
すると、そこへ法正から正式の書簡が届いた。書中には大勢を説き、今のうちに劉備と講和する利を弁じ、家名の存続を保つことが賢明だと勧めてある。
しかし劉璋は怒って使いを斬り、ただちに綿竹関の防御に増軍を決行した。
★井波『三国志演義(4)』(第64回)では、(劉璋の)妻の弟の費観(ひかん)と李厳(りげん)が3万の軍勢を召集し、綿竹の守備に向かったとある。
なお『三国志』(蜀書・楊戯伝〈ようぎでん〉)の裴松之注(はいしょうしちゅう)に引く『季漢輔臣賛(きかんほしんさん)』によると、費観は劉璋の妻の弟ではなく娘婿。
さらに董和(とうか)の勧めを容れ、漢中(かんちゅう)の張魯(ちょうろ)に急使を遣わす。背に腹は代えられぬと、ついに危険なる思想的侵略主義の国へ泣訴して、その援助を乞うという苦し紛れの下策に出たのであった。
管理人「かぶらがわ」より
雒城の攻防戦が中心だった第201話。史実でも劉備は、雒城の攻略に1年以上を要しています。このときは劉循がかなりの粘りを見せたのですが、吉川『三国志』では張任らのほうが目立っていましたね。
まぁ、ここに来て鄭度の策はないかな? 水には毒を流すって、何だか黄巾賊みたい。

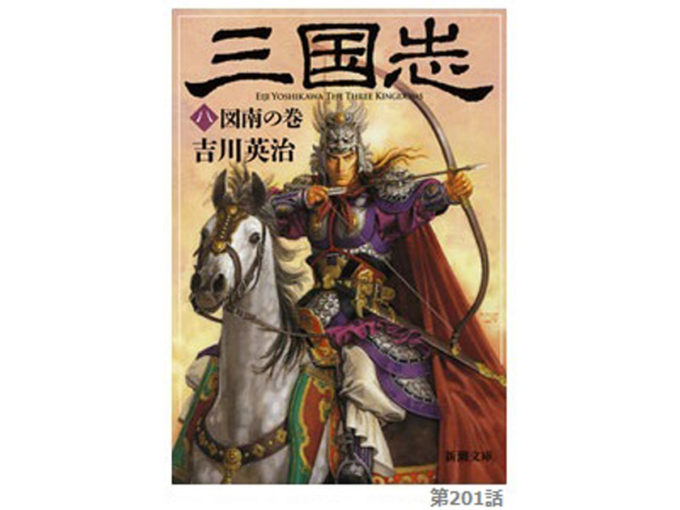













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます