諸葛亮(しょかつりょう)は蜀軍をひきい、みたび祁山(きざん)に進出する。今回は陰平(いんぺい)と武都(ぶと)の両郡の攻略を目指し、王平(おうへい)と姜維(きょうい)に1万騎ずつを付けて差し向けた。
これに対し魏の曹叡(そうえい)は、長安(ちょうあん)で病臥(びょうが)していた曹真(そうしん)に替え、司馬懿(しばい)を大都督(だいととく)に起用する。
第291話の展開とポイント
(01)武昌(ぶしょう)
魏蜀の消耗(しょうこう。「しょうもう」は慣用読み)を喜び、その大戦のいよいよ長く、いよいよ苛烈になることを願っていたのは、言うまでもなく呉であった。
このときにあたって、呉王の孫権(そんけん)は、ついに宿年の野望を表面にした。彼もまた魏や蜀に倣い、皇帝を僭称(せんしょう)したのである。
(呉の黄武〈こうぶ〉8〈229〉年の)4月、武昌の南郊に盛大な壇を築いて大礼の式典を執り行い、天下に大赦を令した。
また即日、黄武8年を黄龍(こうりゅう)元年と改め、亡き父の孫堅(そんけん)に武烈皇帝と諡(おくりな)した。
併せて嫡子の孫登(そんとう)が皇太子に昇る。その輔育(ほいく)の任には、諸葛瑾(しょかつきん)の子の諸葛恪(しょかつかく)を太子左輔(たいしさほ)とし、張昭(ちょうしょう)の子の張休(ちょうきゅう)を太子右弼(たいしゆうひつ)とした。
(02)諸葛恪について
諸葛恪は、蜀の諸葛亮の甥にあたる。資質聡明、声は甚だ清高だったという。つとに神異の才をたたえられ、6歳の時にはこのようなこともあった。
★史実の諸葛恪は建安(けんあん)8(203)年生まれ。6歳の時なら建安13(208)年のことになるが、その年に孫権は呉王ではなかった。
なお『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第98回)では、以下の件について、(諸葛恪が)6歳の時、たまたま呉で宴会が開かれ、諸葛恪が父のお供で宴席に連なった際の話としており、このとき孫権が呉王だったとは書いていない。
ある折、呉王の孫権が戯れに、一頭の驢馬(ロバ)を宮苑(きゅうえん)に引き出させ、面に白粉(おしろい)を塗らせたうえ、「諸葛子瑜(しょかつしゆ。子瑜は諸葛瑾のあざな)」という四文字を書く。
諸葛瑾が人一倍の長面なので、それを揶揄(やゆ)して笑ったのである。だが、君公の戯れなので、当人も頭を搔(か)いて苦笑していた。
すると父のそばにいた6歳の諸葛恪が、いきなり筆を持って庭へ飛び下り、驢馬の前に背伸びして、面の四文字の下に二字を書き加える。
人々が見ると、「諸葛子瑜之驢」と読まれた。見事、からかわれている父の恥をそそいだのである。
★井波『三国志演義(6)』(第98回)では、別の日の宴席で張昭が諸葛恪に言い負かされ、無理に酒を飲むことになった話も採り上げていた。だが、吉川『三国志』では使われていない。
(03)武昌
この輔弼(ほひつ)に加え、丞相(じょうしょう)の顧雍(こよう)と上将軍(じょうしょうぐん)の陸遜(りくそん)を武昌に残し、皇太子の守りとする。そして孫権自身は建業(けんぎょう)へ帰った。
(04)建業
かくて魏蜀が戦えば戦うほど、呉の強大と国力は日を追うて優位になるばかり。宿老の張昭は固く兵を戒め、産業を興し、学校を建て、農を励まし、馬を養って、ひたすら他日に備える。
一面で蜀へ特使を遣わし、なおの善戦を慫慂(しょうよう)していた。特使の使命には、孫権の皇帝即位を伝えて、これを国際的に承認させる副意義もあったことはもちろんである。
(05)漢中(かんちゅう)
この特使は成都(せいと)の劉禅(りゅうぜん)だけでなく、漢中の諸葛亮のもとへも同様に臨んだ。
★井波『三国志演義(6)』(第98回)では、呉の使者が成都に着いた後、劉禅が諸葛亮の意見を聴くため、漢中へ(別の)使者を遣わしたとある。
諸葛亮は、心の内に安からぬものを抱いたに違いない。なぜなら彼の理想は、漢朝の統一にあるからだ。天にふたつの日なしという信念が、彼の天下観だからである。
しかし、今はそれを唱えていられないときだった。ひとたび呉が離脱せんか、魏と結ぶことは必然であり、かくては永遠に蜀の興隆はない。蜀の滅ぶときは、彼の理想もついに行い得ないことになる。
「それは実に慶祝に堪えない。いよいよ蜀呉両帝国の共栄を確約するものです」
ただちに諸葛亮も、漢中の礼物を山と積ませ、呉へ賀使を遣わして喜びの表を呈した。
★井波『三国志演義(6)』(第98回)では、諸葛亮の意見に従った劉禅が、太尉(たいい)の陳震(ちんしん)に名馬・玉帯・黄金・真珠・宝物を持たせ、祝賀すべく呉に向かわせたとある。
その際、呉へこう申し入れ、朝野に向かって、時は今なることを大いに鼓欣(こきん)宣伝させた。
「いま貴国の強兵をもってお攻めになれば、魏は必ず崩壊を兆すことでしょう。わが蜀軍が不断に彼を打ち叩いて、疲弊に導きつつあるのは申すまでもございません」
(06)建業
申し入れを受け、陸遜はにわかに建業へ召還される。孫権が意見を求めると、陸遜は言った。
「修好の約がある以上、容れなければなりますまい。けれど、多くを蜀に労させて、呉はもっぱら虚をうかがいます。いよいよというとき、洛陽(らくよう)へ入城する者は、諸葛亮よりひと足さきに、わが呉軍であれば最上でしょう」
これを聞いた孫権は快げに笑う。
(07)陳倉(ちんそう)
諸葛亮は三度目の祁山出兵を決行した。その動機となったのは、陳倉の守将の郝昭(かくしょう)が、このところ病にかかって重体だという確報を得たこと。
郝昭は洛陽へ急報し、自分に代わる大将の援軍を仰いだ。長安にあった郭淮(かくわい)は、洛陽へ奏していたのでは遅いとし、すぐに張郃(ちょうこう)に3千騎を付けて陳倉へ向かわせる。だが、このときはもう遅かった。郝昭は死し、陳倉は陥ちていた。
★郝昭の死(病死)には、前の第290話(11)でも触れられていたものの、時間的な経過がわかりにくい。井波『三国志演義(6)』(第98回)では、王双(おうそう)の戦死を知らせたのが(陳倉城にいた)郝昭だとしており、吉川『三国志』のようなわかりにくさは感じられない。
どうしてこう迅速だったかと言えば、しきりに諸葛亮の来襲を伝えたものは、実は魏延(ぎえん)や姜維などの一軍だった。
諸葛亮の本軍は疾(と)く密かに漢中を発し、間道を通って陳倉城の搦(から)め手(裏門)に迫った。夜中に乱波(らっぱ。間者)を放ち、城内に火をかけ、混乱に乗じてなだれ入ったものである。
そのため味方の魏延や姜維が城中へ来たときですら、すでに落城した後だった。いかに魏の張郃が急いで救援に来たところで、とうてい間に合うわけはなかったのである。
落去の跡を視察する諸葛亮。火中に死んだ郝昭の屍(しかばね)を捜させると、こう言い、兵を用いて手厚く弔えと命じた。
「この人は敵ながら、その忠魂は見上げたものだ。死すとも朽ちさすべき人ではない」
★ここも「火中に死んだ郝昭」が気になった。前の第290話(11)では病死だったはず。病死した後、安置されていた遺体が、城内の火に焼かれてしまったということだろうか?
なお井波『三国志演義(6)』(第98回)では、郝昭が病死したという記述はなく、蜀軍の来襲を聞いた(重病の)郝昭が、城壁の上に登って守備せよと命じている。だが、このとき各門から一斉に火の手が上がり、城内は大混乱に陥る。これを知った郝昭は驚いて亡くなり、蜀軍がドッと城内に突入した、という展開になっていた。
諸葛亮は、魏延と姜維に、まだ鎧を解くなと言い、ただちにふたりを散関(さんかん)へ向かわせる。もし時を移しておれば、魏の兵馬が充満し、第二の陳倉になるだろうと。
(08)散関
散関は手薄だったので、蜀軍は難なく乗っ取ることを得た。ところが蜀旗を掲げて半日もしないうちに、士気すこぶる盛んな魏軍が寄せ返してくる。張郃の軍勢だった。
しかし、すでに散関すら蜀軍に奪われているのを見ると、張郃はにわかに帰ろうとする。蜀勢は関を出て追撃。張郃軍は若干の損害を受け、むなしく長安へ壊走した。
(09)祁山
諸葛亮は散関から戦況報告を受けると、いよいよ総兵力を挙げ、陳倉から斜谷(やこく)へ進む。さらに建威(けんい)を攻め取り、祁山へ出た。
ここは二度の旧戦場。しかも両度とも蜀軍は戦いに利あらず、退却のやむなきをみている。諸葛亮にとっては実に痛恨の深い地であるに違いない。
諸葛亮は、帷幕(いばく。作戦計画を立てる場所、軍営の中枢部)の将星を集めて告げた。
「魏は二度の勝利に味を占めて、このたびも旧時の例に倣い、われ必ず雍(よう)と郿(び)の二郡をうかがうであろうとなし、そこを防ぎ固めるに違いない。ゆえに我は、矛を転じて陰平と武都の二郡を急襲せん」
★ここで雍(雍城)・郿(郿城)を二郡と表現していたが、これが適切なのかわからなかった。
そして王平と姜維に1万騎ずつを付け、陰平と武都の攻略に差し向けた。
★井波『三国志演義』(第98回)では、王平が陰平へ、姜維が武都へ、それぞれ向かっている。
(10)長安
張郃の報告と諸葛亮の祁山出陣を聞き、郭淮は驚きに打たれる。郭淮は張郃に長安を守るよう言うと、自らは郿城を固め、雍城へは孫礼(そんれい)を派遣した。
張郃は早馬に次ぐ早馬をもって、祁山一帯の戦況を洛陽へ伝える。
「大兵と軍馬を続々下したまえ。さもなくば、事態は予測を許さず」
(11)洛陽
魏の朝廷は狼狽(ろうばい)。このときすでに、呉の孫権の登極が伝わっていた。
そのうえ蜀呉の特使交換や、武昌の陸遜が大兵を整え、今にも魏に攻め入ろうとする空気が濃厚にみなぎっているなどという、魏にとって不気味きわまる情報がやたらに入っていたからである。
「司馬懿(しばい)に問うしかない」
重臣や宿将は多しといえども、曹叡もついにはひとりの司馬懿に頼みを帰するしかなかった。
召された司馬懿は闕下(けっか。ここでは御前の意)に伏したが、このごろの風雲にはまるで聾(ろう)のような顔をしている。けれど曹叡が下問すると、その定見を、糸を吐くように述べた。
「孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)が呉をけしかけたのは当たり前の考えです。呉がこれに応ずるのも修交上は当然と言えましょう。ですが、呉は陸遜という偉物(えらもの)が軍を握っております」
「また、呉が率先挺身(ていしん)しなければ、条約にたがうという理由はございませんから、攻めんと言い、攻めるぞと見せ、実は軍備ばかりしていて容易に動かない。蜀の戦いと魏の防ぎをにらみ合わせて、ひたすら機を測っているものに違いありません」
「ゆえに、呉の態勢は虚です。蜀の襲攻は実です。まずもって、実に全力を注ぎ、のち虚を始末すればよろしいでしょう」
言われてみると、このようにわかりきっていることをなぜ迷っていたのかと、曹叡は膝を打って嘆ずる。
嘆賞のあまり、曹叡はこの場で司馬懿を大都督に任じ、併せて総兵之印をも取り上げて、汝(なんじ)に授けんと詔(みことのり)した。
しかし、司馬懿は甚だ迷惑そうな顔をする。なせなら総兵之印は、全軍総司令たる曹真が持っているもの。勅命否みがたしと受けはしたが、司馬懿は言った。
「勅をもって取り上げられるのはお気の毒の限りですし、それでは当人の面子(メンツ)もありません。臣が参って自ら頂戴いたしましょう」
(12)長安
司馬懿は長安へ行き、府中で病臥している曹真を見舞う。
★どちらでも大差はないと思うが、井波『三国志演義(6)』(第98回)では、曹真は洛陽の自邸で療養していた。
そして、四方山(よもやま)の話の後で尋ねた。
「時に、呉の陸遜と蜀の諸葛亮が緊密に機を結び合い、同時にわが国の境へ攻め入ってきたのをご存じですか?」
曹真は愕然(がくぜん)とする。何しろこの病体なので、誰も本当のことは知らせてくれないとも言う。
司馬懿が慰めると、さらに曹真は言った。
「いやいや。この病身では、ついに国家の大危局を救う力など到底わしにはない。どうかご辺(きみ)がこれを譲り受けて、この大艱難(だいかんなん)にあたってくれ」
司馬懿は総兵之印を押しつけられる。これを再三辞退すると、なお曹真が言う。
「朝廷へは、後でわしから奏聞しておく。決して卿(けい)に科(とが)はかけない」
どうしても曹真が聞かないので、司馬懿も断りあぐねた態をし、それでは一応お預かりしておきますと答えて受け取った。
管理人「かぶらがわ」より
諸葛恪の機知を描いた子瑜之驢の逸話は『三国志』(呉書・諸葛恪伝)に見えました。ただ、そのとき彼が6歳だったとか、孫権が呉王だったということには触れられていません。
ですが本伝に、諸葛瑾は面長で、驢馬に似ていたとは書かれていました。ちょっと書かれ方がひどい気もしますけど、弟の諸葛亮もそのような風貌だったのでしょうか?

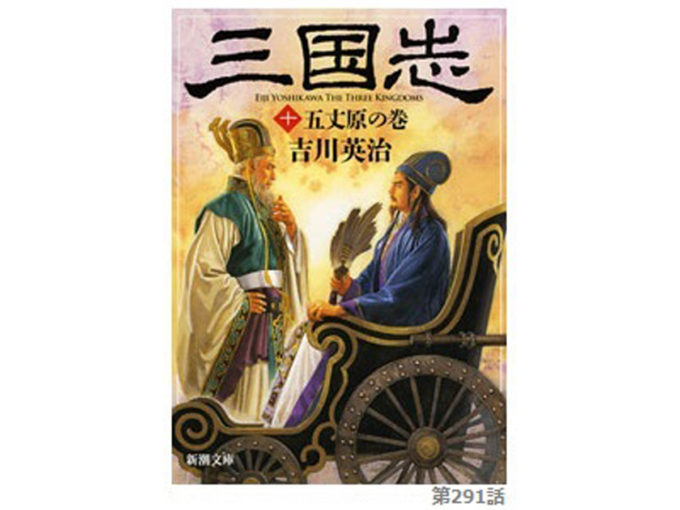














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます