建安(けんあん)9(204)年、曹操(そうそう)は袁氏(えんし)の本拠だった鄴城(ぎょうじょう)を陥落させ、堂々たる入城を果たす。
そして、袁氏に仕えていた賢才を余すところなく用い、冀州(きしゅう)の復興に注力させる。
第120話の展開とポイント
(01)冀州(鄴城)
曹操は審配(しんぱい)の忠烈な死に心を打たれ、城北に墳(つか)を建て手厚く葬る。
建安9(204)年の秋7月、さしもの強大な河北もここに滅ぶ。冀州の本城たる鄴城には曹操軍の軍馬が充満した。
曹操の嫡子の曹丕(そうひ)はこのとき18歳で、今回の戦にも参加していたが、城が陥ちるとすぐに随身の兵を連れて城内へ入った。
★史実の曹丕は中平(ちゅうへい)4(187)年生まれ。このとき(建安9〈204〉年)18歳というのは史実とも合っている。
曹丕は、後堂の片隅で震えていた袁紹(えんしょう)の後室(身分の高い人の未亡人)の劉夫人(りゅうふじん)と、袁熙(えんき)の妻(甄氏〈しんし〉)を見つけて保護する。聞くと袁熙は、もう遠くへ逃げたということだった。
そのころ曹操も威武堂々と入城にかかっていた。ここでいきなり許攸(きょゆう)が前列に躍り出し、黄河での献策を誇ったが、曹操は非常に笑い、彼の得意を煽(あお)るだけだった。
★許攸の黄河での献策については先の第115話(01)を参照。
やがて府門を通るとき、先に通った者がいることを知った曹操が番兵を詰問。それが曹丕だと聞くと、荀攸(じゅんゆう)と郭嘉(かくか)に捕らえてくるよう命ずる。だが、郭嘉に諫められると不問に付した。
曹操は劉夫人と甄氏を引見するが、甄氏の天麗の美質に驚く。そこで曹丕の意を察し、このたびの行賞として甄氏を与えることにした。
こうして冀州攻略がひとまず片づくと、袁紹と袁家累代の墳墓を祭る。人民にはこの年の年貢を許し、旧藩の文官や賢才は余さず自己の陣営に用い、土木農田の復興に力を注がせた。
府堂の出入りは日ごとに頻繁を加えたが、ある日、許褚(きょちょ)が馬に乗り東門から入ろうとすると、例の許攸が立っていた。
許攸が広言を吐くと、許褚は、先の曹操入城時の態度も思い起こして匹夫呼ばわりする。さらに彼が蹴殺すと言っても、許攸は高をくくっていた。
すると許褚は、本当に馬の蹄(ひづめ)を上げて許攸にのしかかる。それのみか、とっさに剣を抜いて首を斬り飛ばし、すぐに府堂へ行って訴えた。
聞くと曹操は、瞑目(めいもく)してしばらく黙っていた。そして、許攸は御しがたい小人には違いないとは言いながらも、自分とは幼少からの朋友(ほうゆう)で、確かに功があったとし、許褚を叱って7日間の謹慎を命じた。
許褚と入れ替わりに、河東武城(ぶじょう)の隠士の崔琰(さいえん)が礼厚く案内されてくる。
★崔琰は正しくは清河郡(せいかぐん)東武城県(とうぶじょうけん)の出身。『三国志演義(2)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第33回)でもそのようになっている。
崔琰は求めに応じ、乱雑な民簿をよく統計整理して軍政経済の資に供えた。曹操は彼を別駕従事(べつがじゅうじ)に任ずる一方、袁紹の息子たちや冀州の残党が落ち延びた先の消息も怠らずに探らせていた。
その後、(袁紹の)長男の袁譚(えんたん)は甘陵(かんりょう)・安平(あんぺい)・渤海(ぼっかい。勃海)・河間(かかん)などの諸地方を荒らして兵を集めると、中山(ちゅうざん)にいた(袁紹の)三男の袁尚(えんしょう)を攻め、これを奪った。
袁尚は中山から幽州(ゆうしゅう)へ逃げ去る。幽州には(袁紹の)次男の袁熙がいたので、二弟合流して長兄を防ぐ一面、亡父の領地を奪い返さねばと弓矢を研ぎ、遠く冀州をうかがっていた。
それを知った曹操は試みに袁譚を招いてみる。再三の招きにもかかわらず、袁譚は気味悪がって出向かなかった。
曹操はこれを口実に断交の書を送ると、大軍を差し向ける。袁譚は恐れてたちまち中山を捨て、平原(へいげん)も捨てて荊州(けいしゅう)の劉表(りゅうひょう)に救援を乞うた。
ところが劉表は劉備(りゅうび)の助言を聞き、救援要請を態よく断る。これを受け、袁譚は是非なく南皮(なんぴ)へ落ちていった。
(02)南皮
建安10(205)年の正月、曹操の大軍が氷河雪原を越えて南皮に迫る。南皮城は八門を閉ざし、壁上に弩弓(どきゅう)を植え並べ、濠(ほり)には逆茂木を結い、城兵の守りはすこぶる堅かった。
それでも、寄せては返し、寄せては返し、昼夜新手を加えて猛攻を続ける曹操軍の根気強さに袁譚は夜も眠れず、心身ともに疲れてしまう。そのうえ部将の彭安(ほうあん)が討たれたので、辛評(しんぴょう)を遣わし降伏を申し出た。
★井波『三国志演義(2)』(第33回)では、彭安は曹操配下の徐晃(じょこう)に斬られたとある。
曹操は弟の辛毘(しんび。辛毗)が自分に仕えていることに触れ、兄である辛評にも仕官を促すが断られた。曹操は袁譚の降伏について、許すとも許さぬとも言わない。
袁譚はありのままを辛評から聞くと、すでに弟が曹操の身内なのに、その兄を講和の使いに遣ったのは誤りだったと、ひがみっぽく言う。
これを聞いた辛評は気を激し、恨めしげに叫ぶと地に倒れて昏絶(こんぜつ)。そのまま息絶えてしまった。
袁譚はひどく後悔し、郭図(かくと)に善後策を諮る。郭図は袁譚を励まし大決戦の用意にかかる。突如、袁譚は南皮城の全兵力を挙げ、四門を開いて攻勢に出、雪に埋もれた曹操の陣所を猛襲した。
一時は曹操軍もまったく壊乱に墜(お)ちたが、曹洪(そうこう)や楽進(がくしん)らがよく戦って食い止める。大勢を盛り返し、城兵をひた押しに濠際まで追い詰めていく。
曹洪はひたすら袁譚の姿を捜していたが、とうとう見つけると名乗りかけ、馬上のまま重ね討ちに斬り下げた。
袁譚が討たれたことが伝わると城兵は戦意を失い、城門の橋を争って逃げ込む。この中にいた郭図は、楽進に首筋を射抜かれて首を取られた。
南皮城が陥ちると、付近にある黒山(こくざん)の強盗の張燕(ちょうえん)や、冀州の旧臣の焦触(しょうしょく)や張南(ちょうなん)などが、5千、1万と手下を連れ、続々と降伏を誓いに出てきた。
★『三国志』(魏書・武帝紀)にも、建安10(205)年4月に張燕が曹操に降伏したことが見える。だが、そのとき彼は10余万の軍勢をひきいていたともあり、ここで言われているような小規模の勢力ではなかった。ちなみに井波『三国志演義(2)』(第33回)でも、張燕は10万の軍勢をひきいて投降したとある。
曹操は楽進と李典(りてん)のふた手に張燕も加え、新たに10万騎の大部隊を編制。幷州(へいしゅう)の高幹(こうかん。袁紹の甥)にとどめを刺すよう命ずる。そして自身は幽州の袁熙と袁尚を誅伐する準備を進めた。
この間に袁譚の首を北門に掛け、「これを見て嘆く者があれば、その三族を罰すであろう」と、郡県にあまねく布令する。
★袁譚の首を掛けたのが南皮城の北門なのか、鄴城(へ戻って)の北門なのかイマイチよくわからなかった。井波『三国志演義(2)』(第33回)の記述を見ると、鄴城へ戻ってということではなく、南皮城の北門に掛けたようだ。
★井波『三国志演義(2)』の訳者注によると、「(三族については)諸説あるが、漢代(かんだい)において三族皆殺しの対象となるのは、父母・妻子・兄弟姉妹である」という。
ところがある日、布冠(ぬのかんむり)をかぶり黒い喪服を着た一処士が、番兵に捕まって引っ立てられた。布令が出ているにもかかわらず、袁譚の首を拝して獄門の下で慟哭(どうこく)していたのだという。
人品が常ならぬのを見て曹操が自らただすと、処士は北海(ほっかい)営陵(えいりょう)の生まれで王修(おうしゅう。王脩)と名乗る。
もとは青州別駕(せいしゅうべつが)を務めていたが、袁紹に諫言を容れられず、朋人の讒(ざん)を受けて辞職し、野に流れ住むこと3年になるとも話した。
曹操は王修の乞いを容れ、袁譚を手厚く葬ることを許す。そのうえ彼を司金中郎将(しきんちゅうろうしょう)に任じて上賓の礼を与えた。
(03)幽州
幽州方面では早くも曹操軍の襲来が伝わり大混乱を起こす。しょせんかなわぬ敵と恐れ、袁尚はいち早く遼西(りょうせい)へ逃げ延びる。
別駕の韓珩(かんこう)一族は城を開いて曹操に降った。曹操は韓珩の降を容れ鎮北将軍(ちんぼくしょうぐん)に任じ、さらに幷州方面の戦況を案ずると、自ら大軍をひきいて加勢に赴く。
★井波『三国志演義(2)』(第33回)では、曹操から鎮北将軍に任ぜられたのは(幽州刺史〈ゆうしゅうしし〉の)烏桓触(うがんしょく)。
★井波『三国志演義(2)』の訳者注には以下のようにある。「(正史の)『三国志』に烏桓触という人名は見えない。ちなみに同書の『袁紹伝』には『熙・尚為其将焦触・張南所攻、奔遼西烏丸。触自号幽州刺史……』。すなわち『袁熙と袁尚は部将の焦触と張南に襲撃され、遼西の烏丸族のもとへ逃げた。焦触は勝手に幽州刺史と称した……』とある。『三国志演義』の作者はこれを読み間違って烏丸と触をくっつけてしまい、烏丸(桓)触なる人名だと誤って解釈したものとみえる。以下、ここで烏桓触の名が用いられている箇所はすべて『袁紹伝』では焦触を指し、焦触が曹操に降伏する際のエピソードとする」とも。
なお、吉川『三国志』では烏桓触を使わない代わりに、別駕の韓珩が鎮北将軍に任ぜられたということにしている。
(04)幷州 壺関(こかん)
袁紹の甥の高幹は壺関を死守し、なお陥ちずにあった。そこへ数十騎を連れた旧友の呂曠(りょこう)と呂翔(りょしょう)がやってきて開門を求める。
ふたりはいったん曹操に降ったものの、やはり降人扱いされ、ろくな待遇をしてくれないと不満を訴えた。高幹は疑いつつも、ふたりだけを城中に迎え入れる。
ここでふたりは、曹操はたったいま幽州から着いたばかりだと言い、今夜打って出ればきっと勝てると告げた。浅はかにも高幹はこの言葉に乗ってしまう。堅城壺関も、その夜ついに陥落する。
高幹は命からがら北狄(ほくてき。北方の異民族)の境を越え、胡(えびす)の左賢王(さけんおう)を頼ったが、途中で家来に刺し殺された。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(左賢王とは)匈奴において、単于(ぜんう。君主)の後継者が就く地位」だという。また「(匈奴は)北方の異民族。漢の高祖(劉邦〈りゅうほう〉)に対抗した冒頓単于(ぼくとつぜんう)以来、強大な勢力を有していた」という。
★なお『三国志』(魏書・武帝紀)によると、「高幹は荊州へ逃げようとしたところを、上洛都尉(じょうらくとい。上洛県の都尉)の王琰(おうえん)に捕らえられて斬られた」という。井波『三国志演義(2)』(第33回)でもほぼ同様に描かれており、吉川『三国志』ではこの部分の話をいくらか変えている。
管理人「かぶらがわ」より
父の曹操に先んじて入城し、甄氏を賜ることになった曹丕。袁譚が討ち死にしたことにより、袁熙と袁尚のふたりだけになってしまった袁氏兄弟。
そして冀州の旧臣たちをうまく用い、幽州や幷州へと勢力圏を広げていく曹操。このあたりでは彼の勢力拡大が加速している感じがしますね。

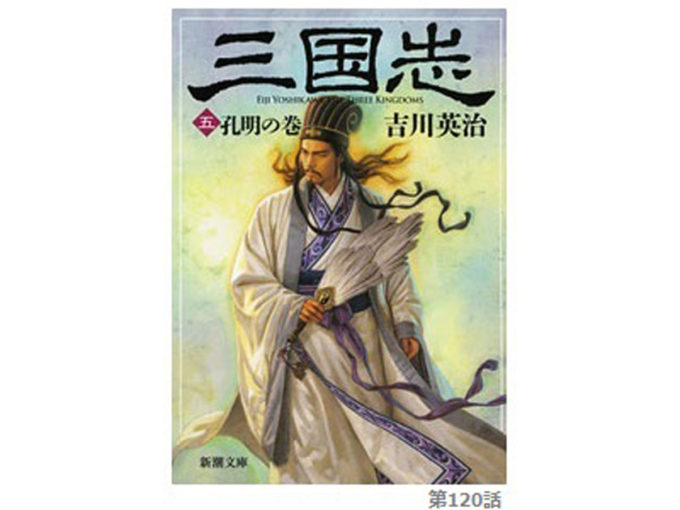














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます