よたび自陣に戻った孟獲(もうかく)は、弟の孟優(もうゆう)と相談し、南蛮国の知恵者として名高い朶思王(だしおう)の助力を仰ぐ。
朶思王の治める禿龍洞(とくりょうどう)へ向かった蜀軍は、強烈な毒泉の影響で死傷者を出す。諸葛亮(しょかつりょう)も困り果てたが、馬援(ばえん)を祭る廟(びょう)に祈りを捧げて窮状を訴えたところ、ひとりの老人が現れる。
第270話の展開とポイント
(01)孟獲の本営
孟獲は自陣に帰ったものの、数日はぼんやりと考え込んでばかりいる。その様子を見て弟の孟優が言った。
「兄貴。とても孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)にはかなわないから、いっそ降参したらどうかね?」
これを聞くと俄然(がぜん)、孟獲は魂が入ったように目をむいて怒る。そしてこう言った。
「俺が四度も生け捕られたのは計略に負けたのだ。だから今度は、俺のほうから孔明を計略にかけてやろうと思って、グッと知恵を絞っているところだ」
孟優が、南蛮国での知恵者ならばと朶思王の名を挙げると、孟獲も同調する。そこで孟優が、禿龍洞の朶思王のもとへ使いすることになった。
(02)禿龍洞
孟優を通じて頼みを聞くと、朶思王は一議に及ばず、洞兵を集めて孟獲を自領に迎える。
朶思王は、たび重なる敗戦の状と、諸葛亮が知謀に長じていることを聞くと、噴笑して言った。
「心配ない、心配ない。孟王、お心安く思われるがよい。わが洞界は不落の険要。ここに兵をお集めあれば、おそらく孔明といえど、蜀軍の将士たりと、生きて帰ることはできない」
続けて朶思王が語る。
「孟王が今これへ来られた一道の通路は、平常だから開いてある。だが、いざという時になれば、あの途中の絶壁と絶壁の寄り合った隘路(あいろ)は巨木大石をもってふさぎ、たちまち洞界の入り口を遮断できるようになっている」
「また、西北(いぬい)の一方は岩石がそびえ、密林が茂り、毒蛇や悪蝎(あっかつ。質〈たち〉の悪い蝎〈サソリ〉)の類いも多く、鳥すら翔(か)けぬ険しさ」
「ただ一日中の未(ひつじ。午後2時ごろ)・申(さる。午後4時ごろ)・酉(とり。午後6時ごろ)の時刻だけしか往来できぬ」
孟獲が理由を聴くと、朶思王はつぶさに語った。
「どういう訳かわからないが、未・申・酉の時刻以外は濛々(もうもう)と瘴煙(しょうえん。高熱を伴う病の気を含む煙)が起こるのだ。地鳴りがして岩間から煮え立った硫黄が噴くので、人馬は恐れて近づけない」
「ために、そこらはすべて草木も枯れ、見る限り荒涼な焼け地獄みたいなところだが、ひと山越えて密林の谷間へ入ると、4か所に毒の泉がある」
「そのひとつを啞泉(あせん)と呼び、飲めば一夜のうちに口が爛(ただ)れて腸(はらわた)も引きちぎられ、5日を出ずに死んでしまう」
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第89回)では、朶思大王が孟獲に、(啞泉の)水はなかなかうまいが、飲むと口が聞けなくなり、10日も経たないうちに必ず死ぬと話していた。
孟獲が、ほかの3つの泉についても尋ねると、朶思王はこう答えた。
「二の泉を滅泉(めっせん)といい、これはその色あくまで青く、泉流は温かでまるで湯のようだ。だが、もしこれに浸って沐浴(ゆあみ)すれば、たちまち皮肉は崩れて死んでしまい、後に底をのぞけば白骨があるだけのものだ」
「三の泉を黒泉(こくせん)という。水は清く美しいが、これに手足を漬ければみな黒くなって、なかなか激痛がやまない」
★井波『三国志演義(6)』(第89回)では、朶思大王が孟獲に、(黒泉の)水はやや澄んでいるが、これを体にかけると手足が黒くなり、死んでしまうと話していた。
「四の泉を柔泉(じゅうせん)という。氷のごとく冷ややかで、炎暑を越えてきた旅人はみな飛びついて飲むが、これを飲んで助かった人間は昔からひとりもなかった」
また後漢の時代に、伏波将軍(ふくはしょうぐん)の馬援という者だけは、ここへ来たことがあるともいう。ただしそれ以来、いかなる英雄の軍勢でも、この洞界を通り切った者はないとも。
孟獲は額を叩いて喜ぶこと限りなく、「いざ、来てみろ孔明。来られるものならやってこい!」と、北の天に向かって罵った。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(馬援は)光武帝(劉秀〈りゅうしゅう〉)の功臣。現在のヴェトナムにあたる交州(こうしゅう)でチュンチャク・チュンニ姉妹の反乱を平定した」という。
★なお、馬援の名は先の第181話(03)で既出。
(03)行軍中の諸葛亮
そのころ、すでに諸葛亮は西洱河(せいじが)地方を宣撫(せんぶ)し終え、炎気焦(や)くがごとき南国の地を、さらに南へ南へ行軍し続けていた。
蜀の偵察隊が報告する。
「この先、数百里の間、まったく蛮軍なく、一兵の旗も見えません。土人を捕らえてただすと、孟獲と孟優は、もっと奥の禿龍洞と呼ぶ山岳地方にみな兵を集めてしまったそうです」
諸葛亮は絵図を取り出してみたが、例の(南方)指掌図(ししょうず)にそのような洞界は書いてなかった。
★(南方)指掌図について、井波『三国志演義(6)』(第87回)では平蛮指掌図と呼ばれていた。
傍らの呂凱(りょがい)に尋ねたが、「指掌図にもないような地方では、よほど不便な蛮界でしょう。手前も何も知りません」との答え。
後ろから地図をのぞいていた幕僚の蔣琬(しょうえん)が、思わず嘆息して諫める。
「もう十分に蜀の武威をお示しになり、原住民を宣撫して、あまねく王風をお布きになったのですから、このへんで帰還されてはいかがです? あまり奥地に入りすぎて、ついに三軍むなしく蛮地の鬼(死者)となろうやもしれません」
諸葛亮は、ひょいと蔣琬の顔を振り仰いで言った。
「それは孟獲も大いに希望しているだろうな」
蔣琬は赤面して口をつぐむ。
ここで諸葛亮は王平(おうへい)の手勢に先行を命じ、西北の山地へ分け入らせる。しかし数日経っても戻らない。さらに関索(かんさく)に1千騎を与えて連絡を取らせたところ、やがて引き返してきて前途の大変を告げた。
★井波『三国志演義(6)』(第89回)では、泉への道を探り当てた王平が立ち戻って報告しようとしたところ、(泉の水を飲んでいたため)口が聞けなくなり、みなただ口を指すだけというありさまだったとある。
王平の兵は、ほとんど九分通り四泉の毒水にあたって病み苦しみ、あるいは死んでいる。自分の部隊の人馬も行路の炎暑に渇し、戒める暇(いとま)もなく泉に近づき、たちまち数十人の犠牲を出した。その苦悶(くもん)と死状は酸鼻見るに堪えないものであると。
諸葛亮は驚く。彼の該博なる知識をもっても解決はつかない。意を決して三軍に出発を命じ、自身は四輪車に押され、兵馬は相助けつつ、ものすさまじいあえぎとともに、あえて未曾有の難所へかかった。
一木一草なき岸々(がんがん)たる焼け山や焼け河原を越え、ようやく峰また峰を巡って密林地帯に入る。ただちに王平が迎えに来て、諸葛亮の車を四泉のほとりへ案内した。
(04)四泉
見れば泉は水気凜々(りんりん)として、彼すらすぐに飛びついて口づけたい誘惑をたたえていた。仰げば、四山は屛風(びょうぶ)のごとく屹立(きつりつ)し、一鳥鳴かず、一獣駆けず、誠に妖気肌を刺すものがある。
諸葛亮はふと一峰の中腹に、人工の色ある廂屋(しょうおく)を見る。そこで徒歩で絶壁をよじ、藤(フジ)や葛(カズラ)にすがって登った。
(05)馬援の廟
岩盤をくりぬいた窟(いわや)がある。それを廟としてひとりの将軍の石像が祭られていた。傍らに建ててある碑銘を読んでみると、これなん漢の伏波将軍の石像で、遠き昔、将軍、南蛮を征してこの地に至り、土人その徳を慕ってこれを祭る、と刻んである。
諸葛亮は石像の前にひれ伏し、祈念久しゅうして、生ける人に言うがごとく烈々と助力を訴えた。するとひとりの怪しげな老翁が、杖にすがって彼方(かなた)の岩に腰を据え、「丞相(じょうしょう)、これへ来たまえ」と呼んでいる。
諸葛亮が誰かと尋ねると、老翁は土地の者とのみ答え、こう教えた。
「これから2、30里ほど谷の奥へ分け入ると、さらに五峰の懐に万安渓(ばんあんけい)というやや広い谷間がある。そこに人呼んで万安隠者という隠士がおりまする」
「この人、谷を出でぬこと数十年。庵(いおり)の裏に一水を持ち、これを安養泉(あんようせん)と唱え、四毒にあたれる旅人や土地の人々を救うてきたこと、今日まで何千人かわかりません」
★井波『三国志演義(6)』(第89回)では安楽泉(あんらくせん)とあった。
「いま丞相の軍もさだめしお困りでしょう。丞相の徳により、わしどももいささか王化の何たるかを解し、今日生まれたかいがあるように思っております。ま、とにかく万安渓へ行ってご覧なさいまし」
言うかと思うと飄(ひょう)として名も告げず、老翁はそのまま立ち去ってしまった。
諸葛亮は、神廟のお告げに相違ないと信ずる。そして翌日、扈従(こじゅう)の人々とともに、老翁に教えられた五峰の奥谷を尋ねてみた。
管理人「かぶらがわ」より
毒の河(先の第266話〈05〉で登場)に続き、「出ました!」という感じの毒の泉。これもいかにも南蛮っぽい。このあたりは史実の制約がないためか、なかなかの弾けっぷりですね。

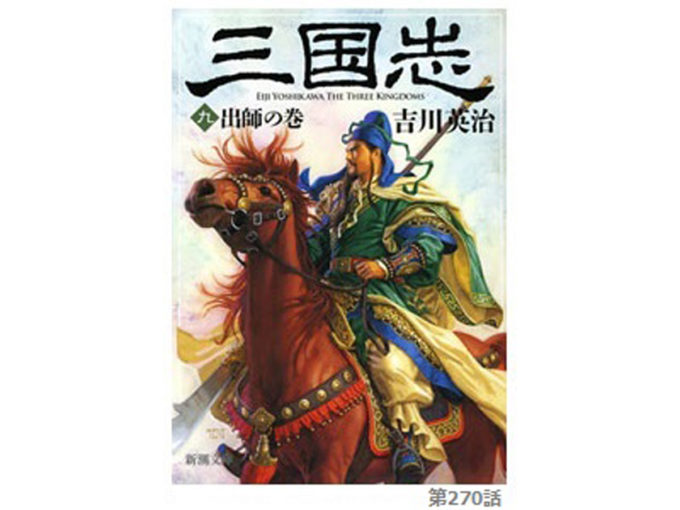















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます