巴西(はせい)から漢中(かんちゅう)を目指して出撃した張飛(ちょうひ)は、宕渠寨(とうきょさい)に籠もった曹操(そうそう)配下の張郃(ちょうこう)をおびき出そうとする。
しかし張郃に打って出る気配が見えなかったので、張飛は宕渠山のふもとまで本営を進め、敵前で酒宴を開く。この報告を成都(せいと)で聞いた諸葛亮(しょかつりょう)は笑い、驚く劉備(りゅうび)に意外な提案をした。
第217話の展開とポイント
(01)下弁(かべん。下辨)
四川の巴西と下弁地方は、今やみなぎる戦気に雲は風をはらみ、鳥獣も声を潜めている。魏兵5万は漢中から積極的に蜀の境へと出て、その辺りの険阻に霧のごとく密集していた。
正面の敵は馬超(ばちょう)である。馬超は下弁方面に、そして張飛は巴西から漢中をうかがってきたのだ。これに対し魏の総大将は曹洪(そうこう)、その下に張郃。兵力と装備においては、圧倒的に魏のほうが優れて見える。
序戦は魏の主力と馬超の部下の呉蘭(ごらん)と任双(じんそう)の兵とから開始され、第一戦で任双は討たれ、呉蘭は敗走した。
★『三国志演義(5)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第69回)では、任双と思われる人物を任夔(じんき)としていた。任夔の名は正史『三国志』にも見える。
「なぜ敵を軽んずるか。以後は険を守って滅多に動くな!」
馬超は呉蘭の軽忽(けいこつ)な戦いぶりを大いに叱る。
曹洪は敵が動きを見せないことを怪しみ、大事を取って南鄭(なんてい)まで兵を退げた。張郃がおもしろくない顔をすると、こう応ずる。
「都(ここでは鄴都〈ぎょうと〉のこと)を出るとき管輅(かんろ)に卜(うらない)を観てもらったら、『このたびの戦場ではひとりの大将を失うであろう』と言われた。ゆえにあえて入念に作戦しているわけだ」
張郃は笑った後、兵3万騎を分けてもらえれば、巴蜀のほうに出てきた張飛の軍勢を、ひと叩きにするとも言う。
曹洪は、張飛を侮る様子を見て危うく思い、容易には許さない。だが張郃は自信満々で、しつこく自説の実行を求める。
やむなく曹洪は誓紙を書かせたうえ、3万の兵を分けて進発を許した。張郃は意気揚々と巴西へ向かう。
(02)巴西
巴西地方から閬中(ろうちゅう)の辺りは、山みな峨々(がが)として谷は深く、険峰は天に並び、樹林は千尋の下に埋もれている。どこに陣して、どこに兵馬を歩ませるか? ちょっと見定めがたいような地勢ばかりだった。
張郃は3か所に陣地を構築。というよりも、天険へ拠り、巣を作るように立て籠もった。一の陣を宕渠寨と呼び、二の陣を蒙頭寨(もうとうさい)と号し、三の陣を蕩石寨(とうせきさい)と唱えた。
まずその布陣を誇って兵力の半数を置くと、あとの1万5千をひきい、自ら巴西間近へ詰め寄せた。
(03)閬中
張飛は部下の雷同(らいどう。雷銅)に諮る。雷同は、地勢の険しいところだから、出かけていって不意を突いたほうがおもしろいかもしれないと進言。張飛は進言を容れ、おのおの5千ずつをひきいて巴西を発した。
★井波『三国志演義(5)』(第70回)では、張飛は5千の精鋭を雷銅に与えて出発させた後、自ら1万の軍勢をひきいて出撃したとある。
図らずも、張飛らの兵と張郃の兵とは閬中の北30里の山あいで、約束したようにぶつかった。張郃は予期せぬ敵にぶつかったことと、峰や谷から上がるすさまじい鬨(とき)の声に、自分の位置を危惧した。
振り返ってみると、後方の山にも蜀の旗が立っているし、遥か下のほうにも蜀の旗が見える。張郃は退路に危険を感じた。こういう心理が首脳に働いたとき、もう全軍は支離滅裂。彼自身も、呼ばわって追いかけてくる張飛に後ろを見せていた。
張郃は蜀の旗が見える山を避け回ったが、それはみな擬兵(敵を欺くための偽りの兵。疑兵)にすぎなかったことが後でわかった。先回りした雷同が諸所へ兵を登らせ、やたら旗ばかり立てていたのである。
(04)巴西 宕渠寨
張郃は辛くも宕渠寨までたどり着くと、岩窟(いわあな)の門をふさいで渓谷の柵門を固め、「戦うなかれ」を旗印にした。
張飛もまた、彼方(かなた)の一山まで来て山陣を張る。ところが張郃は、絶対に戦わない。
こちらの山陣から小手をかざして見ると、宕渠寨の高地へ登って毎日、蓆(むしろ)を延べ、帷幕(いばく。作戦計画を立てる場所、軍営の中枢部)の連中と笛を吹いたり、鼓を打ったり、酒を飲んだりしている様子である。
張飛は下手な手に乗るなと注意したうえ、雷同に出陣を命ずる。
雷同は一手の勢をひきいて、向こうの山の下へ迫った。そして声の限り、口の限り、張郃を悪罵し、魏兵に悪たれ口を叩いた。だが、何の手ごたえもない。「戦うなかれ」という敵の鉄則はひどく固かった。
雷同は翌日も繰り返す。昨日にも勝るほど、声をそろえて張郃を罵り辱めた。けれど宕渠寨は頑固な啞(おし)のごとく、うんともすんとも答えない。
「掛かれっ! 攻め登れっ!」
とうとう雷同は癇癪(かんしゃく)を起こし、まず渓流を踏み越え、沢辺の柵門へ掛かった。バリバリとそこらを踏み破り、声を合わせて山肌に取りつく。
たちまち、万雷の一時に崩れてくるかのような轟(とどろ)きがした。巨木や大岩石、雨のごとき矢や石鉄砲などが、待っていたとばかりに浴びせかけられたのである。
蜀兵の死者は数百人。過日の勝ちをこの日に埋め合わせられて、戦は五分五分となり、またまた山と山はにらみ合いに入ってしまった。
翌日、張飛は自ら乗り出し、部下を伴って向こうの山の下へ迫る。そこで雷同に命じたように、自分も声限りに様々な悪罵を浴びせた。
張飛の悪口となると、なかなか雷同などの比ではなく、辛辣(しんらつ)を極めたものだったが、依然として敵は緘黙(かんもく)を守り続けている。張り合い抜けの形で、彼はすごすごともとの山陣へ戻った。
(05)巴西 張飛の山陣
幾日かすると――。何としたことか、今度は張郃の陣から、こちらの山に向かって悪罵が飛んできた。遥かに望めば魏兵が山上に打ちそろい、一斉に大声を発して悪たれをついている。
雷同はこれを眺めて切歯した。「なかなか憎い致し方、このうえは一挙に……」と、真っ赤になって息巻く。
張飛は雷同を抑え、「いまこちらが動いては、まんまと敵の術中に陥るというもの。しばらく待て」と言った。
しかし、このような状態が50日余りも続いては、部下の兵士も安らかでない。不穏な形勢さえ見えてきたため、張飛は一策を案じ、山を下って敵前に陣を構えた。
(06)宕渠山のふもと 張飛の本営
張飛は酒を運ばせ、部下とともに酒宴を張る。大いに酔っては、山上に向かって悪罵すること、前よりも激しかった。
だが、張郃はこの様子を見ると、「張飛もついにヤケになったわい。必ず手出しすな」と命じたので、かえって山中は静かになった。
(07)成都
劉備は張飛のもとへ使者を遣り、復命を待っていた。やがて使者が戻り、報告をもたらす。
「張飛の軍、閬中の北方において張郃の兵とぶつかり、双方対陣のまま50余日に及びます。張郃いかに謀れども出でて戦わず、ために張飛は敵を欺くと称し、山を下って敵前に備え、毎日酒を飲んで敵を罵りおります」
驚いた劉備はさっそく諸葛亮を呼び、張飛が悪い癖を出している様子であるが、どうしたものかと問うた。
諸葛亮は委細を聞くと笑い、おそらく閬中には良い酒がないだろうから、成都の美酒を集め、50樽(たる)ほど送り届けてやるよう勧める。
劉備は、とんでもないことだと言うが、諸葛亮は、必ずや張郃を欺くための深慮遠謀があってのことと信じますと言い、ただちに助けるよう促す。
劉備は不安を残しながらも魏延(ぎえん)を呼び、成都の名酒50樽の調達を命ずる。
魏延が名酒を集めて示すと、諸葛亮は黄色の旗に「陣前公用の美酒」と書き付け、「これを3輛(りょう)の車に立て、ただちに宕渠の陣にある張飛がもとに届けよ。疾(と)く行け」と急がせた。
(08)宕渠山のふもと 張飛の本営
魏延が着くと、張飛は大いに喜び、酒樽を拝した。そのうえ魏延と雷同にこう命ずる。
「魏延は右翼にあれ、雷同は同じく左翼に陣せよ。軍中紅き旗振るを合図として、その折は全力をもって打って出よ」
そして、陣中に美酒を迎えて肴(さかな)を集め、前にも増した大酒宴を始めた。
(09)巴西 宕渠寨
張郃は見張りから報告を受けると、山上から遥かに敵陣を眺める。張飛は中軍に陣して平坐(へいざ)、痛飲している様子。ふたりの童子に相撲を取らせては、しきりと喜んでいるのがわかった。
張郃は蒙頭と盪石(とうせき)の両寨にも戦闘用意を命じ、これを左右とすると、月明かりを利して山を下り、張飛の本営に迫った。
★この第217話(02)では蕩石寨とあったが、ここでは盪石寨とあり、表記が揺れている。
(10)宕渠山のふもと 張飛の本営
敵前に近づいてから、なお張郃が眺めれば、依然として張飛は酒を飲んでいる。「突っ込め!」の命とともに2か所の勢も鬨を作ってなだれ、鼓を打ち、銅鑼(どら)を鳴らして突っ込んでいく。
張郃は馬を躍らせ、槍で張飛を突き通したが、まるで手ごたえがない。確かに張飛と思ったのは人ではなく、草で作った人形だった。焦りぎみに退こうとすると突然、鉄砲が響いた。それと同時に、張飛を先頭にした一群の兵が道をふさぐ。
張郃はとっさに張飛の大矛を受け、必死に打ち合うこと4、50合に及ぶ。その間に雷同と魏延の軍も、それぞれ蒙頭と盪石のふた手の勢と戦い、瞬く間に追いまくった。
味方の崩れを見ながらも、張郃は張飛の鋭い矛と打ち合っていたが、かくするうちに山上に火がかかる。蜀軍が勢いを得てますます数を増やし、周囲すべて敵となっていくのがわかった。
さらに退路も絶たれる様子に、張郃は寸隙を狙い、馬に一鞭(いちべん)を与えて逃げる。張飛は全軍に追撃を緩めるなと号令し、しゃにむに突進した。
管理人「かぶらがわ」より
馬超配下の任双が、はかない最期。彼は正史『三国志』における任夔らしく、井波『三国志演義(5)』(第69回)にも登場していましたが、とにかく登場から退場までが短い。
最近は計略も用いるようになった張飛。今回の根比べは張郃の負けですね。

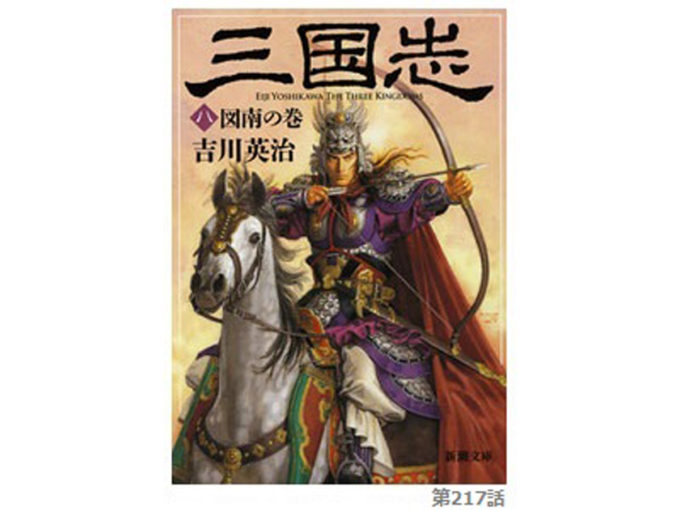












コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます