鹵城(ろじょう)にいた諸葛亮(しょかつりょう)は、永安城(えいあんじょう)の李厳(りげん)から急報を受け、にわかに総退却を命ずる。
司馬懿(しばい)は諸葛亮の計略を警戒したため、あえて追撃の速度を緩めていたが、再三の請いを容れ、張郃(ちょうこう)に先駆けを許す。喜び勇んだ張郃は蜀軍を猛追し、木門道(もくもんどう)の谷口まで入り込むが――。
第300話の展開とポイント
(01)鹵城
永安城の李厳は増産や運輸の任にあたり、もっぱら戦争の後方経営に努めている。いわゆる軍需相(ぐんじゅしょう)ともいうべき要職にある蜀の大官だった。
その李厳から届けられた書簡を見ると、近ごろ呉が洛陽(らくよう)へ人を遣り、魏と連和したようだと急告している。
諸葛亮は大きな衝撃を受けた。事実、この書面に見えるような兆候があるとすれば、これは誠に重大である。
魏に対しての蜀の強みは何と言っても、一面に蜀呉相侵すことなき盟約下にあることが基幹をなしている。呉がいま寝返りを打ち、魏と連和するような事態でも起こるとしたら、これは根本的に蜀の致命とならざるを得ない。
諸葛亮は大英断をもって、ただちに全戦線の総退却を決意した。
「まずは速やかに祁山(きざん)を退くべきである」と、鹵城から使いを急派し、祁山に残してきた王平(おうへい)・張嶷(ちょうぎ)・呉班(ごはん)・呉懿(ごい)らに、次のような命を言い送った。
「予がここにあるうちは、魏もうかつには追うまい。乱れず、騒がず、順次退陣して、ひとまず漢中(かんちゅう)に帰れ」
一面、楊儀(ようぎ)と馬忠(ばちゅう)のふた手を、剣閣(けんかく)の木門道へ急がせる。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「木門は地名。天水郡(てんすいぐん)西県(せいけん)に属す。現在の甘粛省礼県(れいけん)東北、漾水(ようすい)北岸」という。また「『三国志演義』では剣閣の木門道と称しているが、剣閣は益州(えきしゅう)に属しており、木門とは位置が異なっている」ともいう。
★なお『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第101回)では、このとき楊儀と馬忠がひきいたのは、1万の弓と弩(ど)の射手。
こうした後、鹵城には擬旗を植え並べ、柴(シバ)を積んで煙を上げ、あたかも人がいるように見せておく。諸葛亮とその麾下(きか)も、ことごとく木門道を指して急速に引き退いた。
(02)上邽(じょうけい)
渭水(いすい)にあった張郃が、馬に鞭(むち)打って上邽へくる。そして司馬懿にこう諮った。
「何か起こったに違いない。蜀軍の退陣はただごとではありません。今こそ急追し、殲滅(せんめつ)を食らわす時機ではないでしょうか」
司馬懿が張郃を制しているところへ、一兵が鹵城の変を告げる。司馬懿は張郃を伴って高きに登り、鹵城の旗をしばし眺めていたが、突然、哄笑(こうしょう)して言った。
「なにさま、旗も煙も、確かに擬勢だ。鹵城は空城(あきしろ)に違いない。いざ追い撃たん」
今は疑う余地もなしと、にわかに司馬懿は、上邽から奔軍を駆って急進する。
(03)木門道の近く
すでに木門道に近づくと、張郃が言った。
「かかる大兵の行軍では、どうしても遅鈍ならざるを得ません。それがしが軽騎数千を引っ提げて先駆し、まず敵を捉えて食い下がっておりますから、都督(ととく)の本軍は後からおいでください」
司馬懿が応えて言う。
「いや。行軍の速度が遅いのは、大兵なるゆえばかりではない。孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)の詭計(きけい)を慎重に打診しながら進んでおるせいにもよるのだ」
張郃は再三の諫めを聞かず、なお急追の許しを乞い続ける。ここで、ついに司馬懿が言った。
「それほどに言うならば、ご辺(きみ)は5千騎をもってまず急げ。別に賈翔(かしょう)と魏平(ぎへい)に2万騎を付けて後から続かせる」
★賈翔は、正史『三国志』では賈栩(かく)。『三国志演義』には賈翔(賈栩)の名は見えない。
張郃は喜び勇んで、手兵5千騎、みな軽捷(けいしょう)を旨とし、飛ぶがごとく敵を追った。70里も行くと、一叢(いっそう)の林の内から鼓鉦(こしょう)や鬨(とき)の声が上がり、蜀の魏延(ぎえん)が姿を見せる。
ひと声おめき返すやいな、張郃は魏延の兵を追い散らす。魏延はちょっと出て槍を合わせたものの、すぐに偽り負けて逃げ奔った。
張郃は先を急ぎ、さらに20里ほど進む。ここで一山から蜀の関興(かんこう)と名乗り、軍馬が駆け下ってくる。張郃が憤怒して迎えると、関興は勢いに恐れたかのごとく逃げ出す。
張郃は追うが、一方の密林を見てふと万一を思い、兵に下知してしばし息をついた。
「伏兵があるかもしれぬ。そこの林を搔(か)き捜せ」
すると先に隠れた魏延が後ろから襲ってくる。張郃が当たって力戦していると、関興が引き返してきて鼓躁(こそう)した。
あるいは逃げ、あるいは挑み、こうして張郃を翻弄して疲れしめながら、ついに魏延は目的通り、木門道の谷口まで強引に誘い込んだ。
(04)木門道
地形の険隘(けんあい)に気づき、張郃もここまで来ると盲進せず、一応軍勢を整えていた。だが魏延はその暇を与えず、絶えず戦いを挑んでは辱める。
とうとう張郃は司馬懿の戒めも忘れ、木門道の谷まで駆け込んでしまう。しかも時はようやく薄暮に迫り、西山の肩に茜(あかね)を見るほか、すでに谷の内はほの暗い。
魏の将士は後ろから口々に、「将軍、帰りたまえ。将軍、引き返したまえ」と呼んでいたが、張郃は、憎き魏延を討ち止めぬうちはと、奔馬の脚に任せて鞭打つ敵を追った。
はや手も届かん間近にある魏延の背へ向かい、張郃は罵ってやまず、いきなり馬上から槍を投げつける。
魏延は馬のたてがみに首をうつぶせ、槍は兜の錣(しころ。垂れ)を射抜き、彼方(かなた)へ飛んだ。
「アッ、将軍!」
味方の声に、思わず張郃が振り向くと、彼の先途を案じて慕ってきた100余騎の将士が、一斉に山を指さして叫んだ。
「あの山頂に怪し火が見えますぞ。何かの合図やもしれません。夜に入ってはいよいよ大事。早々、後へお帰りあって、明日を期されたほうがよろしいでしょう」
けれどこれらの忠告すら、すでに遅きに失していた。
突然、虚空に大風が起こった。それは万弩(ばんど)の矢うなりである。たちまち絶壁は叫び、谷の岩盤はみな吼(ほ)えた。それは敵の降らせてくる巨木や大石の轟(とどろ)きである。
張郃が気づいたときは、あちこちに火が起こっていた。灌木(かんぼく)も高い木も焼け始める。狂い回る馬に任せて谷口を探したが、そこの隘路もふさがれていた。
性火のごとしと言われた張郃は、炎の中に身をも焼いてしまう。
★井波『三国志演義(6)』(第101回)では、張郃や配下の部将たちはみな(木門道の途中で)射殺されたとある。
諸葛亮は、木門道の外郭をなす一峰に姿を現し、うろたえ惑う魏兵に言った。
「今日の狩猟(かり)に、我は馬を得んとして猪(イノコ)を得た。次の狩猟には、仲達(ちゅうたつ。司馬懿のあざな)という希代の獣を生け捕るだろう。汝(なんじ)らは帰って司馬懿に告げよ。兵法の学びは少しは進んでおるかと」
★井波『三国志演義(6)』(第101回)では、ここで諸葛亮は司馬懿を「馬」と、張郃を「獐(ノロ)」と、それぞれ例えていた。
★井波『三国志演義(6)』の訳者注によると、「獐は鹿の一種。『張』と『獐』は同音」だという。
(05)司馬懿の本営
張郃を失った魏兵は我先に逃げ帰り、実情を司馬懿に告げる。
張郃の戦死は惜しまれた。彼が魏でも屈指の良将軍たることは誰もが認めていたし、実戦の閲歴も豊かで、曹操(そうそう)に仕えて以来の武勲も数えきれないほどである。
「彼を討ち死にさせたのは、実に予の過ちであった。あくまでも彼の深入りを許さなければよかったのだ」
こう痛嘆して、誰よりも責めを感じていたのは、もちろん司馬懿その人だった。同時に司馬懿は、諸葛亮の作戦が何を狙っていたものかを、今は明瞭に悟ることもできた。
「敵を険に誘い、味方を不敗の地に拠らせ、そうして計を動かし、変をもって、これを十分に捕捉滅尽する」
ここに諸葛亮の根本作戦があるものと看破する。そう考えてくると、渭水から邽城(けいじょう。上邽)、邽城からこの剣閣へと、いつか自分も次第に誘い出され、危険極まる蜀山蜀水の内に踏み入りかけていることも顧みられた。
「危ういかな。知らず知らずに自分も彼の誘導作戦にかかっている――」
司馬懿は急に兵を返す。要所要所に諸将を配し、ただよく守れと境を厳にして、やがて自身は洛陽(らくよう)へ上った。
(06)洛陽
司馬懿が戦況を奏上すると、曹叡(そうえい)も張郃の死を悲しみ、群臣もみな落胆した。
「敵国のまだ滅ばぬうちに、我は国の棟梁(とうりょう)を失った。前途の難をいかにすべき」
嘆きの声と沈滅の色は、魏の宮中を一時沈衰の底へ落とす。そのとき諫議大夫(かんぎたいふ)の辛毘(しんび。辛毗)が曹叡に奏し、群臣にも言った。
「武祖(曹操)文皇(ぶんのう。曹丕〈そうひ〉)二代を経、今帝また龍のごとく世に興りたまい、わが大魏の国家は強大天下に比なく、文武の良臣また雨のごとし。何ぞ一張郃の戦死を、さまで久しく悲しまるるか」
「家人の死は、一家の情をもって嘆くもよし惜しむもよろしいが、国民の死は国家の大をもってこれを悠久に崇(あが)め、これを盛葬し、これをたたえて、全土の人士を振るわすべきではありませんか」
やがて木門道から取り上げてきた屍(しかばね)に対して、曹叡は厚き礼を賜い、洛陽を人と弔旗に埋むるの大葬を執り行って、いよいよ討蜀の敵愾心(てきがいしん)を振起させた。
(07)漢中
一方の諸葛亮は、軍を収めて漢中の営に帰ると、すぐに諸方へ人を遣り、魏呉の両国間の機微を探らせていた。そこへ成都(せいと)から尚書(しょうしょ)の費禕(ひい)が来て、率直に朝廷の意を伝える。
「何の理由もなく、漢中へ兵をお返しになったのはなぜですか? 天子(劉禅〈りゅうぜん〉)もご不審を抱いておられますぞ」
諸葛亮は事情を話す。
「近ごろ呉と魏との間に、秘密条約が結ばれた形跡ありとのことに、万一、呉が矛を逆しまにして、蜀境を突くような事態でも起こっては重大であると思うて、急きょ祁山を捨てて万全を期したまでであるが」
費禕は、兵糧運輸の線の活動状況を尋ねる。そして諸葛亮に、とかく後方からの運送は滞りがちだったと聞くと、さらに言った。
「それでは、李厳の話とまるであべこべです。李厳の申すには、『このたびこそ兵糧にも困らぬほど、後方からの運輸も十分に行っておるのに、丞相(じょうしょう。諸葛亮)が突然退軍したのはいぶかしいことである』と、しきりに申し触らしております」
それは言語道断と、諸葛亮もあきれ顔に言う。
「魏呉両国間に秘密外交の動きが見ゆると、我に知らせてきた者は、その李厳であるのに……」
これを聞いて費禕が言った。
「ははぁ。それで読めました。李厳の督しておる軍需増産の実績がここ甚だ上がらないので、科(とが)を丞相に転嫁せんとしたものでしょう」
諸葛亮は赫怒(かくど。怒るさま)して言った。
「もってのほかだ。もし事実とすれば、李厳たりとも許してはおかれない」
(08)成都
諸葛亮は成都へ還り、府員に厳密な調査を命ずる。その結果、李厳の弄策は事実とわかった。
「本来なら首を刎(は)ねても足らぬ大罪ではあるが、李厳もまた、先帝(劉備〈りゅうび〉)が孤(みなしご)をお託しあそばした重臣のひとりだ。官職を剝いで、一命だけは助けおく。即日、庶人に貶(おと)して、梓潼郡(しどうぐん)へ遠流(おんる)せよ」
★井波『三国志演義(6)』(第101回)では、李厳の処分を決めたのは(まだ漢中にいた)諸葛亮ではなく(成都にいた)劉禅。
諸葛亮はかく断じたが、その子の李豊(りほう)は留めて、長史(ちょうし)の劉琰(りゅうえん)らとともに兵糧増産などの役に用いた。
★井波『三国志演義(6)』(第101回)では、諸葛亮は成都に帰り着くと、李厳の息子の李豊を取り立てて長史としたとある。
管理人「かぶらがわ」より
『三国志』(魏書・張郃伝)には、略陽(りゃくよう)に到着した張郃が、祁山へ引き返した諸葛亮を追い、木門で右膝に矢を受けて戦死したことが見えます。
なぜここで剣閣が出てくるのか疑問でしたが、『三国志演義大事典』に指摘がありました。『三国志演義』では木門の位置にも誤解があるようです。
それにしても、確かに張郃は名将でした。袁紹(えんしょう)は情けない形で彼を手放すことになりましたが、曹操に仕えてから大飛躍を遂げましたね。
★張郃が袁紹のもとを離れた経緯については、先の第115話(07)を参照。

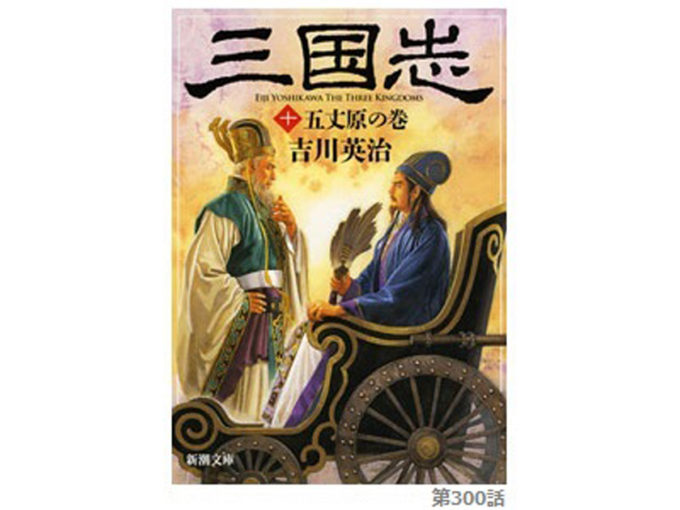














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます