【姓名】 常林(じょうりん) 【あざな】 伯槐(はくかい)
【原籍】 河内郡(かだいぐん)温県(おんけん)
【生没】 ?~?年(83歳)
【吉川】 登場せず。
【演義】 登場せず。
【正史】 登場人物。『魏書・常林伝』あり。
寒門(権勢のない家柄)出身ながら、高潔な人柄で高官を歴任、諡号(しごう)は貞侯(ていこう)
父は常伯先(じょうはくせん。名はわからず)だが、母は不詳。息子の常旹(じょうじ)は跡継ぎで、常静(じょうせい)も同じく息子。
常林が7歳のころ、父の友人らが訪ねてきて聞いた。
「伯先はおられるか? ところで、なぜお前は我らに拝礼せぬのか?」
すると常林が答えた。
「私が頭を下げねばならないお客さまであっても、子に向かって父のあざなを呼ぶ方に、どうして拝礼する必要がありましょうか」
みな彼の言葉に感心したという。
常林は寒門の出で、若いころ貧しかった。それでも自分の働きによるもの以外、他人から何かをもらおうとはしなかった。
常林は学問が好きで、漢末に太学の学生となったものの、やがて経典を携え耕作に従事する。妻は弁当を届けたが、常林は田野にあっても、賓客と対するような態度で彼女に接した。
190年、河内太守(かだいたいしゅ)の王匡(おうきょう)は、挙兵して董卓(とうたく)討伐軍に加わった。
一方で書生らを属県に遣って官民の罪科を密かに探らせ、該当者を逮捕し取り調べ、金銭や穀物を要求して罪を購わせる。従わない者は一族を皆殺しにし、それによって自身の威厳を高めた。
そのような中、常林の叔父が食客を鞭(むち)打ち、書生の密告を受ける。王匡は腹を立てて逮捕した。
一族の者たちは王匡の要求がどのくらいになるかわからず、あわてふためく。そこで常林は、王匡と同県の胡母彪(こぼひゅう)を訪ねる。
そして王匡の才能をたたえつつ、現在の争乱に打ち勝てるかは人の和にかかっており、恩徳がないことで任用に人を得なければ、今にも滅亡してしまうと述べ、この話に絡めて叔父が逮捕された件についても説明した。
胡母彪が手紙を遣って王匡を責めると、常林の叔父は釈放された。その後、常林は上党(じょうとう)へ移り、山奥で耕作をして暮らす。
このころ干害やイナゴの被害に見舞われたが、常林のところだけは豊作だった。彼は近所の者を呼び寄せ、1升や1斗のますで穀物を分け与えた。
後に常林は、もと河間太守(かかんたいしゅ)の陳延(ちんえん)の砦(とりで)に身を寄せる。
陳氏と馮氏(ふうし)は古い氏族のうちでも最高の家柄だったが、河内太守の張楊(ちょうよう)が陳延のもとにいる婦女子に目を付け、財産を奪い取ろうとした。
そこで常林は一族をひきい、陳延らのために策を立てる。張楊から60余日にわたる包囲を受けたものの、砦を守り切ることができた。
やがて幷州刺史(へいしゅうしし)の高幹(こうかん)の上奏により騎都尉(きとい)に任ぜられるも、常林は辞退する。
後に幷州刺史の梁習(りょうしゅう)が、州内の名士である常林・楊俊(ようしゅん)・王淩(おうりょう)・王象(おうしょう)・荀緯(じゅんい)を推薦したところ、曹操(そうそう)は全員を県長(けんちょう)に起用する。
★206年、梁習は別部司馬(べつぶしば)のまま幷州刺史を代行し、後に本官(正式な幷州刺史)となった。
このとき常林は南和県長(なんかけんちょう)に任ぜられ、当地で治績を上げた。
次いで博陵太守(はくりょうたいしゅ)を経て幽州刺史(ゆうしゅうしし)に昇進したが、やはり各地で治績を上げた。
211年1月、曹丕(そうひ)が五官将(五官中郎将)になると、常林は召されて功曹(こうそう)に任ぜられる。
同年7月、曹操が関中(かんちゅう)の韓遂(かんすい)と馬超(ばちょう)を討伐するため西征。この間に田銀(でんぎん)と蘇伯(そはく)が河間で反乱を起こし、幽州や冀州(きしゅう)は動揺した。
これを曹丕が自ら討伐しようとすると、常林は言った。
「私は博陵太守をお引き受けしたことがあり、また幽州にもおりましたので、賊の形勢は予測がつきます」
「北方の官民は平安を喜び、騒乱を嫌っており、長く教化に心服していて善を守る者も多数おります」
「田銀と蘇伯は犬や羊の集まりのようなもので、知力は小さいのに野心だけは大きく、とても害をなすことはできません」
「ただいま味方の大軍は遠方にあり、外部には強敵がおりますが、あなたさまは天下の押さえ。軽はずみに遠征なされば、たとえ勝たれても武威を示したとは言えないでしょう」
曹丕は常林の意見に従い、代わりに将軍を遣って討伐させ、すぐに賊を討ち滅ぼした。
常林は地方へ出て平原太守(へいげんたいしゅ)や魏郡東部都尉(ぎぐんとうぶとい)を務め、中央に戻って丞相東曹属(じょうしょうとうそうぞく)となる。
★213年10月、魏郡は東西の両部に分割され、それぞれに都尉の官が置かれた。
★曹操が丞相を務めていた期間は208~220年。
213年5月に魏が建国されると、同年11月、常林は尚書(しょうしょ)に任ぜられた。
220年、曹丕が帝位に即くと、常林は少府(しょうふ)に昇進し楽陽亭侯(らくようていこう)に封ぜられる。後に大司農(だいしのう)に転任した。
226年、曹叡(そうえい)が帝位を継ぐと高陽郷侯(こうようきょうこう)に爵位が進み、光禄勲(こうろくくん)や太常(たいじょう)を歴任した。
当時の朝廷では、常林の節操が清く気高いことから、彼を三公の位に就けたいと考える。しかし常林は重病と称して受けなかった。
後に常林は光禄大夫(こうろくたいふ)に任ぜられ、83歳で死去(時期は不明)する。
驃騎将軍(ひょうきしょうぐん)の官位が追贈され、貞侯と諡(おくりな)された。葬儀は三公の礼をもって執り行われ、息子の常旹が跡を継いだ。
管理人「かぶらがわ」より
本伝によると、司馬懿(しばい)は常林が故郷の有徳の先輩であることから、いつも彼に拝礼していたそうです。
★司馬懿も河内郡温県の出身。
この様子を見たある人が、常林に忠告します。
「司馬公は高貴なお方ですよ。あなたは拝礼をやめさせるべきでしょう」
これに常林が応えます。
「司馬公は長幼の序を大切にされ、自ら若者の模範になるおつもりなのだ。私は高貴など恐れないし、拝礼も私がどうこうできることではない」
忠告した人は辟易(へきえき)して引いたのだとか。常林の性格がうかがえる記事だと思います。一方の司馬懿には、こういう態度を見せることでの計算もあったのかどうか?
常林は享年しかわかりませんが、曹叡の時代(226~239年)に83歳で亡くなったのなら、司馬懿より25歳ほど年長だったと思われます。
★司馬懿は光和(こうわ)2(179)年生まれ。
また『三国志』(魏書・盧毓伝〈ろいくでん〉)によると、(237年2月に陳矯〈ちんきょう〉が死去してから)しばらく欠員となっていた司徒(しと)について、盧毓が曹叡に適任者として推挙した人物の中に「誠実で純粋な太常の常林」の名が見えていました。
なので、常林の死が237年以降であることは確かです。
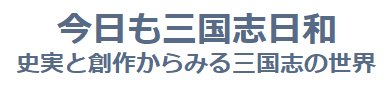














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます