周瑜(しゅうゆ)の指図に従い、満を持して動きだす、長江南岸の孫権軍(そんけんぐん)。
黄蓋(こうがい)も、先に施した苦肉の計の総仕上げとばかりに、対岸の曹操(そうそう)陣営に突入するため火船の準備を整える。
第164話の展開とポイント
(01)長江の南岸 周瑜の本営
魯粛(ろしゅく)の諫めに励まされた周瑜は、まず甘寧(かんねい)を呼び、蔡仲(さいちゅう。蔡中)を案内者として曹操に降参すると唱え、敵の北岸へ船を寄せ、烏林(うりん)に上陸するよう命ずる。
そして蔡仲の旗をかざし、曹操が兵糧を蓄えている粮倉(りょうそう)へ迫り、縦横無尽に火を付けるようにと。火の手の盛んなるを見たら同時に敵営へ迫り、側面から攪乱(こうらん)せよとも。
続いて周瑜は太史慈(たいしじ)を呼び、3千余騎を引っ提げて黄州(こうしゅう)の境に進出し、合淝(がっぴ。合肥)にある曹操軍に一撃を加え、まっしぐらに敵の本陣へ掛かり、火を放って焼き討ちせよと命ずる。紅の旗を見るときは、わが主たる呉侯(孫権)の旗下勢と知れかしとも。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「黄州は荊州(けいしゅう)江夏郡(こうかぐん)に属す。この地名が行政区画として置かれたのは、実際には元代以降のことである」という。
周瑜は3番目に呂蒙(りょもう)を呼び、兵3千をひきいて烏林へ渡り、甘寧と一手になって力戦を助けるよう命ずる。
4番目に呼んだ凌統(りょうとう。淩統)には、夷陵(いりょう。彝陵)の境にあって、烏林に火のかかるのを見たらすぐおめきかかれと命じ、兵3千を預ける。
★ここで夷陵が出てくるのはよくわからなかった。夷陵は烏林のずっと上流にあるはずだが……。
さらに董襲(とうしゅう)に兵3千を預け、漢陽(かんよう)から漢川(かんせん)方面へ行動させ、潘璋(はんしょう)にも同様に兵3千を預け、漢川方面への突撃を命ずる。
★『三国志演義大事典』によると「漢陽は荊州江夏郡に属す。この地名が行政区画として置かれたのは実際には隋代のことである」という。
★同じく『三国志演義大事典』によると「漢川は荊州江夏郡に属す。この地名が行政区画として置かれたのは実際には唐代のことである」という。
★なお『三国志演義(3)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第49回)では、潘璋は3千の軍勢をひきいて漢陽へ向かい、董襲を救援するよう命ぜられていた。
こうして先鋒の6部隊は、白旗を目印として早くも打ち立った。水軍の船手もそれぞれ活発な動きを見せていたが、かねてこの一挙に反間の計を施さんものと手に唾をして待っていた黄蓋は、さっそく曹操のもとへ人を遣る。
そして、今夜の二更(午後10時前後)に兵糧や軍需品を満載し、約束通り降参して出ること。よって船檣(せんしょう。船の帆柱)に青龍の牙旗(がき)を翻した船が見えたら、それが呉からの降参船であると言い送った。
★『三国志演義 改訂新版』(立間祥介〈たつま・しょうすけ〉訳 徳間文庫)の訳者注によると、「(牙旗は)大将の旗。陣頭に立てる大きな旗で、竿(さお)の先を象牙で飾るからこう言うともいわれる」とある。
一方で黄蓋は着々と準備を進める。まず20艘(そう)の火船を先頭に立て、その後に4隻の兵船をつなげた。
これに続き、第1船隊には領兵軍官(りょうへいぐんかん)の韓当(かんとう)が控え、第2船隊には周泰(しゅうたい)、第3船隊には蔣欽(しょうきん)、第4船隊には陳武(ちんぶ)、約300余の大小の船が舳(みよし。船首)を並べて夜を待ち受けた。
すでに宵闇は迫り、江上の風波はしきりと暴れている。今暁からの東南風(たつみかぜ)は、昼を通してなお盛んに吹いていた。
何となく生暖かい。そして気だるいほどに陽気外れな晩だった。そのためか江上一帯には水蒸気が立ち込めている。幸先よしと、黄蓋は纜(ともづな)を解いて一斉に発動を命じた。
(02)長江
300余の艨艟(もうどう。突撃艦)は淙々(そうそう)と白波を切り、北岸へ進んでいく。
★艨艟は「もうどう」と「もうしょう」でルビに揺れが見られる。
その後に付いて、周瑜や程普(ていふ)の乗り込んだ旗艦も満帆をはためかせながら動いていった。後陣として続くのは、右備えが丁奉(ていほう)の船隊、左備えが徐盛(じょせい)の船隊。この夜、魯粛と龐統(ほうとう)は後に残り、留守の本営を守っていた。
★井波『三国志演義(3)』(第49回)では、本陣の残留組として闞沢(かんたく)の名も見える。
その日の夕、孫権の本軍は旗下の軍勢とともに黄州の境を越えて前進していた。兵符を受けて発向を知った周瑜。すぐに一軍を派し、南屛山(なんぴょうざん)の頂に大旗を差し揚げる。
こうして先手の大将の陸遜(りくそん)を迎えると、続いて孫権のもとへも、「今はただ夜を待つばかりにて候(そうろう)」と報告。
(03)夏口(かこう)
夏口の劉備(りゅうび)は、諸葛亮(しょかつりょう)の帰りを一日千秋の思いで待ちわびていた。そこへ昨日から季節外れの東南風が吹きだしたので、かねて諸葛亮が言い残した言葉を思い出し、にわかに趙雲(ちょううん)を迎えに行かせる。
★諸葛亮が言い残した言葉については、先の第151話(01)を参照。
趙雲を遣った翌朝も望楼に上がり、今か今かと江を眺めていた。すると一艘の小舟がさかのぼってくる。だが、これは江夏の劉琦(りゅうき)だった。
劉琦は、東南風が吹くとともに呉の兵船や陸兵が色めき立っているとして、この風がやまないうちに必ず一会戦あらん、という物見の報告を伝える。
ふたりが語り合っているうちに番将のひとりが駆け上がってきて、樊口(はんこう)のほうから趙雲の舟らしきものが近づいてくると告げた。
劉備と劉琦が急いで楼を降り、埠桟(ふさん)にたたずんで待っていると、果たして諸葛亮を乗せた趙雲の舟だった。互いに無事を祝すと、袂(たもと)を連ねて夏口城の一閣に登る。
劉備が呉魏両軍の模様をただすと、諸葛亮は、事はすでに急だと言い、味方の用意が整っているか確かめる。
そして水陸の諸軍勢が整っていることを聞くと、まず趙雲を呼び、手勢2千を引き連れて江を渡り、烏林の小路に隠れるよう命ずる。
★井波『三国志演義(3)』(第49回)では、このとき諸葛亮が趙雲に預けたのは3千の軍馬。
今宵の四更(午前2時前後)のころ、曹操が逃げ走ってきたなら前駆の人数はやり過ごし、その半ばを中断して存分に討ち取れと。ただ、残らず討ち止めんとしてはならないともし、逃げるは追わず、頃合いを計って火を放ち、あくまで敵の中核に粉砕を下せとも。
趙雲は退がりかけたが、踵(くびす。きびす)を返し、こう質問した。
「烏林にはふた筋の道があります。ひと筋は南郡(なんぐん)に通じ、もうひと筋は荊州(襄陽〈じょうよう〉)へと分かれている。曹操はそのいずれへ走るでしょうか?」
諸葛亮は、必ず荊州へ向かい、転じて許都(きょと)へ帰ろうとするだろうと答える。
★井波『三国志演義(3)』の訳者注によると、「赤壁(せきへき)での敗北後、曹操は曹仁(そうじん)の出迎えを受け南郡に入城した(『三国志演義』〈第50回〉)。諸葛亮の予想に反する結果となっているが、(『三国志演義』の)作者が荊州・南郡・江陵(こうりょう。南郡の郡役所が置かれた地)の地理関係に注意を払わず、適当に使ったために生じた矛盾だろう」という。また「次に出る夷陵も、あくまで実際の地名だとすれば南郡の西北に位置しており、曹操の逃走経路にはなり得ない」ともいう。
続いて諸葛亮は張飛(ちょうひ)を呼び、3千騎を引き連れて江を渡り、夷陵の道を切りふさぐよう命ずる。
さらに、そこの葫蘆谷(ころこく)に兵を伏せて待てば、曹操は必ず南夷陵の道を避け、北夷陵を指して逃げてくるだろうと言い、明日、雨がやんだ後、曹操の敗軍がこのあたりで腰兵糧を炊(かし)ぐ。その炊煙を望んで一度におめきかかるようにと、つぶさに教えた。
★ここで葫蘆谷が出てくるのはよくわからなかった。そう呼ばれていた場所がいくつかあるのかも?
このことについて『三国志演義大事典』によると、「葫蘆口(ころこう)は後漢では荊州南郡に属す。現在の湖北省江陵県西北」という。
次に糜竺(びじく。麋竺)・糜芳(びほう。麋芳)・劉封(りゅうほう)の3人を呼び、船を集めて江岸を巡り、魏の軍営が壊乱に陥ちたと見たら、軍需兵糧の品々をことごとく船に移して奪ってくるよう命ずる。また、諸所の道にかかる落人(おちうど)たちの馬具や物の具なども余すことなく鹵獲(ろかく)せよとも。
そして、劉琦には武昌(ぶしょう)を離れずに守るよう伝える。
★『三国志演義大事典』によると「武昌は後漢では荊州江夏郡に属す。もとの名は鄂県(がくけん)。孫権が呉王となったときに改名され都とされた」という。これを踏まえると、ここで武昌の名を持ち出すのは時代に合わない。
最後に諸葛亮は劉備を誘い、樊口の高地へ登り、今宵の周瑜の指揮するところの大江上戦を見物しましょう、と支度を促した。
すると、このとき初めて関羽(かんう)が言葉を発する。自分に一片の示命もないのはどういうわけかと、涙をたたえて詰め寄った。
諸葛亮は、以前に関羽が曹操から厚遇されていたことに触れる。
いま曹操は必ず烏林に敗れ、その退路を華容道(かようどう)に取って奔亡してくるだろうが、ご辺(きみ)の性情として旧恩に動かされ、彼の窮地に同情し、放免するに違いないと。
関羽は諸葛亮の思いすぎだと言い、ぜひ自分を遣ってほしいと望む。万一私心に動かされたりなどしたら、潔く軍法に服するとも。
劉備が執り成すと、諸葛亮は誓紙を入れることを条件に出撃を認める。さらに関羽の問いに答え、もし曹操が華容道へ落ちずに別な道へ逃れたときは、自分も必ず罪を被るであろうと約した。
加えて、足下(きみ)は華容山に潜み、峠のほうには火を付けて柴(シバ)を焼かせ、わざと煙を上げ、曹操の退路に伏せているよう命ずる。
関羽は峠に火煙を上げることに懸念を示すが、諸葛亮は、曹操は元来、虚実の論に詳しい者だとして、怪しむことなく早く行くよう促した。
関羽は嘆服して退くと、養子の関平(かんぺい)や腹心の周倉(しゅうそう)らを伴い、手勢500余騎をひきいて華容道へ駆け向かう。
そのあと劉備は、かえって諸葛亮よりも心配顔をしていた。やはり関羽は曹操を助けるような処置に出ないとは限らない、というのだった。
だが諸葛亮はその言を否定して、こう応ずる。
「あながちそれが良策とも言えません。むしろ関羽を差し向けたほうが自然にかなっておりましょう」
劉備が不審顔をすると、諸葛亮は理を説いて付け加えた。
「私が天文を観じ人命を相するに、このたびの大戦に曹操の隆運と軍力の滅散するのは必定ですが、まだ曹操個人の命数はここで絶息するとは思われません。彼にはなお天寿がある」
「ゆえに関羽の心根に、以前に受けた恩に対して今も報じたい情があるなら、その人情を尽くさせてやるのもよいではありませんか」
劉備は諸葛亮の洞察に驚きながら、ふたりで樊口の山頂へと登っていく。
(04)長江の北岸 曹操の本営
昨日から東南風が吹いているのを見て程昱(ていいく)が注意を促す。しかし曹操は、冬至に東南の風が吹き競うのは、何も怪しむことではないと答える。
このようなところへ江南から一舟が着き、黄蓋の密書を届けた。曹操はさっそく読んで大いに喜び、各部の大将に旨を伝える。自身もまた多くの旗下とともに水寨(すいさい)へ臨み、その中にある旗艦に座乗していた。
★黄蓋の密書は建安(けんあん)13(208)年11月21日付だった。
(05)長江の南岸 周瑜の本営
すでに黄蓋や甘寧も発ち、後には蔡和(さいか)がひとり残っていた。すると突然、一隊の兵士がやってきて周瑜の召しだと言い、彼を囲んで捕縛してしまう。
周瑜は蔡和を見るやいな、こう言って剣を抜き払った。
「汝(なんじ)は曹操の間諜(かんちょう)であろう。出陣の血祭りに軍神(いくさがみ)に供えるにはちょうどよい首と、今日まで汝の胴に持たせておいたが、もうよかろう。いざ祭らん」
蔡和は哀号し、甘寧や闞沢も自分と同腹なのに、とわめく。
周瑜は笑い、「それはみな自分がさせた謀略(はかりごと)である」と耳も貸さず、一閃(いっせん)の下に屠(ほふ)った。
管理人「かぶらがわ」より
周瑜と諸葛亮が次々に命を下していた第164話。時代に合わない地名が数多く出てきたり、劉備軍の配置がほとんど創作だったりと、いろいろ捉えにくいところがありました。
曹操を見逃す可能性が高いと感じながら、関羽を華容道へ派遣するなんて――。こういうことは実際にはあり得ないでしょうね。

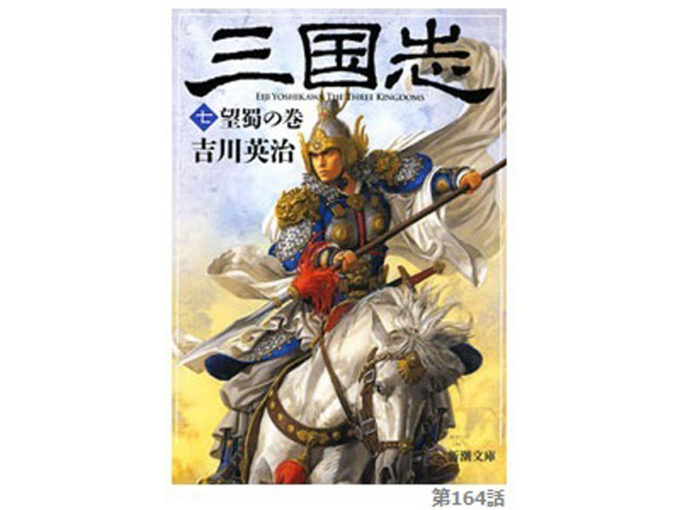














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます