ごたび捕らえられ、ごたび諸葛亮(しょかつりょう)に放された孟獲(もうかく)。とうとう蛮都の銀坑山(ぎんこうざん)まで戻り、八納洞長(はちのうどうちょう)の木鹿王(もくろくおう)に協力を求めるべく、義弟の帯来(たいらい)を遣わす。
だが、三江城に置いた朶思大王(だしだいおう)の敗報が伝わると、孟獲は焦りの色を濃くし、一族を集めて評議を開く。そのとき屛風(びょうぶ)の陰から、妻の祝融(しゅくゆう)の笑う声が聞こえてきた。彼女が言うには――。
第272話の展開とポイント
(01)禿龍洞(とくりょうどう) 諸葛亮の本営
諸葛亮は五度(ごたび)孟獲を放したが、放つに際して言った。
「汝(なんじ)の好む土地で、汝の望む条件で、さらに一戦してやろう。しかし今度は、汝の九族まで滅ぼすかもしれないぞ。心して戦えよ」
弟の孟優(もうゆう)と朶思大王も同時に許す。3人は馬をもらい、恥ずるがごとく逃げ帰った。
★ここで孟獲五放。
(02)銀坑山
そもそも孟獲の本国、南蛮中部の蛮都は、雲南(うんなん。昆明〈こんめい〉)より遥か南にあった。蛮都の地名を銀坑洞と呼び、沃野広く、三江の交差地に位置しているという。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第90回)によると、瀘水(ろすい)・甘南水(かんなんすい)・西城水(せいじょうすい)の3本の川が合流しているため、三江と称するという。
これを現今の地図で測ると、もとより1,700年前の地名は残されていないが、南方大陸の河流から考察するに、仏領(フランス領)印度支那(インドシナ)のメコン河の上流、また泰国(タイこく)のメナム河の上流、ビルマのサルウィン河の上流などは、ともに遠くその源流を雲南省・西康省(せいこうしょう)・西蔵(チベット)東麓(とうろく)地方から発し、ちょうど諸葛亮が遠征した当時の蛮界を貫いているのではないかと思われる。
要するに、現今のビルマ・仏印・雲南省境の辺りと想像して大過なかろうかと思う。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「『明史』によれば、実際には現在の雲南省大理市(だいりし)付近を指す」という。
今や孟獲は敗れ敗れて、望むところの蛮都まで帰ってきた。緑沙銀壁の蛮宮には、四方の洞主や酋長(しゅうちょう)が数千人も集まり、まさに世界滅亡の日でも来たような異変を語っている。
ほとんど蛮土開闢(かいびゃく)以来の大評議で、日々議を重ねていたが、時に孟獲の夫人の弟にあたる八番部長(はちばんぶちょう)の帯来が、こう提唱した。
★八番について、『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「八番九十三甸は地域名。八番とは本来、元代に貴州省恵水県(けいすいけん)一帯に居住していた少数民族の総称」だという。
「これは西南の熱国に威勢を振るっている、八納洞長の木鹿王に力を借りるしかない」
「木鹿王はいつも大象に乗って陣頭に立つや、不思議な法力をもって風を起こし、虎豹(こひょう)・豺狼(さいろう)・毒蛇・悪蝎(あっかつ。質〈たち〉の悪い蝎〈サソリ〉)などの類いを眷族(けんぞく)のように従えて敵陣へ進む」
「また手下には3万の猛兵があり、今やこの王の武威は隣界の天竺(てんじく。インド)をも恐れさせている。わが蛮都とは対立していたが、こちらから礼を低うして礼物を供え、蛮界一帯の大難をつぶさに訴えれば、彼も蛮土の人、必ず加勢してくれるに違いない」
★ここは一応、原文通り「礼をひく(低)うし」としておくが、この用法は微妙。「辞を低うし」ならわかるが、「礼を低うする」と無礼になるのでは?
満堂の賛礼を受け、孟獲は帯来に使いを命ずる。おそらくは現今のビルマ印度地方の一勢力であったのだろう。
銀坑山の蛮宮の前衛地として、三江の要地に三江城がある。孟獲はそこへ朶思大王を込めて、前衛の総大将たることを命じた。
(03)三江城
蜀の大軍は日を経て三江に着く。実に長途を克服してきたことは、戦い以上の戦いであっただろう。三江城は三面が江水に続き、一面は陸に続いている。
諸葛亮は、まず趙雲(ちょううん)と魏延(ぎえん)の兵に命じて城下へ迫らせ、ひと当てあててみる。さすがに城は堅く、蛮軍とはいえ、ここの兵もまた精鋭だった。
城壁の上には無数の弩(ど)を据えている。それは一度に十箭(じっせん。10本の矢)を射ることができ、鏃(やじり)には毒が塗ってあった。これに当たると負傷ということはない。皮肉が爛(ただ)れ、五臓を露出して死ぬのである。
城への攻撃は三度に及んだが、諸葛亮は四度目に、サッと10里ほど陣を退いてしまう。
「蜀兵は毒弩を恐れて陣を退いた」
南蛮軍は誇り驕(おご)る。7日、10日と日を経るに従い、彼らの単純な思い上がりは、いよいよ敵を見くびってきた。
(04)三江城の近郊 諸葛亮の本営
諸葛亮は天候を見ていたが、このところ強風の日が続いていた。砂交じりの猛風は明日もまだ続きそうである。
諸葛亮の名をもって、諸陣地に布告が掲げられた。
「明夕の初更(午後8時前後)までに、各部隊の兵はひとり残らず、おのおの一幅の襟(きん。衣服)を用意せよ。怠る者は首を斬らん」
翌日の夕方、どういうことなのかわからなかったが、厳令なので隊将から歩卒に至るまで、一衣の布を手に怪しみながら待っていた。
すると諸葛亮が将台に立ち、三命を発した。
一、携えたるおのおのの襟に足元の土を搔(か)き入れて土の囊(ふくろ)となせ。
二、兵ひとりに土囊(どのう)ひとつの割で次々と令に従って行動せよ。
三、三江城の城壁下に至らば、土囊を積んで捨てよ。土囊の山が壁の丈と等しからば、ただちに踏み越え城内に入れ。疾(と)くと早く入りたる者には重き恩賞があるぞ。
みなこのとき初めて諸葛亮の考えを知る。その勢20余万、蛮土の降参兵を加うること1万余、一兵ごとに一囊を担い、早くも三江城の城壁へ迫った。
★井波『三国志演義(6)』(第90回)では、10余万の蜀兵および1万余りの降伏した蛮兵とあった。
(05)三江城
乱箭(箭〈矢〉が乱れ飛ぶ様子)や毒弩も平気なように、雲霞(うんか)のごとき大軍が一度に寄せたので、その勢力の1千分の1も射倒すことはできない。
見る間に土囊の山が数か所に積まれた。兵員と等しく20万個という数である。いかなる高さであろうと届かぬはない。
魏延・関索(かんさく)・王平(おうへい)らの手勢は先を争い、城壁の間へ飛び降りた。担ぎ上げた土囊を投げ込み、ここも難なく通路となる。
蛮軍は釜中(ふちゅう)の魚のように右往左往して抗戦のすべを知らない。その多くは銀坑山方面へ逃げ、あるいは水門を開いて江上へあふれ出す者もある。
生け捕りは無数と言ってよい。例により、彼らには諭告を与え仁を施す。そして城中の重宝を開き、ことごとく三軍に分け与えた。
朶思大王は、このときの乱軍の中で討たれたといううわさがある。口ほどにもない哀れな最期だった。
(06)銀坑山
三江城の敗報を聞き、孟獲は色を失う。一族を集めて評議中も転動惑乱、なすことも知らないありさま。
すると後ろの紗(しゃ)の屛風の陰で、クツクツ笑った者がある。一族の者がのぞいてみると、孟獲の妻の祝融が牀(しょう。寝台)に寄り、長々と昼寝をしていた。
猫のようにかわいがり、日ごろから部屋で飼い馴(な)らされている牡獅子(オジシ)も、彼女の腰の辺りに顎を乗せ、睡眼を半ば閉じている。
そのまま評議を続けていると、また隣室でクツクツ笑う。皆が耳障りな顔をしたので、夫として孟獲も黙っておられず、ついに座から叱りつけた。
祝融は牡獅子とともに牀から起きるや、一族の者には目もくれず、夫の孟獲に頭から怒鳴り返す。
「何ですっ、あなたは! 男と生まれながら意気地もない。蜀の勢の10万や20万蹴散らせないで、この南蛮に王者だと言っていられますか? 女でこそあれ、私が行けば、孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)などにこの国を踏みにじらせておきません」
この夫人は、上古の祝融氏の後裔(こうえい)だと言われる家から嫁いできて、よく馬に乗り、よく騎射をする。わけて短剣をつかんで飛ばせば百発百中という秘技を持っていた。
★井波『三国志演義(6)』の訳者注によると、「(祝融氏は)伝説の5人の聖天子のひとりである顓頊(せんぎょく)の息子。火の神」という。
その代わり細君天下とみえ、孟獲はそう言われると、ぺしゃんこになった顔つきでひと言もない。一族の者たちも事実として敗戦に敗戦を重ねているので、ともに沈黙していた。
(07)銀坑山の郊外
翌日、祝融は巻き毛の愛馬に乗り、髪をさばいて裸足のまま、赤き戦衣に珠をちりばめた胸当てを着け、陣頭に立つ。背に7本の短剣を挟み、1丈余の矛を抱え、炎のごとく戦火の中を駆け回っていた。その矛にかかり、おびただしい蜀兵が倒れる。
張嶷(ちょうぎ)は、この不思議な敵に後ろから迫った。しかし突如、天空から飛んできた1本の短剣が股(もも)に立ち、馬から逆さまに転げ落ちる。祝融は手下に縛るよう言い捨て、次の敵へ打ちかかっていた。
馬忠(ばちゅう)もまた彼女を追い、同じように2本の短剣を投げつけられ、その1本を馬の顔に受けたため、やはり落馬して蛮軍に捕らえられる。この日の戦況は甚だしく蛮軍が振るい、急に孟獲も躍り立って喜びだす。
(08)銀坑山
祝融は、捕らえた張嶷と馬忠を首にして、士気を鼓舞するよう言ったが、孟獲はこう応じた。
「いや、俺も五度捕らわれて孔明から放されている。すぐにこいつらを殺すと、いかにも俺が小量のようだ。孔明を生け捕った後、並べておいて首を斬ろう」
こうしてふたりを生かしておき、ときどき見ては笑い楽しんでいた。
(09)諸葛亮の本営
諸葛亮は張嶷と馬忠の身を案じてはいたが、おそらく孟獲は殺すまいとも語っていた。そして救出策を考え、趙雲と魏延に計を授ける。
(10)銀坑山の郊外
炎熱下の交戦は日々続いていた。その中に炎の飛ぶを見れば、必ず祝融夫人の姿である。趙雲は近づいて決戦を挑む。
だが祝融もさすがで、この敵にはかなわぬと思うと、短剣を飛ばした隙にサッと逃げてしまう。豪勇の趙雲も嘆じていた。
「まるで梢(こずえ)の鳥を追いかけているようだ。どうも捕れぬ……」
翌日、魏延は陣前に現れず、雑兵を出して揶揄(やゆ)させる。怒った祝融が追いかけてくるのを誘導し、頃合いを見て躍り出た。彼女は短剣を投げ、そのまま例のごとく帰り去ろうとする。
そこへ一方から趙雲が現れ、鼓を鳴らさせて囃(はや)した。ついに祝融は感情のまま蜀軍の中に駆け込む。わざと蜀軍は逃げ崩れ、彼女が止まるとまた、悪口三昧(ざんまい)を叩く。
次第に山間へと誘い込み、予定の危地を作るや、ドッと八面から覆い包み、祝融を生け捕ることに成功した。
(11)諸葛亮の本営
諸葛亮は孟獲のもとへ使いを遣る。
「汝のおかみさんは予の陣に来ている。張嶷、馬忠と交換せん」
孟獲は驚き、すぐに二将を帰してきた。諸葛亮も、祝融に酒を飲ませて送り帰す。彼女は少ししおれていたが、1斗の酒を飲んだ揚げ句、縄を解かれると非常にはしゃぎだし、孟獲と似たような大言壮語を残して帰った。
管理人「かぶらがわ」より
これで孟獲、五擒五放。孟獲の妻の祝融は正史『三国志』に見えません。しかし、孟獲の妻というポジションの女性を登場させたことは、とても興味深いと思います。
ここで描かれた女傑という設定もおもしろいですし、占いに長けた女性にするとか、かえって南蛮には似つかない深窓の女性(がいるのかわかりませんけど)にするなど……。このあたりはいろいろな創作の入り込む余地が大きいと感じました。

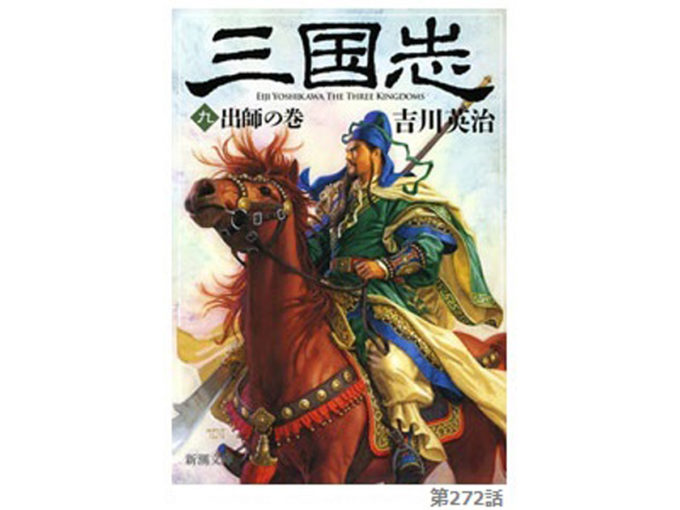













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます