太和(たいわ)4(230)年7月、体調も回復した曹真(そうしん)が朝廷に姿を見せ、曹叡(そうえい)から蜀攻めの許可を取りつける。魏軍40万が蜀の剣門関(けんもんかん)に押し寄せたのは、それから10か月後のことだった。
ところが諸葛亮(しょかつりょう)は、王平(おうへい)と張嶷(ちょうぎ)にわずか1千騎ずつをもって、陳倉道(ちんそうどう)の険に拠り、難所を支えよと命ずる。敵の40万に対して味方は2千、さすがにふたりは困惑を覚えるが――。
第294話の展開とポイント
(01)洛陽(らくよう)
(魏の太和4〈230〉年の)秋7月、曹真は健康を回復して朝廷に姿を見せ、表を奉り、このように勧める。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第99回)では明確だったが、吉川『三国志』では、前年(229年)の祁山(きざん)夏の陣と称する戦いから1年以上経ったことがわかりにくかった。
「秋涼しく、人馬安閑。聞くならく諸葛亮病み、漢中(かんちゅう)に精鋭なしという。蜀、いま討つべし。魏の国患、いま除くべし」
曹叡が諮ると、侍中(じちゅう)の劉曄(りゅうよう)はすぐに答えた。
「討たざれば百年の悔いです」
(02)洛陽 劉曄邸
劉曄が屋敷に帰ると、朝廷の武人や大官が、入れ替わり立ち替わり来て彼をただす。
「この秋(とき)こそ大兵を起こし、年来の魏の憂いたる宿敵の蜀を討つのだと、天子(てんし。曹叡)は仰せられている。そのことは本当でしょうか?」
すると劉曄は一笑の下に否定し去り、まるで顔でも洗ってきたまえ、と言わぬばかりの返事をした。
(03)洛陽
楊曁(ようき)という一官人が、劉曄の発言の矛盾をいぶかり、今度は直接、曹叡に尋ねた。
曹叡は、楊曁から劉曄の発言を聞くと、さっそく召して詰問する。
「先には朕に蜀を討つべしと勧めながら、宮廷の外では反対に、討つべからずと唱えているそうだが、汝(なんじ)の本心はいったいどこにあるのか?」
劉曄は、けろりと答えた。
「何かのお聞き違いでございましょう。臣の考えは決して変わっておりません」
「蜀山蜀川の険を冒し、無碍(むげ)に兵馬を進めるなどは、我から求めて国力を消耗(しょうこう。「しょうもう」は慣用読み)し、魏を危うきへ押し込むようなものです」
「彼から来るなら仕方がありませんが、我から攻めるべきではありません。蜀、討つベからずであります」
曹叡は妙な顔をして、彼の弁に任せていた。やがて話がほかへ逸れると、侍座に立っていた楊曁はどこかへ立ち去る。
すると、劉曄は声を潜めて言った。
「まだ陛下は、兵法の玄機(奥深い道理)をお悟りになっておられないとみえます。蜀を討つことは大事中の大事です。何ゆえ楊曁や宮中の者に、そのような秘事を御自らお漏らしになられましたか」
曹叡は初めて悟った。
そこに、荊州(けいしゅう)へ行っていた司馬懿(しばい)が帰ってくる。彼も劉曄と同意見だった。荊州ではもっぱら呉の動静を視察してきたのである。
司馬懿の観るところでは、「呉は蜀を助けそうに見せているが、それはいつでも条約に対する表情だけで、本腰のものではない」という見解が確かめられていた。
(04)剣門関
号して80万、実数40万の大軍が、蜀境の剣門関へ押し寄せたのは、わずか10か月後のことである。洛陽の上下があっけに取られたほど、迅速かつ驚くべき大兵の動きだった。
★剣門関は、『三国志演義』(第99回)の原文では「剣閣(けんかく)」とある。
★井波『三国志演義(6)』の訳者注によると、「剣閣は漢中の西南、すなわち漢中と成都(せいと)の中間に位置しており、漢中攻略のために魏軍がその地を経由することはあり得ない」という。
なお訳者の井波先生は、ここにある剣閣(剣門関)を採らず、「(魏軍が)漢中攻略に向かった」という表現に改められていた。さらに「その他の箇所でも地理的な誤りが少なからず見られるが、あまりに煩雑になるので、いちいち訂正は行わなかった」と断っておられた。
★また「わずか10か月後のこと」という記述は、いつを起点に数えたものなのか、よくわからなかった。
(05)成都
このとき幸いにも、すでに諸葛亮の病は回復していた。
「血を吐いて昏絶(こんぜつ)す」というと、よほどの重体か不治の難病にでもかかったように聞こえるが、「血を吐く」も「昏絶」も、原書のよく用いている驚愕(きょうがく)の極致を表す形容詞であることは言うまでもない。
諸葛亮は王平と張嶷を招き、こう命ずる。
「汝らはおのおの1千騎を引っ提げ、陳倉道の険に拠って、魏の難所を支えよ」
★井波『三国志演義(6)』(第99回)では、王平と張嶷のふたりで1千の軍勢をひきいていた。
ふたりは啞然(あぜん)とした。いや、悲しみわなないた。敵は実数40万という大軍。わずか2千騎でどうして食い止められよう。死にに行けというのと同じだと思った。
その様子を察した諸葛亮は、自分の言に説明を加えた。
「このごろ天文を観ていると、太陰畢星(ひっせい。二十八宿)に濃密な雨気がある。おそらくここ十年来の大雨が、この月中にあるのではないかと考えられる」
★井波『三国志演義(6)』(第99回)では、「昨夜、天文を観察したところ、畢星が太陰の領域に入るのが見えたゆえ、今月のうちに必ず大雨が続くに相違ない」となっており、こちらの表現のほうがわかりやすい。
「魏軍の何十万騎が剣門関をうかがうも、陳倉道の隘路(あいろ)に途上の幾難所。加うるにその大雨に遭えば、とうてい軍馬を進め得るものではない。ゆえに、我はあえてその困難にあたる要はない」
「まず汝らの軽兵を差し向けておき、のち敵の疲労困憊(こんぱい)を見澄ましてから、一度に大軍を押し進めて討つ。やがて予も漢中へ行くであろう」
(06)陳倉道
王平と張嶷は軽兵2千をひきいて到着。高地を選んで長雨のしのぎを考慮し、1か月余の食糧を準備して滞陣した。
魏の40万騎は、曹真を大司馬(だいしば)・征西大都督(せいせいだいととく)に頂き、司馬懿を大将軍(だいしょうぐん)・副都督(ふくととく。征西副都督)に、そして劉曄を軍師とし、壮観極まる大進軍を続けてくる。
ところが陳倉道へ入ると、道々の部落は例外なく焼き払われており、籾(モミ)一俵、鶏一羽も得られない。
なお数日進むうち、司馬懿は突然、曹真や劉曄にこう言いだした。
「これから先へは、もう絶対に進軍してはなりませぬ。昨夜、天文を案じてみるに、どうも近いうちに大雨が来そうです」
曹真も劉曄も疑うような顔をしていたが、司馬懿の言である。万一のことも考慮し、その日から前進を見合わせる。
竹や木を切って急ごしらえの仮屋を作り、十数日ほど滞陣していると、果たして、今日も雨、翌日も雨。明けても暮れても、雨ばかりの日が続いた。
大雨は30余日も続き、病人や溺死者が続出し、食糧も途絶える。後方への連絡もつかず、40万の軍馬はここに水膨れとなってしまいそうだった。
(07)洛陽
このことが洛陽に聞こえたため、曹叡の心痛もひとかたではなかった。壇を築いて、「雨、やめかし」と天に祈ったが、そのかいも見えない。
太尉(たいい)の華歆(かきん)、城門校尉(じょうもんこうい)の楊阜(ようふ)、散騎黄門侍郎(さんきこうもんじろう)の王粛(おうしゅく)らは、初めから出兵に反対だったので、民の声として曹叡を諫めた。
「早々、師(いくさ)を召し還したまえ」
(08)陳倉道 曹真の本営
曹叡の詔(みことのり)は陳倉に達した。そのころようやく雨は上がっていたが、全軍の惨状は形容の辞もないほどである。勅使は泣き、曹真と劉曄も泣いた。
司馬懿は慙愧(ざんき)して言う。
「天を恨むよりは、自分の不明を恨むしかありません。このうえは帰路に際して、再びこの兵を損ぜぬようにするしかありません」
水の引いた谷々に入念に殿軍(しんがり)を配し、主力の退軍もふた手に分け、一隊が退いてから次が退くというふうに、あくまで緻密に引き揚げた。
(09)赤坡(せきは)
諸葛亮は蜀の主力を赤坡まで出し、この秋晴れに、魏軍撤退の心地よい報告を受け取る。
★『三国志』(蜀書・後主伝)によると、赤坡は正しくは赤阪(せきはん)。
だがこう言って、少しも意(こころ)を動かさなかった。
「追えば必ず仲達(ちゅうたつ。司馬懿のあざな)の計にあたろう。この天災による敗れを、蜀に報復し、面目を立てて帰らんとしている必勝の心ある者へ、我から追うのは愚である。帰るに任せておけばよい」
管理人「かぶらがわ」より
進攻ルートこそ違いますが、魏軍が三路から漢中へ攻め寄せた際、大雨のために撤退したことは史実に見えます。このときの魏軍の実数が40万だった、というのは根拠のない数字でしょうが、予想外に大きな損害が出たことは想像できますね。

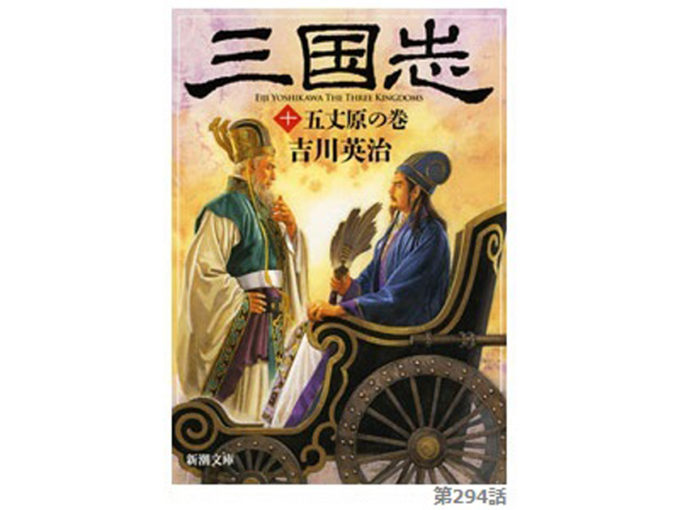













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます