ひとまず祁山(きざん)から引き揚げ、漢中(かんちゅう)への帰還命令を出す蜀の諸葛亮(しょかつりょう)。魏の張郃(ちょうこう)は追撃を強く願い出、ついに司馬懿(しばい)の許しを得た。
張郃ひきいる精兵3万に続き、司馬懿自身も、中軍の5千騎をひきいて追撃にかかる。しかしこれこそ、諸葛亮が待ち望んでいた動きだった。ほどなく両軍の間で死闘が繰り広げられ――。
第293話の展開とポイント
(01)祁山 諸葛亮の本営
先に街亭(がいてい)の責めを負うて、諸葛亮は丞相(じょうしょう)の職を朝廷に返していた。
費禕(ひい)がもたらした成都(せいと)からの詔書は、その儀について、再び旧の丞相の任に復すべしという、彼への恩命にほかならない。
諸葛亮は依然として固辞したが、「それでは、将士の心が奮いません」という人々の再三の勧めに従い、ついに朝命を拝して、勅使の費禕が都へ帰るのを見送った。
それからまもなく、「我々もひとまず帰ろう」と突然、漢中への総引き揚げを発令する。
(02)祁山 司馬懿の本営
司馬懿は蜀軍の動きを聞いたものの、「追わば必ず孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)の計にあたろう。守って動くな」と、かえって固く自戒していた。
しかし、張郃らはむずむずして言う。
「敵は兵糧に詰まったのです。追撃して完滅を下すのはこのときではありませんか?」
司馬懿は諸将をなだめた。
「いやいや。漢中は去年も豊作だったし、今年も麦は熟している。兵糧がないのではなく、ただ運輸の労に困難しているにすぎない。量るに孔明は自ら動いて、我を動かさんと誘うものであろう。しばらく物見の報告を待て」
情報は次々に届く。
「諸葛亮の大陣、30里往いてしばらく留まる」と聞こえたが、それ以後は10日ばかり何の変化も伝えてこない。するとやがて、「蜀軍すべて、さらに遠く行く」と知らせてくる。
ここで司馬懿が言った。
「見よ。30里ごとに計をうかがい、変を案じ、ひたすら我の追撃を誘っている。危うし危うし。滅多に孔明の好みに落ちるな」
翌日も30里退いたという報があり、さらに2日ほど置いて、「蜀軍はまた30里行軍して止まっております」との物見の言葉。
幕将たちの観察と司馬懿の見方とは、だいぶ相違があった。幕将たちは躍起になり、再び司馬懿に迫る。
「諸葛亮の退く手口を見ると、緩歩退軍の策です。一面退却、一面対峙(たいじ)の陣形を取りながら、極めて平凡な代わりに、極めて損害のないような、正退法(しょうたいほう)によっているものでしかありません。これを見過ごして討たずんば、天下の笑いぐさになりましょう」
そうまで言われると、司馬懿もいささか動かされた。わけて張郃は極力、追撃を望んでやまない。
ついに司馬懿は、にわかに考えを一転させて、張郃に言った。
「しからばご辺(きみ)は、最も勇猛なる一軍をひきいて追え。ただし、途中で一夜を野営して、兵馬の足を十分に休ませ、しかるのち猛然と蜀軍へ突っ込め。儂(み。我)もまた強兵をすぐって第二陣に続くであろう」
張郃の精兵3万、続いて司馬懿の中軍5千騎。弦を離れたごとく、急追を開始する。
(03)蜀軍を追撃中の司馬懿と張郃
魏軍は速度をピタと止めると、全軍その日の疲れを休め、明日の英気を養う。概すでに敵を吞むものがあった。
(04)引き揚げ途中の諸葛亮
かくと殿軍(しんがり)の物見から聞くと、諸葛亮は初めて、薄い微笑を面に持つ。生唾を吞むように、待ちに待っていたものなのである。
その夜、諸葛亮は諸将を集めて、悲壮なる訓示をなした。
「この一戦の大事は言うまでもない。蜀の運命を決するは、まさに今日である。卿(けい)らみな命を捨てて戦え。味方ひとりに敵数十人を引き受けて当たるほどな覚悟を持て」
さらに、こう言って座中を見回す。
「この強敵の背後へ迂回(うかい)して、かえって敵の後ろを脅かす良将が欲しい。それには誰がよいか? 自らこの必死至難な目的にあたり、よく成し遂げんと名乗って出る者はいないか?」
誰も答える者がない。我こそと名乗り出て、その至難に赴こうという者がない。それもそのはず。諸葛亮は、この大事に赴く者は、知勇胆略の兼ね備わっている良将でなければ用いがたい、と前提しているのである。
諸葛亮の眸(ひとみ)は、魏延(ぎえん)の顔を見た。だが、その魏延すら首を垂れて無言だった。
すると王平(おうへい)が進み出て、思い切った語調で言う。
「丞相。それがしが赴きましょう」
諸葛亮は、あえて喜びもせず反問した。
「もし仕損じたらどうするか?」
王平は悲壮な面色で答える。
「成功するや否やなどは考えておりません。ただいま丞相のお言葉には、この一戦こそ、蜀の興亡にも関わる大事と仰せられましたゆえ、不才を顧みる暇(いとま)なく、ただ一死をもって国に報ぜんとするのみです」
諸葛亮は念を押して尋ねた。
「王平は平時の良才、戦時の忠将。そのひと言でよし。しかし、魏の大軍は二段に分かれ、前軍の張郃と後陣の司馬懿の間は、まさにおのずから死地そのものだ」
「わが命ずるところは、その死地の間に入って戦えという無理な兵法なのである。いわゆる捨て身の戦いだ。それでもなお赴くか?」
「断じて赴きます」と王平。
ここで王平の副将として赴く者を、もうひとり募る。前軍都督(ぜんぐんととく)の張翼(ちょうよく)が名乗って出たものの、諸葛亮はこう言った。
「せっかくだが、敵の副将の張郃は万夫不当の勇。張翼では相手に立てまい」
これを聞いた張翼は、残念がって奮い立つ。
「丞相には何事を仰せある。それがしとて、死をもって当たれば恐るる者を知りません。もし卑怯(ひきょう)があれば、後にこの首をお刎(は)ねください」
諸葛亮は張翼の起用を認めると、王平とふたりに命じた。
「それほど言うならば、望みに任せてやろう。王平と汝(なんじ)とおのおの1万騎を連れて、今宵のうちに密かに道を引き返し、途中の山に潜め」
「そして明日、魏の前軍が我を追撃にかかり、通り過ぎるのを見たら、司馬懿の第二軍が続く前に、その間へ突として打って出よ」
「王平は張郃軍の後ろへ掛かり、張翼は司馬懿の出ばなへぶつかって戦え。後は予に別の計もあれば、味方を思わず、その1か所を一期の戦場として死志を励め」
王平と張翼は令を受けると、諸葛亮の前に立ち、「では、お別れいたします」と、暗に死別を告げて、すぐにその行に就いた。
ふたりの後ろ姿を見送ると、続いて諸葛亮は、姜維(きょうい)と廖化(りょうか)を呼ぶ。それぞれに3千騎を授けたうえ、王平と張翼の後を追い、戦場となるべき付近の山上へ登り、待機せよと言い渡す。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第99回)では、それぞれが3千の精鋭をひきいたのか、ふたりで3千の精鋭をひきいたのか、イマイチはっきりしなかった。
そしてふたりが行く前に、「ここぞと戦機の大事を見極めたら、この囊(ふくろ)に聞け」と、錦の囊を手渡した。いわゆる知囊(ちのう)である。
このあと諸葛亮は、呉班(ごはん)、呉懿(ごい)、馬忠(ばちゅう)、張嶷(ちょうぎ)の順に呼び、こう命ずる。
「その方たちは正陣をもって、寄せきたる敵の前面に当たれ。壁となって防ぎ戦え。しかし明日の魏軍の猛気は、おそらく必殺必勝の気で来るであろうゆえ、無碍(むげ)に支えれば必定、支えきれなくなる」
「一突一退。緩急の呼吸を計って、やがて関興(かんこう)の一軍が打って出るのを見たら、そのとき初めて、一斉に奮力を挙げて死戦せい」
諸葛亮は、最後に関興に命じた。
「汝は一軍をもって付近の山間に潜み、明日、予が山上にあって紅の旗を動かすのを見たら、一度に出て敵とまみえよ。必ず日ごろの戦いと思うな」
★井波『三国志演義(6)』(第99回)では、このとき関興がひきいていたのは5千の精鋭。
かくてすべての手はずが整うと、諸葛亮は一睡を取り、黎明(れいめい)早くも山上へ登っていく。この日、朝雲は低く、日輪は雲表を真紅に染め、いまだ万地の血にならない前に、天すでに血のごとしであった。
(05)蜀軍を追撃中の魏軍
蜀の馬忠・張嶷・呉懿・呉班らが四陣を展開して、手ぐすね引いて待つところへ、魏の張郃と戴陵(たいりょう)の軍勢3万は、ほとんど鎧袖一触(がいしゅういっしょく)の勢いで当たる。
時は(魏の太和3〈229〉年の)大夏6月、人馬は汗に濡れ、草は血に燃え、一進一退、叫殺は天に満つばかり。蜀軍は時に急に、時に緩に、やがて約20里も崩れ、さらに50里も追われた。
朝から急歩調で追撃を続け、かつ攻勢を緩めずにあった魏軍は、炎日と奮闘にようやく疲れを示す。このとき、日も中天の午(うま)の刻(正午ごろ)に近かった。
すると一峰の上で、突として紅の旗が動く。諸葛亮の下せる大号令の印である。今か今かと待っていた関興の5千騎は、疾風(はやて)のごとく谷の内から出て、魏勢の横を突いた。
いったん退いた蜀の四軍も、たちまち翻って、張郃と戴陵に大反撃を巻き起こす。凄愴(せいそう)なる血の雲霧が、目の届く限りの山野にみなぎった。屍山(しざん)血河。馬さえ敵の馬をかんで闘い狂う。
蜀軍の損害も甚だしいが、魏の精兵もこの一刻においておびただしく討たれる。そのうえ、蜀の王平と張翼のふた手が後ろへ回って出たため、魏軍3万はことごとく壊滅し去るかと危ぶまれた。
そこへ魏の司馬懿ひきいる主力が着く。蜀の王平と張翼は、初めから進んで危地に入っていたので、「諸軍、命を捨てて戦え!」と、この新手に向き直って奮迅する。
時に蜀の姜維と廖化は、「今こそ、あれを……」と、かねて諸葛亮から授けられていた錦の囊を解いてみた。
令札には一行の命令がしたためてある。
「汝ラ二隊ハココヲ捨テテ司馬懿ガ後ニセル渭水(いすい)ノ魏本陣ヲ突ケ」
山づたい、峰づたいに、姜維と廖化の二隊は、逆に渭水方面へ駆けた。
これを知った司馬懿は色を失い、にわかに総退却を命ずる。すなわち司馬懿の主力以下、眼前の惨敗を打ち捨てて、急きょ渭水の固めに引き返したのである。
さしもの大戦も暮れた。夜に入るも月は赤く、草に伏す両軍の屍(しかばね)は、実に、万余の数を超えていたと言われる。
「勝った。わが軍の勝ちだ!」
魏は言った。蜀も唱えた。要するに損害は互角だった。またその戦力も伯仲していたものと言えよう。けれど、この一戦で魏将の討たれた数は蜀以上のものがあり、史上、記すに暇なきほどであると言われている。
(06)引き揚げ途中の諸葛亮
しかし、このすぐ後、蜀にも一悲報が来た。それは、先に負傷して成都へ帰っていた張苞(ちょうほう)の死である。破傷風を併発して、ついに没したという知らせが届いた。
★張苞の負傷については前の第292話(03)を参照。
諸葛亮は声を放って泣いたが、とたんに血を吐いて昏絶(こんぜつ)する。その後、10日を経て、ようやく少し元気を取り戻したものの、年来の疲れも出たのか、容易に以前のような健康には返らなかった。
諸葛亮はこう戒め、旌旗(せいき)粛々と漢中へ帰る。
「悲しむな。予の憂いを陣上に表すな。われ病むことを、もし仲達(ちゅうたつ。司馬懿のあざな)が知ったら、大挙して再びこれへ来るだろう」
(07)渭水 司馬懿の本営
このことを後で知った司馬懿は、機を悟らなかったことを大いに悔い、顧みて言った。
「彼の神謀は到底、人知をもって測りがたいものがある」
以後いよいよ要害を固め、洛陽(らくよう)へ帰って曹叡(そうえい)に委細を奏する。
(08)成都
そのころまた諸葛亮も、久しぶりに成都へ戻って劉禅(りゅうぜん)を拝し、丞相府に退き、しばし病を養っていた。
管理人「かぶらがわ」より
魏軍の追撃を蜀軍が迎え撃つ形の大激戦は、両軍で万余の戦死者を出しての痛み分け。ただ、損害が同程度だったのなら、実際のところは魏の勝利と言えるのかもしれません。
それにしても、今回の諸葛亮の戦法はきつかった。敵の前軍と後陣の間に入って戦えって、そんな無茶な……。まさに文字通りの死地でした。

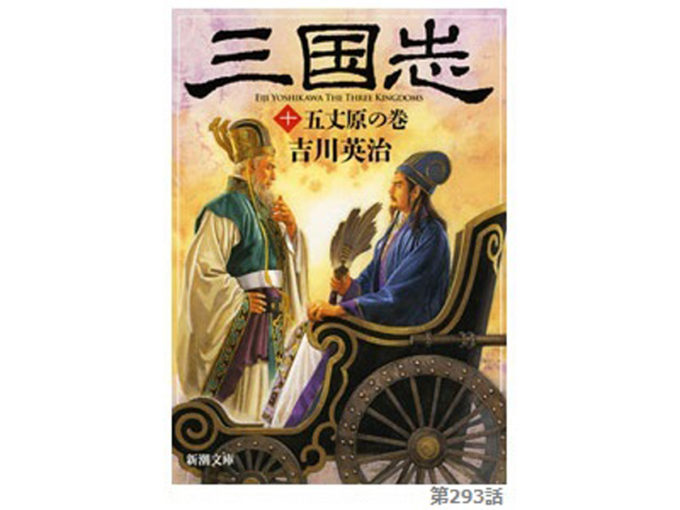














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます