次男の曹彰(そうしょう)が援軍をひきいて合流したことにより、ここしばらく劉備軍(りゅうびぐん)に押されっぱなしだった曹操(そうそう)も、気を取り直す。
ところが、斜谷(やこく)の関城(かんじょう)で夕食を取っていた際、曹操がつぶやいたひと言から、楊修(ようしゅう。楊脩)が命を落とすことになる。
第224話の展開とポイント
(01)斜谷
ここまで敗走一路をたどってきた曹操も、わが子の曹彰に行き会い、新手の5万の兵を見ると、俄然(がぜん)、鋭気を新たにする。
曹操は斜谷に拠り、この間からの敗辱を一戦にそそごうと考え直す。かくて戦の様相はここに改まり、魏蜀両軍とも整備と休養を新たにし、第二次の対戦となった。
劉備は、曹彰が出てきたときに迎え撃つ将を募る。すると孟達(もうたつ)と劉封(りゅうほう)が等しく進み出た。
しかし孟達は、劉備の養子である劉封も望んで出たため、少し遠慮する様子を示す。それでも劉備はふたりに命じ、おのおの5千騎をひきいて先鋒の左右に控え、曹彰が出たら思い思いに功名せよと言った。
やがて斜谷に拠る魏の一軍が、平野へ戦列を布いたかと思うと、曹彰がただ一騎で陣列を離れ、大声で劉備を差し招く。
左翼の孟達が、ここは劉封に譲るべきだと考えて控えていると、右翼の劉封は、たちまち駒を飛ばして出た。だが、曹彰に近づいて10合とも戦わないうちに、その一騎討ちは誰の目にも曹彰の勝利とわかった。
孟達は急に駆け出し、劉封と入れ替わってぶつかる。曹彰は孟達を振りのけつつ、劉封を辱めながら追いかけた。
ところが、ここで曹彰のひきいる手勢が後ろのほうから崩れだす。驚いて引き返すと、蜀の馬超(ばちょう)や呉蘭(ごらん)などが、いつの間にか斜谷のふもとへ出て退路を断とうとしている。
曹彰は父に似て、兵機を見るに敏だった。すでに受けた多少の損害が致命とならないうちにサッと軍をまとめ、呉蘭の陣中を蹴散らし、首尾よく斜谷の本陣へ引き揚げた。
しかもその途中、道を遮った呉蘭を馬上のまま一閃(いっせん)に薙(な)ぎ払い、これを討ち取って帰る。
劉封は面目を失う。劉備に合わせる顔もない気がした。ただ孟達に対しては、「自分の負けが余計にぶざまに見えたのは、彼が横から出しゃばって、曹彰を追いのけたせいもある」と、変な妬みを抱いた。
以来、劉封と孟達とは、何となく打ち解けない仲になる。劉封は武勇に乏しいのみか、器量においても劉備の養子というには多分に欠けているものがあった。
とはいえ曹操のほうでも、序戦以後は日ごとに士気が衰える。蜀の張飛(ちょうひ)・魏延(ぎえん)・馬超・黄忠(こうちゅう)・趙雲(ちょううん)などという名だたる将が陣を連ね、斜谷の下まで迫っていた。
(02)斜谷 曹操の関城
ここは都(ここでは鄴都〈ぎょうと〉の意か?)に遠い斜谷の地。もしこれ以上の大敗を喫して多くの将士を失うときは、本国まで帰ることすら甚だおぼつかない。
曹操も重なる敗色に包まれ、心中悶々(もんもん)たるものがあった。今宵も関城の一室に籠もり、ひとり頰杖をついて考え込んでいた。
そこへ膳部(ぜんぶ。食事をつかさどる役)の官人が、恐る恐る夕食を運んでくる。温かい盒(ごう)の蓋を取ると、好物の鶏の柔らか煮が入っていた。曹操は鶏の肋(あばら)をほぐしつつ口へ運ぶ。
すると夏侯惇(かこうじゅん)が帳(とばり)を払い、「今宵の用心触れは何と触れましょうか?」と尋ねた。これは毎夕の定刻に曹操の指令を仰ぐことになっている。つまり夜中の警備方針だった。
曹操は何の気なしに「鶏肋(けいろく)、鶏肋……」とつぶやく。鶏の骨をしゃぶっていたので無意識に言い間違えたものだろう。
だが夏侯惇は、曹操の言なので何か含蓄のある命令に違いないと吞み込んでしまう。城中の要所を巡り、警固の大将たちに「今宵の用心触れは『鶏肋』との仰せである。鶏肋、鶏肋――」と触れ回った。
諸将は怪しみ合う。「鶏肋」とはいったい何のことか? 誰にも解けない。時に行軍主簿(こうぐんしゅぼ)の楊修(楊脩)だけは、部下を集めて帰還の用意をさせた。
自分で触れながらもわかっていない夏侯惇は驚き、さっそく尋ねる。
「どういう訳で、貴公の隊ではにわかに引き揚げの用意にかかられたか?」
楊修が答えた。
「されば、『鶏肋』というお触れを案じてのことでござる。鶏の肋は、これを食らわんとするも肉なく、これを捨てんとするも捨てがたき味あり。いま直面している戦は、あたかも肉なき鶏の肋を口にねぶるに似たり、との思し召しかと拝察いたす」
「それにお気づきあるからには、わが魏王(曹操)も益なき苦戦は捨てるにしかずと、はやご決心のついたものと存ずる」
夏侯惇は感服し、おそらく魏王の肺腑(はいふ)を見抜いた言であろうと、密かにその旨を諸将へ告げた。
その夜も曹操は、心中の煩乱に寝もやられず、深更(深夜)に自ら銀斧(ぎんぷ)を引っ提げ、陣々の要害を見回っていた。
★『三国志演義(5)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第72回)では、このとき曹操が手にしていたのは鋼鉄の斧。
曹操は、みな引き揚げの支度をしているのを見て驚き、夏侯惇を呼ぶ。そして話を聞くと、楊修を呼べと言う。
楊修は平伏しながらも、憚(はばか)りなく言った。
「今宵の用心触れは『鶏肋』との仰せと伺い、諸人お心の中を計りかねて難儀しておりました。それゆえそれがしがお言葉の意中を解き、人々に引き揚げの用意あってしかるべしと申しました」
自分の胸奥を鏡にかけたように言い当てられ、曹操はひどく恐れた。かつ甚だしく不機嫌に、「『鶏肋』とはその意味で申したのではない。慮外者め!」と一喝したのみか、即座に首を打てと命ずる。
暁寒き陣門の柱に、楊修は首となって掛けられていた。
「あぁ、はかないかな……」
さすがの武骨の将たちも慄然(りつぜん)として、曹操の冷虐な感情におぞけを震い、また楊修の才を悼んだ。
(03)楊修の才
実に楊修の一代は、才をもって彩られていた。しかしその豊かな才も、あまりに曹操の才をも超え、常に曹操をして恐れしめていたため、かえって彼の忌み憎むところとなった。
かつてこういうこともあった。
鄴都の後宮に一園を造らせ、多くの花木を移植して常春の園ができ上がった。曹操はある日、その花園を見に出かける。
そして好(よ)いとも悪いとも言わず、ただ帰る折に筆を求め、門の額を掛ける横木へ「活」の一字を書いて去った。
造庭師(にわし)も諸官もただ首を傾け、曹操の意中を恐れ合うばかり。そこへ楊修が通りかかる。人々が当惑を告げると、彼は笑って言った。
「何でもないことではありませんか」
「魏王のお胸は、花園にしてはあまりに広すぎるから、もっとちんまり造り直せ、というご注文に違いない」
「なぜかとお尋ねか?」
「はははは。『門』の中に『活』という字を書けば、すなわち『闊(ひろし)』となるでしょう」
みな感心してすぐに庭を造り直し、再び曹操の一遊を仰いだ。曹操も今度はひどく気に入ったらしく、「誰が予の心をくんで、こう直したのか?」と尋ねる。
庭造りの役人が「楊修にて候(そうろう)――」と答えると、曹操は急に黙り、喜ぶ色を潜めてしまった。
魏王の位に即いてからの曹操は当然、太子を誰にしようとかとわが子を眺めていた。
あるとき侍側の臣に命じ、「明日、長男の曹丕(そうひ)と三男の曹植(そうしょく)とを鄴城へ呼ぶが、ふたりが城門に来たら決して通すな」と言いつけておいた。
★井波『三国志演義(5)』(第72回)では、曹操がふたり(曹丕と曹植)に命じたのは鄴の城門を出ること。そのうえで密かに使者を遣り、門番の役人に、ふたりを城外へ出すなと申しつけたとある。
曹丕は門で拒まれると、やむなく後へ帰った。次に曹植も来て、同じように門で通過を拒まれた。
すると曹植は、「王命を奉じて通るに何人(なにびと)か我を拒まん。召しを受けて行くは弦を離れた矢のごときもので、再び後へ帰ることを知らぬ」と言い捨てて通った。
これを聞いた曹操は、さすがわが子だと大いに褒めたが、後になり、それは曹植の学問の師である楊修が教えたものだとわかった。
曹操はがっかりするとともに、「余計な知恵をつけおる」と、そのときも楊修の才に眉をひそめた。
また、楊修は『答教(とうきょう)』という一書を作って曹植に与えた。そして「もし父君から何か難しいお尋ねのあったときは、これをご覧なさい」と言っていた。『答教』には、父問30項に対する答えが書いてあった。
★井波『三国志演義(5)』(第72回)では、楊修が曹植のために作った模擬回答案の項目は十数項目だった。
こういうふうに曹植には楊修の後ろ盾があったので、長男の曹丕より何事にまれ優れて見えた。太子たらんとしている曹丕は心中大いにおもしろくなく、事ごとに楊修を父に讒(ざん)していた。
何にしても、「才人才に滅ぶ」の例えに漏れず、楊修の死は、彼の才がなした禍いであったことに間違いはない。
★井波『三国志演義(5)』(第72回)と比べると、このくだりで語られた楊修の逸話には省かれているものもあった。
(04)斜谷 曹操の関城
けれど楊修の言は、彼が死んでから3日と経たないうちに、その言葉の所以(ゆえん)を現す。魏の諸将をして、「鶏肋」の解釈を再び思い起こさせた。
蜀軍はその日も次の日も、斜谷の陥落もはや旦夕にありとみて、息もつかせず攻め立てていたのである。ことに最後の日は両軍の接戦が惨烈を極め、曹操自身も乱軍の中に巻き込まれた。
そして蜀の魏延と刃を交えているうちに、「斜谷の城中から裏切り者が火の手を上げた」という混乱ぶりだった。
だが、これは裏切りがあってのことではなく、蜀の馬超が斜谷の険をよじ登り、不意に搦(から)め手(裏門)から関内へ攻め込み、後方の攪乱(こうらん)の策に出た結果だった。
しかし、関城を出て戦っていた魏軍の狼狽(ろうばい)はひと通りでなく、後方の騒動に前軍も混乱し、まったく統一を失い、収拾がつかない。
ここで曹操の危急を見た龐徳(ほうとく。龐悳)が駆けつけ、張飛や魏延の手勢を防ぐ。このとき後ろで曹操が落馬。遠矢に面を射られ、2本の前歯が欠けていた。
★井波『三国志演義(5)』(第72回)では、曹操の鼻の下に矢を当て、その門歯を2本折ったのは魏延。
龐徳は曹操を馬上に抱え、乱軍の中から落ちていく。斜谷の関城は全面が炎に包まれ、山々の樹木まで焼け続けている。
(05)敗走中の曹操
魏軍は完敗した。曹操の面部は腫れ上がり、金瘡(きんそう。刀傷や矢傷)は甚だ重かった。彼は病軀(びょうく)を氈車(せんしゃ)に横たえ、残余の兵をひきいて帰った。
★『角川 新字源 改訂新版』(小川環樹〈おがわ・たまき〉、西田太一郎〈にしだ・たいちろう〉、赤塚忠〈あかつか・きよし〉、阿辻哲次〈あつじ・てつじ〉、釜谷武志〈かまたに・たけし〉、木津祐子〈きづ・ゆうこ〉編 KADOKAWA)によると、氈車は「毛氈などを張りめぐらした車」、毛氈は「毛と綿糸をまじえて織り、圧縮した織物。しき物などにする」とあった。
その途中、うわ言のようにつぶやく。
「そうだ。楊修の屍(しかばね)は捨ててきたが、何か遺品はあるだろう。どこかへ厚く葬ってやりたいものだ……」
さらに進むと、待ち構えていた蜀軍が猛烈に包囲してくる。ようやく車は京兆府(けいちょうふ。ここでは長安〈ちょうあん〉を指す)まで逃げ走ったが、一時は曹操も、ここに死すかと、観念の目をふさいでいたようだった。
管理人「かぶらがわ」より
楊修が丁儀(ていぎ)や丁廙(ていい)らとともに、曹植の羽翼となって助けたことは『三国志』(魏書・陳思王植伝)に見えています。
その裴松之注(はいしょうしちゅう)に引く魚豢(ぎょかん)の『典略』によると、楊修(楊脩)が曹操に処刑されたのは、建安(けんあん)24(219)年の秋だということでした。
『三国志』(魏書・武帝紀)には、曹操が(漢中〈かんちゅう〉から)軍を引き揚げて長安に帰ったのは、建安24(219)年の5月だったとあります。なので、楊修は斜谷の陣中で処刑されたわけではないということに――。
なお、裴松之注に引く司馬彪(しばひゅう)の『九州春秋』に、この第224話で採り上げられていた「鶏肋」の話が出てきました。
吉川先生の文中の楊修評。
「要するに、彼の才能は惜しむべきものであったが、もう少しそれを内に包んで、どこか一面は抜けているふうがあってもよかったのではあるまいか?」
あれこれとできる人は、どうしても楊修のような態度を取りがち。彼の場合はハッタリでもなかったので、なおさらのこと。
あまりに才を隠しすぎても切り捨てられる。あまりに才を示しすぎても切り捨てられる。相手にもよることですから、このバランスは非常に難しいと思います。曹操の側近は気が抜けませんね。

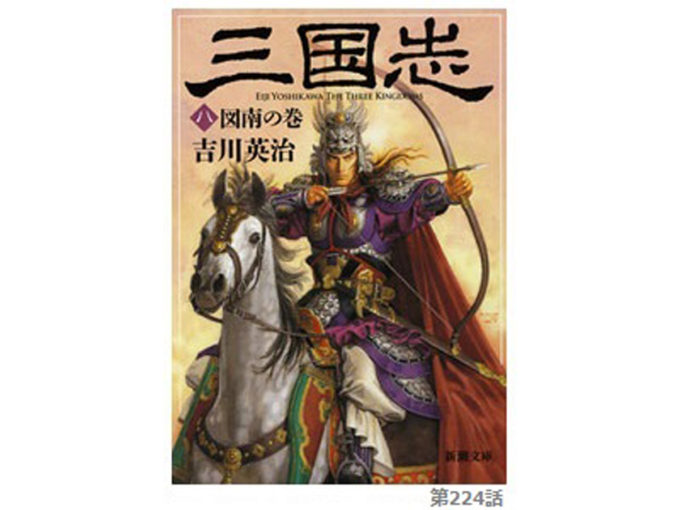














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます