劉禅(りゅうぜん)の許しを得て、むたび北伐に出る諸葛亮(しょかつりょう)。しかし北原(ほくげん)を攻めると見せかけ、渭水(いすい)の魏の本営を狙った策は、司馬懿(しばい)に看破されていた。
このため蜀軍は、北原と渭水の双方で大敗。諸葛亮は祁山(きざん)にやってきた費禕(ひい)に、呉への使いを頼む。孫権(そんけん)を説得し、魏の側面を突いてもらおうとの考えだった。
第301話の展開とポイント
(01)成都(せいと)
多年、軍需相(ぐんじゅしょう)として、重要な内政の一面に才腕を振るっていた李厳(りげん)の免職。このことは、何と言っても蜀軍の一時的な休養と、延(ひ)いては国内の諸部面の大刷新を促さずにはおかない。
★原文「李厳の退職」だが、ここは「李厳の免職」としておく。
ここにおいて諸葛亮は、「3年は内政の拡充に力を注ごう」と決意する。そしてこの間、彼は百姓を哀れみいたわった。百姓は天地か父母のように見た。
また、教学と文化の振興にも努める。児童も道を知り、礼をわきまえた。教学の根本は師弟の結びにありとして、師たる者を重んじ、その徳を涵養(かんよう)させた。
さらに、内治の根本は吏にありとして、吏風を醇化(じゅんか)し吏心を高めさせる。吏にしてひとたび瀆職(とくしょく)の恥を犯す者があれば、市にさらして、民の刑罰より数等厳罰に処した。
かくて3年の間に蜀の国力は充実し、朝野の意気もまったく一新された。諸葛亮は劉禅に奏し、六度目となる北伐に臨む。
この際にも成都人の一部では、宮門の柏樹(はくじゅ。檜〈ヒノキ〉の木)が毎夜泣くとか、南方から飛翔してきた数千の鳥群が、一度に漢水(かんすい)へ落ちて死んだなど、不吉な流言を立てて、諸葛亮の出軍を阻めようとする者もあった。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第102回)では、これら不祥の兆しを太史(たいし)の譙周(しょうしゅう)が上奏している。ちなみに、鳥が漢水に落ちたという件は、「近ごろ数万羽の鳥が南から飛来し、漢水に飛び込んで死にました」と述べていた。
だが諸葛亮の大志は、決してそのような虚謬(きょびゅう)の説に弱められるものではない。
彼は一日、成都郊外にある先帝(劉備〈りゅうび〉)の霊廟(れいびょう)に詣でて、太牢(たいろう。牛・羊・豕〈し。ブタ〉)を供え、涙を流して何事か久しく祈念した。
その数日後、大軍は成都を発する。劉禅は百官を従えて城外まで見送った。
(02)漢中(かんちゅう)
蜀道の険や蜀水の危を踏み渡ること幾度。延々として、やがて軍馬は漢中へ入った。
ところがまだ戦わぬうちに、諸葛亮はひとつの悲報に接する。それは関興(かんこう)の病没だった。
漢中で勢ぞろいをなし、祁山へ進発した蜀軍は、五大部隊に分かれ、総兵34万と号する。
(03)洛陽(らくよう)
時に魏は改元の第二年を迎え、青龍(せいりゅう)2(234)年の春2月だった。昨年、摩坡(まひ。摩陂)という地方から、青龍が天に昇ったという奇異があり、これ国家の吉祥なりと、改元されたものである。
司馬懿は勇躍して詔(みことのり)を拝すと、かつて見ぬほどの大軍備を整えた。その出陣に先立ち、曹叡(そうえい)に奏する。
「かつて漢中で討たれた夏侯淵(かこうえん)の子ら4人が、常に父を蜀のために亡くした恨みを吞んで切歯扼腕(せっしやくわん)しております。願わくは今度の軍(いくさ)に、その遺子4人を伴ってまいりたいと存じますが――」
曹叡はこの願いを許した。これらの四子は、以前に失敗を招いた夏侯楙(かこうも)などとは大いに質が違っている。
兄の夏侯覇(かこうは。夏侯霸)は弓馬武芸に達し、弟の夏侯恵(かこうけい)は六韜三略(りくとうさんりゃく。『六韜』と『三略』。ともに中国古代の兵法書)を諳(そら)んじて、よく兵法に通じていた。ほかのふたりの兄弟(夏侯威〈かこうい〉と夏侯和〈かこうわ〉)も俊才の聞こえがあった。
(04)長安(ちょうあん)
長安に集結した魏の精鋭は44万と言われた。そして宿命の決戦場の渭水を前にして、従前通りに布陣する。
(05)渭水 司馬懿の本営
祁山の蜀勢も、渭水の魏勢も、戦いの回を追うごとに、その経験から地略的な攻究が進んでいた。装備や兵力は逐次増強され、これを第一回や第二回ごろの対峙(たいじ)から比べると、双方の軍容にもわずかな年月の間に著しい進歩が見える。
作戦上から今次の相違を見ると、魏は5万の工兵隊を駆使して竹木を伐採させ、渭水の上流9か所に浮き橋を架した。こうして夏侯覇と夏侯威のふた手が河を渡り、河の西に陣地を築く。
これは従来には見られなかった、魏の積極的な攻勢を示したものであるとともに、用意周到な司馬懿は、本陣の後ろにある東方の広野に一城を構築し、恒久的な基地となした。
(06)祁山 諸葛亮の本営
この恒久戦の覚悟はまた、より強く、蜀軍の備えにも看取できる。祁山に構えた5か所の陣屋は、これまでの規模とそれほど変わりない。
だが、斜谷(やこく)から剣閣(けんかく)にわたって14か所の陣屋を築き、一塁ごとに強兵を込めて、運輸の連絡と呼応連環の態勢を作った。
★剣閣については先の第294話(04)を参照。
これは、「魏を討たずんば還らじ」となす諸葛亮の意志を、無言に儼示(げんじ。厳かに示すこと)しているものにほかならない。
ここでその一塁から一報が届き、敵陣に変化のあることを告げる。
「魏の郭淮(かくわい)と孫礼(そんれい)の二軍が、隴西(ろうせい)の軍馬を領して北原へ進出し、何事か為すあらんとするもののごとく動いております」
諸葛亮は、この情報を聞いて言った。
「司馬懿は前に懲りて、隴西の道を我に断たれんことを恐れ、手配を急いだものと思われる。いま偽って、蜀が彼の恐れる隴西を突く態をなすならば、司馬懿は驚き、その主力を応援に差し向けるだろう。敵の備えなきを討つ。その虚は後ろの渭水にある」
北原は渭水の上流である。諸葛亮はこのような策を立てた。
まずは100余座の筏(いかだ)に乾いた柴(シバ)を満載させ、夜中に、水に慣れた5千の兵をすぐって北原を襲撃させる。
魏の主力が動くのを見たら、ただちに筏に火を付けて下流へ押し流し、敵の浮き橋を焼き立て、西岸の夏侯兄弟の軍勢を捕捉。また、たちどころに渭水の南岸へ兵を上げて、魏の本陣を乗っ取る。
★ここで諸葛亮の策の最後に、「渭水の南岸へ兵を上げて」とあった。これだと司馬懿の本営が、渭水を渡って南側にあることになり、この第301話(04)の記述と矛盾する。ただ、このとき渭水の南岸にも魏の陣営は築かれていたので、本営が北岸にあるのか南岸にあるのかには、それほどこだわっていないのかもしれない。
(07)渭水 司馬懿の本営
果たしてこの策がうまく魏軍を計り得るかどうかは、魏の触覚たる司馬懿その人の頭脳ひとつにある。
さすがに彼は看破し、こう言った。
「いま孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)が上流に多くの筏を浮かべ、北原を攻めそうな擬勢を作っておる。だが、これは虚を見て筏を切り流し、それに積んだ松柴と油をもって、わが数条の浮き橋を焼き払うつもりに違いない」
司馬懿は夏侯覇と夏侯威に何事か命じ、郭淮・孫礼・楽綝(がくりん)・張虎(ちょうこ)らの諸将へも、それぞれ秘命を授け終えた。
(08)北原
やがて戦機は、蜀軍の北原攻撃から口火を切る。呉懿(ごい)と呉班(ごはん)の蜀兵は、かねての計画通り、無数の筏に焚草(やきぐさ)を積んで、河上に待機していた。
日が暮れてくる。北原の戦況は、初め魏の孫礼が打って出たが、脆(もろ)くも打ち負けて退却した。そこへ掛かった蜀の魏延(ぎえん)と馬岱(ばたい)は、敵の負けぶりがおかしいと見て、あえて深追いしなかった。
それでもたちまち両岸の物陰から魏の旗がひらめき見え、喚声や雷鼓の潮とともに、司馬懿と郭淮が刹出。魏のふたりは半円陣を結び、敵と河とを一方に見て圧縮してくる。
魏延と馬岱は命をかざして奮戦したが、とうてい勝ち目のない地勢にあった。河流へせき落とされて溺れる者、包まれて討たれる者など、大半の兵を失ってしまう。
蜀のふたりは辛くも水上へ逃げる。しかしこのころ、呉懿と呉班の手勢が待ちきれずに、大量の筏を流し始めていた。
ところがそれらの筏群は、魏軍の架けた浮き橋まで流れてこないうちに、張虎や楽綝らの手勢が別の筏で縄を張り巡らせたため、ことごとくせき止められてしまう。魏軍はそこを足場にして矢戦をしかける。
蜀兵は何らの飛び道具も備えていなかったので、筏を寄せて斬り結ぶしか手がない。蜀兵を寄せつけては、魏兵が雨のごとく矢を浴びせた。
蜀の呉班も、ついに一矢を受けて水中に落命する。そのうえ火計はまったくの失敗に帰し、蜀軍の敗亡も惨たるものだった。
(09)渭水
火計の失敗は当然、別動隊たる王平(おうへい)と張嶷(ちょうぎ)のほうへも狂いを生じさせないはずはない。この二軍は諸葛亮の命によって、渭水の対岸をうかがい、浮き橋が焼ける火を見たら、ただちに司馬懿の本陣へ突入しようと息を凝らしていた。
けれど、夜が更けても一向に上流に火光が揚がらないので、「はて、どうしたものだろう?」としびれを切らしていた。
張嶷は待ちくたびれ、逸(はや)って言う。
「対岸をうかがうに、魏陣は確かに手薄らしく思われる。いっそのこと、突っ込もうか」
だが、王平はこう言って固持し、なお根気よく火の手を待っていた。
「敵にどのような隙があろうと、ここだけの状況で作戦の機約を変えることはできない」
するとそこへ急使が着く。馬を飛ばして駆けてくるなり、大声でふたりを差し招いて告げた。
「王将軍も、張将軍も、はやはや退きたまえ。丞相(じょうしょう。諸葛亮)のご命令です。北原も味方の敗れとなり、浮き橋を焼く計もことごとく齟齬(そご)いたして、蜀勢はみな敗れ去りました」
★ここは原文「平将軍も、嶷将軍も」だったが、「王将軍も、張将軍も」としておく。
こうして急に蜀の二軍が退きだした刹那である。それまで河波の音と蘆荻(ろてき)の声しかなかった付近の闇が、一度に赤くなった。そして一発の轟音(ごうおん)が天地のしじまを破るとともに、魏の伏兵が四方八方から襲いかかってきた。
計ると思いながら、事実はまったく敵の陥穽(かんせい)の中にいたのである。かくては戦う態勢も取り得ない。王平と張嶷の二軍も散々に討たれて逃げ崩れた。
(10)祁山 諸葛亮の本営
渭水の上流と下流の全面にわたり、この夜、蜀軍が受けた兵の損害だけでも1万を超えていた。
諸葛亮は敗軍を収めて祁山へ立ち帰ったが、彼がかくのごとく計を誤ったことは珍しい。日ごろの自信にも少なからぬ動揺を与えたに違いなく、その憂いは面にも包めなかった。
ある日、諸葛亮の憂色をうかがい、長史(ちょうし)の楊儀(ようぎ)が密かに訴える。
「近ごろ魏延が丞相の陰口を叩き、とかく軍中の空気を濁しておりますが、何か原因があるのですか?」
諸葛亮は眉重くうなずき、彼の不平は今に始まったことではないと話す。
楊儀は、なぜ彼の悪態を放置しておかれるのですかと問うが、諸葛亮は、予が胸も察するがいいと答える。
楊儀は沈黙した。諸葛亮の意中を酌むにつけ、断腸の思いがあった。連戦多年、蜀軍の将星は相次いで墜(お)ち、用いるに足る勇将と言えば、実に指を折るほど少なくなっている。ともあれその中にあって、魏延の勇猛は断然、衆を超えているものがある。
いまその魏延をも除くならば、蜀軍の戦力はさらに落莫(らくばく)たらざるを得ない。諸葛亮がジッとこらえているのは、そのためであろうと楊儀は察した。
★井波『三国志演義(6)』(第102回)では、ここにあるような諸葛亮と楊儀とのやり取りは見えない。
時に成都からの用命を帯びて、尚書(しょうしょ)の費禕(ひい)が祁山へ来る。
諸葛亮は彼に会うと告げた。
「ここにご辺(きみ)ならではかなわぬ大役がある。蜀のために、予の書簡を携えて、呉へ使いに赴いてくれまいか」
費禕が承諾すると、諸葛亮は言った。
「快く承知してくれてありがたい。ではこの書簡を孫権に捧げ、なお卿(けい)の才をもって、呉を動かすことに努めてもらいたい」
諸葛亮が彼に託したものは、実に蜀呉同盟条約の発動にある。書中で祁山の戦況を縷々(るる)と告げ、切々と説いていた。
「今や魏軍の全力は、ほとんどこの地に牽引(けんいん)されております。この際、呉がかねての条約に基づいて、魏の一面をお討ちになるならば、魏は両面的な崩壊を来し、中原(ちゅうげん。黄河中流域)のことはたちまちに定まります」
「しかる後は、蜀呉天下を二分して、理想的な建設を地上に興すことができましょう」
(11)建業(けんぎょう)
費禕が建業に着く。孫権は諸葛亮の書簡を見、また蜀の使いを応接するに、その礼は甚だ厚かった。
孫権が言う。
「呉といえど、決して蜀魏の戦局に冷淡なものではない。その時を見、また十分な戦力を養っていたもので、今や機は熟したと思われる」
「日を定めて、朕自ら水陸の軍勢をひきい、討魏の大旆(たいはい。大将の立てる大きな旗)を掲げて長江をさかのぼるだろう」
費禕は拝謝しつつも、その口裏の虚実をうかがった。
「おそらく魏の滅亡は100日を出でますまい。して、どのような進路をお取りになりますか?」
孫権は言下に語る。
「まず総勢30万を発し、居巣門(きょそうもん)から魏の合淝(がっぴ。合肥)、彩城(さいじょう)を取る」
★彩城というのがわからなかった。なお井波『三国志演義(6)』(第102回)では、「居巣から進撃して、魏の新城(しんじょう。合肥新城)を攻略しよう……」となっていた。あまり自信はないが、「合淝、彩城」は「合肥新城(合淝新城)」と混同されたものかも?
「また、陸遜(りくそん)や諸葛瑾(しょかつきん)らに江夏(こうか)と沔口(べんこう)を討たせ、襄陽(じょうよう)へ突入させる。さらに、孫韶(そんしょう)や張承(ちょうしょう)らを広陵(こうりょう)地方から淮陽(わいよう)へ進ませるだろう」
★井波『三国志演義(6)』(第102回)では、「孫韶・張承らに広陵から出撃し、淮陰(わいいん)を攻略させる」となっていた。
酒宴となってくつろいだとき、今度は孫権が費禕に尋ねた。
「いま諸葛亮のそばにいて、功労を記し、兵糧その他の軍政を助けている者は誰だな?」
費禕は、長史の楊儀だと答える。続けて孫権が、先鋒にあたる勇将についても尋ねると、費禕は、まず魏延でしょうかと答えた。
★井波『三国志演義(6)』(第102回)では、孫権は諸葛亮の先鋒にあたる人物についてのみ尋ねており、楊儀の話は出ていない。
すると孫権は、意味ありげに打ち笑って言う。
「朕はまだ、楊儀や魏延の人物は見ていないが、多年の行状で聞き知るところ、いずれも蜀を負うほどの人物ではなさそうだ。どうして諸葛亮ほどの人が、そのような小人輩を用いているのか?」
費禕は言葉もなく、その場はよいほどに紛らわせた。
(12)祁山 諸葛亮の本営
費禕は祁山に戻って復命した後、孫権の言葉をそのまま語る。
諸葛亮は嘆息して、ひとりかこった。
「さすがに孫権も具眼の士である。いかに良く見せようとしても天下の目は欺けないものだ。魏延や楊儀の小さいことは、われ疾(と)くに知るも、呉の主君までが見抜いていようとは思わなかった」
管理人「かぶらがわ」より
司馬懿に計を看破され、渭水一帯で大敗を喫した諸葛亮。蜀の人材難を、呉にあって見抜いた孫権。そのことを費禕に語ってしまうところが、また彼らしくもありました。
ですが孫権に言われるまでもなく、蜀の人材不足は深刻。いつも諸葛亮自身が総指揮を執り、作戦の立案から何から、ほぼひとりでやってしまうわけですから――。これは大変だったでしょう。
吉川『三国志』や『三国志演義』では話の展開上、魏も司馬懿ひとりが目立っていますけど、実際の魏では、北方から南方まで各地に優秀な司令官が派遣されていました。そもそも国力が違いすぎるのですよね……。

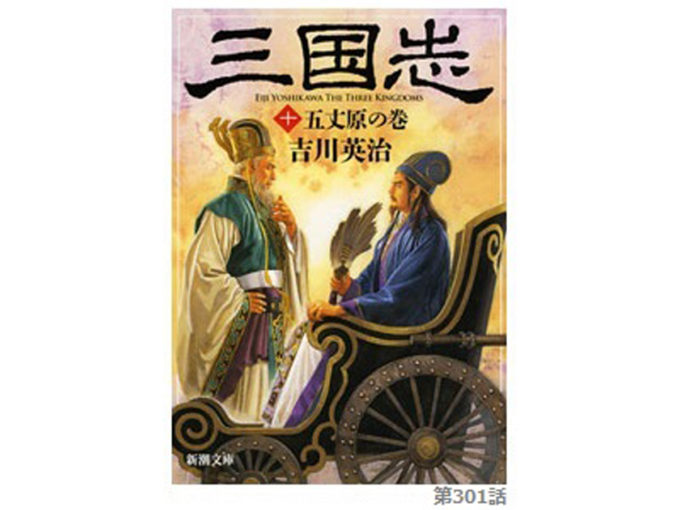














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます