これまでの北伐において、いつも諸葛亮(しょかつりょう)を悩ませたのは兵糧の確保だった。
そこで今回は葫蘆谷(ころこく)に極秘の作業場を設け、「木牛」や「流馬」と呼ぶ運搬車を製作。この車が使われ始めると、剣閣(けんかく)から祁山(きざん)の本営へ大量の兵糧が運ばれるようになる。
第302話の展開とポイント
(01)祁山 諸葛亮の本営
ある日、蜀の陣へ来て、このように言う者があった。
「それがしは、魏の部将の鄭文(ていぶん)という者です。丞相(じょうしょう。諸葛亮)に謁してお願いしたいことがございます」
諸葛亮が対面して何事かとただすと、鄭文は拝伏し、「降参を容れていただきたい」と、剣を解いて差し出す。理由を問うとこう述べた。
「それがしは、もとから魏の偏将軍(へんしょうぐん)でした。しかるに、司馬懿(しばい)の催しに応じて参軍した後、彼は私より後輩の秦朗(しんろう)という者を重用し、それがしを軽んじておりました」
「のみならず、軍功を依怙贔屓(えこひいき)になし、あまつさえそれがしが不平を漏らしたと称して、殺さんとする気ぶりすらあるのです」
「犬死にせんよりはと、丞相のご高徳をお慕いして降伏に来た次第です。お用いくだされば、この恨みを報ぜんためにも、きっと蜀に忠誠を尽くしましょう」
すると、祁山の下の野に一騎の魏将が追ってきて、鄭文を渡せと、しきりにわめいていると、営外の物見が知らせてきた。
諸葛亮に促されると、鄭文は馬を飛ばして秦朗と一騎討ちを遂げ、その首を搔(か)き切って戻る。秦朗の屍(しかばね)や衣装も持ってこいと言われると、鄭文は駆け戻って遺骸をそろえた。
諸葛亮はとくと見ていたが、「鄭文の首を斬れ」と左右の武士に命ずる。
鄭文が絶叫すると、諸葛亮はこう言って笑った。
「この屍は秦朗ではない。秦朗は予も前から見知っている。似ても似つかぬ下郎をもって秦朗なりと欺いても、その計には乗らん。思うに、仲達(ちゅうたつ。司馬懿のあざな)が申しつけた偽計に違いあるまい」
鄭文は震い恐れて、その通りですと自白した。
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第102回)では、鄭文が討ち取ったのは、秦朗の弟の秦明(しんめい)。だが、吉川『三国志』では秦明を使っていない。
諸葛亮は思案した後、何か思い直したように、「鄭文を檻車(かんしゃ)に入れておけ」と、しばらく斬るのを見合わせる。そして翌日、自分の書いた原文を示し、檻(おり)の中の鄭文に司馬懿あての書簡を書かせた。
(02)渭水(いすい) 司馬懿の本営
鄭文の書いた書簡を持った蜀兵は、付近の住民に姿を変えて魏の陣へ紛れ入り、「鄭文という方から頼まれてきた者ですが――」と、司馬懿の側臣に手渡した。
司馬懿は書簡を熟視したが、筆跡は紛れもなく鄭文のもの。いたく喜んだ様子で、使いの男に酒食を与え、誰にも漏らすなと口止めして帰す。
書簡の文意は以下のようなものだった。
「明夜、祁山の火を合図に、都督(ととく。司馬懿)自ら大軍をひきいて攻めかかりたまえ。孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)不覚にもそれがしの降伏を深く信じて、この身は彼の中軍にあり」
「時を合わせて呼応一摑(いっかく)。孔明を擒人(とりこ)になさんこと、いま眼前に迫る。期して外したもうな」
容易に人の計略にはかからない司馬懿も、自分の仕掛けた計略にはついかかった。翌日は密々と準備して、夜に入るや、そっと渭水の流れを渡らんとした。
これを息子の司馬師(しばし)が諫める。一片の紙片を信じて、これまで自重していた戦機を我から動かすなどということは、日ごろの父上らしくもない軽忽(けいこつ)であると直言したのだった。
司馬懿はこの言を容れ、自分は後陣へ回り、別の大将を先陣に配する。
★井波『三国志演義(6)』(第102回)では、司馬懿は司馬師の意見に従い、(本物の)秦朗に1万の軍勢をひきいて蜀の本陣に夜討ちをかけさせ、自身は軍勢をひきいて後詰めとなったとある。
(03)祁山 諸葛亮の本営
その夜、宵のうちは風清く月明らかで、粛々たる夜行には都合が悪かった。だが、渭水を渡るころから夜霧が深く、空も黒雲に閉ざされてきたので、司馬懿は限りなく喜ぶ。
魏軍は枚(ばい。夜に敵を攻める際、声を出さないように兵士の口にくわえさせた細長い木)を銜(ふく)み、馬は口を勒(ろく)し、深く蜀陣へ近づいた。
一方この夜を期し、「必ず司馬懿を捕らえん」と、計りに計っていた諸葛亮。剣に寄り、壇に歩して、昼は必勝の祈とうをなし、夕べは血を注ぎ、諸将と決死の杯を酌み交わす。夜に入るや手分けを定め、三軍は林のごとく待ち受けていた。
夜は更けて、黒霧迷濛(めいもう)たるころ、忽然(こつぜん)、堰(せき)を切られた怒濤(どとう)のごときものが、蜀の中軍へなだれ入る。
しかし、その営内は空虚だった。魏勢は怪しみ疑い、「敵の計に陥ちるな」と戒め合ったが、すでにこのとき完全に出る道を失っていたのである。
鼓角、鉄砲、鬨(とき)の声は瞬時に起こり、魏の先鋒の大半を殲滅(せんめつ)。この中には、討ち死にを遂げた魏将の秦朗も入っていた。
幸いにも司馬懿は後陣だったので、蜀の包囲鉄環から逃れる。残る兵を救わんため、いったんは強襲を試みて、敵の包囲を外から破らんとした。だが、それも自軍の兵力をおびただしく損じたのみで、残る先鋒の約1万も敵の中に見捨てて、引き退くしかなかった。
(04)退却中の司馬懿
滅多に感情を激さない司馬懿も、このときばかりはよほど口惜しかったとみえて、退陣の途中も歯がみをする。
しかもそのころになると、空は再び晴れて、晃々(こうこう)たる月天に返り、一時の黒雲は夢かのように考えられた。
「これは孔明が、八門遁甲(はちもんとんこう)の法を用いて我らを黒霧の内に誘い、また後には六丁六甲(りくていりくこう)の神通力をもって、黒霧を払い除いたせいである」
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(八門遁甲は)道教経典『秘蔵通玄変化六陰洞微遁甲真経(ひぞうつうげんへんげりくいんどうびとんこうしんけい)』のことか。招風の術や縮地の法を収め、諸葛亮が習得したと記す」という。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「六丁六甲は道教の神の名。六丁とは丁卯(ていぼう)・丁巳(ていし)・丁未(ていび)・丁酉(ていゆう)・丁亥(ていがい)・丁丑(ていちゅう)の6人の陰神」だという。
また「六甲は甲子(こうし)・甲戌(こうじゅつ)・甲申(こうしん)・甲午(こうご)・甲辰(こうしん)・甲寅(こういん)の6人の陽神を指す」という。
さらに「彼らは天帝(天をつかさどると言われる神)の配下で、風雷を起こし、鬼神を制することができ、また道教の僧(法師)に呪文で招請され、厄払いに携わると信じられていた」ともいう。
生き残って帰る魏の将士の間には、誰言うとなくこのような妖言が放たれ、誰もそれを疑わなかった。
司馬懿は陣中の迷信に弾圧を加え、厳しく盲言を戒める。それでも、孔明は一種の神通力を持ち、奇跡を行う者だという考えは、牢固(ろうこ)として抜くべからざる一般の通念になってきた傾きすらあった。
魏兵がこのような畏怖にとらわれだしたので、司馬懿もその怯兵(きょうへい)を用いるのは骨だった。そこで以後は堅く要害を守り、一にも守備、二にも守備。ただこれ守るを第一として、あえて戦うことをしなかった。
(05)葫蘆谷
その間に諸葛亮は、渭水の東方にあたる葫蘆谷へ1千の兵を入れ、谷の内で土木の工を起こしていた。
★井波『三国志演義(6)』(第102回)では、司馬懿ら魏軍を敗走させた後、本陣に戻った諸葛亮が鄭文を斬るよう命じたとある。だが、吉川『三国志』ではこのことに触れていない。
★同じく井波『三国志演義(6)』(第102回)では、葫蘆谷での作業を監督した裨将(ひしょう。副将)の杜叡(とえい)と胡忠(こちゅう)を登場させていたが、吉川『三国志』ではふたりとも使われていない。
この谷はふくべ形の盆地を抱いていて、大山に囲まれ、一方に細い小道があるだけで、わずかに一騎一列が通れるにすぎない。諸葛亮も日々そこへ通い、日夜、何事か工匠(たくみ)に指図していた。
(06)祁山 諸葛亮の本営
魏があえて戦わず、長期を持している真意は、明らかに蜀軍の糧食の枯渇を待つものであるのは言うまでもない。
長史(ちょうし)の楊儀(ようぎ)はその点を憂え、しばしば諸葛亮に訴えていた。
「いま蜀本国から運輸された軍糧は、剣閣で山と積まれている状態ですが、如何(いか)んせん剣閣から祁山までは悪路と山岳続きで、牛馬も倒れ、車も潰(つい)え、輸送は少しもはかどりませぬ。この分ではたちまち兵糧に詰まってくると案ぜられますが……」
★剣閣については先の第294話(04)を参照。
(蜀の)建興(けんこう)6(228)年の第二次祁山出陣以来、第三次、第四次と戦を重ねるごとに、常に蜀軍の悩みとされていたのは兵糧と輸送の問題である。
今や約3年の休戦に農を勧め、士を休め、かつて見ぬほどな大規模の兵力と装備を擁して、六度祁山へ出た諸葛亮が、その苦い経験を再びここに繰り返そうとは思われない。
諸葛亮は言った。
「いや、そのことなら近いうちに解決する。心配するな」
(07)葫蘆谷
楊儀をはじめ蜀の諸将は、やがて諸葛亮に導かれ、葫蘆谷の内へ入ることを許される。
ここ1か月も前から何を工事しておられるのかと、いぶかっていた諸将。谷内がいつの間にか一大産業工場と化しているのを見て、みな瞠目(どうもく)した。
何が製産されていたかと言えば、諸葛亮の考案にかかる「木牛」「流馬」と呼ぶ2種の輸送機。これに似た怪獣形戦車は、かつて南蛮遠征の時に敵陣の前に並べられたことがある。
今回の発明は、それを糧運専用の輜重車(しちょうしゃ)に改造したものと言える。そしてそれは第二次、第三次出兵の折にも少しは試用されたものの、効果が少なかった。
そこで、その後の3年の休戦中にさらに鋭意工夫を加え、ここに大量製産にかかる自信を持つに至った新兵器だった。
諸葛亮は、すでに無数に製造されていた実物を示したうえ、分墨尺寸(ぶんぼくしゃくすん。設計図)についても、自らいろいろな説明を加えて話す。
(08)木牛流馬の構造
いったい木牛流馬とは、どのような構造のものかを考えるに、後代に伝わっている寸法や部分的な解説だけでは、概念を知るだけでもかなり困難である。
『漢晋春秋』『亮集(りょうしゅう)』『後主伝』などに記載されているところを総合してみると、大略、次のごとき構造と効用のものであることがほぼ推察される。
★新潮文庫の註解によると「(『漢晋春秋』は)習鑿歯(しゅうさくし)の撰。蜀漢の正統を主張する史書」という。同じく「(『亮集』は)『諸葛氏集』のこと。陳寿(ちんじゅ)が編纂(へんさん)した諸葛亮の文集」という。また同じく「(『後主伝』は)『三国志』後主伝を指す」という。
木牛トハ、四角ナル腹、曲レル頭(かしら)、四本ノ脚、屈折自在、機動シテ歩行ス。頭ハ頸(くび)ノ中カラ出ル、多クヲ載セ得ルモ、速度ハ遅シ。大量運搬ニ適シ、日常小事ノ便ニハ用イ難シ。一頭軽行スルトキハ一日数十里ヲ行クモ、群行スルトキハ二十里ニトドマル。
★井波『三国志演義(6)』(第102回)では、集団で移動するものは30里とある。
また、別の書にはこうも見える。
曲レルハ牛ノ頭トシ、双ナルハ牛ノ脚トシ、横ナルハ牛ノ頸トシ、転ズルハ牛ノ背トシ、方(ほう)ナルハ牛ノ腹トシ、立テルハ牛ノ角トシ。鞅(おう。胸の綱)鞦(しゅう。尾の綱)備ワリ、軸、双、轅(えん。ながえ)ヲ仰グ。
人行六尺(ろくせき)ヲ牛行(ぎゅうこう)相歩(あいほ)ス。人一年分ノ糧食ヲ載セテ一日行クコト二十里。人大イニ労セズ。
さらに、『後山叢譚(ござんそうだん)』にはこう記している。
★新潮文庫の註解によると「(『後山叢譚』は)北宋の陳師道(ちんしどう)『後山談叢(ござんだんそう)』のこと」だという。
蜀中ニ小車アリ。能(よ)ク八石(はっせき)ヲ載セテ、一人ニテ推スヲ得ベシ。前ハ牛頭ノ如シ。マタ、大車アリ、四人ヲ用イテ、十石ヲ推戴(すいたい)ス。蓋(けだ)シ木牛流馬ニ倣エルモノカ。
★吉川『三国志』では流馬について、井波『三国志演義(6)』(第102回)ほど詳しく説明されていなかった。
もちろん、これは後代の土俗運輸を付設したものであることは言うまでもない。いずれにしても、その機動力の科学的構造は甚だ分明でないが、実用されて大効のあったことは疑われていない。
この輜重機が数多く造られだすと、蜀軍は右将軍(ゆうしょうぐん)の高翔(こうしょう)を大将として、続々と木牛流馬隊を繰り出す。
剣閣から祁山へ、たちまち大量の兵糧運輸が開始された。蜀兵はその量を眺めただけで勇気百倍。反対に魏の持久作戦は、根本的にその意義を覆さるるに至った。
管理人「かぶらがわ」より
鄭文を用いた計が失敗し、大きな損害を被った魏軍。鄭文の名は正史『三国志』には見えず、『三国志演義』で創作された人物のようです。
そちらよりも、やはり木牛と流馬が気になりました。何となくわかるようでわからない描かれ方。一輪タイプと四輪タイプの運搬車があり、それを人力で使っていたというイメージでしょうか?
もし詳しい設計図が伝わっていたら、さらに興味深かったでしょうけど――。さすがに2千年近くも前のことだと難しいですよね。

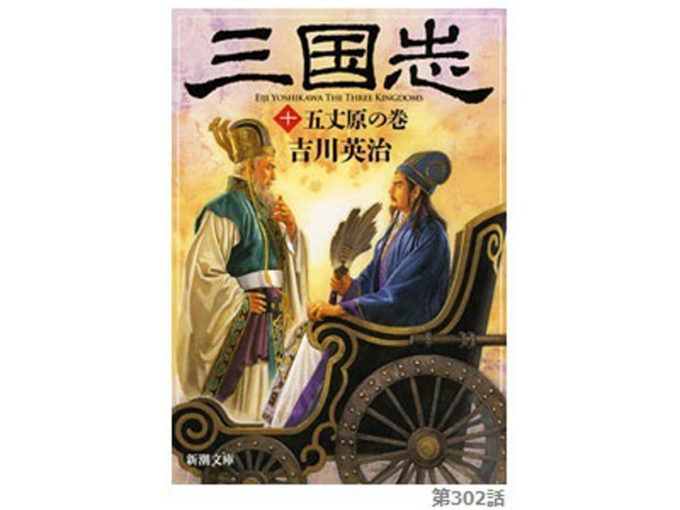













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます