諸葛亮(しょかつりょう)の禱(いの)りは、あと一夜というところで成就しなかった。だが、攻め寄せた魏軍にも取り乱すことなく、魏延(ぎえん)に命じて追い払わせる。
諸葛亮は、自ら著した24編の書物を姜維(きょうい)に託し、楊儀(ようぎ)にも一書を入れた囊(ふくろ)を手渡す。さらに、費禕(ひい)をはじめ信頼する者たちに後事を委ね、劉禅(りゅうぜん)への遺表を書き終えると、54年の生涯を閉じた。
第309話の展開とポイント
(01)渭水(いすい)の北岸 司馬懿(しばい)の本営
魏兵が大勢して、仔馬(コウマ)のごとく草原に寝転んでいる。一年中で一番季節のよい、涼秋8月の夜を楽しんでいるのだった。
そのうち不意にひとりの兵が、アッと言った。またひとりが指さし、そのほかの幾人かも、確かに見たと騒ぎ合う。
兵たちは、めいめい営内のどこかへ去っていく。上将に告げたのだろう。まもなく司馬懿の耳にも入っていた。
折ふし司馬懿の手元には、天文方から今夕に観測された奇象を、次のように記録して報じてきたところだった。
「長星アリ、赤クシテ茫(ぼう。はっきりしない様子)。東西ヨリ飛ンデ、孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)ノ軍営ニ投ジ、三(み)タビ投ジテ二(ふた)タビ還ル」
「ソノ流レ来ルトキハ光芒(こうぼう)大ニシテ、還ルトキハ小サク、其(その)ウチ一星ハ終(つい)ニ隕(お)チテ還ラズ。占(せん)ニ曰(いわ)ク、両軍相(あい)当ルトキ、大流星アリテ軍上ヲ走リ、軍中ニ隕ツルニ及ベバ、其軍、破敗ノ徴ナリ」
兵が目撃したというところと、この報告書とは、符節を合したように一致している。
司馬懿は夏侯覇(かこうは。夏侯霸)を呼び、早口に急命を下す。
「おそらく孔明は危篤に陥ちておるものと思われる。あるいは、その死は今夜中かもしれぬ。天文を観るに、将星(大将に見立てた赤色の大星)もすでに位を失っている。汝(なんじ)、すぐに1千余騎を引っ提げて五丈原(ごじょうげん)をうかがいみよ」
「もし蜀勢が奮然と打って出たら、まだ孔明の病は軽いと見なければならぬ。怪我なきうちに引き返せ」
夏侯覇は手勢を糾合し、星降る野をまっしぐらに進軍した。
(02)五丈原 諸葛亮の本営
この夜は、諸葛亮が禱りに籠もってから6日目だった。あと一夜である。
★諸葛亮が禱りに籠もっていることについては、前の第308話(03)を参照。
しかも本命の主灯がともり続けているので、諸葛亮は「わが念願が天に通じたか」と、いよいよ精神を凝らして禱りの行(ぎょう)に伏していた。
帳外を守護している姜維もまた同様の気持ち。ただ恐れられるのは、諸葛亮が禱りのまま息絶えてしまうのではないかという心配だけである。なので姜維は、折々に帳内の秘壇をそっとのぞいていた。
諸葛亮は髪をさばき、剣を執り、いわゆる罡(こう)を踏み斗を布くという禱りの座にすわったまま、後ろ向きになっている。
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(罡を踏み斗を布くとは)北斗七星の形にステップを踏む動作のこと」だという。
「あぁ、かくまでに――」と、姜維はうかがうたびに熱涙を抑えた。諸葛亮の姿は忠義の権化そのものに見えた。
すると何事か、夜も更けているのに突然、陣外におびただしい鬨(とき)の声がする。すぐに姜維は守護の武者(つわもの)を外へ走らせた。
ところが入れ違いに、魏延が駆け入ってくる。そこにいる姜維も突きのけ、帳中へ駆け込んでわめいた。
「丞相(じょうしょう。諸葛亮)、丞相っ! 魏軍が寄せてきました。ついにこちらの望み通り、しびれを切らして、司馬懿のほうから戦端を開いてきましたぞ」
魏延が諸葛亮の前に回り、ひざまずこうとした弾みに何かにつまずいたとみえ、壇上の祭具や供物が崩れ落ちる。
そのうえ狼狽(ろうばい)した魏延は、足元に落ちてきた主灯のひとつを踏み消してしまった。
それまで、化石のごとく禱りを続けていた諸葛亮は、アッと剣を投げ捨てて高く叫んだ。
「死生命あり! あぁ、我ついに熄(や)むのほかなきか……」
帳中へ躍り込んだ姜維が魏延に斬りかかると、諸葛亮は声を絞って叱る。
「主灯が消えたのは人為ではない。怒るをやめよ。天命である。何の魏延の科(とが)であるものか。静まれ。冷静になれ」
そう言って諸葛亮は床に倒れ伏したが、陣外の鼓や鬨の声を聞くと、すぐに面を上げて命じた。
「今宵の敵の奇襲は、はや仲達(ちゅうたつ。司馬懿のあざな)がわが病の危篤を察し、その虚実を探らせんため、急に一手を差し向けてきたにすぎまい。魏延、魏延。すぐに出て駆け散らせ」
しょげていた魏延は日ごろの猛気を持ち返し、躍り直して出ていく。彼が陣前に現れると、さすがに鼓の音も鬨の声も一度に改まる。攻守たちまち逆転し、魏兵は駆け散らされ、夏侯覇は馬に鞭(むち)打ち逃げ出していた。
諸葛亮の病状は、このときから精神的にも再び回復を望み得なくなる。翌日、彼はその重体にもかかわらず、姜維を身近く招いて言った。
「予が今日まで学び得たところを書に著したものが、いつか24編になっている。わが言も、わが兵法も、またわが姿も、この内にある。いま、あまねく味方の大将を見るに、汝をおいてほかにこれを授けたいと思う者はいない」
諸葛亮は手ずから自著の書巻を積み、ことごとく姜維に授け、さらにこう言った。
「後事の多くは汝に託しておくぞ。この世で汝に会うたのは幸せのひとつであった。蜀の国は諸道とも天険。われ亡しとても、守るに憂いはない。ただ陰平(いんぺい)の一道には弱点がある。子細に備えて国の破れを招かぬように努めよ」
姜維が涙に暮れていると、諸葛亮は「楊儀を呼べ」と静かに言いつける。
★『三国志演義(7)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第104回)では、楊儀がやってくる前に諸葛亮は馬岱(ばたい)を呼び入れ、耳打ちして密計を授けていた。
そして楊儀にはこう言って、一書を秘めた錦の囊を託した。
「魏延は、後に必ず謀反するだろう。彼の猛勇は珍重すべきだが、あの性格は困りものだ。始末せねば国の害をなそう。わが亡き後、彼が背くのは必定である。そのときにはこれを開いてみれば、おのずから策が得られよう」
その夕方から、また容体が悪化する。昏絶(こんぜつ)してはよみがえること数度で、幾日となく、死生の彷徨(ほうこう)状態が続いた。
五丈原から漢中(かんちゅう)へ、漢中から成都(せいと)へと、昼夜の分かちなく駅次ぎの早馬も飛んでいる。成都からは即刻、尚書僕射(しょうしょぼくや)の李福(りふく)が下っていた。
★井波『三国志演義(7)』(第104回)では、尚書の李福とある。
劉禅の驚きと優渥(ゆうあく。極めて厚い様子)なる勅を帯し、夜を日に継いで急いでいるとは聞こえていたが、まだここ五丈原に到着をみない。
しかし幸いなことに、なお費禕(ひい)が滞在している。諸葛亮は、われ亡き後は彼に嘱するもの多きを思った。
諸葛亮は一日、その費禕を招き、懇ろに頼む。
「後主劉禅の君も、はやご成人にはなられたが、遺憾ながら先帝(劉備〈りゅうび〉)のごときご苦難を知っておられない。ゆえに世をみそなわすこと浅く、民の心をくむにも疎くおわすのは是非もない」
「ゆえに、補佐の任たる方々が心を傾けて、君の徳を高うし、社稷(しゃしょく。土地と五穀の神。国家)を守り固め、もって先帝のご遺徳を常に鑑(かがみ)として政治せられておれば間違いないと思う」
「才気辣腕(らつわん)の臣をにわかに用いて、軽率に旧(ふる)きを破り、新奇の政を布くは危うい因(もと)を作ろう。予が選び挙げておいた人々をよく用い、一短あり、一部欠点のある人物とて、みだりに捨てるようなことはせぬがいい」
「その中でも馬岱は忠義諸人に超え、国の兵馬を託すに足る者ゆえ、いよいよ重く扱うたがいい。諸政の部門は卿(けい)がこれを統轄総攬(そうらん)されよ」
「また、わが兵法の機密はことごとく姜維に授けておいた。戦陣国防のことは、まだ若しといえども彼を信じ、その重責にあたらせるとも、決して憂うることはなかろう」
以上の事々を費禕に遺言し終わってから、諸葛亮の面には、何やら肩の重荷が取れたようなすがすがしさが表れていた。
日々、そのような容体の繰り返されていたある朝のこと、諸葛亮は何を思ったか、「予を助けて車に乗せよ」と左右の者に言いだす。人々が怪しんで尋ねると、陣中を巡見するのだという。諸葛亮はすでに立ち、自ら清衣に改めた。
千軍万馬を往来した愛乗の四輪車が押されてくる。諸葛亮は白い羽扇を持ってそれに乗り、味方の陣々を見て回った。白露は轍(わだち)にこぼれ、秋風は面を吹き、冷気は骨に徹(とお)るものがあった。
「あぁ。旌旗(せいき)なお生気あり。われ亡くとも、にわかに潰(つい)えることはない」
諸葛亮は諸陣を眺め、さも安心したように見えた。だが、病室に帰るやすぐに打ち伏し、この日以来、とみに、物言うことばも柔らかになり、眉から鼻色には死の相が表れていた。
諸葛亮は楊儀を呼び、再び懇ろに何か告げる。また、王平(おうへい)・廖化(りょうか)・張嶷(ちょうぎ)・呉懿(ごい)などもひとりひとり枕頭(ちんとう)に招き、それぞれに後事を託するところがあった。
姜維に至っては、日夜そばを離れることなく、起居(たちい)の世話までしていた。諸葛亮は姜維にこう命ずる。
「几(つくえ)を備え、香を焚き、予の文房具を取りそろえよ」
やがて諸葛亮は沐浴(もくよく)して、几前(きぜん)に座る。それこそ蜀の天子(劉禅)に捧ぐる遺表だった。
遺表をしたため終わると、諸葛亮は一同に向かって訓(おし)えた。
「予が死んでも、必ず喪を発してはいけない。必然、司馬懿は好機逸すべからずと、総力を挙げてくるだろう」
「このような場合のために、日ごろからふたりの工匠(たくみ)に命じ、予の木像を彫らせておいた。これは等身大の座像だから車に乗せ、周りを青き紗(しゃ)をもって覆い、滅多な者を近づけぬようにして、孔明なお在りと、味方の将士にも思わせておくがいい」
「しかる後、時を計って魏勢の先鋒を追い、退路を開いた後、初めてわが喪を発すれば、おそらく大過なく全軍帰国することを得よう」
しばらく諸葛亮は呼吸を休めていたが、やがてこう言い足す。
「予の座像を乗せた喪車には、座壇の前に一盞(いっさん)の灯明をともし、米7粒と水少しを唇に含ませよ」
★井波『三国志演義(7)』(第104回)にも「米7粒を口の中に入れて……」という記述は見られた。だがこれは座像の口にではなく、(諸葛亮の)遺体の口に入れるよう言いつけられていた。
★井波『三国志演義(7)』の訳者注によると、「米7粒は北斗七星になぞらえたもの」だという。
「柩(ひつぎ)は氈車(せんしゃ)の内に安置し、汝らが左右を護って歩々(一歩一歩)粛々と通るならば、たとえ千里を還るも、軍中常のごとく、少しも乱れることはあるまい」
★『角川 新字源 改訂新版』(小川環樹〈おがわ・たまき〉、西田太一郎〈にしだ・たいちろう〉、赤塚忠〈あかつか・きよし〉、阿辻哲次〈あつじ・てつじ〉、釜谷武志〈かまたに・たけし〉、木津祐子〈きづ・ゆうこ〉編 KADOKAWA)によると、氈車は「毛氈などを張りめぐらした車」、毛氈は「毛と綿糸をまじえて織り、圧縮した織物。しき物などにする」とあった。
さらに退路と退陣の法を授け、語を結ぶにあたって言った。
「もう何も言いおくことはない。みなよく心をひとつにして、国に報じ、職分を尽くしてくれよ」
人々は流涕(りゅうてい)しながら、違背なきことを誓う。
黄昏(たそがれ)ごろ、諸葛亮は一時、息絶えたが、唇に水を受けると、また覚めたかのごとく目を見開き、宵闇の病床から見える北斗星のひとつを指さす。
「あれ、あの煌々(こうこう)と見ゆる将星が、予の宿星である。いま滅前の一燦(いっさん)をまたたいている。見よ、見よ。やがて落ちるであろう……」
言うかと思うと、たちまち諸葛亮の面は白蠟(びゃくろう)のごとく化して、閉じた睫毛(まつげ)のみが植え並べたように黒く見えた。
黒風(暴風)一陣。北斗は雲ににじみ、燦また滅、天ただ啾々(しゅうしゅう。ここでは「枯れ葉が音を立てている様子」の意か?)の声のみ。
だがその後、成都から勅使の李福が着くと、諸葛亮は再び目を見開いて言ったという。
「国家の大事を誤った者は自分だ。慙愧(ざんき)するほか、お詫びの言葉もない」
★このあたりは、井波『三国志演義(7)』(第104回)といくらか展開が異なる。李福は諸葛亮が亡くなる前(遺表を書く前)に五丈原に到着し、諸葛亮と話した後でいったん辞去していた。
そして彼が人事不省に陥った後、突然、李福が戻ってきたとあり、まもなく意識の戻った諸葛亮が、丞相の後任についての考えを伝えている。
それからまた、こう尋ねたという。
「臣亮の亡き後は、誰をもって丞相の職に任ぜんと……。陛下には、それをば第一に、勅使をもってご下問になられたことであろう。われ亡き後は、蔣琬(しょうえん)こそ丞相たる人である」
李福が重ねて尋ねる。
「もし蔣琬がどうしてもお受けしないときは、誰が適任でしょう?」
諸葛亮が答えた。
「費禕がよい」
李福がさらに次のことを尋ねると、もう返事がない。諸人が近づいてみると息絶え、まったく薨(こう)じていたというのである。
時は蜀の建興12(234)年の秋8月23日。寿54歳。これのみは、多くの史書も演義の類書もみな一致している。
彼の死は、蜀軍をしてむなしく故山に帰らしめ、また以後の蜀の国策も、一転機するのほかなきに至ったが、個人的にもずいぶん影響は大きかったらしい。
蜀の長水校尉(ちょうすいこうい)を務めていた廖立(りょうりゅう)という者は、前から自己の才名を頼み、同僚にもこのように放言していたくらいの男だった。
「孔明が俺を用いないなどというのは、人を使う目のないものだ」
その覇気と自負が過ぎるので、諸葛亮は一時、彼の官職を取り上げ、汶山(ぶんざん)という僻地(へきち)へ追って謹慎を命じた。
廖立は諸葛亮の死を聞くと、自己の前途を見失ったように嘆き、「吾(われ)終ニ袵(えり)ヲ左ニセン」と言ったということである。
★左袵(さじん)は、着物を左前に着る異民族の着方。
また、先に梓潼郡(しどうぐん)に流されていた前軍需相(ぜんぐんじゅしょう)の李厳(りげん)も、こう言った。
「孔明が生きてあらんほどには、いつか自分も召し還されることがあろうと楽しんでいたが、あの人が亡くなられては、自分が余命を保っている意味もない」
その後ほどなく、李厳も病を得て死んだと言われている。
★李厳が梓潼郡に流されたことについては、先の第300話(08)を参照。なお、当時の蜀に軍需相なる官職があったわけではない。
とにかく諸葛亮の死後は、しばらくの間、天地も寥々(りょうりょう)の感があった。ことに蜀軍の上には、天愁い地悲しみ、日の色も光がない。
姜維や楊儀らは遺命に従って深く喪を秘し、やがて一営一営と静かに退軍の支度をしていた。
管理人「かぶらがわ」より
まさに蜀そのものだったと言える諸葛亮の死。司馬懿との戦いに明確な決着はつきませんでしたが、やはりこれは「司馬懿の勝ち」ということになるのでしょうね。
吉川『三国志』は『三国志演義』がベースになっているので仕方ないのですけど……。李福が着いた後に諸葛亮を生き返らせる必要があったのか? とは感じました。

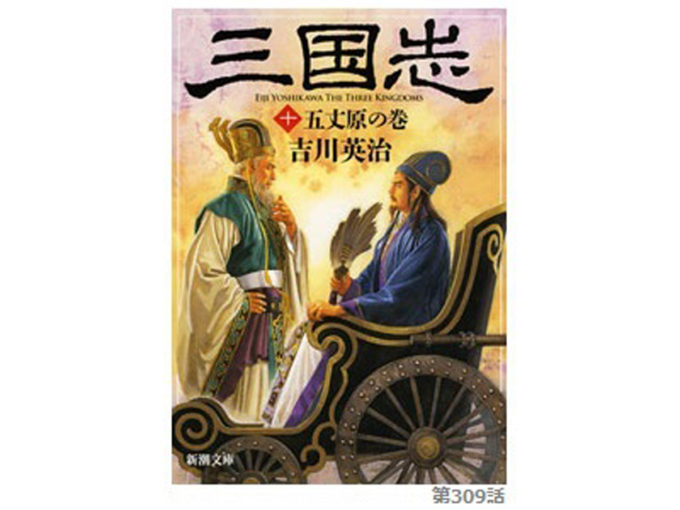















コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます