【姓名】 董卓(とうたく) 【あざな】 仲穎(ちゅうえい)
【原籍】 隴西郡(ろうせいぐん)臨洮県(りんとうけん)
【生没】 139?~192年(54歳)
【吉川】 第011話で初登場。
【演義】 第001回で初登場。
【正史】 登場人物。『魏書・董卓伝』あり。
歴史に残る暴虐宰相
父は董君雅(とうくんが)だが、母は不詳。董擢(とうてき)は兄で、董旻(とうびん)は弟。
董卓は若いころ男だてを気取り、羌族(きょうぞく)の住む地を放浪したことがあった。このときに羌族の顔役たちと交わりを結んだ。
のち郷里の隴西郡へ帰り、農耕に従事したが、羌族の顔役が訪ねてくると、耕牛を殺して宴会を催すほど歓迎した。顔役は意気に感じ、1千頭余りの家畜を集めて董卓に贈ったという。
桓帝(かんてい。在位146~167年)の末年、6郡(漢陽〈かんよう〉・隴西・安定〈あんてい〉・北地〈ほくち〉・上郡〈じょうぐん〉・西河〈せいか〉)の良家の子弟から羽林郎(うりんろう)が選抜された際、董卓も選ばれた。
董卓は戦功を上げて昇進したものの、たびたび免官になる。やがて彼は独自色を強めるに至った。
189年、董卓は大将軍(だいしょうぐん)の何進(かしん)の命を受けて上洛すると、混乱に乗じて勢力を拡大。
同年9月には、少帝(劉辯〈りゅうべん〉)を廃して献帝(劉協〈りゅうきょう〉)を擁立。少帝の生母である何太后(かたいこう)を毒殺した。
翌190年1月、袁紹(えんしょう)を盟主とする反董卓連合軍が挙兵。
同年2月、董卓は郎中令(ろうちゅうれい)の李儒(りじゅ)に命じ、弘農王(こうのうおう)に貶(おと)していた劉辯も毒殺。さらに長安(ちょうあん)への遷都を強行し、洛陽(らくよう)は焦土と化した。
翌191年2月、董卓は太師(たいし)に就任したうえ、尚父(しょうほ)と号する。4月には自身も長安へ入る。
翌192年4月、司徒(しと)の王允(おういん)と尚書僕射(しょうしょぼくや)の士孫瑞(しそんずい)が呂布(りょふ)と共謀。ついに董卓は誅殺された。
主な経歴
生年は不詳。
-166~167年-
このころ軍の司馬(しば)として、使匈奴中郎将(しきょうどちゅうろうしょう)の張奐(ちょうかん)に付き従い、幷州(へいしゅう)征伐で戦功を上げた。
このときの功により郎中(ろうちゅう)に任ぜられ、縑(きぬ)9千匹を賜ったが、恩賞は部下にみな分け与えた。
この後、広武県令(こうぶけんれい)、蜀郡北部都尉(しょくぐんほくぶとい)、西域戊己校尉(せいいきぼきこうい)と昇進したものの免官になる。やがて再び召し出され、幷州刺史(へいしゅうしし)・河東太守(かとうたいしゅ)に任ぜられた。
-184年-
この年、黄巾(こうきん)の乱が勃発。優勢に戦いを進めていた北中郎将(ほくちゅうろうしょう)の盧植(ろしょく)が、宦官(かんがん)の誣告(ぶこく)によって失脚すると、代わって中郎将として張角(ちょうかく)と戦うも敗れ、またも免官になった。
-187年-
この年、韓遂(かんすい)らが涼州(りょうしゅう)で反乱を起こし、隴西郡を包囲すると、再び中郎将に任ぜられ、西進して韓遂軍を防いだ。
このとき、董卓を含めて6つの軍が隴西へ向かったが、彼だけが兵を損ずることなく帰還し、扶風(ふふう)に駐屯した。功により前将軍(ぜんしょうぐん)に任ぜられ、タイ郷侯(たいきょうこう)に封ぜられた。
-188年-
この年、少府(しょうふ)に任ずるので、扶風に駐屯させている軍勢を左将軍(さしょうぐん)の皇甫嵩(こうほすう)に預け、行在所(あんざいしょ)へ出頭するよう詔(みことのり)を受けた。
そこで霊帝に上奏し、いまだ涼州が騒乱状態であること、配下の兵士が自分を慕い、引き留めていることを訴え、出頭命令には従わなかった。
-189年-
?月、霊帝の詔により幷州牧(へいしゅうぼく)に任ぜられ、配下の軍勢を皇甫嵩に預けるよう命ぜられる。再び霊帝に上奏し、軍勢をひきいて幷州の辺境地帯で尽力したいと訴え、このときも詔に従わなかった。
4月、霊帝が崩御(ほうぎょ)し、少帝が即位。大将軍の何進は、司隷校尉(しれいこうい)の袁紹(えんしょう)らと協力して宦官の誅滅を計画したものの、何太后は聞き入れようとしなかった。
?月、何進の命を受けて上洛し、宦官を誅殺する旨の上書を奉る。
8月、洛陽に到着する前、中常侍(ちゅうじょうじ)の張譲(ちょうじょう)や段珪(だんけい)により、何進が殺害される。これを受けて、袁紹や虎賁中郎将(こほんちゅうろうしょう)の袁術(えんじゅつ)が東宮と西宮を焼き、宦官を皆殺しにした。
段珪らは、少帝と異母弟で陳留王(ちんりゅうおう)の劉協を城外へ連れ出し、小平津(しょうへいしん)まで逃走。だが、段珪らは追い詰められて自殺した。
ほどなく少帝を北邙(ほくぼう)で出迎え、ともに洛陽へ帰還。
亡くなった何進の兵に加え、何進配下の部曲将だった呉匡(ごきょう)によって殺害された、車騎将軍(しゃきしょうぐん)の何苗(かびょう。何進の弟)の兵も手中に収めた。
さらに、呂布に命じて執金吾(しつきんご)の丁原(ていげん)を殺害させ、その配下の軍勢も併せる。こうして洛陽の軍権を一手に握ることに成功した。
8月、長期にわたって雨が降らなかったことを理由に、少帝が司空(しくう)の劉弘(りゅうこう)を罷免。その後任として司空に就任。
9月、太尉(たいい)に昇進。少帝から節(せつ。権限を示すしるし)と鉞(えつ。まさかり。軍権の象徴)を貸し与えられたうえ、虎賁兵を持つことも許された。
9月、少帝を廃して弘農王に貶し、陳留王の劉協を帝位に即ける(献帝)。
9月、何太后を毒殺。
10月、白波(はくは)の賊が河東郡に侵攻。部将の牛輔(ぎゅうほ)を遣わして討伐にあたらせる。
11月、相国(しょうこく)に昇進し、爵位も郿侯(びこう)に進む。併せて「帝に拝謁する際に名乗らなくてもよい」「剣を帯び、履(くつ)をはいたまま上殿してもよい」という特権も認められた。
董卓の母は池陽君(ちようくん)に封ぜられ、家令(かれい)と家丞(かじょう)を置くことが許された。
-190年-
1月、後将軍(こうしょうぐん)の袁術、冀州牧(きしゅうぼく)の韓馥(かんふく)、豫州刺史(よしゅうしし)の孔伷(こうちゅう)、兗州刺史(えんしゅうしし)の劉岱(りゅうたい)、河内太守(かだいたいしゅ)の王匡(おうきょう)、勃海太守(ぼっかいたいしゅ)の袁紹、陳留太守(ちんりゅうたいしゅ)の張邈(ちょうばく)、広陵太守(こうりょうたいしゅ)の張超(ちょうちょう)、東郡太守(とうぐんたいしゅ)の橋瑁(きょうぼう)、山陽太守(さんようたいしゅ)の袁遺(えんい)、済北国相(せいほくこくしょう)の鮑信(ほうしん)、長沙太守(ちょうさたいしゅ)の孫堅(そんけん)らが同時に挙兵。
それぞれ数万の軍勢を擁しており、袁紹を盟主に推挙した。このとき曹操(そうそう)は奮武将軍(ふんぶしょうぐん)を兼務した。
2月、郎中令の李儒に命じ、弘農王の劉辯を毒殺。
2月、城門校尉(じょうもんこうい)の伍瓊(ごけい)と督軍校尉(とくぐんこうい)の周毖(しゅうひ)を殺害。当初は伍瓊や周毖らを信任し、彼らが推挙した韓馥・劉岱・孔伷・張咨(ちょうし)・張邈らを取り立て、州や郡を治めさせることにした。
これが裏目となり、韓馥らは軍勢を糾合して反董卓連合軍を結成。このことを聞いた董卓は、伍瓊や周毖らが内通したと思い込み、彼らをことごとく斬殺した。
2月、献帝に迫り、長安への遷都を強行。洛陽の住民を追い立てて、西方の関中(かんちゅう)へ移らせる。一方で自身は洛陽に留まり、畢圭苑(ひっけいえん)に駐屯した。
3月、洛陽に火を放つよう命じ、宮廟(きゅうびょう)や民家を焼き尽くす。
3月、袁紹の一族である太傅(たいふ)の袁隗(えんかい)と太僕(たいぼく)の袁基(えんき)を殺害したうえ、その一族も皆殺しにする。
6月、五銖銭(ごしゅせん)を廃止し、新たに小銭(しょうせん)を鋳造。この貨幣は粗悪なもので、物価の暴騰を招いたため、結局は流通しなくなった。
この年、曹操の軍勢を滎陽(けいよう)で撃破した。
-191年-
2月、太師に就任したうえ、尚父と号する。
2月、部将の胡軫(こしん)が、陽人聚(ようじんしゅう)で孫堅に大敗する。
2月、洛陽近郊にある歴代の皇帝の陵墓を発(あば)き、財宝を奪い取る。
?月、孫堅が軍勢をひきいて洛陽へ入城。
4月、長安へ入城。弟の董旻は左将軍・鄠侯(ここう)に取り立てられ、甥の董璜(とうこう)は侍中(じちゅう)・中軍校尉(ちゅうぐんこうい)として軍勢を統率するなど、董卓の一族はみな高官となった。
?月、郿に城を築き、城壁を長安城と同じ高さとし、城内に30年分の穀物を蓄える。
10月、衛尉(えいい)の張温(ちょうおん)を殺害。
-192年-
4月、司徒の王允と尚書僕射の士孫瑞が呂布と共謀し、董卓の殺害を計る。
このとき献帝の病が快癒したことを寿ぎ、未央殿(びおうでん)に多くの臣下が列席する機会があった。呂布は騎都尉(きとい)の李粛(りしゅく)らに命じ、10人ほどの偽衛士を仕立てて掖門(えきもん)を固めさせた。
董卓は李粛に門の通過を阻まれると、呂布を呼んだ。呂布は懐から詔書を取り出すと、董卓を殺害。その三族(父母・妻子・兄弟姉妹、異説もある)も皆殺しにした。長安の士人や庶民は喜び合い、董卓に迎合していた者たちは投獄後に処刑されたという。
管理人「かぶらがわ」より
董卓は生まれつき武芸の才能があり、類いまれな腕力の持ち主だったそうです。馬を疾駆させながら、左右から矢を射ることができたのだとか。
本伝の裴松之注(はいしょうしちゅう)に引く司馬彪(しばひゅう)の『九州春秋』には、こういう話もありました。
「董卓が上洛した当初、配下の歩騎は3千にすぎなかった。これでは遠近の者を従わせることはできないと考え、夜になると4、5日おきに、配下の歩騎を城外へ出す」
「翌日には旗を連ね、陣太鼓を鳴らしてにぎやかに再入城させ、『西方の兵がまた洛陽に着いた』と宣伝した。人々はからくりに気づかず、『董卓の軍勢は数えきれないほど多い』とうわさした」のだと。
本伝には「董卓は残忍非情な性格で、厳しい刑罰をもって人々を脅し、わずかな恨みにも必ず報復した」ともあり、その性格を表すエピソードとして次のような話がありました。
「董卓が軍勢をひきいて陽城(ようじょう)へ赴いたとき、ちょうど春祭のために集まっていた男子の首をことごとく斬り、婦女子や財物を略奪した」
「斬り落とした首を車の轅(ながえ)にぶら下げて洛陽へ戻ると、『賊を討ち破り、大量の鹵獲品(ろかくひん)を得た』と吹聴し、万歳を唱えさせる始末」
「持ち帰った首は街中で焼かせ、略奪してきた婦女子を兵士たちに与えた。董卓は宮女や公主に暴行を加えるまでに及び、横暴を極めた」のだと。
さらに本伝には、このような話も。
「あるとき董卓が郿へ赴くことがあり、公卿(こうけい)以下がそろって横門(おうもん。長安城から北へ出る門のうち、最も西にある門)の外で送別の宴会が催された」
「あらかじめ董卓は幔幕(まんまく)を張って準備しておき、酒宴の席に、反乱を起こしたあと降伏した北地郡の数百人を引き入れた。董卓は降伏者の舌を切らせると、手足を切ったり眼をくりぬかせたりし、大きな鍋で煮たりもした」
「死にきれない者が机の間を転げ回り、皆が箸やさじを取り落としても、董卓だけは平然と飲み食いを続けていた」
「太史(たいし)が雲気を観て占い、『公卿の中に死刑になる者がいるはずです』と伝えた。董卓は、かねて恨んでいた衛尉の張温に、袁術と内通したと言いがかりをつけ、鞭(むち)で打ち殺した」
「法令が過酷であるうえ、愛憎により刑罰を乱用したため、人々は互いに誣告し合うようになった。冤罪(えんざい)で死ぬ者は4桁の数に上った」
そして本伝の裴松之注に引く『英雄記(えいゆうき)』には、「董卓の屍(しかばね)は市場にさらされた」とありました。
「見張りの役人は、日が暮れると大きな灯心を作り、これを董卓のへそに置いた。明かりは朝まで消えず、このようなことが何日も続いた」のだとも。
『三国志』には、こういう桁外れの人物も登場しますよね。豪快な親分というわけでもないですし、董卓には何か病的なものを感じました。
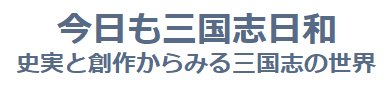














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます