広大な蜀の地を手にした劉備(りゅうび)に対し、孫権(そんけん)も当然のごとく、荊州(けいしゅう)返還問題の決着を迫る。
使いを命じた諸葛瑾(しょかつきん)が戻り、劉備が荊州のうち3郡の返還を認めたとの報告を受けると、孫権は官吏に軍勢を付けて差し向けた。ところが、みな関羽(かんう)の配下に追い払われてしまう。
第205話の展開とポイント
(01)成都(せいと)
ある日、劉備は、やや狼狽(ろうばい)の色を眉にたたえながら、諸葛亮(しょかつりょう)を呼んで言った。
「先生の兄上が蜀へ来たそうではないか」
諸葛亮は、昨夜客館に着いたようだと話し、もとより荊州の問題で見えたのだろうと言う。そして座へ寄り、劉備の耳元に何かささやく。
(02)成都 諸葛瑾の客館
その晩、諸葛亮は不意に兄の諸葛瑾を訪ねる。
諸葛瑾は声を放って大いに泣き、妻子一族がみな呉で投獄されたと話す。
諸葛亮は、お気遣いには及びませんと言い、君に申し上げ、きっと荊州は呉へ還しますと応じた。
(03)成都
翌日、諸葛瑾は密かに劉備と会い、孫権の一書を呈する。劉備はそれを披見し、たちまち色をなす。諸葛瑾はハッとした。そばにいた諸葛亮も目を見張った。
劉備の手にある書簡は引き裂かれ、その眸(ひとみ)は天の一方を見て、独り言にこう叫ぶ。
「無礼なり孫権――。もとより荊州はいつか呉へ還さんとは思っていたが、汝(なんじ)いたずらに小策を弄(ろう)し、わが夫人(つま)を欺いて呉へ呼び返すなど、玄徳(げんとく。劉備のあざな)の面目を無視し、夫婦の情を虐げ、いつかはこの恨みをと骨髄に刻んでいた心を知らないかっ!」
「むかし一荊州にありしときだに、汝ごときは物の数としていた我ではない。いわんや今、蜀四十一州を併せて精兵数十万、肥馬無数、糧草は山野に蓄えて、国人(くにびと)みな時に当たるの覚悟を持つ。汝いかに狡知(こうち)を弄すとも、力をもって荊州を取ることを得んや」
ここで諸葛亮が面を覆って嘆き悲しみ、兄と妻子一族のため配慮を求める。
すると劉備も次第に感情を抑制し、荊州のうち長沙(ちょうさ)・零陵(れいりょう)・桂陽(けいよう)の3郡だけを呉へ還すと言いだす。
(04)荊州(江陵〈こうりょう〉?)
結局、諸葛瑾はその趣を記した劉備の書簡をもらい、山羈(さんき。山の旅)舟行数十日、荊州へ着くや城を訪れ関羽と対面した。関羽のそばには養子の関平(かんぺい)が侍立していた。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると「荊州城は地名で(ここでは)江陵を指す。後漢末、関羽が荊州を守ってきたときここに駐屯していた」という。
この解説により、最近の荊州(城)がどの城のことなのかという疑問もだいぶ解けた気がする。ただ、この項目は『三国志演義』(第73回)の荊州城が対象になっていて、上の記述に対応する『三国志演義』(第66回)を対象にしたものではなかった。
結局、荊州城を巡る『三国志演義』や吉川『三国志』のわかりにくさは解消されないままだ。劉備の入蜀時には襄陽にいたように見える諸葛亮と関羽だが、後に諸葛亮が張飛(ちょうひ)や趙雲(ちょううん)らと蜀へ援軍に駆けつけた際は、公安(こうあん)から出発しているようにも見える。さらにこの第205話あたりの記述では、確かに関羽は江陵にいるように見える。「荊州へ行く」という書き方ではなく、「荊州の○○へ行く」というふうに、明確に街(城)の名を記すようにしてほしかった。
諸葛瑾は劉備の書簡を示し、3郡返還の手配を申し入れたが、関羽は呉の計略だと言って聞こうとしない。
やむなく諸葛瑾は荊州から再び成都へ向かい、劉備に訴えようとしたものの、折から病中とあって典医(てんい)が面会を許さなかった。ならばと弟の諸葛亮に会おうとすれば、郡県の巡察に出張中で、しばらくは成都に帰らないという。
★『三国志演義(4)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第66回)では、ここで諸葛瑾は劉備には会えていた。諸葛亮のほうは巡察に出ていて会えなかったという同様の設定。
(05)建業(けんぎょう)
千里の往来もむなしい旅となり、諸葛瑾は呉へ帰ってくる。
孫権は、みな諸葛亮のからくりに違いないと足ずりして怒ったが、仮に獄中につないでおいた諸葛瑾の家族は帰した。
孫権は諸官吏を荊州へ遣り、劉備が言った以上、強硬に交渉して関羽の下の地方官吏を追い払い、汝らの手で3郡の政庁を取って代われと厳命する。
もちろん軍隊もついていったが、ほど経てからそれらの官吏はみな逃げ帰ってきた。関羽の部下に追い払われたのだという。軍隊のほうはひどい目に遭わされ、生きて帰った兵は3分の1しかいなかった。
これを受けて魯粛(ろしゅく)が進言。陸口(りくこう)の塞外にある臨江亭(りんこうてい)に会宴を設け、関羽を招き、よく談じてみるという。もし彼が聞かなければ、即座に刺し殺してしまうとも。
反対する者もあったが孫権は許可し、早く行けと魯粛を励ました。
(06)臨江亭
船に兵を積み、表には親睦の使いと唱え、魯粛は揚子江(長江)を遠くさかのぼっていく。
そして、陸口城市の河港に近い風光明媚(めいび)の地、臨江亭に盛大な会宴の準備をする。一面では呂蒙(りょもう)や甘寧(かんねい)らに、関羽が見えた後の計を伝えていた。
臨江亭は湖北省(こほくしょう)にある。荊州は言うまでもなく湖南の対岸。
★このあたりの地理の説明がわかりにくい。臨江亭はいいとして、ここで湖南の対岸(にある荊州)と言っているのは、益陽(えきよう)のことではないだろうか?
湖南が現在の湖南省という意味で使われたのか、洞庭湖(どうていこ)の南という意味で使われたのかはわからないが、やはり益陽を指して荊州と呼んでいる気がする。もしそうだとすれば、史実と『三国志演義』の創作がごちゃ混ぜになった印象で、益陽を荊州と称するのはまずい。
なお井波『三国志演義(4)』(第66回)では、以下に出てくる魯粛の使者は船で長江を渡り、北岸へ上がったあと関平の尋問を受け、関平に連れられ荊州城へ行っていた。この記述なら荊州城が江陵城に見える。
魯粛の使いは舟行して江を渡った。しかもその使いは、ことさら華やかに装い、従者に麗しい日傘をかざさせ、いかにも悠暢(ゆうちょう)に会宴の招待に行く使いらしく、平和に漕(こ)いでいった。
(07)荊州(江陵?)
やがて魯粛の使いは荊州の江口から城下に入り、謹んで書を呈する。関羽は簡単に承諾して使いを返した。
関平は驚き、かつ危ぶんで諫めるが、関羽は案ずるなと応ずる。供は周倉(しゅうそう)ひとりを連れていくという。
さらに関平には、精兵500人に早舟20艘(そう)をそろえ、こなたの岸に遠く控えているよう伝える。もし父が彼方(あなた)の岸で旗を揚げて招くのを見たら、初めて舟を飛ばして馳(は)せつけてこいとも。
★井波『三国志演義(4)』(第66回)では、関羽が関平に用意を命じたのは腕利きの水兵500と10隻の快速船。
その日になると関羽は緑の戦袍(ひたたれ)を着け、盛冠花鬚(かびん)、ひときわ装い小舟に乗る。供の周倉は「桃園の義盟」以来、関羽が常に離すことなき82斤の青龍刀を持ち、主人の後ろに控えていた。
(08)臨江亭
もし関羽が大兵を連れてきたら、鉄砲を合図に呂蒙と甘寧の二軍で袋包みにしてしまおう――。これが魯粛の備えた第一段の計だった。
ところが案に相違して、関羽は常にもなく華やかに装い、供ひとりを連れてきたので、「さらば第二段の計で」と、早くも目くばせを交わし合っていた。臨江亭の庭後に屈強な武士ばかり50人を伏せ、ここへ関羽を迎えたのである。
もちろん沿道の林間、園内随所の林泉の陰にも雑兵は充満している。とはいえ、客の視野にはひと筋の素槍(すやり)の光だに、目に触れないよう隠してあった。
魯粛は拝伏して、関羽を上賓の席に据え、酒を勧め、歌妓(かぎ)や楽女(がくじょ)をして歓待させたが、話になると眸を伏せた。どうしても関羽の目を正視できない。
しかし酒が半酣(はんかん)のころ、ようやくややくつろいだ態を仕向け、荊州の返還問題に触れる。
魯粛が舌鋒鋭く急所を突くと、関羽も答えに詰まり、「家兄(このかみ)の皇叔(こうしゅく。天子の叔父。ここでは劉備のこと)には、別に正当なご意見があることでしょう。それがしの与(あず)かり知ることではない」と言い逃れた。
それでも魯粛は「桃園の義」を持ち出し、あなたが与かり知らぬでは世間が通さないと畳みかける。
すると、関羽のそばに立っていた周倉が突然、家鳴りするような声で怒鳴った。
「天上地下、ただ徳ある者がこれを保ち、これを政(まつり)するは当然。あに荊州を領する者、汝の主である孫権でなくてはならぬという法があろうかっ!」
ハッと色を変じながら、関羽が席から突っ立つ。そして、周倉に持たせておいた偃月(えんげつ)の青龍刀を引ったくるように取って叱りつける。
「周倉、黙れっ。これは国家の重大事である。汝ごときがみだりに舌を動かすところではない!」
騒然と亭中は色めき立った。やにわに関羽が巨腕を伸ばし、魯粛の臂(ひじ)をつかんで歩きだしただけでなく、周倉が亭の欄まで走り、江上へ向かってしきりに赤い旗を振ったのを見たからである。
関羽は大酔したふうを装いながら、今日はひとまずお別れしようと言い、魯粛を伴い江岸まで出てきた。呂蒙と甘寧は大兵を伏せ、関羽を討ち漏らさぬようにと鉄桶(てっとう)の構えを備えている。
だが、関羽の右手には大反りの偃月刀が、また左手には魯粛がつかまれているのを見て、うかつに出るなと制し合った。
その間に関羽は、周倉が寄せた小舟に飛び乗ってしまう。そこで初めて魯粛を岸へと突っ放し、「おさらば」とひと言、岸を離れた。
交渉はここに破れ、国交の断絶は避けがたい。魯粛のつぶさな書状を奉じ、早馬は呉の秣陵(まつりょう)へ急ぎに急いだ。
呉の国都には、これと同時に別の方面から、魏の曹操(そうそう)が30万の大軍をもって南下しつつある、という飛報が入っていた。
★すでに秣陵は建業と改称されており、ここで秣陵の名を持ち出すのは適切でない。このことについては先の第193話(01)を参照。
管理人「かぶらがわ」より
この第205話では「単刀会」として有名なエピソードが描かれていました。
『三国志』(呉書・魯粛伝)には魯粛と関羽が会見したことは見えますが、これは益陽でのこと。そのときの会見の流れは、ここで語られたものに大筋こそ似ていましたが、やはりというか、だいぶ関羽側を持ち上げぎみです。

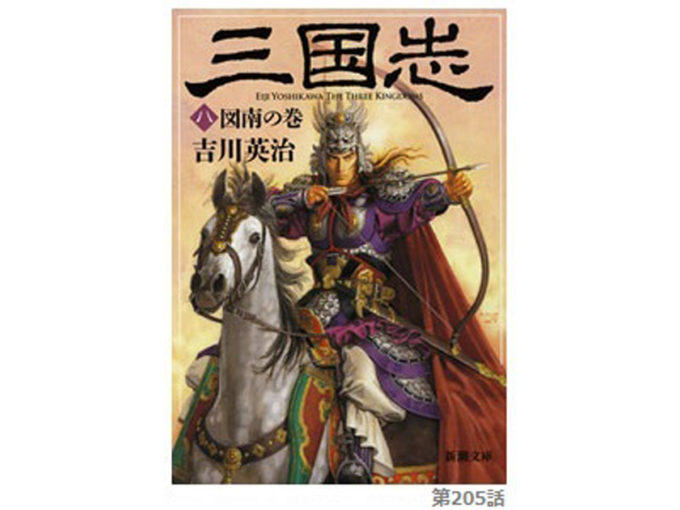














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます