曹操(そうそう)と孫権(そんけん)は濡須(じゅしゅ)で激戦を続けていたが、孫権は軽率な判断から劣勢を招き、陸遜(りくそん)がひきいた援軍の到着で何とか総崩れを免れる。
陸遜の反撃を受けた曹操軍は一転して敗北を喫し、その勢いも大きく削がれる。さらにひと月余りの対陣を経て、両軍の間で和睦がまとまった。
第211話の展開とポイント
(01)濡須
曹操は百戦錬磨の人。孫権は体験が少なく、ややもすれば血気に陥る。今や濡須の流域を境として、魏の40万、呉の60万、ひとりも戦わざるはなく、全面的な大激戦を現出した。
天候が利さなかったとはいえ、呉は孫権の軽忽(けいこつ)な動きにより軸枢を見失う。孫権自身もまんまと張遼(ちょうりょう)と徐晃(じょこう)の二軍に待たれ、その包囲鉄環の内に捉われてしまった。
曹操は小高い丘の上から心地よげに見ていたが、「今ぞ、孫権を擒(とりこ)にするのは」との声に、許褚(きょちょ)が馬を飛ばして駆け入る。
呉兵の死屍(しし)は累々と積まれ、あまりの惨状に孫権の姿すらどこにあるのか、誰が誰なのか見分けもつかぬばかりだった。
呉の周泰(しゅうたい)はその中をよく奮戦し、一方に血路を開き、河流の岸まで逃れてくる。顧みると、なお孫権は囲みから出られず、彼方(かなた)にあってもみ包まれている様子。周泰は孫権に呼ばわりつつ、敵の背後へ回って包囲を脅かす。
そして一角が崩れるのを見ると孫権と駒を並べ、脇目も振らずに矢道を走り抜けた。そこへ折よく、呂蒙(りょもう)の一軍が中軍の大敗を案じて引き返してきた。周泰は声をからして呼び、ともあれ孫権を舟へ移す。
孫権が徐盛(じょせい)のことを心配すると、周泰は魏の人馬の中へ戻っていく。しばらくすると、周泰は徐盛を助けて帰った。けれどふたりとも満身朱(あけ)にまみれ、水際まで来たところで歩む力もなく座ってしまう。
その間に呂蒙は射手100人の弓陣を布き、追ってくる敵を食い止め、さらに弓陣を船上に移し、孫権を守りながら下流へ退陣した。
この戦いでは、呉の陳武(ちんぶ)が悲壮な討ち死にを遂げる。彼は魏の龐徳(ほうとく。龐悳)の勢に包まれて退路を失い、次第に山間の狭隘(きょうあい)へ追い込まれた末、龐徳と闘って首を取られた。
曹操は、前夜に中軍を攪乱(かくらん)された不愉快な思いを、今日は万倍にもして取り返した。
わずかな将士に守られ、孫権が濡須の下流へ落ちていくと見るや、曹操は「あれを見失うな!」と、自ら江岸に沿いつつ士卒を励まし、数千の射手に絶好な的を競わせる。
だが、この日の風浪は孫権の僥倖(ぎょうこう)となり、ついに彼の身まで届く一矢もなかった。
そのうえ広やかな河の合流点まで来ると、本流の長江のほうから、呉の兵船が数百艘(そう)もさかのぼってきた。これは陸遜がひきいた10万の味方で、孫権は初めて蘇生の思いをなす。
しかし10万の味方を見ても、孫権以下の諸将はみな重軽傷を負っていたので、退くことしか考えていなかった。
陸遜は、活を入れようとして言う。
「このまま総退軍しては、曹操は呉に対していよいよ必勝の信念を持つ。また味方の兵も、魏は強しと深く彼を恐れ、勝ちを忘れるに至るであろう。退くにせよ、呉にもなお後備の実力のあることを示してからでなければならん」
陸遜は孫権や重傷者を船に残し、その余の残兵に守らせると、新手の10万をすべて岸へ上げ、呉のために死せよと命ずる。曹操は、呉の新手の堅陣が射る確かな矢風に射立てられ、形勢の悪化に狼狽(ろうばい)せざるを得なかった。
陸遜は曹操がひるみ立った刹那、総突撃を敢行する。兵数や新手の精気において、陸遜軍は圧倒的に優れていた。討ち取った兜首が700余級、雑兵に至っては数えきれない。分捕りの馬匹(ばひつ)だけで1千余頭もあった。
こうして陸遜は魏の勢を遠く追い、完全なる呉の勝利を取り返したばかりでなく、先に孫権が大敗した戦場まで行き、味方の死体や旗、それにおびただしい陣具まできれいに収容した。
その結果、陳武は討たれ、董襲(とうしゅう)は水中に溺れ、このほか日ごろの寵臣も無数に亡き数に入ったことがわかった。
孫権は声を上げて泣き、「せめて董襲の死骸なりとも捜し求めよ」と、水練に長じた者を入れて屍(しかばね)を求め、厚く船中に祭って引き揚げたという。
(02)濡須城
濡須城まで帰った孫権はある日、営中に宴を設ける。そして自ら杯を取ると、こう言って周泰に杯を持たせた。
「周泰。汝(なんじ)は呉の功臣だぞ。今日以後、われは汝と栄辱をともにし、命のある限りこのたびの働きは忘れない」
また、「先ごろの傷はどうか?」と肌を脱がせ、その傷跡を見る。
「あぁ、この傷跡のひとつひとつが、みな汝の忠魂と義心を語っている。皆も見よ。武人の亀鑑を――」
孫権は周泰の背をなで、果てしなく彼の誠をたたえた。さらに、彼の功を平常にも輝かすべく、羅(うすもの)の青い蓋(がい)を張らせ、「陣中に用いよ」と与えた。
もちろん陸遜以下の諸将にも、おのおの恩賞は行われ、依然として濡須の堅塁を誇り、末輩に至るまで意気は高かった。
対陣は1か月余になる。ここで孫権は張昭(ちょうしょう)の進言を容れ、歩隲(ほしつ。歩騭)を遣わして和議を申し入れた。
★『三国志演義(4)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第68回)では、孫権に和議を進言したのは張昭と顧雍(こよう)。
曹操からは「中央の府に対し、毎年貢ぎを献ずるというならば――」と、案外受けやすい条件が提示されたため、たちまち和睦はまとまった。
★井波『三国志演義(4)』(第68回)では、この条件で和平を申し入れたのは孫権のほう。
それでも、真の平和の到来でないことは、魏にも呉にもわかっていた。曹操は全軍をひきいて都(許都〈きょと〉)へ帰り、孫権も秣陵(まつりょう)へ引き揚げた。
ただ、その前線たる濡須口も、魏の境界たる合淝(がっぴ。合肥)の守りも、双方ともいよいよ堅固に堅固を加え合うばかりだった。
★なぜ旧称の秣陵にこだわるのかわからないが、ここは改称後の建業(けんぎょう)とすべきだろう。このことについては先の第193話(01)を参照。
管理人「かぶらがわ」より
激戦となった濡須口の戦いでしたが、和睦による決着が図られます。吉川『三国志』では魏軍が40万、呉軍が60万とありましたが、この数は正史『三国志』には見えないもの。
『三国志演義』もそうですが、赤壁(せきへき)の戦いなどでも訳がわからないほど両軍の兵力を盛っています。話を大きく見せるためなのでしょうか? 魏はともかく、この時期の呉に、60万という大軍を動員する力はなかったでしょう。
この後にも同じような傾向が見られますので、そのあたりを史実と比べてみるとおもしろいと思います。

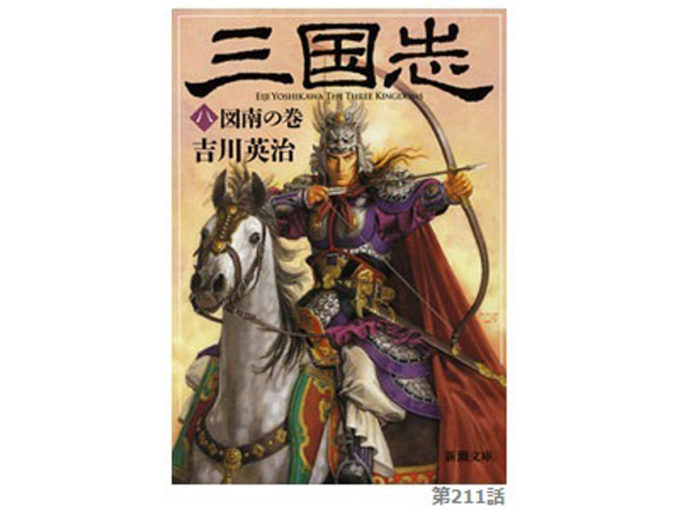














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます