漢水で黄忠(こうちゅう)と趙雲(ちょううん)に敗れた曹操(そうそう)は、北山(ほくざん)に続いて米倉山(べいそうざん)も失い、南鄭(なんてい)の辺りまで引く。
さらに曹操は、陽平関(ようへいかん)も捨てて斜谷(やこく)へ後退したが、ここで思わぬ援軍が現れる。代州(だいしゅう)の反乱を治めに遣わしたはずの息子、曹彰(そうしょう)だった。
第223話の展開とポイント
(01)漢水
横道から米倉山の一端へ出て、魏の損害をさらに大にしたものは、蜀の劉封(りゅうほう)と孟達(もうたつ)だった。
これらの別動隊は、もちろん諸葛亮(しょかつりょう)の指図により遠く迂回(うかい)し、敵も味方も不測な地点から、黄忠や趙雲らを助けたものである。
それにしても、ふたり(黄忠と趙雲)の功は大きい。わけて趙雲の今度の働きには、平常よく彼を知る劉備(りゅうび)も、「満身これ胆(きも)の人か」と、いまさらのように嘆称した。
その後の敵情を探るに、さしもの曹操も、予想外の損害にすぐ立ち直ることもできず、遠く南鄭の辺りまで退陣し、ひたすら軍の増強を急ぎつつあるという。
(02)漢水 徐晃(じょこう)の本営
ここに巴西(はせい)宕渠(とうきょ)の人で王平(おうへい)、あざなを子均(しきん)という者がある。この辺の地理に詳しいことから曹操に挙げられ、牙門将軍(がもんしょうぐん)として用いられていた。
王平は徐晃の副将となり、ともに漢水の岸に立ち、次の決戦を計っていたが、徐晃が「河を渡って陣を取らん」と言うのに反対し、「水を背にするは不利だ」と主張していた。
けれど徐晃はこう言い、浮き橋を渡して漢水を越える。
「韓信(かんしん)にも背水の陣があったことを知らぬのか。孫子も言っている。『死地ニ生アリ』と。ご辺(お前)は歩兵をひきいて岸に防げ。俺は馬武者をひきいて敵を蹴破るから」
(03)漢水 劉備の本営
徐晃は一歩対岸を踏んだらば、必ず蜀の勢が鼓を鳴らして向かってくるだろうと予測していたが、一本の矢すら飛んでこない。
拍子抜けしながらも、敵の柵を破壊し、壕(ほり)を埋め、日没に近づくと、蜀の陣地に対してある限りの矢を射た。
劉備のそばにいてこの日、敵のなすままにさせていた黄忠や趙雲は、夜になる前に退く気だとつぶやき、その退路を脅かすのは今だがと、身をむずむずさせていた。
劉備も機微を察したか、急に命令を下してふたりを急き立てる。勇躍した黄忠と趙雲は、薄暮の野に兵を動かし始めた。徐晃は蜀兵を見ると、終日の血の飢えを一気に満たさんとする餓虎のようにおめき出る。
黄忠の部下は、一時は鼓を鳴らして喚声を上げ、甚だ盛んに見えたが、脆(もろ)くも潰(つい)え、蜘蛛(クモ)の子のように夕闇へ逃げなだれた。
徐晃はわざと敵を辱めながら、どうかして黄忠を捕捉しようと試みるも、そのうち後ろのほうで敵のどよめく気配がする。ハッと驚いて振り向くと、漢水の浮き橋が炎々と燃えていた。
徐晃は急に引き返し、全軍に向かい「渡渉退却!」とわめいたが、河原の草木はことごとく蜀兵と化し、趙雲と黄忠が包囲してくる。
(04)漢水 徐晃の本営
ようやく徐晃は危地を切り抜け、ほとんど身ひとつで漢水の向こうまで逃げてきた。この敗戦の罪が、あたかも副将の罪でもあるかのごとく当たり散らし、味方の王平を罵った。
「何だって足下(きみ)は俺の後詰めもせず、浮き橋を焼かれるのを黙って見ていたのだ。この報告はつぶさに魏王(曹操)へ申し上げるぞ!」
王平は黙然と罵言に耐えていた。
けれど意見を異にしたときから、すでに徐晃の無能を蔑み、魏軍に見切りをつけていたものとみえる。その夜の深更(深夜)、王平は自分の陣地に火を放つや、密かに脱して漢水を越え、部下とともに蜀へ投降してしまった。
「招かずして王平が降ってきたのは、われ漢水を取る前表である」
劉備は彼を容れて偏将軍(へんしょうぐん)に任じ、もっぱら軍路の案内者として重用した。
(05)漢水 曹操の本営
徐晃のしたまずい戦は、すべて王平の罪に嫁された。曹操は憤懣(ふんまん)に憤懣を重ね、再び漢水を前面にして重厚な陣を布く。
(06)漢水 劉備の本営
一水を隔て、劉備は諸葛亮とともに、冷静にその動きを眺めていた。
諸葛亮が言う。
「この上流に七丘を巡らせ、一山をなしている山地があります。蓮華(レンゲ)のごとく七丘の内は盆地で、よく多数の兵を隠すことができる。銅鑼(どら)や鼓を持たせ、あれへ兵6、700を埋伏させておけば、必ず後に奇功を奏しましょう」
劉備が適任者を問うと、諸葛亮は、万一敵に見つかると、一兵残らず殲滅(せんめつ)の憂き目に遭う恐れもあるので、やはり趙雲を遣るしかないと答えた。
翌日、諸葛亮はまた別の一峰に登り、魏の陣勢を眺めていた。この日、魏の一部隊は渡渉してしきりに矢を放ち、鉦(かね)を叩き、罵詈(ばり)を浴びせたが、蜀は一兵も出さなかった。
(07)漢水 曹操の本営
魏兵もより以上、軽々しく進出はしない。夜に入るとことごとく陣に収まり、篝火(かがりび)もかすかに自重していた。
すると突然、真夜中の静寂を破って一発の石砲が轟(とどろ)く。銅鑼・鼓・喚呼などをひとつにして、ワアッという声が一瞬天地を翔(か)け去った。上を下への騒動である。
曹操は安からぬ思いを抱き、四方の闇を見回していたが、何の発見もなかった。
「いたずらに騒ぐをやめよ。立ち騒ぐ兵どもを眠らせろ」
曹操も枕に就いたが、また爆音や鬨(とき)の声がする。それがいったいどこでするものか、見当がつかない。
3日の間、毎晩である。曹操は士卒が寝不足になった様子を見て、急に30里ほど退き、広野のただ中に陣を営み直した。
(08)漢水 劉備の本営
諸葛亮は笑って、「曹操も怪(け)に取り憑(つ)かれた」と言った。もちろん夜ごとの砲声や銅鑼は、上流の盆地に潜んだ趙雲軍の仕業であったこと言うまでもない。
4日目の夜が明けてみると、蜀軍は先鋒から中軍もみな河を渡り、漢水を後ろに陣容を展開していた。
(09)漢水の近く 曹操の本営
曹操は、敵が背水の陣を取ったことを疑いもし、かつその決意のただならぬものを悟り、「明日、五界山(ごかいざん)の前にて会わん」と戦書を送った。戦書、すなわち決戦状である。劉備も快く承知した。
★『三国志演義大事典』(沈伯俊〈しんはくしゅん〉、譚良嘯〈たんりょうしょう〉著 立間祥介〈たつま・しょうすけ〉、岡崎由美〈おかざき・ゆみ〉、土屋文子〈つちや・ふみこ〉訳 潮出版社)によると、「五界山は山の名。益州(えきしゅう)漢中郡(かんちゅうぐん)の漢水北岸にあるとされる。後漢・三国時代にはこの地名はなかった」という。
(10)五界山のふもと
曹操と劉備は陣頭で言葉を交わした後、戦線数里にわたる大野戦を展開。午(うま)の刻(正午ごろ)を過ぎるまで、魏の大勝をもって終始した。
蜀兵は馬や物の具を捨て、我がちに壊走しだす。しかし曹操は退鉦(ひきがね)を打たせる。魏の諸将は疑ったが、蜀兵の壊走が本当でないとみたので大事を取ったものだ。
ところが魏軍が退くと、果然として蜀軍は攻勢に転ずる。どうも曹操は事ごとに自分の知恵と戦い、その知に敗れている形だった。かくて曹操が自負していた知謀も、かえって彼の黒星を増すばかりとなる。
甚だしく精彩を欠いた魏軍は、南鄭から褒州(ほうしゅう)の地も連続的に敵の手に任せ、一挙に陽平関まで追われてしまった。
蜀の大軍は、すでに南鄭・閬中(ろうちゅう)・褒州の地方にまで浸透して、宣撫(せんぶ)や治安に取りかかり、遺漏のない完勝ぶりを示していた。
★『三国志演義大事典』によると「褒州は正しくは褒中県(ほうちゅうけん)。後漢では益州漢中郡に属す」という。
(11)陽平関
ここへまたも、味方の兵糧貯蔵地の危急が聞こえてくる。曹操は許褚(きょちょ)を呼び、兵糧奉行(ひょうろうぶぎょう)の手勢と協力し、危地にあるすべての兵糧を、後方の安全な場所へ移すよう言いつける。
(12)魏軍の兵糧貯蔵地(場所は不詳)
許褚が1千余騎をひきいて着くと、兵糧奉行は歓喜して迎える。うれしさのあまりか、兵糧奉行は歓迎しすぎた。許褚は宴に臨み、大酔してしまったのである。
(13)褒州
宵に出て夜半(よなか)ごろ、延々たる輜重(しちょう)の行軍は褒州の難所へかかった。すると谷間から一軍の蜀兵が突貫してきた。
許褚が、下の谷にいる敵に岩石を落とせと言うと、今度は自分たちの頭上から岩や石ころが落ちてくる。伏兵は山の上下にいた。
輜重車は、なだれ下って谷間の懐へ出る。だが、ここに張飛(ちょうひ)の部隊が待っており、張飛は大矛を差し伸べて許褚の肩先を突く。不覚にも許褚は、戦わないうちから痛手を受けたのみか、どうと馬から転げ落ちた。
張飛の二の矛がとどめを刺そうとしたとき、彼の鞍(くら)の腰へも大きな石が当たる。張飛の馬が跳ねたとたん、許褚の部下が切っ先をそろえて立ちふさがった。
許褚は部下に助けられ、辛くも一命は拾い得たが、輜重の大部分は張飛の手勢に奪われ、ほうほうの態で陽平関へ逃げ戻る。
(14)陽平関
すでに陽平関は炎に包まれていた。敗れては退き、敗れては退き、前線からなだれくる味方は関の内外に充満し、曹操の所在もわからない。
「北門を出、斜谷を指して、退却しておられる」
味方の一将からこう聞くと、許褚は事態の急に驚きながら、ひたすら主君を追い慕った。
(15)斜谷
曹操は扈従(こじゅう)や旗本に守られ、陽平関を捨ててきたが、斜谷に近づくと、彼方(かなた)の険は天を覆うばかりな馬煙を上げている。
諸葛亮の伏兵かと色を失うも、これは次男の曹彰が、5万の味方をひきいて駆けつけたものだった。
曹彰は父とは別に、代州烏丸(うがん)の夷(えびす)の反乱を治めに行っていた。しかし漢水方面の大戦の不利を聞き、あえて父の命も待たず、夜を日に継いで加勢に向かってきたのだった。
よほどうれしかったとみえ、曹操は馬上から手を差し伸べてわが子の手を握り、しばらく離さなかった。
★後漢時代に代州という行政区画は存在しない。新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると「(代州は)後漢では幷州(へいしゅう)の東端部にあたる」という。
★新潮文庫の註解によると「(烏丸は)幽州(ゆうしゅう)北部に居住する騎馬民族。かつて曹操に平定された。第5巻『遼西・遼東(りょうせい・りょうとう)』参照」という。
管理人「かぶらがわ」より
兵糧の貯蔵地を次々に失い、ついに漢中から斜谷へ退く曹操。ここで曹彰が到着しましたが、漢中攻防戦の救援としては少し遅かったかもしれません。

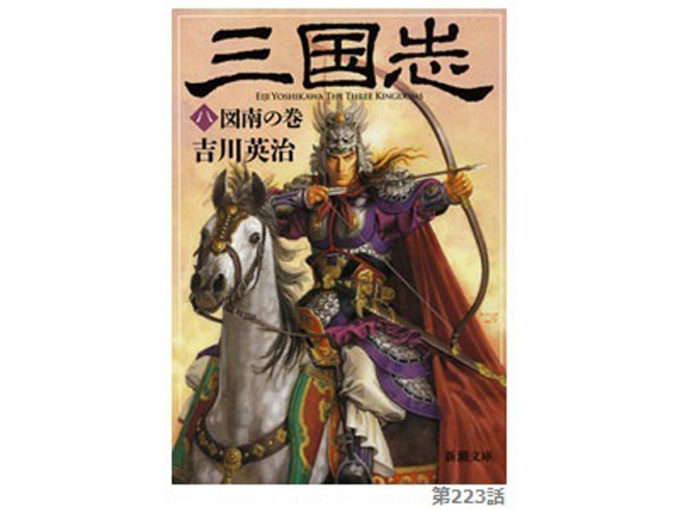














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます