魏王の曹操(そうそう)に対抗し、劉備(りゅうび)が漢中王(かんちゅうおう)に即位したことを知り、呉侯の孫権(そんけん)はいらだちを隠せない。
さらに、荊州(けいしゅう)へ遣わした諸葛瑾(しょかつきん)が関羽(かんう)に追い返されたと聞くや、密かに曹操と結んで荊州攻略に動きだす。だが、そのころ関羽は王甫(おうほ)の進言を容れ、各地に烽火台(のろしだい)を築かせていた。
第226話の展開とポイント
(01)建業(けんぎょう)
諸葛瑾の荊州への使いは失敗に帰す。ほうほうの態で帰ってありのままを復命したところ、孫権は荊州攻略の大兵を動かさんと、建業城の大閣に群臣を集めた。
その場で歩隲(ほしつ。歩騭)が、荊州進攻は断じてご無用と、反対の意見を述べた。それは魏の思うつぼで、呉の兵馬を曹操のために用いるも同様ではないかと。
さらに歩隲は主戦的な人々を抑え、今こそかねて懸案の対魏方策を一決し、曹操の望み通り同盟を結ぶよう主張。その代わり襄陽(じょうよう)から樊川(はんせん)地方に陣取る曹仁(そうじん)の軍勢をもって、荊州へ攻め入ることを条件とするのだと。
孫権は献策を容れ、すぐに曹操のもとへ使者を送り、魏呉不可侵条約ならびに軍事同盟の締結を急いだ。
(02)鄴都(ぎょうと)
呉の使節が入府したとき、曹操は歯医者を呼んで入れ歯をさせていた。斜谷(やこく)の乱軍中に口に鏃(やじり)を受け、その折に欠けた2本の前歯の修繕ができた日だったのである。
★前後の話を読むと『三国志演義(5)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第73回)では、このとき曹操は長安(ちょうあん)にいた。
曹操は使者を引見し、条約の文書に調印を与えた。この直後、満寵(まんちょう)を樊川軍参謀(はんせんぐんさんぼう)に任じ、曹仁のいる前線基地である樊城へ派遣した。
(03)成都(せいと)
この間に蜀は、内治と対外的な防御に専念。漢中王の劉備は成都に宮室を造営し、百官の職制を立てた。
そして、成都から白水(はくすい)までの400余里の道中に駅舎を設け、官の糧倉を建て、商工業の振興と交通の便を促進するなど、着々とその実を上げていた。
★井波『三国志演義(5)』(第73回)では、(400余里ではなく、)400余りの宿舎や駅舎を設置したとある。
ここへ荊州から急使が着き、魏の曹仁が突如、境を侵してきたことが伝わる。諸葛亮(しょかつりょう)は劉備をなだめ、関羽がいるから心配ないと言った。
(04)荊州(江陵〈こうりょう〉?)
諸葛亮の旨を受けた司馬(しば)の費詩(ひし)が、荊州へ急行する。
★井波『三国志演義(5)』(第73回)では、費詩は前部司馬(ぜんぶしば)。
費詩は関羽に会うと、漢中王の王旨であるとして、州中の兵を起こし、ただ守るにとどまらず、敵の樊城をも攻め取るよう伝えた。
また、関羽が五虎大将軍(ごこだいしょうぐん)のひとりに列せられたことも告げ、印綬(いんじゅ。官印と組み紐〈ひも〉)を受けるよう言う。
★五虎大将軍について、井波『三国志演義(5)』(第73回)では五虎大将となっていた。
だが関羽は、自分のほかに馬超(ばちょう)や黄忠(こうちゅう)も五虎大将軍に任ぜられたと聞くと、児戯に等しいと笑い、不満の色を見せる。
★井波『三国志演義(5)』(第73回)では、関羽は馬超の五虎大将への叙任に不満を述べていない。不満の対象は黄忠ひとりだった。
この様子を見た費詩は諭す。そのお考えは、大いなる国家の職制と私の交情とを混同されたものだと。
すると関羽は、急に費詩の前に拝伏して慙愧(ざんき)。卒然と自分の小心を恥じて、印綬を受けた。
関羽は一夜のうちに麾下(きか)を集め、曹仁が境に迫りつつある事態を告げ、これを迎撃したうえ、樊城も奪うと演説。
この場で先陣を廖化(りょうか)とし、副将には関平(かんぺい)を添え、参謀として馬良(ばりょう)と伊籍(いせき)を付けることを決めた。
その夜は満城に篝(かがり)を焚き、未明の発向に備えて腰に兵糧を付け、馬にも飼い葉を与える。陣々には少量の門出酒も配られ、東雲(しののめ。夜明け)の空を待っていた。
関羽も支度を整え、「帥」の大字を書いた旗の下で盾に寄り、居眠っていた。するとどこからか全身真っ黒な大猪(オオイノシシ)が走ってきて、いきなり具足の上から足にかみつく。
驚きざま、抜き打ちに大猪を斬ったかと思うと、目が覚めていた。夢だったのである。
父の声に、養子の関平が来て尋ねた。夢ではあったが、大猪にかまれた跡が、まだズキズキ痛む気がすると言い、苦笑する関羽。
(05)襄陽の郊外
曹仁の大軍は襄陽へ突入したが、関羽が全軍をひきいて荊州を出たとの報を受けると、にわかにたじろぎ、襄陽平野の西北に物々しく布陣。
魏の進撃が思いのほか遅かったのは、曹仁が樊城を発つときから、参謀の満寵と夏侯存(かこうぞん)などの間に作戦上の齟齬(そご)があり、出足が一決しなかったためである。
たちまち関羽軍は、襄陽の郊外まで来て対陣した。魏の翟元(てきげん)が蜀の廖化に挑み、この戦の口火を切る。
やがてやや乱軍の相を呈してきたころ、廖化は偽って敗走しだす。そのころ夏侯存と戦っていた関平も崩れ立つ。
関羽軍は全面的な敗色に包まれたかに見えたが、20里も追われてくると、逆に追撃してきた曹仁や夏侯存らの魏軍が、乱脈に騒ぎ始めた。
後方に関羽を見ると、曹仁は肝を飛ばしたまま逃げる。偽って敗走していた関平と廖化の二軍も、遥か後ろに味方の鼓を聞くと、にわかに踵(くびす。きびす)を返し、圧倒的な攻勢に出た。
魏軍は網中の魚に等しかったが、関羽から言われている旨もあったので、長追いや悪戦はせず、ただ退路を失い、四方に壊乱した敵を手ごろに捉えては壊滅を加えた。
関羽軍としては、ほとんど損害という程度の兵も失わなかったが、敵に与えた損害と心理的な影響とは、相当大きなものだった。
なぜなら、曹仁こそ辛くも生きて帰ったが、夏侯存は関平に討たれ、翟元は廖化に追い詰められて乱軍中に倒れた。いわゆる先陣の二将を序戦に失ったためである。
2日目も3日目も曹仁は不利な戦ばかり続け、ついに襄陽市中からも撤退。襄陽を越えて遠く退いてしまう。
★井波『三国志演義(5)』(第73回)では、夏侯存を討ち取ったのが関羽、翟元を討ち取ったのが関平になっていた。
(06)襄陽
関羽の軍勢が襄陽に入ると、城下の民衆は旗を掲げ、道を掃いて酒食を献じたりし、慈父を迎えるような歓迎ぶりを示した。
このとき司馬の王甫が一案を述べる。呉の呂蒙(りょもう)が陸口(りくこう)に一軍を屯(たむろ)させていることに触れ、つなぎ烽火の備えをしておくに限るというもの。
★井波『三国志演義(5)』(第73回)では、王甫は随軍司馬(ずいぐんしば)。
(07)荊州(江陵?)
王甫は関羽の許しを得ると、ひとまず荊州へ帰って人夫や工人を集め、地形を視察したうえ、烽火台の築造に着手した。
烽火台は1か所や2か所ではない。陸口の呉軍に備えるためであるから、その動きを遠望できる地点から、江岸の10里、20里おきに適当な丘や山地を選び、見張り所を建て、兵5、60人ずつを昼夜交代で詰めさせておくのである。
ひとたび呉の動きに異変があると見るや、まず第一の見張り所の丘から烽火を上げる。夜ならば曳光弾(えいこうだん)を上げる。
★曳光弾には違和感があった。曳光弾のようなもの、という意味合いだろう。
第二の見張り所はそれを知るや、またすぐ同様に打ち上げる。第三、第四、第五、第六というふうに、一瞬の間に烽火が次々の空へと走り移って、数百里の遠くの異変も、わずかなうちに本城で知り得るという仕組みなのである。
(08)襄陽
やがて王甫は襄陽へ戻り、着々と工事が進んでいることを伝え、あとは人の問題だと言う。
「江陵方面の守備は糜芳(びほう。麋芳)と傅士仁(ふしじん)のふたりですが、ちといかがと案ぜられます」
★傅士仁は、正史『三国志』では士仁とある。傅は衍字(えんじ。間違って入った不用の文字)だという。
「荊州の留守をしている潘濬(はんしゅん)も、政事(まつりごと)に私の依怙(えこ)が多く、貪欲だといううわさもあっておもしろくありません」
★このあたりの記述が相変わらず不可解。荊州の留守をしているというが、その荊州(城)が江陵なのでは?
「烽火台はできても、それをつかさどる人に人物を得なければ、かえって平時の油断を招き、不時の禍いを招くもととならぬ限りではありませんからな」
だが関羽は生返事だった。自分が選んで留守を預け、あるいは江岸の守備にあたらせた以上、その者たちを疑う気にはなれない。考えておこうという程度に、王甫の言葉を聞き流してしまった。
襄陽滞陣中に船筏(ふないかだ)の用意を整えた関羽は、ほどなく襄江(じょうこう)の渡河を決行させる。しかし、渡河中に予想された敵の猛襲はなく、大軍は難なく舟航を進め、続々と対岸へ上陸を果たした。
(09)樊城
ここでも魏軍は、内部的な不一致を暴露している。先に逃げ帰った曹仁は以後、関羽の武勇を恐れることひと通りでない。
関羽軍が歴然と渡河の支度をしているのを眺めながらも、参謀の満寵に、ひたすら策を求めているようなありさまだったのである。
満寵は初めから関羽を強敵と見て、曹仁が襄陽へ軍勢を出すことさえ極力諫めた守戦主義だったので、ふた言もなく、出て戦っては勝ち目はないと言った。
ところが、城中の呂常(りょじょう)らの考えはまったく背馳(はいち)しており、城に籠もるのは最後のことだと痛嘆した。
前夜が激論に暮れてしまうと、翌朝には、もう関羽の旗がこちらの岸へ上っていた。
呂常は自説を曲げず、上陸中の関羽軍を襲撃したが、関羽の雄姿を見た部下たちは戦いもせず、城門の内に逃げ込む。
管理人「かぶらがわ」より
兵員には限りがありますから、王甫の指摘した通り、烽火台ごとの指揮官に優秀な人物を得られれば、効果的に国境を守ることができるでしょう。
ですが、その人選は非常に難しい……。この時期から荊州の関羽配下は、駒不足の感が否めません。

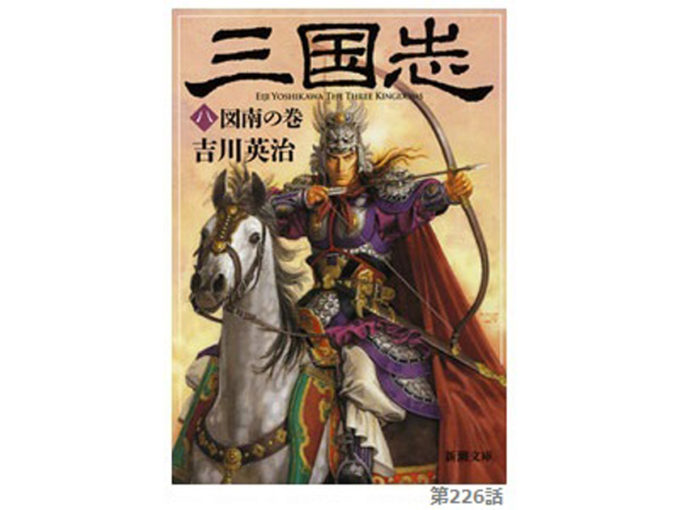













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます