曹真(そうしん)は郭淮(かくわい)の進言を容れ、孫礼(そんれい)に兵糧運搬を装わせ、蜀軍をおびき寄せようと計った。
だが報告を受けた諸葛亮(しょかつりょう)は、孫礼が曹叡(そうえい)から信寵されている人物だと聞き、これが罠であることを看破する。
第290話の展開とポイント
(01)洛陽(らくよう)
呉の境から退き、司馬懿(しばい)が洛陽に留まっているのを、時の魏人(ぎひと)は、この時勢に閑を偸(ぬす)むもの(閑を見つけては怠けるもの)なりと非難していた。
ところがここ数日にわたり、「諸葛亮が再び祁山(きざん)に出てきた。ために、魏の先鋒の大将は幾人も戦死した」という情報が、旋風のように聞こえてくると、彼への非難はピッタリやんでしまう。
やはり司馬懿は凡眼ではないと、言わず語らず、その先見にみな服した形だった。
どのようなときにも、何か誹謗(ひぼう)やあげつらいの目標を持たなければ寂しいというような、一種の知識人や門外政客は洛陽にも数多い。それらの内からは向きを変え、このような非難が囂々(ごうごう)と起こってくる。
「いったい総兵都督(そうへいととく)はいるのか、いないのか? 曹真は何をしているか!」
曹真は魏の帝族である。それだけに曹叡は心を悩ませ、司馬懿を召して対策を下問した。
「恐るべきは蜀と呼ばんより、むしろ諸葛亮そのものの存在である。どうしたらよいであろう?」
司馬懿は、おっとりと答えた。
「さほどご宸念(しんねん)には及ばないでしょう」
司馬懿は、諸葛亮が1か月分ほどの兵糧しか持たないに違いないと言い、速戦即決を望んでいると観る。なので、こちらは長期持久の策を採るべきだと。
朝廷から使いを遣り、総兵都督にその由を仰せつけられ、諸所の攻め口を固くして、曹真が滅多に戦わないようお命じあることが肝要だとも。
さっそく曹叡はこの方針を採る。さらに司馬懿は言った。
「山険の雪が解けるころともなれば、蜀兵の糧も尽き、嫌でも総退却を開始しましょう。虚はそのときにあります。追撃を加えて大勝を得ること間違いございませぬ」
曹叡は先見をたたえつつも、なぜ陣頭に出て計策しないのかと尋ねる。
すると司馬懿はこう答えた。
「臣はまだ洛陽に老いを養うほどの者でもありませんが、さりとてまた、生命を惜しんでいるわけでもございません。要は、呉の動きの見通しがつきかねるからです」
以後、数日の間にも、曹真から届く報告は、ことごとく魏に利のないことのみ。そしてようやく曹真は、その自信まで失ってきたもののごとく、このように伝えてきた。
「とうてい現状のままでは守りに堪えません。ひとえにご聖慮を仰ぐ」
暗に曹叡の出馬なり、司馬懿の援助を求めている。けれど司馬懿は、何か思うところがあるらしく容易に立たない。そのうえで、曹叡にこういった献言ばかりしていた。
「今こそ総兵都督の頑張るべきときです。お使いをもって丁寧に戒められ、諸葛亮の虚実にかかるな、深入りして重地に陥るなと、くれぐれも持久策をお採らせなさるように」
朝廷では韓曁(かんき)を使いに立て、こうした方針を伝えさせる。すると司馬懿は、わざわざ韓曁を洛外まで見送りに行き、別れに臨んで言づてを頼む。
「言い忘れたが、これは総兵都督の功を願うために、ぜひ注意してさしあげてくれ」
「蜀勢が退くとき、決して性質の短慮な者や狂躁(きょうそう)な人物に追わせてはいけない。軽々しく追えば必ず諸葛亮の計に陥る。このことを、朝廷の命として付け加えておいてもらいたい」
そのくせ、それほど魏軍の苦境を知りながら、自分は車を巡らせて、悠々と洛陽へ戻るのだった。
(02)曹真の本営
太常卿(たいじょうけい)の韓曁が総兵都督の本部に着き、曹真に朝廷の方針を伝える。
曹真は謹んで詔(みことのり)を拝受し、韓曁の帰るのを見送ったが、後にこの由を副都督(ふくととく)の郭淮にも語った。
郭淮は笑って言う。
「それは朝廷のご意見でも何でもない。すなわち司馬懿の見ですよ」
郭淮は、洛陽から伝えられた方針には十分感心していたが、その通りに行うだけというのも、この総司令部に人なきようで嫌だった。
そこで彼がささやいた一策は、これも曹真を動かすに足りた。曹真も、何かで連戦連敗の汚名から免れたいのである。
で、計画は徐々に実行されだす。事実、蜀軍の大なる欠陥は、大兵を養う「食」にあることは万目一致していた。
いまや日を経るに従い、諸葛亮が「食」の徴発に奔命しつつあるは必定だから、敵の求めるそれを好餌に用いて、罠にかけようというのが郭淮の着想である。
★郭淮も絡んでいないわけではないが、『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第98回)で具体的な策を献じていたのは孫礼。
(03)祁山の西
それから1か月ほど後、魏の孫礼は、兵糧を満載したように見せかけた車輛(しゃりょう)を何千となく連れ、祁山の西にあたる山岳地帯を延々と行軍していた。陳倉城(ちんそうじょう)と王双(おうそう)の陣へ輸送していくものとは、一見して誰でもわかる。
けれど車輛にはみな青い布がかぶせてあり、その下には硫黄や焰硝(えんしょう。火薬)、また油や柴(シバ)などが隠してあった。これが郭淮の考えた、蜀軍を釣る餌なのである。
一面。その郭淮は、箕谷(きこく)と街亭(がいてい)の二要地へ大兵を配して、自ら指揮に臨み、張遼(ちょうりょう)の子の張虎(ちょうこ)と楽進(がくしん)の子の楽綝(がくりん)を先鋒とし、あらかじめある下知を付しておいた。
さらに陳倉道の王双とも連絡を取り、蜀軍が乱れたときの配置を万全にしておいたことは言うまでもない。
★張虎は、先の第33話(07)で登場した張虎とは別人。
(04)祁山 諸葛亮の本営
蜀の物見は、鬼の首でも取ったように報告する。
「隴西(ろうせい)から祁山の西を越え、数千輛の車が、陳倉道へ兵糧を運んでいく様子に見えます」
蜀の諸将はみな、その好餌に目色を輝かせたが、諸葛亮はまったく別のことを左右に尋ねた。
「兵糧隊の敵将は、誰だと言ったな?」
それが孫礼だと聞くと、諸葛亮は、その人物を知る者はないかと、また尋ねる。
むかし魏にいた一将が話す。
「かつて魏王が大石山(だいせきざん)に狩猟をなしたとき、一頭の大きな虎が魏王に跳びかかったことがありました」
「そのとき孫礼がいきなり盾となり、大虎に組みつき、剣をもって刺し殺したことから非常に信寵を受け、今日(こんにち)に至った人物です」
★ここでいう魏王とは、魏の皇帝である曹叡のこと。
諸葛亮は謎が解けたように笑い、諸将に言った。
「兵糧を運送するに、それほどの上将を付けるわけがない。思うに車輛の覆いの下には、火薬や枯れ柴などが積んであるのだろう。笑うべし、わが胃に火を食わせんとは――」
諸葛亮はこれをまったく無視したが、ただ無視し去ることはしない。帷幕(いばく。作戦計画を立てる場所、軍営の中枢部)に将星を集め、敵の計を用いて敵を計るの機をつかみにかかる。
情報が集められ、風のごとく物見が出入りした。その帷幕の内から命令は次々に発せられている。真っ先に馬岱(ばたい)が、3千の軽兵をひきいてどこかへ走った。
次に、馬忠(ばちゅう)と張嶷(ちょうぎ)が5千騎ずつをひきいて出動する。呉懿(ごい)や呉班(ごはん)らも何か任を帯びて出た。
そのほか関興(かんこう)や張苞(ちょうほう)などもことごとく兵をひきいて出払い、諸葛亮自身も床几(しょうぎ)を祁山の頂に移し、しきりと西の方角を望んでいた。
(05)祁山の西
魏の車輛隊の行軍は、すこぶる遅々としている。2里行っては物見を放ち、5里行っては物見を放つ。魏の物見は、諸葛亮の本陣が動きだしたことを告げた。孫礼は得たりと思い、この旨をただちに曹真の陣へ急報する。
曹真は張虎と楽綝の先鋒に向かい、こう激励した。
「今宵、祁山の西方に炎々の火光を見るときこそ、蜀兵がわが火計にかかり、本陣を空虚にしたときである。空が赤く染まるのを合図に、敵の本陣へ突っ込め」
日も暮れようとして、祁山の西に留まった孫礼の運送部隊は、野営の支度にかかると見せる。だがその実は、1千余輛の火攻め車をあなたこなたに屯(たむろ)させ、蜀兵を焼き殺す配置を終えていた。
発火、埋兵、殲滅(せんめつ)の三段に手はずを定め、全軍ヒソと仮寝のしじまを装っていると、やがて人馬の音が粛々と夜気を忍んでくる様子。
折ふし、西南の山風が強い。孫礼は「敵きたらば」と、手に唾して待っていた。
ところが、いまだ魏軍が立たないうちに、風上から火を放った者がある。何ぞ図らん、敵の蜀兵だった。
初め孫礼は味方の手違いかと狼狽(ろうばい)したが、蜀兵が火を放ったものだと知ると、躍り上がって無念がる。
「すでに諸葛亮は看破しているぞ。わが事破る――」
1千余の車輛を焼き立てると、蜀兵はふた手に分かれて矢を送り、石を飛ばした。鼓角は夜空に響き、火光は天を焦がし、魏兵の混乱ぶりはひとかたでない。
風上から攻めくるのは蜀の馬忠や張嶷など。風下からも蜀の馬岱の一軍が鼓噪(こそう)して攻めかかる。
自ら設けた火車(ひぐるま)の死陣の中に、魏兵は火をかぶって戦うほかなかった。のみならず、魏勢は谷間や山陰の狭路に埋伏していたため、その力が分散しており、主将の命令も各個に一貫していない。
火光の中に討たれる数もおびただしかったが、踏み迷い、逃げ惑って焼け死ぬ者や、火傷(やけど)を負って狂う者も数知れなかった。かくてこの一計は、見事に魏の失敗に終わっただけでなく、火をもって自ら焼け滅ぶの惨禍を招いてしまう。
(06)祁山 諸葛亮の本営
この夜、このような不測が起こっているとも知らず、ただ空を焦がす火光を望み、「時こそ至る」と、いたずらに行動を開始したのは、曹真から命を受けていた張虎と楽綝の二隊だった。
危ういかな、ふたりは盲進して、諸葛亮の本陣に突入したのである。敵影はない。それは予期したところだが、須臾(しゅゆ。しばらく)にして陣営の周りから、突然、湧いて出たような蜀軍の鬨(とき)の声が起こる。呉懿と呉班の軍勢だった。
ここでも魏勢は残り少なに討たれたうえ、散々の態で逃げ崩れてくる道を、さらに関興と張苞の二軍に、完膚なきまで痛撃される。
(07)曹真の本営
夜明けとともに曹真の本陣には、西から南から北からと、落ち集まってきた残軍と敗将の姿こそ見る影もないもの。
食うか食われるか、戦の様相は常に苛烈である。この苛烈を肝に銘じていながら、曹真の軽挙は重ねがさねの惨敗をみてしまった。
曹真の落胆は恐怖に近づく。今は郭淮の献策を恨むこともできない。彼は総兵大都督である。そこで警戒を非常なものとした。むしろ度が過ぎるほど、堅固に堅固を取った。
「以後は、必ずみだりに動くな。敵の誘いに乗るな。ただ守れ。固く守備せよ」
このため、祁山の草は幾十日も兵に踏まるることなく、雪は解け、山野は靉靆(あいたい。雲が横に長く引くさま)たる春霞(はるがすみ)をほの赤く染めてくる。
(08)祁山 諸葛亮の本営
諸葛亮は悠久なる天地を眺め、あたかも霞を食うて生きている天仙か地仙のごとく、もの静かに日々を送っていた。
そのようなある日、書をしたため、陳倉道の魏延の陣へ密かに使いを遣る。楊儀(ようぎ)は、魏延の陣に引き揚げが命ぜられたと聞いて怪しむ。
だが諸葛亮は、陳倉道だけでなく、ここの陣地も引き払おうと思うと話す。進発するわけではなく、漢中(かんちゅう)へ退くのだと。
楊儀は解せないとして言った。
「でも、かくのごとく蜀が勝っているところを……。しかも万山の雪は解け、いよいよ士気旺盛(おうせい)たろうとしている矢先ではございませんか」
これを聞き、諸葛亮が言う。
「さればこそ、今を退くときと思うのである。魏がいたずらに守って戦わないのは、わが病を深く知らないからだ。わが病とは、ほかでもない兵糧の不足」
「如何(いか)んともなしがたい重患だが、幸いにも、敵はただその枯渇を待っていて、積極的にわが通路を断とうとはしていない。これなおわが余命のある所以(ゆえん)だ。もし今のうちに療養に帰らなければ、この大軍をして、救いがたい重体に落とすだろう」
それでも楊儀は言った。
「その点は、我々も絶えず腐心しているところですが、先ごろの大勝に、だいぶ戦利品も加えましたから、なおしばらくは支えられないこともありません」
「そのうち勝ち続けて自然と活路に出れば、敵産をもって長安(ちょうあん)に攻め入るまで、食い続けられないこともないと思いますが……」
諸葛亮は、かんで含めるように諭す。
「否とよ。草は食えるが、敵の死屍(しし)は糧にならない。魏の陣気を遥かにうかがうに、おそらく大敗のことが洛陽に聞こえ、思い切った大軍をもって助けに来るに違いない」
「さもあらば、敵は新手。後方にいくらでも運輸の道を持つ大軍。いかにして、わが勝利を保ち得よう」
「敗れて退くにあらず、勝って去るのである。退くとは戦いの中のこと、去るとは作戦による行動にほかならない。さように歯がみして無念がるな」
また、諸葛亮はこうも言う。
「しかし、魏延へ遣った使いに一計を授けてあるから、引き揚げると言っても、無為に退くわけではない。見よ。やがてあそこにある魏の王双の首は、魏延のよい土産となるであろう」
関興や張苞らの若手組は、案のごとく、この陣払いに対して不満を表したが、それも楊儀になだめられ、着々と引き揚げにかかりだした。もちろん、それは密かに行われたことは言うまでもない。
(09)曹真の本営
一方で魏の曹真はその後、守るに専念し、とみに気勢も上がらずにいた。そこへ折から、左将軍(さしょうぐん)の張郃(ちょうこう)が洛陽から一軍をひきいて到着する。曹真が尋ねると、司馬懿の計らいで加勢に来たとの答え。
逆に張郃が、このごろの戦況を尋ねると、曹真は初めて少しニコッとして言った。
「この数日の戦況は、大いに味方の有利に転回してきた。以後まだ大合戦はないが、諸所において、いつも味方が勝ちつつある」
ところが張郃は、「アッ、それはいかん」と言う。そのことも離京の際、司馬懿がくれぐれも警戒せよと言っていたのだと。
張郃は司馬懿に言われたことを話す。
「蜀軍はたとえ兵糧が欠乏しだしても、決して軽々しくは退くまい。だが、彼の兵がしばしば小勢で出没して、そのたび負けて逃げるようなときは、大いに機微を見ていないといけない」
「反対に、彼が大軍を動かすか、大いに強みのあるときは、まだ退陣の時は遠いと見ていて間違いない。このへんが兵家の玄妙であるから、よくよく曹真閣下にお伝えしておくがいい」
曹真は何か思い当たるものがあるらしく、急に間諜(かんちょう)の上手な者を数名放ち、諸葛亮の本陣をうかがわせる。
間諜が帰ってきて報告した。
「祁山の上にも下にも、敵は一兵もおりません。ただ備えの旗と囲いが残されているだけです」
続いて帰った者も言う。
「諸葛亮は、漢中を指して総引き揚げを行ったようです」
曹真は頭を搔(か)いて後悔する。聞くやいな、張郃は新手の勢をもって急追してみたが、時すでに甚だ遅かった。
(10)陳倉道
陳倉道の口に残り、久しい間、魏の王双を防ぎ支えていた蜀の魏延。諸葛亮の書簡に接すると、こちらも陣払いを開始した。
当然、その動きは王双の知るところとなり、暇(いとま)を置かず追撃してくる。
蜀兵の逃げ足は速かった。王双の追うことがあまりに急だったので、彼の周囲には、旗本の騎馬武者が2、30騎しか続いてこられない。
すると、後から駆けてきた一騎が注意した。
「わが大将。ちと急ぎすぎましたぞ。敵将の魏延は、まだ後ろのほうにおります」
王双が振り向くと、どうしたことか、陳倉の城外にある自分の陣営から黒煙が上がっていた。あわてて引き返し、途中の有名な険路である陳倉峡口の洞門までくる。ここで上から大岩石が落ちてきて、王双の馬や部下たちはみな、くじきつぶされた。
突如、王双の後ろに一彪(いっぴょう)の軍馬が見え、その中に魏延の声がした。一度、馬上からもんどり打ったため、王双は逃げられない。その武力を表すに暇なく、ついに魏延の大剣に、その首(こうべ)を任せてしまった。
魏延は王双の首を、高々と槍(やり)の先に掲げさせ、悠々と漢中への引き揚げを果たす。
(11)曹真の本営
王双の死が、曹真の本営へ知らされてから幾ばくもなく、陳倉の守将たる郝昭(かくしょう)の死が続けて報ぜられる。郝昭は病死だったが、曹真にとっても、魏にとっても、重ねがさねの凶事ばかりだった。
管理人「かぶらがわ」より
郭淮の計を逆用し、魏軍に大打撃を与えた諸葛亮。ホント、この人を計るのは難しい。こうなるのなら司馬懿に言われた通り、ひたすら堅守に努めていたほうがマシだったかも?
とはいえ、魏は長安へ迫られたわけでもない。こうやって魏の兵力をいくらか削ってみても、なかなか蜀の突破口は見えてきませんね。

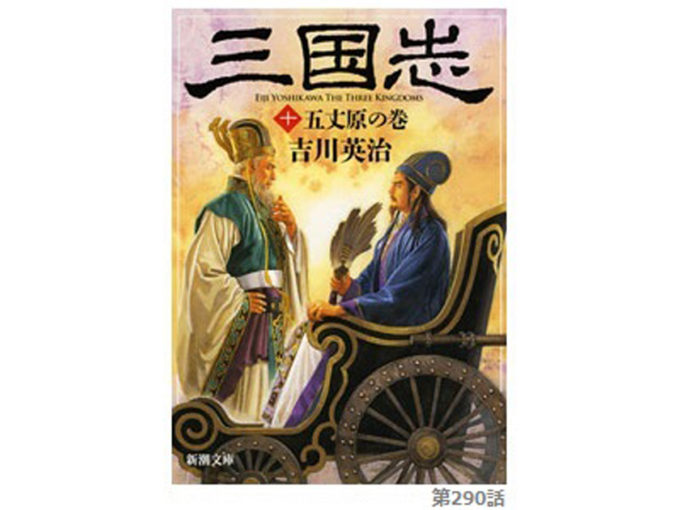














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます