陳倉道(ちんそうどう)の長雨で大きな被害を出し、蜀軍と戦うことなく退却した魏軍。
曹真(そうしん)は諸葛亮(しょかつりょう)が追撃してこないことをいぶかるも、司馬懿(しばい)の見解は彼と異なるものだった。そこで曹真は、司馬懿とふた手に分かれて蜀軍を待ち受けつつ、ある賭けに臨む。
第295話の展開とポイント
(01)赤坡(せきは)
魏の総勢が遠く退くと、諸葛亮は八部の大軍を分けて箕谷(きこく)と斜谷(やこく)の両道から進ませ、よたび祁山(きざん)へ出て戦列を布かんと言った。
★『三国志』(蜀書・後主伝)によると、赤坡は正しくは赤阪(せきはん)。
蜀の諸将は尋ねる。
「長安(ちょうあん)へ出る道は幾条(いくすじ)もございます。丞相(じょうしょう。諸葛亮)には、なぜいつも決まって祁山へ出られるのですか?」
諸葛亮は、祁山は長安の首であるとして、このように教えた。
「見よ。隴西(ろうせい)の諸郡から長安へ行くには、必ず通らねばならぬ地勢にあることを。しかも、前は渭水(いすい)に臨み、後ろは斜谷に寄る」
「重畳の山や起伏する丘、また谷々の隠見する自然は、ことごとくみな絶好の盾であり、壁であり、石垣であり、塹壕(ざんごう)である」
「右に入り、左に出て、よく兵を現し得るところ、かくのごとき戦場は少ない。ゆえに長安を望むには、まず祁山の地の利を占めないわけにはいかないのだ」
人々は初めて会得する。そして数次の苦戦を重ねながらも、地の利に惑ったり、地を変えてみたりしない諸葛亮の信念に心服した。
(02)退却中の魏軍
そのころ魏軍はようやく、難所を脱して遠く引き退き、ホッとひと息ついていた。道々に残した伏勢も、追い追い引き揚げてきて報告する。
「4日余り潜んでおりましたが、一向に蜀軍の追ってくる気配もありませんので、立ち帰りました」
ここで7日ほど留まり、蜀軍の動静をうかがっていたが、何の訪れもない。
曹真は司馬懿に言った。
「察するに、先ごろの長雨で山々の桟(かけはし)も損じ、崖道もなだれたため蜀兵も動くことならず、我々の退軍したのもまだ知らずにおるのではあるまいか」
だが、司馬懿はその見解を否定。諸葛亮はこの晴天を望み、一転して祁山方面へ進んでいるのだろうと言う。おそらく全軍をふた手に分け、箕谷と斜谷の両道から祁山へ出てくるとも。
司馬懿は、今からでも箕谷と斜谷の途中へ急兵を差し向け、道に伏せておけば、敵の出鼻を叩くには十分間に合うと力説。
しかし曹真は信じない。常識から判断しても、諸葛亮たる者がそのような迂愚(うぐ)な戦法は採るまいというのである。やってくるなら、わが方の退却は絶好の戦機だから、急追また急追し、これへ迫ってくるのが本当だと主張して譲らない。
司馬懿も自説に固執して、ついにこう言いだす。
「いま閣下と私とで、おのおの二軍を編制し、箕谷と斜谷に分かれて、お互いに狭路を擁し、敵の通過を待ち伏せましょう。そして、もし10日後までに諸葛亮がやってこなければ、私はいかなるお詫びでもいたしますが――」
曹真から、どういう謝罪の法を採るかね、と聞かれると、司馬懿は答えた。
「この面に紅粉を塗り、女の衣装を着て、閣下の前にお辞儀いたします」
曹真は、おもしろいと言い、司馬懿の説が当たっていたときは、天子(曹叡〈そうえい〉)から拝領した玉帯一条と名馬一頭を贈ると約束する。
その夕べ、司馬懿は祁山の東にあたる箕谷へ向かい、曹真も一軍をひきいて、祁山の西方にあたる斜谷口へ伏せた。
(03)箕谷
伏勢の任務は戦うときより遥かに苦しい。来るか来ないか知れない敵に備えて、ジッと昼夜少しの油断もできないうえ、もちろん火気は厳禁。害虫や毒蛇に襲われながら、身動きもならない忍耐の一点張りである。
慨然と、ひとりの部将が部下に不平を漏らしていた。
「何たることだ。敵も来ないのに幾日も気力を費やしているなどとは――。いったい、主将たる者が無用の意地を張り、物賭(ものかけ)などのため、多くの兵をみだりに動かすということからして怪しからぬ沙汰だ」
折ふし陣地を見回っていた司馬懿が、ふとその声を聞き留める。営所に帰るやすぐに左右の者を遣り、不平を唱えた部将を連れてこさせた。
司馬懿は面を改めて言う。
「賭け事をなすために兵を動かしたと汝(なんじ)は曲解しておるらしいが、それは予の上官たる曹真を励ますためである」
「また、ただ魏の仇(あだ)たる蜀を防がんという願いのほかに、私心のあるものでもない。もし敵に勝たば、汝らの功もみな天子に奏し、魏の国福をともに喜ぶ存念であるのだ」
「しかるに、みだりに上将の言行を批判し、あまつさえ怨言を部下に唱えて士気を弱めるなど、言語道断である」
ただちに司馬懿は打ち首を命ずる。
部将の首が陣門に掛けられたのを見て、多少同じ気持ちを抱いていた者は、みな肝を冷やした。そして、一倍に油断なく埋伏のつらさを耐え、蜀軍が来るのを今か今かと待っていた。
折しも、蜀の魏延(ぎえん)・張嶷(ちょうぎ)・陳式(ちんしき)・杜瓊(とけい)らの2万騎が、この一道へ差しかかる。
ここで別に斜谷道を進軍している諸葛亮から連絡があり、伝言が届けられた。
「丞相の仰せには、『箕谷を通る者は、くれぐれも敵の伏勢に心をつけ、一歩一歩もかりそめに進まれるな』とのご注意でありました」
このときの使者は鄧芝(とうし)である。聞いた者は魏延と陳式。
ふたりは、またいつもの用心深いお疑いが始まったことよと一笑に付して言った。
「魏軍は30余日も水浸しになった揚げ句、病人も増え、軍器も役に立たなくなり、ことごとく退いてしまったものだ。これへ出直してくる余力などあるものではない」
★『三国志演義(6)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第100回)では、この発言をしたのはほぼ陳式。
鄧芝は諫めたが、なお魏延は皮肉を弄する。
「それほど達見の丞相ならば、街亭(がいてい)であのような敗れを取るわけもないではないか」
さらにこうも言った。
「一気に祁山へ出て、人より先に陣を構えてみせる。そのとき丞相が恥じるか恥じないでいるか、その顔を足下(きみ)も見ていたまえ」
(04)斜谷 諸葛亮の本営
鄧芝の復命を受けた諸葛亮は、何事か思い当たっているらしく、さしても意外とせずに言う。
「近ごろ魏延は、予を軽んじている。魏と戦って幾度か利あらず。ようやくこの孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)に愛想を尽かしておるものと思われる。是非もない……」
諸葛亮は自己の不徳を嘆じ、やがてまたこうかこった。
「むかし先帝(劉備〈りゅうび〉)も仰せられたことがある。魏延は勇猛ではあるが、叛骨(はんこつ)の士であると。予もそれを知らないではないが、つい彼の勇を惜しんで今日(こんにち)に至った。今はこれを除かねばならないだろう」
★このことについては先の第170話(06)を参照。ただしそこでは劉備でなく、諸葛亮のほうが、魏延の後脳部に叛骨が隆起していることに触れ、これは謀反人によくある相だと述べていた。
そこへ早馬が着いて告げる。
「昨夜、箕谷道で真っ先に進んでいた陳式が敵の伏勢に囲まれ、5千の兵が殲滅(せんめつ)され、残る者わずかに800名。続いて魏延の部隊も危ぶまれております」
諸葛亮は軽く舌打ちして命じた。
「鄧芝。もう一度、箕谷へ急げ。そして陳式をよく慰めておけ。うっかりすると、罪を恐れて、かえって豹変(ひょうへん)する恐れがある」
鄧芝を遣った後、諸葛亮はしばし眉を寄せて苦吟していた。やがて静かに目を開くと、馬岱(ばたい)・王平(おうへい)・馬忠(ばちゅう)・張翼(ちょうよく)を呼ぶ。4人そろうと何事か秘策を授け、「おのおの。すぐ行け」と急がせた。
続いて関興(かんこう)・呉懿(ごい)・呉班(ごはん)・廖化(りょうか)らも招き、それぞれに密計を含ませる。その後、諸葛亮自身も大軍をひきいて堂々と前進した。
(05)斜谷 曹真の本営
一方、魏の大都督(だいととく)の曹真は、斜谷方面の要路へ出て、ここ7日ばかり伏勢の構えを持していた。
だが、一向に蜀軍に出会わないので、「司馬懿との賭けはもう自分の勝ちである」と、そろそろ高をくくっている。
彼の意思の対象は蜀軍よりも、むしろ司馬懿との賭けにあった。いや、自己の小さい意地や面子(メンツ)にとらわれていたと言うほうが適切だろう。
そのうちに約束の10日近くとなって、物見の者が告げた。
「数はよくわかりませんが、この先の谷間に蜀の兵がチラチラ出没しているふうです」
曹真は秦良(しんりょう)に5千騎ほど授け、谷口をふさぐよう命ずる。
「10日の期が満つれば、賭けはわが勝ちとなる。だからあと2日ほどは、旗を伏せ鼓を潜め、ただそこをふさぎ止めておれ」
(06)斜谷口
秦良は曹真の命令を守っていたが、広い谷あいをのぞくと、四山の水が溜まるように、刻々と蜀の軍馬が増えてくる。
しかも侮りがたい気勢なので、急に自分のほうからもおびただしい旗風を上げ、ここには備えがあるぞと、堅陣を誇示した。
すると蜀勢は、その夜から翌日にかけ、続々と退いていく様子。秦良は恐れをなして道を変えたと見て、にわかに追撃をかける。谷道を縫って5、6里も駆けると、広やかな懐へ出た。
けれど蜀兵は、どこへ去ったか影も形もない。秦良はひと息入れ、敵をあざ笑っていた。
しかし、その声もやまないうちに四方から喚声が起こる。急鼓が地を揺るがし、激箭(げきせん。激しく飛ぶ箭〈矢〉)が風を切り、秦良軍の5千を覆い包んだ。
馬煙とともに近づく旗々は、蜀の呉班・関興・廖化。魏兵は肝を冷やして四散したが、ここは完全な山懐。逃げ奔ろうとする道はことごとく蜀軍で埋まっている。秦良も囲みを突いて逃走を試みたが、追い慕った廖化のため一刀の下に斬り落とされた。
「降伏する者は助けん。兜を捨てよ。鎧を投げよ」
高きところから諸葛亮と幕将らの声がした。見る間に魏兵の捨てた武器や旗が山をなす。彼らは唯々として降兵の扱いを待つのである。
諸葛亮は屍(しかばね)を谷へ捨てさせたが、その物の具や旗印は取り、自軍の兵に装わせた。つまり敵の物の具をもって全軍偽装したのである。
(07)斜谷 曹真の本営
その後、曹真は秦良の部下と称する伝令からの報告を聞いていた。
「昨日、谷間にうごめいていた敵は、奇計を用いてみな討ち取りました。ご安心くださるように」
その日の後刻、司馬懿からも使いが来る。こちらは本物で口上を述べた。
「箕谷では、すでに蜀軍の先鋒の陳式が現れ、4、5千騎を殲滅いたしました。閣下のほうはいかがですか?」
★井波『三国志演義(6)』(第100回)では、司馬懿の使者が曹真に、(箕谷方面では)蜀軍が伏兵を用いて4千以上の魏兵を殺したことを告げたうえ、くれぐれも賭けのことにこだわらず、注意して防御に努めてほしいと伝えていた。吉川『三国志』とは解釈が異なる。
曹真は噓を答える。
「いや。わが方には、まだ蜀軍は一兵も見ない。賭けは予の勝ちであるぞと、司馬懿に申しておいてくれ」
約束の10日目が来た。曹真は、なお幕僚たちと興じ合っていた。
「賭けに負けるのはつらいので、あのようなことを言ってきたが、箕谷の方面に蜀軍が出たかどうか知れたものではない。何としても賭けに負かして、司馬懿が紅白粉(べにおしろい)をつけ、女の衣装を着て謝る姿を見てやらねばならん」
そこへ鼓角の声がしたので、何事かと陣前へ出てみると。味方の秦良軍が旗指物をそろえて静々と近づいてくる。彼方(かなた)から手を振って合図していた。
曹真は少しも疑わず、同じく手を挙げて迎える。ところが数十歩まで近づくと、味方とのみ思っていたその軍勢は、一斉に槍先をそろえて突進してきた。
仰天した曹真は陣中へ転げ込む。するとほぼ同時に、営の裏手から猛烈な火の手が上がった。前からは関興・廖化・呉班・呉懿。後ろからは馬岱・王平・馬忠・張翼などが、早鼓(はやづつみ)を打ち、火とともに攻め立ててきたのである。
(08)逃走中の曹真
身ひとつで辛くも逃れ、曹真は無我夢中、鞭(むち)も折れよと、馬の背につかまって逃げ奔った。蜀勢は見落とさず、あれを捕れ、あれを射よと、猟師のごとく追いまくる。
だが曹真は一命を拾った。それは突として、山の一方から駆け下ってきた不思議な一軍が助けたからである。ようやく人心地がついて見回してみると、彼は司馬懿の軍勢に護られていた。
曹真が賭けの負けを認めると、司馬懿は駆けつけた事情を話す。
「そのようなことはどうでもよろしいのです。けれど私から使いを差し上げたところ、斜谷方面には何らの異状もない、また蜀の一兵も見ないとのお言葉だったということでした」
「これはいかん。それが真底のお心なら一大事と、取るものも取りあえず、道なき道を横ざまに越えて、お救いに来たわけでございます」
(09)渭水 曹真の本営
曹真は深く恥じた。まもなく渭水の岸へ陣地を移したが、以来、慙愧(ざんき)に責められて病に籠もり、陣頭に姿を見せなくなってしまう。
(10)祁山 諸葛亮の本営
諸葛亮は、予定通り祁山への布陣を終える。諸軍をねぎらい、賞罰を明らかにし、全軍これで事なきかのように見えたが、かねての宿題を不問にしてはおかない。
諸葛亮は魏延と陳式を呼び出し、その罪を責めた。
「鄧芝を使いとして、敵の伏勢を固く戒めておいたのに、わが命を軽んじて大兵を損じたるは何事か!」
陳式は魏延に科(とが)をなすり、魏延は陳式に罪を押しつけた。諸葛亮は双方の言い分を聞いてから、こう罵る。
「陳式がなお一命を保ち、いくらかの兵でも後に残すことができたのは、魏延が第二陣から助けたからではないか。咄(とつ。舌打ちする様子)、卑怯者(ひきょうもの)!」
こうして陳式の首を即座に刎(は)ねさせたが、魏延のほうは責めなかった。叛骨ある男と知りながら、なお助けておいたのは、国運の重大に顧みて、彼の武勇を用うる日のいよいよ多きを考えていたからだろう。
そうした苦衷を吞まねばならぬほど、魏に比べて、蜀には事実、良将が少なかったのである。
管理人「かぶらがわ」より
曹真と司馬懿の賭けとか、話はおもしろかったのですけど、そもそもここで語られていた地理っておかしくないですか?
陳倉を目指すのならともかく、漢中から祁山へ出るのに、なぜ箕谷や斜谷を通ることになるのか? これには相当な違和感がありました。
それに、魏延と陳式がヘマをしたというのなら――。やはり魏延だけを斬らないのは、諸葛亮のスタンスとひどく矛盾するのでは? 先には(泣いて)馬謖(ばしょく)すら斬ったのに……。

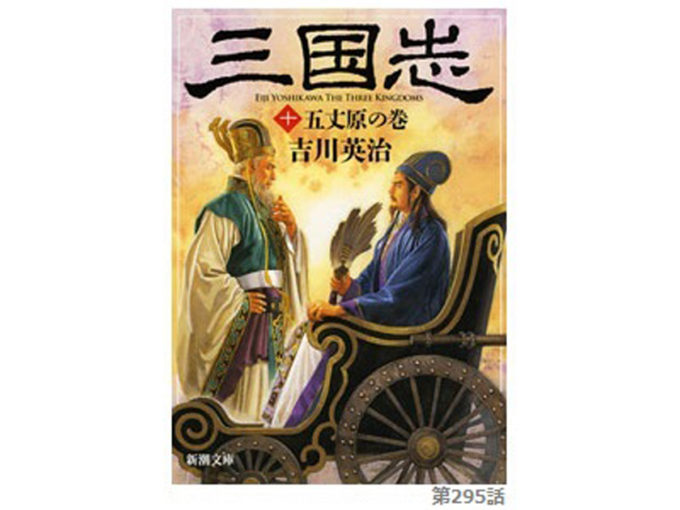














コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます