葫蘆谷(ころこく)で司馬懿(しばい)父子を討ち漏らしたものの、渭水(いすい)における大勝利に蜀軍は沸いていた。
その後、魏蜀両陣営ともに不穏な空気が流れだす。魏は司馬懿の消極的な姿勢への不満が、蜀は魏延(ぎえん)の諸葛亮への不満が、それぞれ高まってきたものだった。諸葛亮は五丈原(ごじょうげん)へ陣を移すと、司馬懿のもとに使者を遣わす。
第307話の展開とポイント
(01)渭南(いなん) 諸葛亮の本営
みな蜀軍の勝ちを、あくまで大勝と喜んでいたが、ひとり諸葛亮の胸には、遺憾やるかたないものが包まれていた。加うるに、ひとまず彼が自軍を渭南の陣にまとめた後、陣中しきりに不穏の空気がある。
ただしてみると、魏延が非常に怒っているという。諸葛亮は彼を呼び、何が不平なのかと尋ねる。
包まずに言うよう促されると、魏延は葫蘆谷でのことを話した。
「幸いにもあのとき、大雨が降り注いできたからよいようなものの、もしあの雨がなかったら、魏延の一命はどうなっておりましょう? それがしも司馬懿父子とともに、焼き殺されるほかはありませんでした」
「思うに丞相(じょうしょう。諸葛亮)はそれがしを憎しみ、司馬懿と一緒に焼き殺さんと計られたのでありましょう」
すると諸葛亮は怪しからんと、馬岱(ばたい)のことを非難する。必ずさような手違いのないようにと、火を掛けるにも、合図をなすにも、すべてを馬岱に命じてあったはずだと。
諸葛亮の怒りのほうが、むしろ甚だしいほどだったので、魏延もやや意外に打たれる。
馬岱は諸葛亮に呼びつけられて、面罵された。そのうえ衣を剝がれ、杖(じょう)50の刑を受ける。職についても一軍の大将から、一組の小頭(こがしら)に貶(おと)されてしまう。
★『三国志演義(7)』(井波律子〈いなみ・りつこ〉訳 ちくま文庫)(第103回)では、ここにあるような諸葛亮と魏延とのやり取りや、馬岱への処分の話は見えない。
(02)渭南 馬岱の軍営
自陣へ戻ると、馬岱は士卒に顔も見せず、痛涙悲憤していた。すると夜に入り、諸葛亮の側近の樊建(はんけん)が、そっと訪ねてきてなだめる。
「まったくは、やはり魏延をお除きになるお心だったが、不幸、大雨のために司馬懿をも取り逃がし、彼を亡き者にする計画も果たされなかったのだ」
「とはいえ、いま魏延に背かれては蜀軍の崩壊になる。そのため何の科(とが)もない貴公に恥と汚名を着せたが、これも蜀のためと、目をふさいでくれよとの丞相のお言葉だ」
「どうかこらえてください。その代わりに他日、この功を第一の徳とし、諸人に向かい、必ずこれに百倍する叙勲をもって、貴下(あなた)の恥をそそぐであろうと約されておられる」
そう聞くと馬岱は口惜しさも解け、むしろ諸葛亮の苦衷が思いやられた。
★井波『三国志演義(7)』(第103回)では、ここにあるような樊建と馬岱とのやり取りも見えない。
(03)渭南 諸葛亮の本営
意地の悪い魏延は、馬岱が平部将に貶されたのを見てやろうとするもののように、「馬岱を私の部下に頂きたい」と申し入れた。
諸葛亮は許さなかったが、今はその足元をも見透かしている魏延なので、「どうしても」と強情を張り通す。それを聞いた馬岱は、進んで魏延の部下になった。もちろん堪忍に堪忍をしてのことである。
★井波『三国志演義(7)』(第103回)では、ここにあるような魏延や馬岱がらみのやり取りも見えない。
(04)渭水 司馬懿の本営
一方、その後の魏軍にも、多少穏やかならぬ空気が内在していた。ここにも、残念だ、無念だ、という声がしきりにある。
もちろん、それはたび重なる大敗から来た蜀軍への敵愾心(てきがいしん)であって、内部的な抗争や司馬懿に対する怨嗟(えんさ)ではない。しかし、怨嗟はないまでも不平はあった。今や満々たる不満がみなぎっていた。
なぜかといえば、以後またも高札を掲げ、「一兵たりと、既定の陣線から出た者は斬る。また、陣中に激語を弄し、みだりに敵に戦いを挑む者も斬罪に処さん」という徹底的な防御主義、消極作戦の軍法が、彼らの行動を一切制圧していたからだ。
渭水の氷は解けても、陽春百日、両軍は依然として対陣のままだった。
あるとき郭淮(かくわい)が来て語る。
「それがしの観たところ、どうも諸葛亮はもう一歩出て、さらにほかへ転陣を策しておるように考えられますが……」
司馬懿は同意したうえ、珍しくこのような意見を漏らす。
「もし孔明(こうめい。諸葛亮のあざな)が、斜谷(やこく)や祁山(きざん)の兵をこぞって武功(ぶこう)に出て、山に依って東進するようだったら憂うべきだが、西して五丈原へ出れば憂いはない」
さすがに司馬懿は慧眼(けいがん)だった。彼がこの言をなしてから日ならずして、蜀軍は果然、移動を開始する。しかも選んだ地は、武功ではなく五丈原だった。
武功は今の陝西省(せんせいしょう)武功に属する地方である。司馬懿の観るところ、もし孔明がこれへ出てきたら、一挙玉砕か、一挙大勝かの大勇猛心の表現であり、魏軍にとっても容易ならぬ構えが要るものと、密かに恐れていたのである。
だが諸葛亮は冒険を避けて、なお持久長攻に便な五丈原へ移った。
五丈原は宝鶏県(ほうけいけん)の東南35里、ここも千里をうねる渭水の南にある。そして従来の数次の陣地に比べると、遥かに遠く出て、中原(ちゅうげん。黄河中流域)に突出している。
ここまで来ると、長安(ちょうあん)も潼関(どうかん)も、また敵国の都の洛陽(らくよう)も、一鞭(いちべん)すでに指呼の内だ。
さらに司馬懿が額をなでて喜悦したわけは、持久戦をもって対するならば、彼にも自信があったからである。
ただ困るのは、大局の見通しを持たぬ麾下(きか)が、ややもすると彼を軽んじて、「卑怯(ひきょう)な総帥、臆病な都督(ととく)」とあげつらい、陣中の紀綱(掟〈おきて〉)を乱しがちなことだった。
ために司馬懿は、わざと朝廷に上表して戦いを乞う。朝廷は再度、辛毘(しんび。辛毗)を前線に差し向け、「堅守自重。ただそれ、守るに努めよ」と、重ねて全軍を戒めた。
(05)五丈原 諸葛亮の本営
諸葛亮は五丈原へ陣を移してからも、種々(さまざま)に心を砕いて敵を誘導してみたが、魏軍はまったく動きを見せない。
敵国の地深くへ進み出ながら、彼がなお自ら軍勢を引っ提げて戦わずに、ひたすら魏軍の妄動を誘う消極戦法を固持している理由は、実にその兵力と装備の差にあった。
後方から補充をなすに地の利を得ている魏の陣営は、動かざる間にも、驚くべき兵力を逐次加えており、今では諸葛亮の観るところ、蜀の全軍の8倍に達する大兵を結集しているものと思われていたのである。
その量と実力に当たる寡兵の蜀陣としては、「誘ってこれを近きに討つ」。この一手しか断じてほかに策はなかったのだ。
しかも、魏はその一活路すら看破している。さすがの諸葛亮も、まったく無反応な辛抱強い敵に対しては計の施しようもなかった。
ある日、諸葛亮は一使を選んで、自筆の書簡と美しい牛皮の箱を託し、司馬懿に渡してくるよう命ずる。
(06)渭水 司馬懿の本営
使者は輿に乗って魏陣へ臨む。輿に乗って通る者は射ず討たず、ということは戦陣の作法になっている。
司馬懿がまず箱を開いてみると、中から艶(あで)やかな巾幗(きんかく)と縞衣(こうい)が出てきた。
司馬懿の唇を包んでいる疎々たる白髯(はくぜん)は震えていた。明らかに赫怒(かくど。怒るさま)している。だがなお、それを手にしたままジッと見ていた。
巾幗というのは、まだ笄(こうがい。簪〈かんざし〉)を簪(かざ)す妙齢にもならない少女が髪を飾る布であり、蜀人は曇籠蓋(どんろうがい)ともいう。また、縞衣は女服である。
との謎を解くならば、挑めども応ぜず、ただ塁壁を堅くして、少しも出てこない司馬懿は、あたかも羞恥(しゅうち)を深く隠して、ひたすら外気を恐れ、家の内でばかり嬌(きょう。美しさ)誇っている婦人のごときものである、と揶揄(やゆ)しているとしか考えられない。
次に彼は書簡を開く。やはり心の内で解いた謎は当たっている。諸葛亮の文辞は、司馬懿の灰のごとき感情も烈火となすに十分だった。
「ははははは。おもしろい」
やがて司馬懿の唇が漏らしたものは、内心の憤怒とは正反対な笑い声。贈られた品物を納めて使者をねぎらい、酒を供して座間に尋ねる。
「孔明はよく眠るかの?」
いやしくも自分の仕える諸葛亮のうわさとなると、軍使は杯を下に置き、ひと言の答えにも身を正して言った。
「はい。わが諸葛公にはつとに起き、夜は夜半に寝(い)ね、軍中のお務めに倦(う)むご様子も見えません」
「賞罰は?」と司馬懿。
「至ってお厳しゅうございます。罰20(鞭〈むち〉打ち20回)以上は、みな自ら裁決なさっておられます」と軍使。
「朝暮の食事は?」と司馬懿。
「お食はごく少なく、一日に数升(わが国における現代の数升とは異なる)を召し上がるにすぎません」と軍使。
「ほ。それでよくあの身神が続くものだの」と司馬懿。
そこではさも感服したような態だったが、使者が帰ると左右の者に言った。
「孔明の命は久しくあるまい。あの激務と心労に煩わされながら、微量な食物しか摂っていないところを見ると、あるいはもう幾分は弱っているのかもしれない」
(07)五丈原 諸葛亮の本営
魏陣から帰ってきた使者に向かい、諸葛亮は敵営の様子と司馬懿の反応をただしていた。
のち諸葛亮は大いに嘆ずる。
「我をよく知ること、敵の仲達(ちゅうたつ。司馬懿のあざな)に勝る者はいない。彼はわが命数まで量っている」
時に楊喬(ようきょう)という主簿(しゅぼ)の一員が進み出て、意見を呈した。
★楊喬は、正史『三国志』や『三国志演義』では楊顒(ようぎょう)。
「例えば、一家の営みを見ましても、奴婢(ぬひ)がおれば、奴(男の召し使い)は出でて田を耕し、婢(女の召し使い)は内にあって粟(アワ)を炊(かし)ぐ」
「鶏は晨(あした。朝)を告げ、犬は盗人の番をし、牛は重きを負い、馬は遠きに行く。みな、その職と分でありましょう」
「また家の主は、それらを督して家業を見、租税を怠らず、子弟を教育し、妻はこれを内助して、家の清掃や一家の和、かりそめにも家に瑕瑾(かきん)なからしめ、夫に後顧のないようにいたしております」
「かくてこそ一家は円滑に、その営みはよく治まってまいりますが、仮に家の主が、奴ともなり婢ともなり、ひとりですべてをなそうとしたらどうなりましょう? 体は疲れ、気根は衰え、やがて家滅ぶの因(もと)となります」
「主は従容として、時には枕を高うし、心を広く持ち、よく身を養い、内外を見ておればよいのです。決してそれは、奴婢や鶏犬に及ばないからではなく、主の分を破り、家の法に背くからです」
「『坐(ざ)シテ道ヲ論ズ之(これ)ヲ三公ト言イ、作(た)ッテ之ヲ行ウ(実行に携わる者)ヲ士大夫ト謂(い)ウ』と古人が申したのも、その理ではございますまいか」
★この記事の主要テキストとして用いている新潮文庫の註解(渡邉義浩〈わたなべ・よしひろ〉氏)によると、「(『坐シテ道ヲ論ズ之ヲ三公ト言イ……』は)『周礼(しゅらい)』冬官考工記に基づく格言」だという。
諸葛亮は瞑目(めいもく)して聞いていた。なお楊喬は続ける。
「しかるに、丞相のご日常をうかがっておりますと、細やかな指示にも、余人に命じておけばよいことも、大小となく自らあそばして、終日汗をたたえられ、真に涼やかに身神をお休めになる閑(ひま)もないようにお見受けいたします」
「かくてはいかなるご根気も倦み疲れ、とうてい神気の続く謂(い)われはございません。ましてやようやく夏に入り、日々この炎暑では、何でお体がたまりましょう」
「どうかもう少し暢(のび)やかに、まれにはおくつろぎくださることこそ、我々麾下の者もかえって喜ばしくこそ思え、毛頭、丞相の懈怠(けたい)なりなどとは思いも寄りませぬ」
諸葛亮は涙を流し、部下の温情を謝して、こう答えた。
「予もそれに気づかないわけではないが、ただ先帝(劉備〈りゅうび〉)の重恩を思い、蜀中にある孤君の御行く末を考えると、眠りに就いても寝ていられない心地がしてまいる」
「かつは、人間にも自ら定まれる天寿というものがあるので、何とぞわが一命のあるうちにと、つい悠久な時を忘れて人命の短きに焦るために、人手よりはわが手で務め、先にと思うことも、今のうちにと急ぐようになる」
「けれどお前たちに心配させてはなるまいから、これからは予も折々には閑(かん)を愛し、身の養生にも努めることにしよう」
諸人もそれを聞き、みな粛然と暗涙を吞んだ。
だが、このときすでに、身に病の起こってきた予感は、諸葛亮自身が誰よりもよく悟っていたに違いない。まもなく彼の容体は常ならぬもののように見えた。
管理人「かぶらがわ」より
一軍の大将の職から貶された馬岱を、部下に欲しいと言い張る魏延。武功ではなく、五丈原へ出ることを選んだ諸葛亮。女衣と巾幗を贈られても笑い、かえって諸葛亮の命数を量る司馬懿。
後半部分は、諸葛亮の劉備への想い、そして劉禅(りゅうぜん)への想いが強くうかがえた第307話でした。

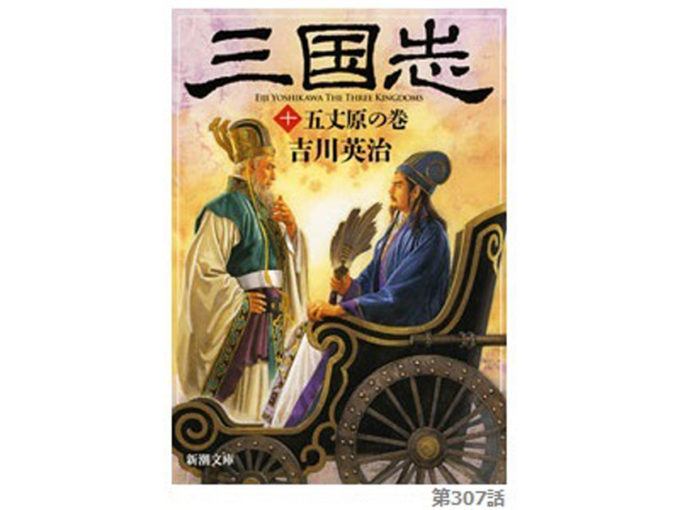













コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます